というわけで、読みました。実篤の詩たち。それはほんとに純粋で、そのままで、生命に満ち、喜びにあふれていた。「偉大な小児の祈祷」と、解説の亀井勝一郎は書いているけど、ぴったりだと思う。あまりに単純に見えるから、あっという間に読み過ぎてしまうけど、一つ一つの詩は、深い生命の信頼に基づいていて、それを体現できるか、体で納得できるか、できたか、一つの詩に立ち止まったとき、反省しないわけにはいかない。
「言葉に羽が生えると詩になる」
実篤が体験から言っている。
「羽毛のように軽いのでなく、鳥のように軽くなければならなぬ」
これはヴァレリーの言葉。
生命のこもっていないとき、言葉は羽毛のように軽くなり、難解そうに見えてもただ言葉の遊戯にすぎなくなる。しかし鳥のように軽快に飛ぶためには、生命がこもっていなければならぬ。あるいは思想が熟していなければならぬ(202ページ/解説より)。
自分の書いてきた詩たち。そこに生命はこもっていただろうか? 自分の内で生きたゆえに、他者の内にも生きただろうか? 鳥のように飛んだであろうか?
今回の読書で、僕の心に強く生きた詩を、二編紹介します。
矢を射る者
俺の放つ矢を見よ。
第一の矢はしくじった。
第二の矢もしくじった、
第三の矢もまたしくじった。
第四、第五の矢もしくじった
だが笑うな。
いつまでもしくじってばかりはいない。
今度こそ、
今度こそと
十年あまり
毎日、毎日
矢を放った。
まだ本物ではないにしろ
たまにはあたり出した
見よ
今度の大きな矢こそ
人類の心の真ただ中を
射あてて見せる
そしてぬけない矢を
俺の放つ矢を見よ。
泉
泉は何処に水が流れるか知らずに水を地上にあふれさす、
鶏はいくつ卵を生んだか忘れて毎日毎日卵を生む。
私は誰がよむとも知らず毎日何かをかく、
時には書き損ないもあるかもしれない。
たまにはいい卵も生むだろう。
見つけるか見つけないか、それは人々にまかせる。
滋味がある卵を見つけたら、食べてくれ、
さもなければすてておいてくれ。
私はそんなことを考えずに卵は生むのだ。
毎日毎日生みっぱなしにするのだ。
生むのは私の任務だ。
それを食べるのは誰かの任務だ。
食べられなければ、くさりもするだろう。
だが何処かで、ひよっこがかえるかも知れない。
泉は流れる所を知らずにあふれ、
鶏は卵を生んで生んで齢とってゆくのだ。
『矢を射る者』
今の僕は、まさにそうです。何度でも放ってやる。今度こそ本物を、と全力で。
『泉』
泉という言葉に、このブログを始めてから敏感です。泉とは、流れるところを知らなかった。くみ上げ、人間の意識に渡してゆくこと。それが僕の任務。「ひよっこがかえるかも知れない」いいですね、これくらいの感覚が。
これもどこかで書いてあったけど、実篤は巨木です。だからこそ様々なものが集い、憩うことができる。みんな幸せであって欲しい、そうであるはずだ。困難が人生につきものであっても、生きること、そのものが喜びだ。その喜びに身を任せ、大いなるものに感謝する。新しい村も、実篤のそんな思想、信念の具体化だった。
読んでいて、楽しかった。安らいだ。
なんというか、感覚的に僕と似ているかもしれない。もちろん、自分は自分にしかなれないけど。
そうだ、せめて、親しみを込めて、「おじいちゃん」ということで。
これからもよろしくお願いします。また伺います。
武者小路実篤著/新潮文庫/1953
「言葉に羽が生えると詩になる」
実篤が体験から言っている。
「羽毛のように軽いのでなく、鳥のように軽くなければならなぬ」
これはヴァレリーの言葉。
生命のこもっていないとき、言葉は羽毛のように軽くなり、難解そうに見えてもただ言葉の遊戯にすぎなくなる。しかし鳥のように軽快に飛ぶためには、生命がこもっていなければならぬ。あるいは思想が熟していなければならぬ(202ページ/解説より)。
自分の書いてきた詩たち。そこに生命はこもっていただろうか? 自分の内で生きたゆえに、他者の内にも生きただろうか? 鳥のように飛んだであろうか?
今回の読書で、僕の心に強く生きた詩を、二編紹介します。
矢を射る者
俺の放つ矢を見よ。
第一の矢はしくじった。
第二の矢もしくじった、
第三の矢もまたしくじった。
第四、第五の矢もしくじった
だが笑うな。
いつまでもしくじってばかりはいない。
今度こそ、
今度こそと
十年あまり
毎日、毎日
矢を放った。
まだ本物ではないにしろ
たまにはあたり出した
見よ
今度の大きな矢こそ
人類の心の真ただ中を
射あてて見せる
そしてぬけない矢を
俺の放つ矢を見よ。
泉
泉は何処に水が流れるか知らずに水を地上にあふれさす、
鶏はいくつ卵を生んだか忘れて毎日毎日卵を生む。
私は誰がよむとも知らず毎日何かをかく、
時には書き損ないもあるかもしれない。
たまにはいい卵も生むだろう。
見つけるか見つけないか、それは人々にまかせる。
滋味がある卵を見つけたら、食べてくれ、
さもなければすてておいてくれ。
私はそんなことを考えずに卵は生むのだ。
毎日毎日生みっぱなしにするのだ。
生むのは私の任務だ。
それを食べるのは誰かの任務だ。
食べられなければ、くさりもするだろう。
だが何処かで、ひよっこがかえるかも知れない。
泉は流れる所を知らずにあふれ、
鶏は卵を生んで生んで齢とってゆくのだ。
『矢を射る者』
今の僕は、まさにそうです。何度でも放ってやる。今度こそ本物を、と全力で。
『泉』
泉という言葉に、このブログを始めてから敏感です。泉とは、流れるところを知らなかった。くみ上げ、人間の意識に渡してゆくこと。それが僕の任務。「ひよっこがかえるかも知れない」いいですね、これくらいの感覚が。
これもどこかで書いてあったけど、実篤は巨木です。だからこそ様々なものが集い、憩うことができる。みんな幸せであって欲しい、そうであるはずだ。困難が人生につきものであっても、生きること、そのものが喜びだ。その喜びに身を任せ、大いなるものに感謝する。新しい村も、実篤のそんな思想、信念の具体化だった。
読んでいて、楽しかった。安らいだ。
なんというか、感覚的に僕と似ているかもしれない。もちろん、自分は自分にしかなれないけど。
そうだ、せめて、親しみを込めて、「おじいちゃん」ということで。
これからもよろしくお願いします。また伺います。
武者小路実篤著/新潮文庫/1953















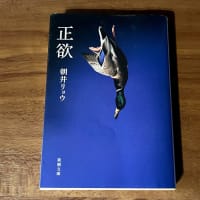









子供の頃、通っていた銭湯に、“きゅうりやなすび”やらの絵が描かれた、ほのぼのとした絵皿が壁に掛かっていました。
子供ごころに、不思議な存在感のある皿として、吸い込まれるようにいつも眺めていました。
そこに書かれてた句が、 『仲良きことは。。』でした。
昭和の子供だった私は、よその家に行ってもその絵を見る機会がよくありました。
その後、武者小路実篤のものと知ったのは、しばらく後になってからでした。
実篤が目指した理想の村、“新しき村”が埼玉にある!と知り、出掛けていったものです。
夕暮れて、やっと辿り着いたその村は、牛舎や鶏舎などがある自給自足の村。
とても理想的な輝く農村
!をイメージしていた私でしたが、その村には“何かが足りないような淋しさ”を感じたのでした。
唯一!?楽しかったのは、牛になつかれたこと!。 牛のヨダレにまみれながら、村を後にしたのを、懐かしく思い出したブログでした。
「新しき村」
新しさはいつも昔にある、ように感じています。
自給自足は確かに一つの理想ですね。みんな、一人ひとりが、少しでもその精神を持ち実践したら、食料問題も環境問題も、少しは改善されますよね。
僕は紙を沢山消費してしまうので、植林活動に少しでも協力できたらと思ってます。あと、ごみの分別。できることから少しずつ。
牛に好かれるとは! おいしそうだったのですかね。