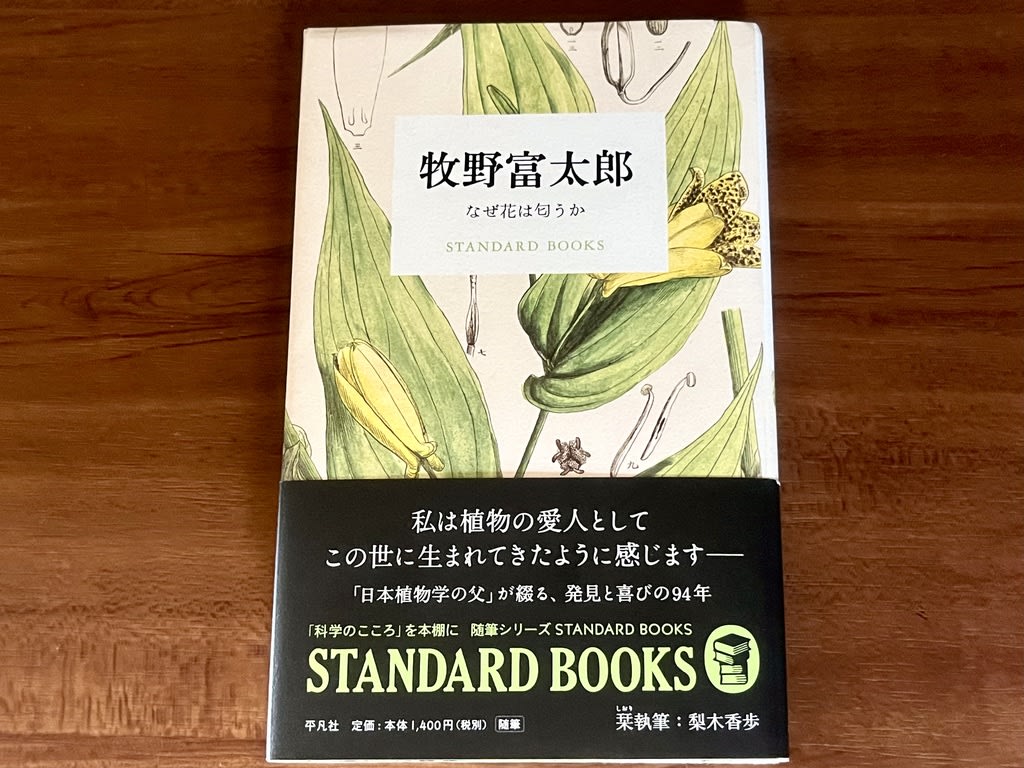一昨年の秋、宮城県の気仙沼に行きました。そのとき、時間が足りずに行けなかった場所がありました。
次回は必ず行く予定にしている「
リアス・アーク美術館」。
この本の新刊案内を見たとき、だから目が止まりました。そして注文していました。
しばらく店に置いていたのですが、自分が読みたくなったので買いました。
読むときが来たわけですが、書いている小説に「被災物」が出てきたので。
というか、この本を読んでわかったのですが、私もまた被災物という呼び水に触発されて、小さな物語を紡ぎ出したのだと。
「被災物」とはなんでしょうか?
「被災者」という言葉があります。人が震災にあったとき、その人を被災者と呼びます。
同じように、物が被災したとき、その物を被災物と呼ぶようにしたのです。
「瓦礫(ガレキ)」という言葉がやたらと使われました。
人々の経験したことのない出来事や見たことのない物が現れたとき、手持ちの言葉でそれをとらえようとします。
でも、経験したことのない出来事や物を、どうして手持ちの言葉で表現できるでしょうか?
「瓦礫」とは、手持ちの国語辞書(岩波国語辞典第8版)によれば「かわら、コンクリートのかけらや石ころなどの集まり。建物・家具などの残骸。また、役に立たないもの。価値のないつまらないもの、その集まり」とあります。
大津波によって被災した物たちが、どうして「瓦礫」なのでしょうか? どこがつまらないものなのでしょうか?
私も感じていました。現地に足を運び入れ、歩いて風を肌に受け、匂いを嗅ぎ、音に耳を澄ませれば、それらの一つ一つは大切な「おらほ」(気仙沼の方言で「私たち」という意味です)の「我が家」でしかありません。その人の足であったであろう車に船。生活に欠かせなかったであろう足踏みミシンや本。決して「瓦礫の山」は存在しなかった。それが存在したとするならば、よく見ること(視力があるという意味ではなく)のできない人たちの頭の中にだけ。
リアス・アーク美術館は、被災物を収集し、展示しています。
ただ展示しているだけではありません。収集した日時と場所とともに「モノ語り」が葉書に認められて添えられてあります。
例えば、63ページにある「ぬいぐるみ」。
2012•3•23 気仙沼市内の脇2丁目
うちの子がね、大切にしてた”ぬいぐるみ”があったのね。
それをね、すぐ帰れると思って、うちに置いてきてしまったのね……
うちの子がね……ポンタが死んじゃったって、泣くの。あの子にとっては、たぶん親友だったんだよね……
あれから、うちの子、変わってしまってね。新しいのを買ってやるからって、おばあちゃんが言うんだけど……いらないって、ポンタじゃなきゃダメだって言うのね。
この「モノ語り」は、モノの持ち主が語ったものではありません。収集した学芸員が想像して書いたものです。
この試みは「
さがしています」(アーサー・ビナード作・童心社)を思い出しました。「さがしています」は、広島の原爆資料館にある「被爆物」のモノ語りを、アーサー・ビナードさんが聞き取ったもの。
「被災物」と違うのは、被災物のモノ語りは、そのモノにまつわる人間に共通する記憶が語られているところです。
「被爆物」は、その持ち主が明確なので、モノ語りは一つの形に収束していきます。「被災物」は、持ち主がはっきりせず、言ってみればみんなのものに変わっていますので、モノ語りは接した人の数ほど増殖していきます。共通しているのは「傷んでいる」ということ。人によってなのか自然によってなのかの大きな違いはありますが。
この本は、以上のようなリアス・アーク美術館にある被災物に接した人たちの応答がまとめられたものです。
ワークショップという形で被災物への応答は行われました。人によって触発されるモノも違います。応答の仕方も、詩だったり踊りだったり文だったりします。
被災物に接して何が出てくるのか? それは記憶の語り直しでした。「記憶のケア」とも言われています。
深いところに潜り込んで見つけられなくなっていた記憶の断片。それらは被災物が呼び水となって鮮やかに意識に上がってくる。
語ったり書いたり歌ったり踊ったりして意識をなぞることでその人の生き直しが生まれる。
さらに興味深かったのは、被災物が恵比寿につながっていくこと。
恵比寿は七福神の一つです。あの突き出した腹に大きな耳たぶ、釣竿と鯛を持っているあの神様。
知らなかったのですが、恵比寿様の謂れはこんな感じでした。古事記という日本の国造りの神話に登場するイザナミとイザナギの第三子(蛭子・ひるこ)は、3歳になっても歩かなかったので海に流されてしまいました。それでも蛭子は生き残り、漂着した浜の人々によって手厚く守られ、やがて祀られるようになった。蛭子は恵比寿となり、海の神となり、豊漁の神となり、転じて商売繁盛の神ともなった。
足が悪いということで、通常恵比寿様は座っています。が、気仙沼にある恵比寿像は立っており、かつ鯛ではなく鰹を抱えています。立っている方が縁起がいいとか何とか大阪人に言いくるめられたそうです。気仙沼人の人の良さと、鰹に変更してオリジナルにしてしまう図太さが伝わってくるエピソードではあります。
恵比寿とは、海からくるモノの総称でした。だから魚も貝も石も海藻も漂流物も水死体も被災物みんな恵比寿。
被災物をありがたい恵比寿に近づけられるかは、被災物に接した一人一人の語りにかかっています。
語りが生まれれば聞き手もまた生まれます。本が生まれれば読者が生まれるのと同じで。
そこにつながりも生まれます。
被災物のワークショップに参加した人たちは、モノ語りの流れに乗って、気仙沼へ旅に出ます。鎮魂と、今ある命を祝うために。
「被災物」に接して語ること。それはそのまま傷ついている自分を修復することにつながっているように感じました。
その作業を、私自身が行なっているということも感じました。だからこそ読む必要に迫られました。
この作業(私にとっては小説を書くこと)には終わりがないことも感じます。
モノ語りは増殖していくから。増殖してつながる相手を求めるから。
もしこの世に「傷ついたもの」がいなくなれば、その必要もなくなるのでしょうが。
私は私に訪れたモノ語りを書き続けます。
気仙沼に行ったら、ぜひリアス・アーク美術館へ足を運んでください。
私も、必ず、近々、行きます。
そしてまたモノ語りの芽を持って帰ってくるのでしょう。意識するにせよ、しないにせよ。持って帰ってくるつもりでないものもくっついてきて。
それが現地に行く貴重さでもあるのでしょうね。
姜(きょう)信子・山内宏泰・志賀理江子・川島秀一 他著/かたばみ書房/2024