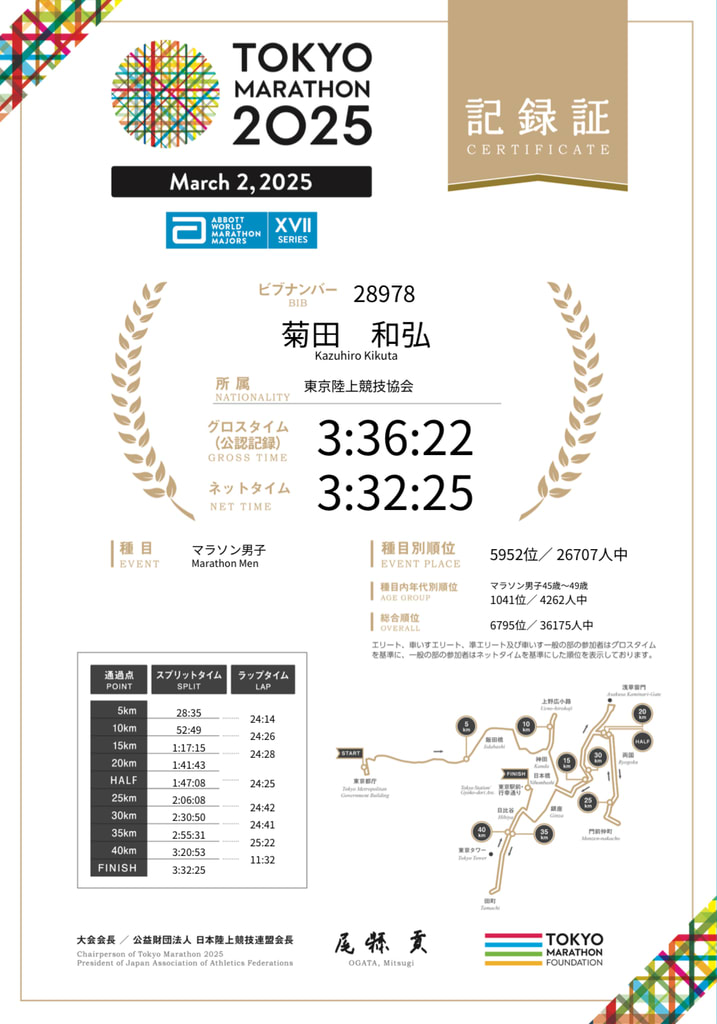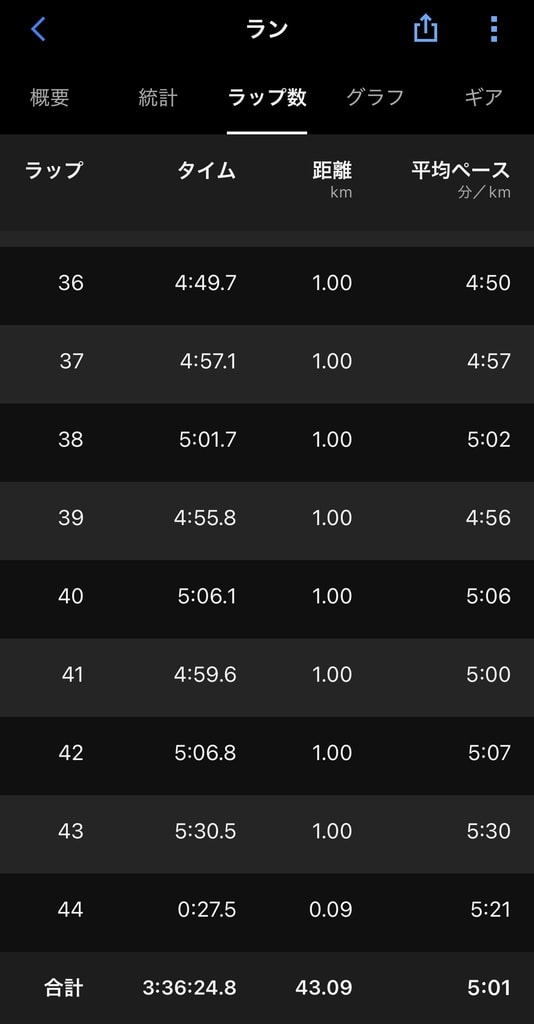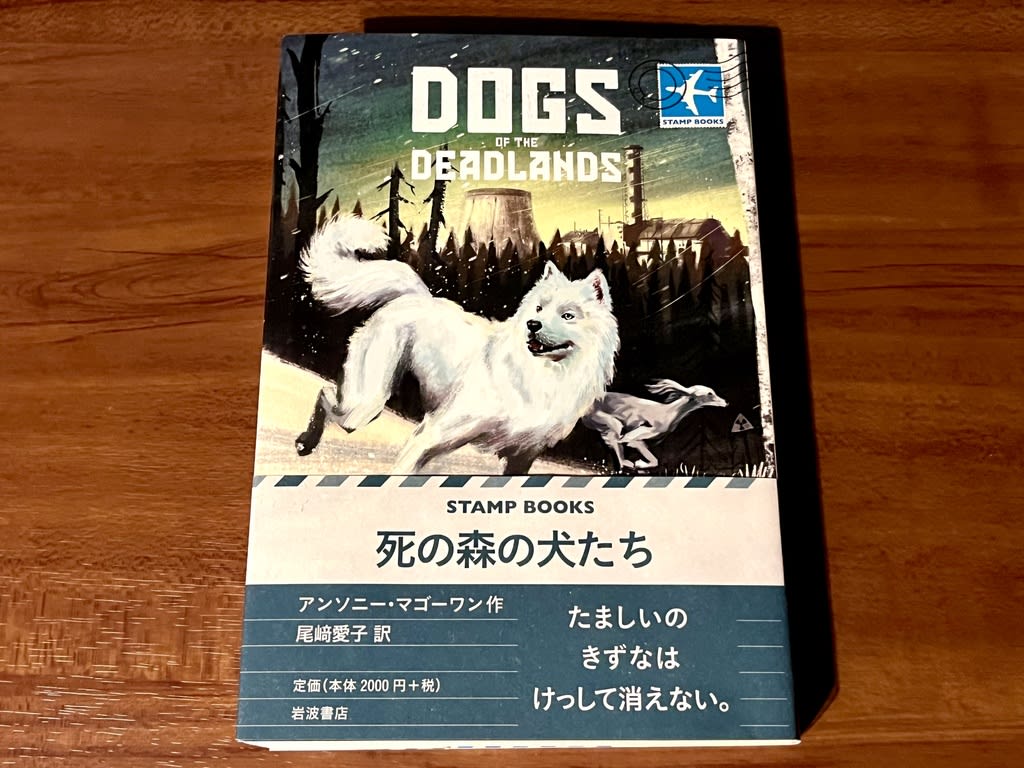先日、久々に連休がありました。そのとき、前から気になっていたCDと本の整理をしました。不要なものを近くのブックオフに持って行き、売りました。6000円くらいになったでしょうか。
ブックオフに行く目的は売るだけでなく、探しているものもあったのです。それは『耳をすませば』のDVDです。ジブリから発売されています。
買取価格が決定するまでの待ち時間で、たっぷりと店内を見ることができました。今はレコードやフィギュア、ゲーム、カード、玩具、スマホまで売っている。それでも大部分は本。そのブックオフはヨーカドーの中に最近できたもので、品揃えはまだまだだなという感じでした。
で、お目当てのジブリのDVDは、なかなか見つけられなかったのですが、3周目くらいでしょうか、やっと見つけました。が、品数は少なく、『耳をすませば』はありませんでした。だけど私の心を引きつけた作品がありました。それが『レッドタートル』です。
ジブリ作品をだいたい知っているつもりでしたが、この作品は知りませんでした。絵の美しさに引かれ、海と亀と島にまた引かれ。連れて帰ることに。
観始めてやがて気づいたのですが、この映画にセリフは一切ありません。ただ男のうめき声ぐらい。それでも映像の美しさに引かれてじっと見入ってしまいます。
この記事の表紙にしたのは『レッド・タートル』の絵本(岩波書店)。映画の中から印象的な場面に池澤夏樹さんが言葉をつけています。池澤さんの解釈によってより作品の理解が深まった感じです。それが正解というわけではありませんが。
例えば、無人島に漂流した男は一人ぼっちになり、いかだを作って島からの脱出を何度も試みますが、何か大きな力によっていかだは破壊されてどうしても島から出ることができません。そのとき、赤い亀が男をじっと見つめます。その亀は島に上がってきて、男に発見され、恨みをぶつけられて棒で打たれ、ひっくり返されてしまいます。私は、男と同じように、その亀が男の脱出を阻んでいたと思ったのですが、池澤さんの理解では、そうではありません。亀は、男と添い遂げることを決めて島に上がってきたのだと。
ひっくり返された赤い亀は、固い甲羅がひび割れてくると、その中身は人間の女性になっていたのでした。女性は男の世話によって元気になり、男の子を産み、家族となります。その子は小さいとき、空のガラス瓶を拾って、この島から遠いところに文明があることを知り、大きくなってから島を出て行きます。ガラス瓶が文明からの誘いだとは映画を観たときには思い至りませんでした。
また二人になった男と女は、穏やかに年を重ね、やがて男は亡くなります。
女は、男を看取ります。そして、赤い亀に戻って海へ帰ります。
それだけの物語。なのになぜ余韻が続くのでしょう?
「十牛図」みたいですね。情報は限りなく少なく、絵だけによって人の真実を表そうとしている。それはこれを作った監督が志向していることでもあって、前作の映画はわずか8分しかありません。だけど、ものすごいインパクト。1度観たら忘れられない。
『岸辺のふたり』 原題は『父と娘』。これも取り寄せて観ましたが素晴らしいアニメーションでした。影が印象的ですね。動きもまた魅力的です。
それで『耳をすませば』ですが、観たくなったのには理由があります。
まず、自作をある知人に読んでもらって感想を聞いたのですが「ジブリの絵がずっと見えていた」とおっしゃいました。それで私は「あーーー」と思ったわけです。
絵は好きでよく観に行きます。そしてもちろんジブリ作品も観てきました。先に触れたように全てではありませんでしたが。
小説を書くとき、私も頭の中で絵を観ています。それでジブリの作品をもっと観たくなりました。何か参考になり、自作を支えてくれるのではないかと。
で、この話をいつもお世話になっている美容師さんに話しました。すると彼はこう言ったのでした。「僕は『耳をすませば』が好きですね〜」と。私はピンときませんでした。観ていなかったからです。
さらに今読んでいる『正欲』(新潮文庫/朝井リョウ 著)に、「まるで『耳をすませば』の天沢聖司みたいに」という文があり、これがシンクロニシティ(意味のある偶然の一致。人生に意味と方向性を与えてくれるもの)かという感じで導かれて。
で、パソコンに外付けできるDVDプレーヤーを買い、『耳をすませば』と前から観たかった『思い出のマーニー』をネットで探し、レンタル落ちという中古のものを買い求めたわけです。
懐かしく温かい手書きの風景。京王線の聖蹟桜ヶ丘駅周辺がモデルとなっているそうです。
読書好きの中学三年生女子、雫が主人公。彼女が図書館で本を借りると、読書カードに必ず「天沢聖司」の名前がすでにあり、誰だろうと気になっていきます。
雫の友人が、意中の人でない人から告白されどうしようと相談。その伝令役を務めた男子が、実はその子の好きな人でした。雫の幼馴染のその男子は、実は雫が好きでした。でも雫はまったく気づいていなかった。そんな自分の鈍感さに落ち込みもします。
彼女が借りていた本をベンチに置き忘れ、取りに戻ったところに天沢はいました。そこから彼との関係が深まっていきます。
彼は、バイオリンを作る職人になりたいのでした。バイオリンも弾けるのですが、雫が演奏をお願いすると、お前が歌うならという条件付き。雫は、下手だからと怖気つきますが、演奏に促されて楽しくリズムに乗って歌うようになる。そのシーンはとても印象的です。
聖司は、腕のいい職人になれるか試すために二ヶ月だけイタリアの職人のもとへ修行に。その間、雫はあることを成し遂げようと決める。それが物語の執筆でした。タイトルは『耳をすませば』。
聖司の祖父が、雫の最初の読者となります。そしてまた印象的なことに、宝石の原石を雫に差し上げる。しっかり磨きなさいと。私もまた大学生のときから物語を書く試みを繰り返していました。だから雫の苦しみは痛いほどわかりました。
聖司は帰ってきて、雫と再会。その後、どうなったのでしょうか? 観てのお楽しみです。
美容師さんはこの作品が好きだから、物書きになりたい私のこともずっと応援してくれているのかもしれません。作品を通じて、人のことが少しわかるっていいですね。
最後に『思い出のマーニー』。
これは昨年夏に原作をとても面白く読みました(岩波少年文庫)。ジブリの映画があるのを知ったのはその後です。
舞台はイギリスから、映画では日本の北海道に移されています。アンナも日本人の杏奈に。だけど、物語の大事なところはそのまま生かされています。驚くほど自然に。
原作の良さはどこも失われていなかった。療養先のむかつく地元の子もしっかり出てくるし、漁師のとても無口なおじさんもちゃんといる。
風車小屋はサイロになっているけれど、その不気味さはまったく変わらない。意地悪婆やもまた、ただ日本人になったというだけで意地悪なまま。マーニーの作った砂の城も、キノコ狩りの風景も、湿っち屋敷も。本当に感心しました。
そしてやっぱり泣けました。自分が嫌いで、「ふつう」であることを願い続ける杏奈が、その核心とも言える「見捨てられることによる不信」をマーニーと追体験することによって克服していく過程が。マーニーが、本当に杏奈を一番大事にしていたことが、杏奈に十分に伝わったことで。そしてそれを可能にした環境が整ったことで。
何度でも観たい作品になりました。
映画、私は好きでした。最近はあまり観ていなかったのですが。
大学生のとき、私も自分のことが嫌いでたまりませんでした。大勢の人たちの中にいるのも苦手で、しかも最初は学生寮に住んでいました。私は逃げるように、仙山線に乗って山寺へ行ったり、ただ広瀬川を眺めていたり、本屋や図書館でぶらぶらしていたりしていました。その中でも映画館に逃げ込む時間は特別でした。
どうして特別だったのかは、映画を観た後、トイレの鏡で自分の顔を見てわかります。見たくもなかった顔が、少しは見れる顔に変わっていたから。その体験を、今回の一連のジブリ映画を観る中で思い出しました。
物語を生きると、受け入れがたかったものが、少しは受け入れられるようになります。それが物語の持つ大きな力です。
杏奈は、物語に没頭することで、許せなかったことを許すことができるようになりました。
無人島に漂流した男も、何度も脱出を試みますが、やがてその島で生き直すことになります。
雫は物語を書き抜こうともがく中で、自分に足りないものを見つけ、それを得るために進路も決まっていく。
物語は目に見えないものです。だけど、語ったり、描いたりすることはできる。その価値は、測ることもできません。
ただ、作品を作る側になることは、とても大変なことだけど、とても素晴らしいことだとも、改めて思いました。
せっせと取り入れてきた作品の一つ一つが、私の作品を支えていることは言うまでもありません。
だから、これからも、ともに。