
コロナ禍にあって、復活する本がある。この本もその一つ。
初版は1984年。今年50回目の重版。37年も生きている。
ピンチになって読まれる本。それこそ本物なのでしょう。
長田弘さんの詩集は、すでに3冊持っています。
『詩の樹の下で』『死者の贈り物』(ともにみすず書房)、『詩ふたつ』(クレヨンハウス)。
『深呼吸の必要』は2回読み、上の3冊も読み直した。
長田さんの詩は想起させてくれます。いつ自分が大人になったのか。その瞬間の一つ一つ。
昔よく遊び、今は見かけなくなってしまった原っぱ。影踏み遊び。
そして大きな木のこと。
私が通っていた小学校にも大きなけやきの木があった。その木は、まだ元気だろうか?
不思議とその木の周りにいれば、みんなにこにこしていた。
木が宿しているのは悠久の時間。時間というものが可視化したもの。
木の命は、人の一生を軽く超えていく。
幸いに、自分が住んでいる周りには大きな木も草花もある。思い切り走って深呼吸できる場所があるのは幸せなことになってしまった。
でも、言葉でも深呼吸できる。みんなそれぞれに、こころに言葉の木を宿しているから。
長田さん自身、言葉の深呼吸の必要を感じたとき、この詩集を編んだ。
私もそうだったと思う。自分の中の言葉の木のこと。
読書体験は、言葉の木にとって、根を張り、水分と栄養を吸収するようなもの。
感想を書いたり、考えたり、本について語ったり聞いたりするのは葉っぱの光合成。
私にとって詩は花であり、小説は果実なのかもしれません。
幹にはいっぱいの沈黙が詰まっている。
人の年輪は、言葉の木の年輪のこと。
真っ直ぐに伸びるだけが木じゃない。
ひしゃげたり、曲がりくねったり、たわんだり、枝分かれを繰り返し、ときに雷に打たれて裂かれ。
それでも空をつかもうとして上に伸びていく。
小説を書くに当たって、大事にしたいことをメモ用紙にしるし、机の前に貼っていました。
その一つが長田さんの詩から引いていた。ちょうど6年前のこと。
理解されるために、ことばを使うな。
理解するために、ことばを使え。 『死者の贈り物』39ページ4行~5行
同書から、今回引いた言葉。
貝殻をひろうように、身をかがめて言葉をひろえ。
ひとのいちばん大事なものは正しさではない。 8ページ5行~6行
わたしたちは、何をすべきか、でなく
何をすべきでないか、考えるべきだ。 11ページ13行~12ページ1行
人間が言葉をうしなうのではない。
言葉が人間をうしなうのだ。 62ページ8行-9行
ひとの人生の根もとにあるのは、死の無名性 80ページ6行
『深呼吸の必要』から
原っぱには、何もなかったのだ。けれども、誰のものでもなかった何もない原っぱには、ほかのどこにもないものがあった。きみの自由が。 97ページ7行~10行
きみはおもいだしてふと、ドキリとすることがある。ひょっとしたら子どもたちは、今日どこかに自分の影法師を失くしてしまったのだろうか、と。 99ページ6行~9行
遊びでほんとうに難しいのは、ただ一つだ。遊びを終わらせること。どんなにたのしくたって、遊びはほんとうは、とても怖しいのだ。 105ページ2行~5行
大事なのは、自分は何者なのかでなく、何者でないかだ。急がないこと。手をつかって仕事すること。そして、日々のたのしみを、一本の自分の木と共にすること。 120ページ1行~5行
長田弘 著/晶文社/1984
初版は1984年。今年50回目の重版。37年も生きている。
ピンチになって読まれる本。それこそ本物なのでしょう。
長田弘さんの詩集は、すでに3冊持っています。
『詩の樹の下で』『死者の贈り物』(ともにみすず書房)、『詩ふたつ』(クレヨンハウス)。
『深呼吸の必要』は2回読み、上の3冊も読み直した。
長田さんの詩は想起させてくれます。いつ自分が大人になったのか。その瞬間の一つ一つ。
昔よく遊び、今は見かけなくなってしまった原っぱ。影踏み遊び。
そして大きな木のこと。
私が通っていた小学校にも大きなけやきの木があった。その木は、まだ元気だろうか?
不思議とその木の周りにいれば、みんなにこにこしていた。
木が宿しているのは悠久の時間。時間というものが可視化したもの。
木の命は、人の一生を軽く超えていく。
幸いに、自分が住んでいる周りには大きな木も草花もある。思い切り走って深呼吸できる場所があるのは幸せなことになってしまった。
でも、言葉でも深呼吸できる。みんなそれぞれに、こころに言葉の木を宿しているから。
長田さん自身、言葉の深呼吸の必要を感じたとき、この詩集を編んだ。
私もそうだったと思う。自分の中の言葉の木のこと。
読書体験は、言葉の木にとって、根を張り、水分と栄養を吸収するようなもの。
感想を書いたり、考えたり、本について語ったり聞いたりするのは葉っぱの光合成。
私にとって詩は花であり、小説は果実なのかもしれません。
幹にはいっぱいの沈黙が詰まっている。
人の年輪は、言葉の木の年輪のこと。
真っ直ぐに伸びるだけが木じゃない。
ひしゃげたり、曲がりくねったり、たわんだり、枝分かれを繰り返し、ときに雷に打たれて裂かれ。
それでも空をつかもうとして上に伸びていく。
小説を書くに当たって、大事にしたいことをメモ用紙にしるし、机の前に貼っていました。
その一つが長田さんの詩から引いていた。ちょうど6年前のこと。
理解されるために、ことばを使うな。
理解するために、ことばを使え。 『死者の贈り物』39ページ4行~5行
同書から、今回引いた言葉。
貝殻をひろうように、身をかがめて言葉をひろえ。
ひとのいちばん大事なものは正しさではない。 8ページ5行~6行
わたしたちは、何をすべきか、でなく
何をすべきでないか、考えるべきだ。 11ページ13行~12ページ1行
人間が言葉をうしなうのではない。
言葉が人間をうしなうのだ。 62ページ8行-9行
ひとの人生の根もとにあるのは、死の無名性 80ページ6行
『深呼吸の必要』から
原っぱには、何もなかったのだ。けれども、誰のものでもなかった何もない原っぱには、ほかのどこにもないものがあった。きみの自由が。 97ページ7行~10行
きみはおもいだしてふと、ドキリとすることがある。ひょっとしたら子どもたちは、今日どこかに自分の影法師を失くしてしまったのだろうか、と。 99ページ6行~9行
遊びでほんとうに難しいのは、ただ一つだ。遊びを終わらせること。どんなにたのしくたって、遊びはほんとうは、とても怖しいのだ。 105ページ2行~5行
大事なのは、自分は何者なのかでなく、何者でないかだ。急がないこと。手をつかって仕事すること。そして、日々のたのしみを、一本の自分の木と共にすること。 120ページ1行~5行
長田弘 著/晶文社/1984















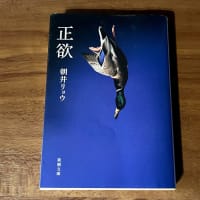









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます