日時:5月24日
映画館:サロンシネマ
パンフレット:A4変形版800円
1965年、インドネシアで発生したクーデター未遂事件に乗じて起こった100万人規模の虐殺事件。当時実行に関わったプルマン(やくざ者)は現在、安定した地位で権力を得て、当時のことを誇らしげに語る。オッペンハイマー監督は彼らに虐殺事件の再現映画を撮ることを提案、快諾(!!)した彼らの制作過程を記録するドキュメンタリー映画。
今年に入ってから、ナチのアイヒマン逮捕の顛末を描いたノンフィクション「獣を鎖に繋げ」を読み、同じくナチの高級将校で戦後も暗躍を続けたクラウス・バルビーに関するドキュメンタリー「敵こそ、我が友~戦犯クラウス・バルビーの3つの人生~」を久しぶりに再見して、全く対極的な2人の戦犯としての戦後に何か感じるところがあった。そして、本作の予告編を観た時、それだけでかきたてられるものがあった。
本作の主人公(?)アンワル・コンゴはおそらく20代の時に殺人部隊を率いて、当時の政権に邪魔と目された共産主義者や労働組合指導者、華僑などを1000人以上を殺害しているのだが、その頃の様子を実演を交えながら再現してくれる。「最初は殴り殺していたが、血だらけになって、後で掃除する時に臭いので、途中から針金で首を絞めることにした。ここがその現場で、ここには亡霊が漂っておる。」などと笑顔で語られて、観ているこちらの価値観がぐらぐら揺らいでしまう。
大量殺人者を訴追する一方的な展開ではなく、今や地元の民兵組織の集会で政治家に挨拶してまわるほどの顔役になったアンワルやその手下で現役プルマンであるヘルマン、アンワルのかっての実行仲間アディといった面々の行動や発言が中立的に記録されていくので、誰に感情移入してよいのか、どんどん混乱してしまう。
現役プルマンであるヘルマンは、インドネシアの猛暑の中、汗をかきかき、地元の華僑からみかじめ料を巻き上げながら、オーバーアクトでエキストラを募り、利権むき出しで選挙に出馬し、ディバインみたいな女装で映画に出演する。書いていても訳が分からないし、同様に映画を観ていても謎なのだが、その勢いに圧倒されてしまう。周囲のかたぎの人は明らかにおびえているし、迷惑そうなのだが、その反応どおりの身近にはいて欲しくないタイプ。
一方、虐殺部隊の一員だったアディは年齢といい、外見といい、ワタシの父親を彷彿とさせる人物。その彼は殺人の理屈をとうとうと語る。不自然なくらい準備されているかのような答え。それを聞いているうちに彼は自分を正当化するためにずっと理由を考えていたのだと推測できる。さらに彼は映画製作によって自分たちの行動が否定されることにつながるのではないかと恐れる。その姿があまりに痛々しい。
さらに新聞社社長は当時、死刑宣告となる共産主義者かどうかの判断をくだしていたことを自慢するし、華僑の継父が殺害されたアンワルの隣人はその時の様子を泣き笑いとともに語る。
彼らが作る映画は殺す側と殺される側が行き来し、文化が違うのか、死生観が違うのか、なぜそんな演出になってしまうのか不可解な演出。しかし、映画を製作するうちに彼らの中でさまざまな変化が起きてくる。分かりやすい改悛や単純な良い悪いではなく、彼らが現在も普通に生活し、権力を得ているだけに、人間の悪とは何かを深く考えさせられる。
結局、この映画には解決はなく、こんな話を世界中に暴露して良いのかと心配になってしまう。延々と「anonymous(匿名)」が続くエンドクレジットに、この話が現在進行形なのだと分かる。
万人受けしないのは確かだが、一度観たら忘れられない映画だ。
映画館:サロンシネマ
パンフレット:A4変形版800円
1965年、インドネシアで発生したクーデター未遂事件に乗じて起こった100万人規模の虐殺事件。当時実行に関わったプルマン(やくざ者)は現在、安定した地位で権力を得て、当時のことを誇らしげに語る。オッペンハイマー監督は彼らに虐殺事件の再現映画を撮ることを提案、快諾(!!)した彼らの制作過程を記録するドキュメンタリー映画。
今年に入ってから、ナチのアイヒマン逮捕の顛末を描いたノンフィクション「獣を鎖に繋げ」を読み、同じくナチの高級将校で戦後も暗躍を続けたクラウス・バルビーに関するドキュメンタリー「敵こそ、我が友~戦犯クラウス・バルビーの3つの人生~」を久しぶりに再見して、全く対極的な2人の戦犯としての戦後に何か感じるところがあった。そして、本作の予告編を観た時、それだけでかきたてられるものがあった。
本作の主人公(?)アンワル・コンゴはおそらく20代の時に殺人部隊を率いて、当時の政権に邪魔と目された共産主義者や労働組合指導者、華僑などを1000人以上を殺害しているのだが、その頃の様子を実演を交えながら再現してくれる。「最初は殴り殺していたが、血だらけになって、後で掃除する時に臭いので、途中から針金で首を絞めることにした。ここがその現場で、ここには亡霊が漂っておる。」などと笑顔で語られて、観ているこちらの価値観がぐらぐら揺らいでしまう。
大量殺人者を訴追する一方的な展開ではなく、今や地元の民兵組織の集会で政治家に挨拶してまわるほどの顔役になったアンワルやその手下で現役プルマンであるヘルマン、アンワルのかっての実行仲間アディといった面々の行動や発言が中立的に記録されていくので、誰に感情移入してよいのか、どんどん混乱してしまう。
現役プルマンであるヘルマンは、インドネシアの猛暑の中、汗をかきかき、地元の華僑からみかじめ料を巻き上げながら、オーバーアクトでエキストラを募り、利権むき出しで選挙に出馬し、ディバインみたいな女装で映画に出演する。書いていても訳が分からないし、同様に映画を観ていても謎なのだが、その勢いに圧倒されてしまう。周囲のかたぎの人は明らかにおびえているし、迷惑そうなのだが、その反応どおりの身近にはいて欲しくないタイプ。
一方、虐殺部隊の一員だったアディは年齢といい、外見といい、ワタシの父親を彷彿とさせる人物。その彼は殺人の理屈をとうとうと語る。不自然なくらい準備されているかのような答え。それを聞いているうちに彼は自分を正当化するためにずっと理由を考えていたのだと推測できる。さらに彼は映画製作によって自分たちの行動が否定されることにつながるのではないかと恐れる。その姿があまりに痛々しい。
さらに新聞社社長は当時、死刑宣告となる共産主義者かどうかの判断をくだしていたことを自慢するし、華僑の継父が殺害されたアンワルの隣人はその時の様子を泣き笑いとともに語る。
彼らが作る映画は殺す側と殺される側が行き来し、文化が違うのか、死生観が違うのか、なぜそんな演出になってしまうのか不可解な演出。しかし、映画を製作するうちに彼らの中でさまざまな変化が起きてくる。分かりやすい改悛や単純な良い悪いではなく、彼らが現在も普通に生活し、権力を得ているだけに、人間の悪とは何かを深く考えさせられる。
結局、この映画には解決はなく、こんな話を世界中に暴露して良いのかと心配になってしまう。延々と「anonymous(匿名)」が続くエンドクレジットに、この話が現在進行形なのだと分かる。
万人受けしないのは確かだが、一度観たら忘れられない映画だ。
| 題名:アクト・オブ・キリング 原題:The Act of Killing 監督:ジョシュア・オッペンハイマー |


















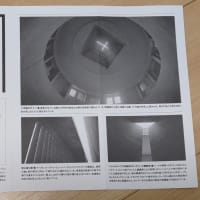







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます