http://www16.ocn.ne.jp/~zeek3333/
こんにちわ、木村国際税務研究所の木村主宰です。
最近、アメリカNSA(国家安全保障局)の通信傍受についてスノーデン容疑者のリークが話題に上っています。アメリカの通信傍受システムはどうなっているのでしょうか。911以降、愛国法にドライブをかけられたアメリカの盗聴法の歴史と現状、並びに日本版の盗聴法、国家機密法の動きにせまります。
□エシュロン
エシュロンは、5つの国、すなわち合衆国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの諜報機関によって運営されている自動的全世界通信傍受・中継システムを呼ぶコード・ネームである。米国国家安全保障局(NSA)が主導しているが、エシュロンはDSD(Defense Signals Directorate:オーストラリア通信防衛信号局)などの他の諜報機関と連携して稼動している(注1)。エシュロンは、GHCQ(Government Communications Headquarters:英国通信本部)や、合衆国の他の関連機関とも、種々の条約に従って運営されている。例えば、ロシアに向けて、中国領域内に通信傍受基地を設置したり、サウジアラビアにも、アメリカが基地を設置しているとされる(注2)。
エシュロンに関する公的な文書の中で、代表的なものは、欧州議会に提出された二つの報告書である。一つ目は、調査員ダンカン・キャンベルによる「通信傍受能力2000」である。
二つ目は、欧州議会の組織「エシュロン特別委員会」が作成した「欧州議会のエシュロンに関する報告」である。前者は、エシュロンシステムの技術的詳細を中心に報告しており、後者は、エシュロンが引き起こす法律問題が内容の中心である。本節と第2節では、「通信傍受能力2000」を中心に参考にしながら、エシュロンの実態をまとめることにした。
■エシュロンの活動
エシュロンは1970年代から存在したとされる。しかし、その能力と重要性は、その結成時から大きく発達した。「通信傍受能力2000」によれば、それは地球上すべてにわたって、多くの形式の送信を傍受し、処理することができる。実際、エシュロンは、電話、電子メール・メッセージ、インターネット・ダウンロード、人工衛星送信など、ほとんどすべての手段の通信を傍受することができる。エシュロンシステムは、これらすべての送信を無差別に集める。エシュロンは、特定の標的についての巨大なデータベースを貯蔵しており、そこには名前、関心ある話題、住所、電話番号、その他選択基準が含まれている。傍受された通信内容はこれらの基準と比較される。その方法はいわゆる「ウェブサイトにおいての「Yahoo」や「Google」などの検索エンジンと、同じようなシステムである。選択基準と一致した場合、その内容は自動的にNSA本部に転送されるようになっている(注3)。
■UKUSA協定
UKUSA同盟(協約、協定)とは、1947年に、英国(UK)と米国(USA)の秘密の合意により、世界的な通信傍受をするために結んだ同盟である。その後、ソ連の通信傍受を目的に再編され、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのコモンウェルス諸国の諜報機関が加わった。豪防衛信号局(DSD)のブレイディ局長はUKUSA協定の存在を認め、外国通信傍受機関と協力していることを認めた(注4)。
UKUSA同盟は冷戦後も、機能し続けている。通信傍受の対象は、ソ連から世界中の通信傍受へと目的を変えた。一九九二年にNSA長官ウィリアム・スタッドマン海軍大将自らが、「全世界に通信に対応できるように、傍受システムを拡大する」と演説している。(注5)
■日本の米軍三沢基地のエシュロン基地・・・トラの檻
日本にもエシュロンの傍受基地が存在するとされる。アメリカ情報自由法によって、解禁扱いとなった、米国の情報活動に関する政府文書に、エシュロンの存在を示す情報が散見される。そのなかで、日本に大規模な通信傍受施設を建設したという記述があった。その作戦は「レディラヴ」とよばれ、ソ連を対象とした安全保障上の傍受活動を円滑に進めるため、日本の米軍三沢基地(青森県三沢市)に大規模な通信傍受基地が建設された。この基地では、冷戦後、日本での衛星経由の民間衛星通信を傍受しているとされる(注6)。 トラの檻の異名がある。
■産業スパイ
2001年7月、欧州議会で承認、9月に決議・採択された「欧州議会のエシュロンに関する報告・決議」では、「システムの目的は軍事通信ではなく、個人の通信や商業通信を傍受することである」と断定した(注7)。
エシュロンの傍受活動によって90年代に日本企業は九件の国際入札で米系企業にやぶれた。1994年、サウジアラビアの電話通信網整備事業の国際入札でNECは米系通信会社AT&Tよりも低い応札額を設定出したにもかかわらず、クリントン大統領によるサウジアラビア国王の特別な働きかけによって、最終的にはAT&Tが落札した(注8)。また、NECは、1989(平成元)年、インドネシア政府の電話交換機の競争入札で一番札を取り、契約寸前までこぎ着けた。だが、上述のサウジの事業落札と同じように米大統領が親書をインドネシアに送り再入札にこぎつけた。約二百億円の契約のうち、半分を米国企業が落札、残り半分がNECの取り分になった(注9)。
日本企業だけでなく、欧州企業も、エシュロンの通信傍受によって、ブラジルやサウジアラビアの公共事業の落札で、米国企業に土壇場で敗戦したとされる(注10)。
■盗聴しやすい仕組み
UKUSA同盟5カ国だけでも、通信傍受基地は地球上にバランスの良い地理的条件で分布している。米国のウエスト・バージニア州シュガーグローブ基地とワシントン州ヤキマ基地は、北米、南米大陸の通信をカバーできる。ニュージーランド、ウェリントンのワイホパイの基地は主に二つのの太平洋通信衛星を対象に傍受し、太平洋、アジア領域の通信をカバーしている(注11)。
北イギリスのメンウィスヒルでは、米軍が所有し、運用している、最先端のコンピュータシステムと、傍受アンテナが設置されている。メンウィスヒル基地で働いている職員の殆どがアメリカ人で、幹部はNSA(米国家安全保障局)から派遣されている(注12)。
また、法律面でも、CALEA(Communications Assistance for Law Enforcement Act:通信傍受援助法)や、FISA(Foreign Intelligence Surveillance Act:外国諜報活動偵察法)など、通信傍受を正当化あるいは、援助するための法整備が確立している。
■盗聴正当化のための法整備
米国では法律上、NSAは米国内のみで完結する通信を傍受することは原則的に禁止されているが、外国発信の通信を米国内で傍受することは何ら制限がない。アメリカの盗聴件数は過去十年間に二倍になっている(注13)。
アメリカは、世界で最もインターネットの回線を所有している国であり、少なからず海外通信をアメリカ国内で傍受できるのが現状である。アメリカ国内で行われる盗聴でも、国内通信に限られることは、考えられない。近年、日本でも盗聴法成立の動きがある。この盗聴法は、アメリカの盗聴法である、「包括的犯罪取締及び街路安全法第3編」(注14)と「通信傍受援助法」、両方の内容を包合するものであり、アメリカ盗聴法より、一段と強力な権限を捜査機関に与えることになると、アメリカのNGOが警告している(注15)。
■CALEA(Communications Assistance for Law Enforcement Act)(注16)
1994年に通信傍受援助法(CALEA)が成立した。通信事業者、メーカーに対して、電話、FAX、パソコンなどの通信設備に盗聴可能な仕様を組み込むことを義務づけるというものである。この法律の成立の背景には、アメリカ副大統領(当時)ゴアの提唱するGII(The Global Information Infrastructure:世界情報通信基盤)構想の実現と、司法省の国際的なコンピュータ犯罪に対処すべく、他の諸国の司法当局と協議を盛んにしている、という動きが深く関与している、とされる(注17)。世界最大のアメリカ通信会社AT&Tがこれらの政策を指示しており、東京大学法学部教授の石黒一憲氏は、着々と進めてきた官民一体の合法的盗聴計画を「雪崩現象的なシナリオ」と分析している。
■FISAと大統領命令12,333号
2000年2月、NSAは「電子調査活動を行う際の諜報機関における法的基準」というレポートを議会に提出した。そこで、通信傍受の正当化のため重要な二つの法律が示された。
一つは、1978年外国情報活動監視法(Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978)である。この法律では、外国政府機関および外国人、外国勢力のエージェントとして雇われているあらゆる人物を対象にした、通信傍受、諜報活動は、大統領が司法長官を通じて、1年以内であれば裁判所の許可令状なしで電子的監視による情報の収集を正当化できるとされている。しかし、「合衆国の人物」がやりとりする通信は禁止している(注18)。
大統領命令12,333号(1992年に立法化)は、CIA、FBI、NSAなどの情報捜査機関に、外国の情報機関の活動に関する情報の収集をおこなう権限を与えている(注19)。しかし、インターネットや携帯電話の通信では、外国情報機関の活動の情報や、テロリストの犯罪捜査とは関係ない内容が殆どであり、アメリカ国内でもプライバシー侵害の批判がおこっている(注20)。
■あらゆる通信の米英経由
エシュロンは、世界中に通信傍受基地を建設、設置してきたが、1980年代から、アメリカ、イギリスから遠く離れた遠隔地の基地を使用しなくとも、米英領域内に居ながら世界中の通信を傍受できるシステムを作り上げた。そのシステムと傍受手段は大別して三つある。一つは、①コールバック通話システム、二つ目は、②インターネット通信傍受③裏口侵入方法による傍受である。③は①と②とは性格が違う。①と②方法は通信媒体に傍受装置の設置が必要であるが、③はNSAの本部や基地のコンピュータから、意図的、選択的に、世界中のコンピュータの情報を収集できる方法である。②と③の共通点はインターネットを利用した傍受システムである。
これら三つのシステムは、1980年代に始まった、世界的な通信事業自由化をきっかけに、形成された。それまでは、通信事業はどこの国も、国家が統制していたが、アメリカ、イギリスが先陣をきって、民間に移行し始めた。他の先進国も米英にならって、自由化を推し進めたが、自由市場においての米英系企業の優位性は崩れていない。どの国の通信会社よりも安価なサービスを達成し、確固たるブランドを築いている。よって、世界的な通信の自由化は、通信の米英集中をもたらしたのである(注21)。
■コールバック通話
1980年代まで、殆どの国が国家統制下であった通信事業の自由化で、先行したアメリカやイギリスには、第三国を経由して国際通話をおこなう「コールバック」事業者が多数登場した。この二国は、国際間の専用線がどこよりも安い。例えば、日本から隣の中国へ国際電話をかける場合、直接中国へかけるよりも、アメリカを経由した方が安い、ということになる。世界中の国際通話を米英経由となり、通信傍受装置を仕掛けると、地球上の大多数の人々のプライバシーが筒抜け状態になる(注22)。米英の国際通話のハブ機能化は米英領域内での「一見」合法的盗聴の促進をもたらしている。
■ドットコムバブルと通信の米英経由
インターネットでは、「米国経由」のながれが一層顕著である。「ドットコム」バブルが示すように、日本在住の個人や企業であっても、アメリカにサーバーをもつ例が多い。米国系プロバイダは世界中にアクセス・ポイントを拡大し、欧州系プロバイダでも、イギリスを中継点にしている大手業者がある
アメリカでは、FBI(Federal Bureau of Investigation:米国連邦捜査局)が「カーニボー」と呼ばれる電子メール収集装置を、アメリカ全土のプロバイダ内に設置しているとされる(注23)。これらの傍受装置は米英領域内に設置されているとはいえ、インターネット通信の米英経由が顕著なため、米英の国民以外の人物がやりとりする通信内容も、傍受されていることは否定できない。
■官民結託がもうけた裏口
アメリカは、インターネット通信網における優位性だけでなく、インターネットにつなぐ、コンピュータのシステムのシェアも独占している。OSは、ウインドウズ、CPUはインテル、パソコン本体もデルコンピュータ、コンパックといった具合に。シェアの独占は、当然製品の技術と仕様が世界の標準規格となりうる。そこで、米政府が、これら民間コンピュータ企業と結託し、アメリカのための通信傍受が行いやすいプログラムを製品に埋めこんでいるのではないか、という疑念が欧州で広がっている(注24)。
カナダのコンピュータ研究家が、世界中の大部分の企業や大学が導入しているマイクロソフト社のOS、「ウインドウズNT」の中に、「NSAKEY」という謎の項目を発見した。これは、NSAが傍受対象のコンピュータ内に侵入させるための、裏口「バックドア」の項目ではないかという疑念が広がっている(注25)。
■傍受方法
エシュロンシステムは、数種類の傍受システムから構成されている。一つは、マイクロ・タワーと、屋内に設置される辞書サイズの小型傍受装置を利用した地上通信と海底ケーブルの監視をするシステムである。また、地上から漏れる国際通信衛星に届く電波の監視もおこなっている。現在のところ、エシュロンの主なターゲットはインターネット通信中心のテキストデータであり、電子メール、ファックスそしてテレックスがその対象となっている。電話盗聴においては、会話中の言葉は特定できないまでも、音声認識による人物特定は可能となっている(注26)。
■地上通信とケーブルの傍受
国際通信へのアクセスには、回線ケーブルの傍受が最も初期から実施されている。1945年以来、NSAは主要なケーブル会社のトラフィックを把握してきた。これはコード・ネーム「SHAMROCK」と呼ばれる作戦で、ウォーターゲイト事件に関連した調査に出るまで30年ものあいだ知られていなかった。1975年に開かれた下院議会のパイク委員会の席上、NSAのアレン長官は、「NSAは組織的に、音声でもケーブルでも国際回線を傍受している」と初めて認めたのである (注27)。
その次に重要な国際通信へのアクセスは、高周波ラジオ(HF)帯域の傍受である。HF帯域は軍事外交用にもっとも利用される周波数であり、こうした帯域の通信にアクセスする拠点がイタリア、イギリスそしてトルコに配備されていたとされる(注28)。
■衛星による傍受
主要都市間を結ぶ極超短波通信については、スパイ衛星によって傍受されてきた。スパイ衛星とは、衛星で直接、通信を傍受するシステムである。
最初の衛星は、最大の標的は旧ソビエトであり、とりわけ地理的理由で地上ケーブルを用いることができないシベリア越えの情報の取得は、NSAに大きな利益をもたらしたと言われている。この衛星によるプロジェクトは予想以上の成果を上げたため延長され、ふたつの新しいタイプの衛星が1978年と79年に発射されている。この衛星は、1991年の湾岸戦争での活動で、有名な「砂漠の嵐」作戦ならびに「砂漠の盾」作戦に対する支援によって表彰を受けている(注29)。
1967年から85年にかけて、スパイ衛星の第二の世代が登場する。この衛星はオーストラリア中央部にあるのパイン・ギャップ基地でコントロールされている。これらの衛星のターゲットは、VHFラジオ、携帯電話、ポケットベル、自動車電話などである。
その次の第三世代は、極地の高度軌道で活動をおこなっている。第1世代や第2世代の衛星ではカバーできない北方地域の通信を傍受するために利用されている(注30)。
■対衛星通信傍受
民間の衛星(インテルサット)を通過する国際通信を盗聴する作戦は、1971年に始まった。ふたつの地上基地が建築され、ひとつはイギリスにあり、二つの30メートル級アンテナでそれぞれ大西洋上のインテルサットとインド洋上のインテルサットをターゲットにしている。もうひとつはワシントン州のヤキマにあり、これは太平洋上のインテルサットを標的とする。1980年にウエスト・バージニア州シュガーグローブに第三のアンテナ群が構築され、このネットワークは完成した(注31)。
■対インターネット傍受
1980年代以降、NSAとUKUSA同盟国は、インターネット上での通信においても大規模かつ国際的な盗聴活動をおこなっている(注32)。
標準的なインターネットのメッセージはパケット(データが小分けされたもの)の集合物である。これはIPアドレスと呼ばれる発信地と宛先情報を含む。このアドレスが個々のインターネットに接続されたコンピュータを特定する。
外国の通信諜報機関が関心を持つインターネット通信の内容は、電子メールとファイル転送である。ほとんどの米国の経由ポイントに毎秒多量のこうした通信データが流れ込む。NSAはインターネットの通信データを収集するために、9つの主要なインターネット経由ポイント(通称IXP、通信ケーブルが集中する中継点)に、1995年までに「スニッファー」と呼ばれる、パケットを捕捉するソフトウェアを設置した。設置された地域は主に西海岸と東海岸で、外国通信の最初と最後の通過ポイントをおさえている(注33)。
もっとも、こうした国際通信へのアクセスは、より多くのデータにアクセスする便宜も与えると同時に、あまりに大量の情報を提供する。そこで、「ディクショナリー」と呼ばれるデータベースを利用して、調査価値のある情報に厳選する。「ディクショナリー」には、「爆弾、テポドン、プロパガンダ」など、傍受対象の人物が使用しそうな言葉が登録されている。「ディクショナリー」に登録された通信内容だけがピックアップされる、いわゆる「サーチエンジン」と同じ仕組みである(注34)。
そしてここに「脱税」もしくは「租税回避」もしくは「違法送金」と入力すれば、確実にリストアップされる。もっとも、犯罪者がそれらの文字を入力する場合は考えられないから、捜査当局・敵対者グループからの情報収集(間接情報)ということになるのであるが・・・










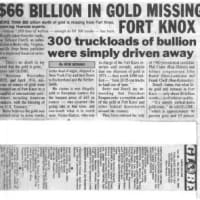




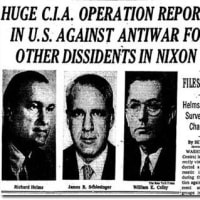

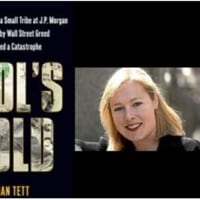

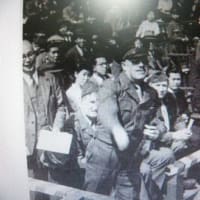
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます