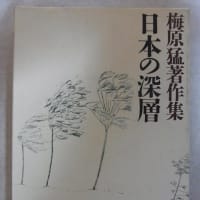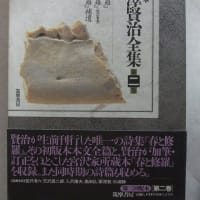“ 芭蕉は、弟子の木節に、「中頃の歌人は誰なるや」と問はれ、言下に「西行と鎌倉右大臣ならん」と答へたさうである(俳諧一葉集)。言ふまでもなく、これは、有名な真淵の実朝発見より余程古い事である。それだけの話と言つて了へば、それまでだが、僕には、何か其処に、万葉流の大歌人といふ様な考へに煩はされぬ純粋な芭蕉の鑑識が光つてゐる様に感じられ、興味ある伝説と思ふ。必度(きつと)、本当にさう言つたのであらう。僕等は西行と実朝とを、まるで違つた歌人の様に考へ勝ちだが、実は非常によく似たところのある詩魂なのである。”
『実朝』 小林秀雄(昭和18年)「現代日本文學大系」筑摩書房
鋭利で鮮やかな書出しと、詩と歴史の深淵にまで至ろうとする凄まじい意思を持つ小文だ。
『吾妻鏡』の「実朝横死」の記事を引きながら、小林はこう言う。
“ 吾妻鏡には、編纂者等の勝手な創作にかゝる文学が多く混入してゐると見るのは、今日の史家の定説の様である。上の引用も、確かに事の真相ではあるまい。併し、文学には文学の真相といふものが、自ら現れるもので、それが、史家の詮索とは関係なく、事実の忠実な記録が誇示する所謂真相なるものを貫き、もつと深いところに行かうとする傾向があるのはどうも致し方ない事なのである。 ”
「渡宋計画」には、“史家は、得て詩人といふものを理解したがらぬものである”と言い、合理的でわかったような気になれ、安心できる説明を斥けている。
例の「子の刻の青女(あををんな)」の記事にも、“僕は、この文章が好きである。”と言及されている。
二十首あまりの歌への評言もあるが、その選び方と読み取りは、人それぞれだ。
〔補遺2〕
ふたりの句と歌の詩人が、『実朝』の新作能を、それぞれ作っている。
① 高浜虚子 (1920年1月)
間(アイ)狂言が、「銀杏の葉の精」で、
“一葉梢をはなれたり。ひらひらと落つるなり。それが下葉を誘ふなり。二葉三葉と殖えて行き。誘ひつれ遊びつれ。日が当り影が出来。影が出来日があたり。露がぴかりと。ぴかりと露が。横に流れ縦に落ち。一葉二葉がだんだんに。千万といふ葉を誘ふ。”
などと、舞ひ歌ふ。
② 土岐善麿 (1950年1月)
喜多実(1900-1986)から、「大海の舞ともいうべきものを舞いたい」と要請されて作ったという。
(参考文献) 『新訂増補 能・狂言辞典』平凡社 , 『岩波講座 能・狂言 Ⅲ』岩波書店
〔補遺3〕
このブログのテーマが、「映画『東京家族』について」である事を、忘れているわけではない(笑)。

サンシャイン劇場開場十周年記念公演 『ロミオとジュリエット 劇場プログラム』(1988年9月4日~25日) ジュリエット・中嶋朋子