
気分で聴き分ける’70年代ロックの名曲シリーズ、今回は最終話:第46話です。
第46話 : 名盤もういちど
★ROBIN TROWER 「LIVE」 ロビン・トロワー 「ライブ」 (1975)
昔のロックを中心にして半分思い出話のような自選名曲シリーズも今回で一旦最終話とします。
その最終話は第1話で少しふれた名ライブ盤を再び登場させて締めたいと思います。
1976年リリースのこのアルバムはまさにロビン・トロワー自身だけでなく、ブルースロックとして、またギターをリーダーとするトリオ編成での同ジャンルにおいてのまさに最高傑作の1つとして後世にまで語り継がれる名作中の名作であると思います。なお第1話目でこのアルバムの曲を取り上げていますのでトロワーは再度の登場となりました。
ロビン・トロワーのギタリストとしての資質がとびきり優れているのは言うに及ばずですが、あとの二人のメンバーの力量にはほとほと感心させられる部分が多いのが、このトリオの真の素晴らしさだと思うのです。
まず、ボーカル&ベースのジェームス・デュワー。この人の素晴らしさはとにかくそのブルージーな歌声と節回しにあります。なんとも哀愁のあるそれでいてベタベタしないそのスタイルは賞賛されるべきものです。そしてベーシストとしては、あくまでもギターがリーダーであるバンドの一員であるという控えめながらもとても大切なポジションをしっかりとキープしている点がまさに理想的です。時には非常に難しい歌を歌いながらグルーヴの効いたベースラインを同時に弾きこなし、それによってリーダーのトロワーをギタープレイだけに専念させてあげられるほどの安定したプレイで縁の下の力持ち的貢献度が非常に高いメンバーであります。
もう一人、ドラマーのビル・ローダン。この人は当時としては大変高度なテクニックを持っていました。そしてトリオ編成におけるドラムスの立場をよく理解し実践しているのでとても頼もしい存在になっています。リフやフレーズの切れ目、ボーカルラインの切れ目など、一瞬、音が薄くなる事がトリオなど特に小編成のバンドの場合あるのですが、そんな時この人はすかさず音と音の隙間をうめるフレーズを叩きだします。この時のフレーズはいわゆるオカズではありません。メロディーと言ってもいいようなみごとな「つなぎ」です。
この瞬間に繰り出されるフレーズによってバンドは音がとぎれてスカスカになることから救われるのです。彼のドラミングは比較的手数(てかず)の多いタイプですが、このバンドのベーシスト同様、リーダーは誰か、ということをよく理解してプレイしています。そんなビルの美点はスローな曲においてもよく聞き取る事ができます。
さらに高度なテクニシャンとして、アップテンポの曲ではリズムをきりっと引き締めながら、華麗なオカズやキュー出しでバンドをグイグイと引っ張っていく様子は、このライブにおいてよく聞き取れるはずです。
さて、1曲目「TOO ROLLING STONED」ですが、前半のアップテンポの部分でのデュワーのボーカルの下でのベースラインは見事です。歌のノリを損なわずに、細かいラインをよく弾きこなしています。中間部(付点リズム)に入ってすぐの所、キーが上がりますがあのアイデアは最高です。これがあるために聴衆はここまで聞き慣れたリズムが変化した事を聴覚上実感するのです。
シェンカー・パティソンでこの曲が取り上げられましたが、大切なキーポイントであるこのキー上げをしていないのは何というばかげたアレンジでしょうか! シェンカーは好きですがこの部分で僕は落胆し、制作したプロデューサーのオンチぶりに泣かされます。
そしてこのライブ、まだ2曲目なのにいきなり最高のトラックとなります。
「DAYDREAM 」、ギターがこの世のものとは思えないほどの浮遊感をもって歌いまくります。デュワーの歌もさすがですが、この曲はトロワーのまさに独壇場といった感じです。歌が終わってからの変幻自在なギターワークは奇跡です。あまり言われないのですがこの人は当時のギタリストの中では一二を争うような早弾きプレーヤーだと思います。
スローにフレーズが流れるその一瞬をついてマシンガンのような高速フレーズがひょいと飛び出します。
4分55秒過ぎのコード・ストロークを聞いてください。8小節の後、そのストロークが倍速になります。この時のトロワーの右手の抜群の安定感は神がかり的ですらあります。
相当な興奮状態にあると思のですが、プレイは冷静ですね。そしてその嵐が止むと、こんどはロングトーンで陶酔の世界へ入っていきます。一つ一つの音が長くなり、意味を持ち始めます。聴衆は沈黙し、音楽はその頭上を宙へ宙へと向かって登り始めます。
この陶酔感こそ、この曲の命です。トロワーの最高の芸術が生れた瞬間です。
さすがに3曲目は軽めにこなす曲になりました。「ROCK ME BABY」です。ブルースギタリストとしての常道を行っている感じです。多少デュワーが軽いのはなぜでしょうか。曲調のせいでしょうか。あまりブルージーではありません。これが英国人のブルース表現なのかもしれません。全体に肩の力が抜けて、前曲の落ち込んだような感覚を吹き飛ばして、リセットしてくれたようです。
4曲目「LADY LOVE」、さらにテンポが上がってロック・コンサートとして盛り上がります。歌を歌いながらのデュワーのベースが見事です。
5曲目は幻想的なコードワークとゆったりとしたテンポで2曲目と共に深い意味を表現している「I CAN'T WAIT MUCH LONGER」です。広がりのある意味深なコードの響きの上に、デュワーの最高のボーカルが聞けます。ドラムスのシンバルに軽くフェイズをかけて独創的なバックをつけているローダンもなかなか名演だと思いました。
さて曲はノリのよいものに変わりました。内容やサイズからして明らかにドラムソロ用に作られた感じですが、案の定ローダンの感動的なドラムソロが後半を華麗に飾ります。
通常ドラムソロには二つのパターンがあります。ひとつは緩急自在にプレーヤーの感情のまま、作り出されるテンポが変化するタイプ。もう1つがテンポは一定に保ち、その枠の中でリズムを変化させるもの、です。
6曲目「ALETHEA」は後者のインテンポ・タイプのソロですね。聞き手は最初の歌の部分のテンポが耳に馴染んでいます。そのテンポ感を崩すことなく(ずっと足踏みでも手拍子でも続けていられる)ノリを壊さないまま聞けるこのタイプのソロは素晴らしく効果的なのですが近年はドラムスのハッタリが増えてきているのであまり聞けなくなったタイプです。ローダンは聞けば聞くほど込み入ったリズムをたくさん聞かせてくれます。テンポは一定、リズムは変化。これがキーポイントですよ。
最後は「LITTLE BIT OF SYMPATHY」 おそらく、ライブのセットリストではもっと多くの曲が演奏されたと思いますが(7曲じゃ少なすぎでしょ)、途中はカットしたにしてもこの曲でコンサートは締められたはずです。テンポが速く、曲調も終盤にふさわしく華麗です。
それにしてもトロワーのプレイは疲れを知らずにぐいぐいとここまで来ました。やはり本物はパワーがあります。ロングトーンから超早弾き、複雑なテンション・コードやリズミックなリフの連発、そしてシングルからダブルに燃え上がるストローク・プレイ。どれをとっても大変なパワーとテクニックが連続して放出されています。
ロビン・トロワーという男、その地味な性格とルックスの点でスター・プレーヤーにはなれないタイプですが、巷でよく言われる「ジミ・ヘン・フォロワー」という言葉だけでは到底表現できない、ギタリストの中のギタリストであり、多くのプレーヤー
にショックを与えたプレーヤーと言えるのではないでしょうか。
本作はそのギタリストがこれまた驚異的な実力と見識をもつ二人のバイ・プレーヤーの協力で成し遂げる事が出来たライブ・コンサートの最高の瞬間を記録した奇跡的な名アルバムです。
聞けば聞くほど味の出てくるライブ盤です。どうぞゆっくりと、できれば多少部屋を暗くして聞いてください。
ご訪問、ありがとうございました。
この最終話で短期連載「この曲が好き!特別企画70年代ロック」を終了いたします。
全96,800文字(原稿用紙242枚)にもおよぶ長文、失礼いたしました。
第46話 : 名盤もういちど
★ROBIN TROWER 「LIVE」 ロビン・トロワー 「ライブ」 (1975)
昔のロックを中心にして半分思い出話のような自選名曲シリーズも今回で一旦最終話とします。
その最終話は第1話で少しふれた名ライブ盤を再び登場させて締めたいと思います。
1976年リリースのこのアルバムはまさにロビン・トロワー自身だけでなく、ブルースロックとして、またギターをリーダーとするトリオ編成での同ジャンルにおいてのまさに最高傑作の1つとして後世にまで語り継がれる名作中の名作であると思います。なお第1話目でこのアルバムの曲を取り上げていますのでトロワーは再度の登場となりました。
ロビン・トロワーのギタリストとしての資質がとびきり優れているのは言うに及ばずですが、あとの二人のメンバーの力量にはほとほと感心させられる部分が多いのが、このトリオの真の素晴らしさだと思うのです。
まず、ボーカル&ベースのジェームス・デュワー。この人の素晴らしさはとにかくそのブルージーな歌声と節回しにあります。なんとも哀愁のあるそれでいてベタベタしないそのスタイルは賞賛されるべきものです。そしてベーシストとしては、あくまでもギターがリーダーであるバンドの一員であるという控えめながらもとても大切なポジションをしっかりとキープしている点がまさに理想的です。時には非常に難しい歌を歌いながらグルーヴの効いたベースラインを同時に弾きこなし、それによってリーダーのトロワーをギタープレイだけに専念させてあげられるほどの安定したプレイで縁の下の力持ち的貢献度が非常に高いメンバーであります。
もう一人、ドラマーのビル・ローダン。この人は当時としては大変高度なテクニックを持っていました。そしてトリオ編成におけるドラムスの立場をよく理解し実践しているのでとても頼もしい存在になっています。リフやフレーズの切れ目、ボーカルラインの切れ目など、一瞬、音が薄くなる事がトリオなど特に小編成のバンドの場合あるのですが、そんな時この人はすかさず音と音の隙間をうめるフレーズを叩きだします。この時のフレーズはいわゆるオカズではありません。メロディーと言ってもいいようなみごとな「つなぎ」です。
この瞬間に繰り出されるフレーズによってバンドは音がとぎれてスカスカになることから救われるのです。彼のドラミングは比較的手数(てかず)の多いタイプですが、このバンドのベーシスト同様、リーダーは誰か、ということをよく理解してプレイしています。そんなビルの美点はスローな曲においてもよく聞き取る事ができます。
さらに高度なテクニシャンとして、アップテンポの曲ではリズムをきりっと引き締めながら、華麗なオカズやキュー出しでバンドをグイグイと引っ張っていく様子は、このライブにおいてよく聞き取れるはずです。
さて、1曲目「TOO ROLLING STONED」ですが、前半のアップテンポの部分でのデュワーのボーカルの下でのベースラインは見事です。歌のノリを損なわずに、細かいラインをよく弾きこなしています。中間部(付点リズム)に入ってすぐの所、キーが上がりますがあのアイデアは最高です。これがあるために聴衆はここまで聞き慣れたリズムが変化した事を聴覚上実感するのです。
シェンカー・パティソンでこの曲が取り上げられましたが、大切なキーポイントであるこのキー上げをしていないのは何というばかげたアレンジでしょうか! シェンカーは好きですがこの部分で僕は落胆し、制作したプロデューサーのオンチぶりに泣かされます。
そしてこのライブ、まだ2曲目なのにいきなり最高のトラックとなります。
「DAYDREAM 」、ギターがこの世のものとは思えないほどの浮遊感をもって歌いまくります。デュワーの歌もさすがですが、この曲はトロワーのまさに独壇場といった感じです。歌が終わってからの変幻自在なギターワークは奇跡です。あまり言われないのですがこの人は当時のギタリストの中では一二を争うような早弾きプレーヤーだと思います。
スローにフレーズが流れるその一瞬をついてマシンガンのような高速フレーズがひょいと飛び出します。
4分55秒過ぎのコード・ストロークを聞いてください。8小節の後、そのストロークが倍速になります。この時のトロワーの右手の抜群の安定感は神がかり的ですらあります。
相当な興奮状態にあると思のですが、プレイは冷静ですね。そしてその嵐が止むと、こんどはロングトーンで陶酔の世界へ入っていきます。一つ一つの音が長くなり、意味を持ち始めます。聴衆は沈黙し、音楽はその頭上を宙へ宙へと向かって登り始めます。
この陶酔感こそ、この曲の命です。トロワーの最高の芸術が生れた瞬間です。
さすがに3曲目は軽めにこなす曲になりました。「ROCK ME BABY」です。ブルースギタリストとしての常道を行っている感じです。多少デュワーが軽いのはなぜでしょうか。曲調のせいでしょうか。あまりブルージーではありません。これが英国人のブルース表現なのかもしれません。全体に肩の力が抜けて、前曲の落ち込んだような感覚を吹き飛ばして、リセットしてくれたようです。
4曲目「LADY LOVE」、さらにテンポが上がってロック・コンサートとして盛り上がります。歌を歌いながらのデュワーのベースが見事です。
5曲目は幻想的なコードワークとゆったりとしたテンポで2曲目と共に深い意味を表現している「I CAN'T WAIT MUCH LONGER」です。広がりのある意味深なコードの響きの上に、デュワーの最高のボーカルが聞けます。ドラムスのシンバルに軽くフェイズをかけて独創的なバックをつけているローダンもなかなか名演だと思いました。
さて曲はノリのよいものに変わりました。内容やサイズからして明らかにドラムソロ用に作られた感じですが、案の定ローダンの感動的なドラムソロが後半を華麗に飾ります。
通常ドラムソロには二つのパターンがあります。ひとつは緩急自在にプレーヤーの感情のまま、作り出されるテンポが変化するタイプ。もう1つがテンポは一定に保ち、その枠の中でリズムを変化させるもの、です。
6曲目「ALETHEA」は後者のインテンポ・タイプのソロですね。聞き手は最初の歌の部分のテンポが耳に馴染んでいます。そのテンポ感を崩すことなく(ずっと足踏みでも手拍子でも続けていられる)ノリを壊さないまま聞けるこのタイプのソロは素晴らしく効果的なのですが近年はドラムスのハッタリが増えてきているのであまり聞けなくなったタイプです。ローダンは聞けば聞くほど込み入ったリズムをたくさん聞かせてくれます。テンポは一定、リズムは変化。これがキーポイントですよ。
最後は「LITTLE BIT OF SYMPATHY」 おそらく、ライブのセットリストではもっと多くの曲が演奏されたと思いますが(7曲じゃ少なすぎでしょ)、途中はカットしたにしてもこの曲でコンサートは締められたはずです。テンポが速く、曲調も終盤にふさわしく華麗です。
それにしてもトロワーのプレイは疲れを知らずにぐいぐいとここまで来ました。やはり本物はパワーがあります。ロングトーンから超早弾き、複雑なテンション・コードやリズミックなリフの連発、そしてシングルからダブルに燃え上がるストローク・プレイ。どれをとっても大変なパワーとテクニックが連続して放出されています。
ロビン・トロワーという男、その地味な性格とルックスの点でスター・プレーヤーにはなれないタイプですが、巷でよく言われる「ジミ・ヘン・フォロワー」という言葉だけでは到底表現できない、ギタリストの中のギタリストであり、多くのプレーヤー
にショックを与えたプレーヤーと言えるのではないでしょうか。
本作はそのギタリストがこれまた驚異的な実力と見識をもつ二人のバイ・プレーヤーの協力で成し遂げる事が出来たライブ・コンサートの最高の瞬間を記録した奇跡的な名アルバムです。
聞けば聞くほど味の出てくるライブ盤です。どうぞゆっくりと、できれば多少部屋を暗くして聞いてください。
ご訪問、ありがとうございました。
この最終話で短期連載「この曲が好き!特別企画70年代ロック」を終了いたします。
全96,800文字(原稿用紙242枚)にもおよぶ長文、失礼いたしました。



















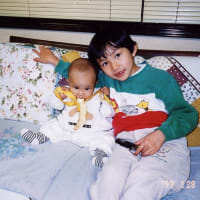
膨大な量の執筆、ごくろうさま!
いや~、あの時代は本当に良かったな。
今でも鮮明にあの頃を思い出せるよ。
70年代ハードロック、バンザイ!
ありがとう!
好み(選曲)にかなり偏りがあるのはご容赦。
まだまだいい曲、いいアルバムは目白押しなんだけど、大半がLP時代なんで、原盤が手元になくて思い出せないんだよね。
今後もこのシリーズ(主に70年代ハードロック)に書き足していくことになると思うよ。
よろしく頼みます。
'70年代の1976年から活動しているようだけど、音楽シーンには何ひとつ残していないよね。
歌詞も日本語もグダグダにして、中村雅俊まで洗脳してしまった桑田狂祖。 その悪行は日本ミュージックシーンから削除したいくらい。 あとユー◯ンの超抽象的世界観、空想じゃなく妄想。 デビュー当時「音楽出来るのは中流階級以上の家庭で育った人だけよね」と平気で週刊誌のインタビューに答えていて、それから- - -。
「問題」くまじー、松本孝弘、高中正義この三人の共通点はなーんだ?
「答」同じ誕生日。 3月27日。 お粗末でした。
ハハハ、お互いアンチ・クワタの身としては、その罪を論じても絶対にその功の部分は認められませんよね。
そもそも軽薄歌謡曲であり、ハードロックじゃないし・・・。
いくらマイナーであっても良いものは構わないけど、ふざけたバンド(ミュージシャン)は今後も糾弾こそすれ、ぜったいに取り上げないことをここに御誓い申し上げます!
認めないものは、認めない。 流石っす。
いや~くまさん、あなたの侵入の仕方がすごい!
70年代ロックを語っている時にそのコメントに「わざわざ」サザンを突っ込んできたパラノイア的攻撃手段に、単に嫌いと言うより強烈な憎しみさえ感じます。
どんなにヒットを放っても認めないものは認めない。
これぞ同世代の連帯感に通じます。
きれいな日本語のアクセントを若者に戻せ!
無視は最高の批判!