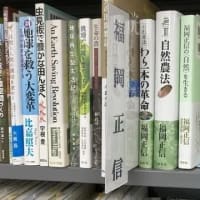茨城に引っ越して10年目にして(農繁期でずっとこの時期忙しくいけなかったため)、
念願の「筑波農林研究団地」の一般公開に4月17日(金)、18日(土)の2日間行ってきました。
近くに「つくば学園都市」があるのだから勉強?研究?にはもってこいの環境ですね。
阿見町“雑多”さの方が好きだけど。
子どもたちも興味津々?
彩葉(いろは)は小学校のため、18日のみ参加でした。
とてもまわりキレないので、絞って見学し、その一部をブログにUpします。
1日目、4月17日(金)は「農業環境技術研究所」「農業環境インベントリー展示館」。。
その他もっとまわる予定でしたが、内容が濃すぎて一カ所のみとなりました。

●国際土壌年ってなに?
農業環境インベントリーセンター 高田裕介氏
公演された「高田裕介」(農業環境技術研究所)さんは、
2015年5月発行の下記の本の著者のメンバーです。
『世界の土・日本の土は今』
地球環境・異常気象・食料問題を土からみると
・著者
日本土壌肥料学会 編
・出版
出版農山漁村文化協会(農文協)
●解説(詳細)農文協HPより
2013年12月に行われた国際連合総会において、12月5日を世界土壌デーと定め、2015年を国際土壌年とする決議文が採択された。決議文には「土壌は農業開発、生態系の基本的機能および食糧安全保障の基盤であることから、地球上の生命を維持する要」とあり、急激に進む砂漠化、土地劣化や干害などの解決を訴え、12月5日を「世界土壌デー」と定めた。
本書は、日本土壌肥料学会の第一線研究者が、地球上の土壌劣化の厳しい現実とともに、食も含めた我々の暮らしと土壌のかかわり、および課題を提起した書である。
●ミニ講演会&フィールド見学・ミニ農村
生物多様性研究領域 楠本良延氏
やっぱりフィールド・ツアーが楽しいですね!


このミニ農村を作るのに全力を注いだのは、
『ザ!鉄腕!DASH!!』の1コーナー「DASH村」のむらづくりアドバイザーの
守山弘さんだそうです。
下記『自然を守るとはどういうことか』(農文協、1988年)は、里山保全を考える上での古典ともいうべき本だそうです。
最近では『里山・遊休農地を生かす: 新しい共同=コモンズの形成の場』 (シリーズ地域の再生17) (農文協、2011年)

■農業環境インベントリー展示館






愛媛県の精錬所からの亜硫酸ガスによる農業への被害や
足尾銅山など各地における煙害関係資料が!


どこまで「土」を汚染し続けるような生活を続けるのか?
調査し続けなくてはいけない「問題」を起こしていること自体が(人間が)、最大の問題では!!
「土壌はかけがえのない、再生することができない資源です」
Healthy Soils for A Healthy Life.
国際土壌年2015&国際土壌デー12月5日のポスターより
専門家や研究者の領域と考えるのではなく、
一人ひとりが「土壌」について向き合うべきだと感じました。