今回も、デジタルコンテンツを使って授業を行う。
テレビにMacintoshを接続。

今回活用したのは5年前に作製したもの。
「鉄道が走る町の様子」のアニメーション。

手前の人々の様子から、時代の変化を様々気づかせる。

次に背景を提示し、バックが海だということに気づかせる。

海の上に、なにか石垣がつくられたことから、
何事が起きようとしているのか予想させる。
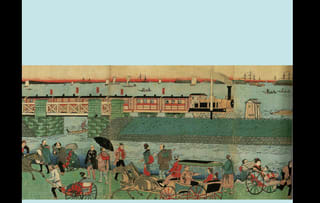
大きな汽笛とともに、左から右へ、機関車が走り抜ける。
子どもたちはびっくり。
=====================
なぜ、海の上を鉄道が走っているのか?
=====================
という疑問を持つ。
そこで、当時の鉄道敷設の様子がわかる資料を畳み掛けるように提示。

このブログの写真では分かりづらいが、どの鉄道も海の上を走っている。
=========================
・当時、政府は鉄道用の土地を買えなかったこと
(大きな反対があった)
・むりやり、海の上に鉄道を敷設したこと
・あまりの激務に、監督の外国人が過労死してしまったこと
=========================
を説明する。

ここで、子どもたちに問う、
=======================
どうして、明治政府は、こんなにも
鉄道を敷くことを急いだのでしょう?
=======================
子どもたちは
********************
・西洋に憧れていた
・西洋に追いつきたい
・文化が遅れている
・このままだと侵略される
・戦争になったら負ける。
********************
という意見を出す。
ここで課題を設定。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
政府は、西洋に追いつくために、
どのような政策を行ったのだろう。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
導入で提示した、鉄道敷設を
===========
輸送力を高める
===========
という言葉でまとめる。

次に、官営工場についての読み取り。
富岡製糸場の錦絵から、当時の様子について調べる。
=================
・外国人がいる
・たくさんの女性がいる
・機械がたくさんならんでいる
・天井が高い
=================
など、様々な読み取りを行う子どもたち。
当時の外国人指導者が、当時の総理大臣の7倍の給料をもらっていた
という話に、子どもたちは目が点になる。
当然、この富岡製糸場は大赤字だったのだが、
それでも、日本にとって良かったと子どもたちに伝える。
子どもたちはここでまた「なぜ?」と悩む。
その答えのヒントは教科書本文にある。
パワーポイントを活用しながら、説明する。

富岡製糸場は赤字だったが、ここで働いていた華族の子女たちが、自分の出身地へ戻り、
そこで知識や技術をふる活用して新しい事業を興していった。
それで、日本の産業が発展していった。
この官営工場建設を
========
産業力
========
とまとめた。

他にも、二つ明治政府の改革があることを伝え、
子どもたちに調べ学習をさせる。
短い時間であったが、子どもたちはしっかりノートにまとめることができた。
==============
◇徴兵令ーー軍事力
◇地租改正ーー経済力
==============

============
・輸送力
・経済力
・軍事力
・産業力
============
子どもの言葉で、なんとかこれらの言葉を引き出し(作り?)、
いよいよ学習課題のまとめ。
これらの4つの力を集めることで
=========
国 力
(こくりょく)
=========
を高めていったことをまとめた。

授業のまとめとして、子どもたちには
====================
自分が明治政府の役人だったら
どの改革に一番力をいれるか選びなさい
====================
と指示を出した。
子どもたちは、4つの中から一つをえらび、
理由をつけながらまとめていた。
ここで時間終了。
なんとか45分におさまった。
※
実は、この授業は自分が5年前に行った研究授業の指導案を基に行った。

その指導案
5年前は、今以上に未熟だった。
指導案を久々に見返しても、エゴに満ちている。
自分が教材研究した物(ネタ)は、できるだけ多く授業に取り入れようとしていた・・・。
正直、赤面。
今回はこの指導案の20%はカットして、授業を行った。
「これじゃあ、45分に収まらない」
「展開が濁る」
授業をして改めて思った。
ブログを続けていると、この時の様子も振り返られる。
5年前の記事を読んでいると、
子どもたちにいかに助けられていたのか、
自分の力のなさも、改めて分かった。
今の自分も
これから(数年後)の自分に論破されていくのでしょう。
・・・こうやって、本当に少しずつでも日々進歩していければいいなぁ。
テレビにMacintoshを接続。

今回活用したのは5年前に作製したもの。
「鉄道が走る町の様子」のアニメーション。

手前の人々の様子から、時代の変化を様々気づかせる。

次に背景を提示し、バックが海だということに気づかせる。

海の上に、なにか石垣がつくられたことから、
何事が起きようとしているのか予想させる。
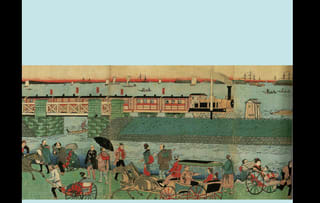
大きな汽笛とともに、左から右へ、機関車が走り抜ける。
子どもたちはびっくり。
=====================
なぜ、海の上を鉄道が走っているのか?
=====================
という疑問を持つ。
そこで、当時の鉄道敷設の様子がわかる資料を畳み掛けるように提示。

このブログの写真では分かりづらいが、どの鉄道も海の上を走っている。
=========================
・当時、政府は鉄道用の土地を買えなかったこと
(大きな反対があった)
・むりやり、海の上に鉄道を敷設したこと
・あまりの激務に、監督の外国人が過労死してしまったこと
=========================
を説明する。

ここで、子どもたちに問う、
=======================
どうして、明治政府は、こんなにも
鉄道を敷くことを急いだのでしょう?
=======================
子どもたちは
********************
・西洋に憧れていた
・西洋に追いつきたい
・文化が遅れている
・このままだと侵略される
・戦争になったら負ける。
********************
という意見を出す。
ここで課題を設定。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
政府は、西洋に追いつくために、
どのような政策を行ったのだろう。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
導入で提示した、鉄道敷設を
===========
輸送力を高める
===========
という言葉でまとめる。

次に、官営工場についての読み取り。
富岡製糸場の錦絵から、当時の様子について調べる。
=================
・外国人がいる
・たくさんの女性がいる
・機械がたくさんならんでいる
・天井が高い
=================
など、様々な読み取りを行う子どもたち。
当時の外国人指導者が、当時の総理大臣の7倍の給料をもらっていた
という話に、子どもたちは目が点になる。
当然、この富岡製糸場は大赤字だったのだが、
それでも、日本にとって良かったと子どもたちに伝える。
子どもたちはここでまた「なぜ?」と悩む。
その答えのヒントは教科書本文にある。
パワーポイントを活用しながら、説明する。

富岡製糸場は赤字だったが、ここで働いていた華族の子女たちが、自分の出身地へ戻り、
そこで知識や技術をふる活用して新しい事業を興していった。
それで、日本の産業が発展していった。
この官営工場建設を
========
産業力
========
とまとめた。

他にも、二つ明治政府の改革があることを伝え、
子どもたちに調べ学習をさせる。
短い時間であったが、子どもたちはしっかりノートにまとめることができた。
==============
◇徴兵令ーー軍事力
◇地租改正ーー経済力
==============

============
・輸送力
・経済力
・軍事力
・産業力
============
子どもの言葉で、なんとかこれらの言葉を引き出し(作り?)、
いよいよ学習課題のまとめ。
これらの4つの力を集めることで
=========
国 力
(こくりょく)
=========
を高めていったことをまとめた。

授業のまとめとして、子どもたちには
====================
自分が明治政府の役人だったら
どの改革に一番力をいれるか選びなさい
====================
と指示を出した。
子どもたちは、4つの中から一つをえらび、
理由をつけながらまとめていた。
ここで時間終了。
なんとか45分におさまった。
※
実は、この授業は自分が5年前に行った研究授業の指導案を基に行った。

その指導案
5年前は、今以上に未熟だった。
指導案を久々に見返しても、エゴに満ちている。
自分が教材研究した物(ネタ)は、できるだけ多く授業に取り入れようとしていた・・・。
正直、赤面。
今回はこの指導案の20%はカットして、授業を行った。
「これじゃあ、45分に収まらない」
「展開が濁る」
授業をして改めて思った。
ブログを続けていると、この時の様子も振り返られる。
5年前の記事を読んでいると、
子どもたちにいかに助けられていたのか、
自分の力のなさも、改めて分かった。
今の自分も
これから(数年後)の自分に論破されていくのでしょう。
・・・こうやって、本当に少しずつでも日々進歩していければいいなぁ。









