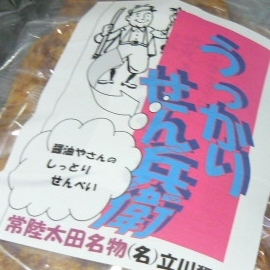業務スーパー鹿嶋店で、職場の年末年始対策で、うまい棒を7種類、各一袋、210本購入しました。まあ、この話は本題と関係ないので割愛します。以前から、売り場の一角が空になっていて、フライまんじゅうと書いてあったのが気になっていました。この買物時に現物を発見し、¥102でした。買ってから商品をよくよく見ると、「体に悪そー(笑)」。でも、これが大人気なんですね。いつも売り切れですし。こしあんの入った、小麦の饅頭を油で揚げた素朴な菓子です。この油が袋にべっとり・・・。8個入りでした。体に悪いんだけど、揚げ菓子は、やっぱり旨いなぁ。懐かしい味ですね。業務スーパーを展開する、神戸物産の本拠の兵庫県の特産品のようです。
農山漁村文化協会著/日本の食生活全集8巻「聞き書・茨城の食事」という本があります。1980年代に刊行していまして、『茨城』の場所に、各都道府県名が入って、全部で50冊近いシリーズです。大概の図書館に置いてあります。このシリーズは、各地の郷土料理を土地の年配者から聞き込んだ情報が本になっています。私のブログでも頻繁に参照しています。さて、「埼玉の食事」には、『ふらい』が載っていません。代わりに『たらし焼き』が載っています。この本の『たらし焼き』は、「フライパンに水溶き小麦粉たらして、ネギなどの具材と共に焼き・・・」と書かれています。行田の『ふらい』は、基本的にこの流れから変わっていないので、『ふらい』の作り方と置き換えて問題ないでしょう。ただし、この文章では、砂糖を入れるとあり、これは近年、栃木県南部にソースメーカーが二社ほどあることから、その影響で味付け方法に変化がもたらされたのではと推測できます。それに比べて、『たらし』は鉄板(ホットプレート)で調理します。座卓ですよね。家庭で、手軽に鉄板焼きができるホットプレート。飲食店より家庭で作る方が圧倒的に認知度が上がるのが当たり前です。『たらし』は、ホットプレート誕生までよく生き延びたものです。ホットプレートの誕生が10年遅れていたら、『たらし』は滅亡していたのではないでしょうか。『たらし』が家庭に入ってきた年代、これなんかも調査テーマとしては重要なのではないでしょうか。
以前、土浦の有名などら焼き専門店「志ち乃」で、帰省の時に土産に大量のどら焼きを買ったことがありました。様々などら焼きの中で、「手亡」というのがあり、そのときは何のことか判りませんでした。最近、いろいろな和菓子に、手亡が使われていることが判り、調べてみました。どうやら、白餡を作る、豆で白インゲン豆の別称らしいことがわかりました。白インゲン豆といえば、今年5月のTBSのテレビ番組のダイエット騒動が思い浮かびますね。ダイエットにも良い成分が入っていると注目された食品です。ですが、白餡としては紹介しなかったのかな。番組内容は判らないんですけど。砂糖も入れますからダイエットにはならないと思うけど。手亡=白餡=白いんげんと覚えておくと、便利かも?。
「もんじゃ」の歴史について。以前、テレビ番組で、群馬県伊勢崎市は、もんじゃ焼きの店が多いということをやっていました。たぶん、当ブログでも紹介したと思います。そして、放送中に東武伊勢崎線を伝って、浅草界隈から、もんじゃブームが波及したという説が紹介されていました。私も迂闊でした。ろくに裏を取っていませんでした。東武伊勢崎線全通開通は1968年なんです。1965年にはじめて、群馬県に進出しています。このことから、伊勢崎と浅草界隈、両方に発祥の地説ができたとおもわれます。群馬県は饂飩の産地で余った小麦粉の有効利用が群馬説といわれています。この話を論じるときに必ず出てくるのが、東武伊勢崎線です。しかし、開通は、たかだか40年弱前なんですね。この程度の短いスパンで食文化が果たして波及するものなのか。インターネットなんて無い時代ですからね。このことから、たまたま、違う場所で発祥したんじゃないでしょうか。ちなみに、北千住から久喜までは1955年に開通しています。久喜でも、もんじゃ焼きが盛んらしいので、これは興味深い点です。加須には、1958年に開通し、加須や行田に目立った、もんじゃ文化がない点、そして、明治から続く、行田近郊のふらいの文化。ここに、伊勢崎線伝達説の弱点があります。おそらく、もんじゃ文化は、東京から北上し、加須・行田で消滅。どうでしょうかね、この仮説。いずれにしても、もんじゃ焼きの原型の、文字焼きは明治時代という説が大半です。その場所は、東京説も群馬説もありなのではないでしょうか。最後に補足として、群馬と東京のもんじゃは若干違いがあるそうです。
おからというのは、昔から粗末な扱いを受けてきました。だから名前がありません。「おから」というのは、茶殻のように、豆腐を作る課程の不要なものというような意味の「がら」や「から」を丁寧に表現したに過ぎません。現在では、東日本で「卯の花」、西日本では「きらず」と呼ぶようです。先日の別の記事で、「おから」をATOKで変換した場合、「雪花菜」と変換されたんで、『=(イコール、ソフトバンクじゃないですよ)』だと思いこんで使ったのですが、これの読みは、おそらく「きらず」です。はっきりしないので、今後は「卯の花」を使うようにします。「卯の花」は、陰暦の四月を卯月といいます。このころにウツギの白い花が咲くらしいのです。これに似ていたためだと思われます。陰暦の4月と言えば初夏で、この時期に雪の花という表現は妥当ではないでしょう?。関東では夏を、関西では冬を連想する食べ物、おそらくそういうことだと思います。「きらず」は包丁を使わずに調理できることから来ています。いずれにしても、この二つの呼称は、「おから」の調理後の名称でもあるので、「おから」の別名とは言い難い面もあります。「おから」は、家庭での調理が難しい素材だと、個人的には思っています。驚くほど水分を吸って増えるからです。味付けが難しい。逆に言うと、素材のうまみを吸収しやすいと言うことで、魚のワタを抜いて、おからを詰める郷土料理もあります。
先日書いたように、行田市の白木堂というパン屋のメロンパンは、一般的なものと異なっていました。メロンパンが登場したのは、文明開化の明治時代後期と思われます。パン業界は、「俺が作ったんや」と誰かが叫べば、それが事実になってしまう風潮があるそうで、××がはじまりというのが、メロンパンについても何十通りもあるそうです。しかし、当時から、パン生地の上に甘いビスケット生地を乗せた形だったと言われています。そして、洋食店のライスを成形する半楕円形の金型を使って焼き上げていたため、ラグビーボールを半分に割った形で、さらに楕円形の頂点から頂点に筋を付けた模様になっていまして、当時、メロンとも言われていた、マクワウリに似ていたために、メロンパンと呼ばれるようになりました。中に餡やクリームが入ったものがあったというのも現代と通じるものがあります。その後、日の出をモチーフにしたサンライズというパンが登場します。材料は同じで形が違うだけです。大正時代に新たに輸入されたマスクメロン(はじめは筋がないのでプリンスメロンか?)がメロンの主流となり、楕円メロンパンは衰退し、いつしか、サンライズをメロンパンと呼ぶそうになったそうです。以上が、通説だそうです。そして、長い歴史の中でメロンパンはいくつもの亜種を生み出しました。ですから、パン生地+ビスケット生地なら、メロンパンと言っていいようです。白木堂のものは、パン生地の中央を窪ませ、ビスケット生地を敷いて、マーガリンと砂糖を混ぜたものが乗っています。これは、マーガリンメロンパンという種類で、通常は、一般的なメロンパンの上に切り込みを入れてマーガリンを載せるのだそうです。美味しい食べ方は軽くレンジで温めることで、溶けたマーガリンが生地に染み込むのを楽しむのだそうです。なかなか、メロンパンは奥が深いです。
熊谷に本店をもつ、和洋菓子の店、梅林堂で売られていた大福です。行田店で購入しました。4個入りで税別¥520でした。そうすると一個あたり¥130ですね。土産に買おうと思いましたが、「当日中にお召し上がりください」とあったので諦めました。まあ、こんな高級品を買う相手もいないし(笑)。そういった理由だと思いますが、Webショップに掲載されていません。製法や原料はよく判らないんですが、自然な海塩を使っているそうです。適度な塩分が甘さを引き立てています。おそらく、これが、この地方で塩あんびんと呼ばれているものではないでしょうか。塩あんびん、または、あんびん餅は、塩豆の入った餡を餅で包んだ、大福より大きめの食べ物です。適度な塩分は、甘さを引き立てますので、砂糖が高級品だった時代の知恵だと考えられます。
行田及びその周辺で見られる、『ふらい』という食べ物は、生地だけを先に焼いて、途中から、豚肉や葱などの具材を加えて、さらに焼きます。簡易的なお好み焼きで、ソースか醤油をかけ、青海苔や唐辛子を振りかけて食します。全てではないでしょうが、足利市の月星食品のソースが最適と言われています。太田の焼きそばにもよく使われるそうですが、佐野のイモフライには、佐野市の早川食品のソースがよく使われるそうです。購入しようと思ったのですが、行田市内のスーパーには置いていませんでした(ベルクとエコス)。このことから、醤油よりもソースかなと思います。写真は奥が、「ふらい」右が「卵入りふらい」、手前が、「ゼリーフライ」です。かねつき堂のものです。行田市内及び周辺に20~30店舗ほどあります。
和歌山市に近い、臨海の街「有田市」は、太刀魚が特産です。この商品は、有田かまぼこ協業組合で発売している、薩摩揚げの一種です。太刀魚を骨ごと使っているのでカルシウムが豊富です。頭と内臓を除いた太刀魚を骨ごとミンチにして、塩や調味料で味を調え油で揚げた物で、食感や風味は、つみれに近いです。つみれを油で揚げた感じですかね。ほねくの語源は、「骨くり天ぷら」の略だそうです。私は、「おでん」ではなく、袋ラーメンの具としました。塩ラーメンでしたけど、結構いけます。チャーシューの代わりです・・・。
日本テレビの某番組で登場していたので買ってみました。ジャスコ鹿嶋店で以前より見かけていたのですが正体がわからず購入を躊躇っていた商品です。写真の製造元は愛媛県のヒサシ水産です。まず、どんなものか。原材料は、光を出して泳ぐ『ホタルジャコ』と『ヒメチ(ヒメジ?)』が主な物で、頭と内臓を取って、骨ごとミンチにした物を、板状に形を整えて油で揚げた物で、DHAやカルシウムが豊富に摂れるそうです。もともと、愛媛県南西部、南予と呼ばれる地域の八幡浜や宇和島で、江戸時代から続く郷土料理だそうです。現在では、アジやタラなどの魚肉で嵩まししているみたい。食べてみると、さつま揚げと代わらないけど、多少堅めですが、おでんでも、ラーメンでも合いそうな味です。3枚で¥200くらい。