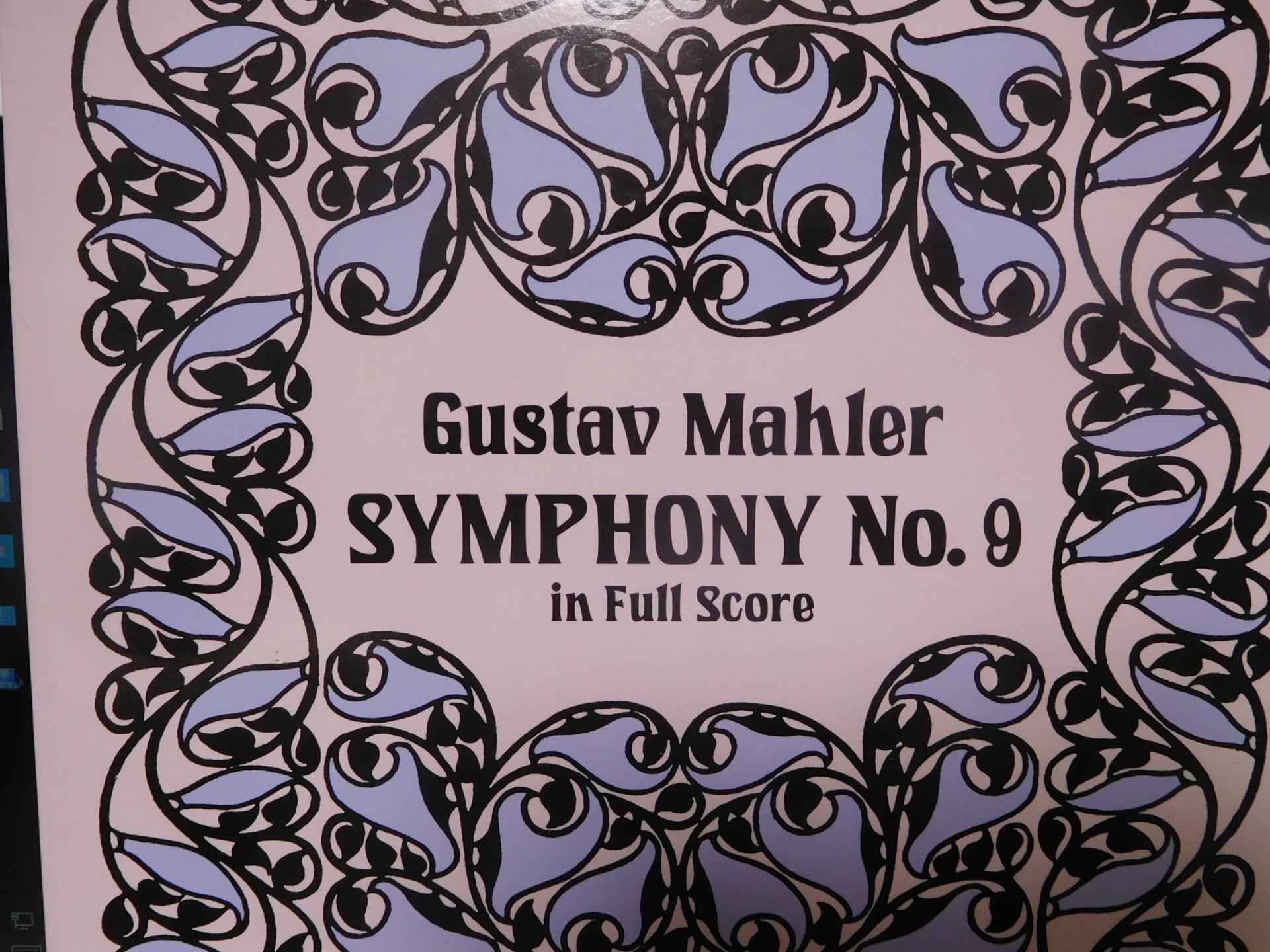マリス・ヤンソンス率いるバイエルン放送交響楽団のコンサートを聴いた(11/26ミューザ川崎・11/27サントリーホール)。
一時期、体調不良が伝えられていたヤンソンスだが、ミューザのステージにはにこやかに登場。
「颯爽」というには足取りはやや重そうだったが、あの笑顔があれば何も言うことはない。
ハイドンの交響曲第100番『軍隊』はスタイリッシュで楽し気で、近代以降に書かれた大規模な「戦闘的」交響曲を
時代を先取りして揶揄していたような、軽やかなユーモアが感じられる。
第4楽章では打楽器隊が客席を行進し、大太鼓には「We💛Japan」のステッカーがお茶目にも貼られていた。
ハイドンの洗練と瀟洒、ヤンソンスの日本への友情がミックスしたイントロダクションだった。
R・シュトラウス『アルプス交響曲』は、先日ティーレマンとシュターツカペレ・ドレスデンによる演奏を聴いたばかり。
ミューザの音響とこの大規模編成のシンフォニーは相性がよく、カウベル、チェレスタ、風音器やカミナリ音などの演劇的なディティールも素晴らしく映えた。
ティーレマンが英雄的なアルプスを描写したのに対し、ヤンソンスは太陽のもとにある人間の素朴な偉大さ、
逆境にあっても挫けない、登山者の克己心を表していたように感じられた。
ヤンソンスは1943年生まれの73歳の巨匠だが、世代的にもクラシック音楽というジャンルが
戦禍によって一度解体され、深刻な傷を負ったものだという歴史観があるのだと思う。
20世紀の大戦では、多くの指揮者、オーケストラがダメージを受け、人間の作り出した最も良質な文化が傷つけられた。
ドイツのオーケストラにも同じことが言えるだろう。欧州の中で「人間性」ということの吟味を、最も逼迫した課題として引き受けていることがオーケストラの音から感じ取れる。
ミューザの一階席で聴くと驚異的なシンフォニーで、巨大な太陽と風雨、干し草の香りや家畜の鳴き声を浴びた心地がした。
サントリーホールでのマーラー『交響曲第9番』は筆舌に尽くしがたい演奏だった。
この曲をある種の文明批評として解釈した演奏に何度も触れてきて、それに納得していたのだが、
ヤンソンスの解釈は「マーラーその人の人生」に惜しみなく接近し、そのシンパシーに染められていたと感じた。
一楽章の冒頭のクラリネットの音が、生まれたばかりの赤ん坊が揺り籠の中で聴く子守歌に聴こえ、
弦とハープと溶け合ってこの上なく優しく優雅なハーモニーを醸し出した。
ヤンソンスは手で何か丸いものを描いて、風船のように飛ばしていく仕草をしていた。
彼の指揮を見ていて、右利きなのか左利きなのか知りたくなったが
基本的に右手に指揮棒を持っているのだが、しょっちゅう左手に指揮棒を持ち替え、素手の右手を動かしているのである。
マーラーのこのデリケートな音楽を作り出すためには、指揮棒という道具は時折邪魔になっていたのかもしれない。
マーラー特有の、急に曲調が変わる場面も、ヤンソンスは子供が夜に見る夢のように
自然なイメージの変化として顕していた。
何かグロテスクなものが乱入してくるような表現ではなかった。
長大な一楽章から感じたのは、ヤンソンスのマーラーに対する、一種「母性的な」愛情で
作曲家の分裂症的な気質と、それゆえに現世において感じていた苦痛をすべて包み込んでいるようだった。
マーラーの音楽には「生まれてはみたけれど、まだ生きると決めたわけではない」といった
胎内回帰願望というか、タナトスの欲動というか、霊的に迷っている感覚がつねにある。
音楽という魑魅魍魎とした世界においては、その混迷の感覚は放蕩的なまでの霊感の宝庫であったはずだが
現実における「生きづらさ」は想像を絶するものがある。
肉体が、精神にとっての居心地のよい居場所ではないのだ。
(そういう人間の挙動不審を、マーラーをモデルにしたヴィスコンティの映画でダーク・ボガードは実にうまく演じていた)
9番は、50歳を間近に迎えたマーラーが、まだ生きようか生きるのを拒否しようか夢うつつの精神にありながら
いよいよ本物の死を受け入れるまでの、詳細なストーリーが記されている。
第2楽章は、1楽章で幼少期を終えたマーラーの意識が、若者の生命を得て
集団的な狂騒へと溶け込んでいくダンスであった。
思春期から青年期へ、木管とホルンの善良な響きが青年マーラーの声に思えた。
バイエルン放送響の合奏は真剣で、変幻自在のリズムを乗りこなし、微かな乱れもなく、膨らんだり縮んだりして、ハーモニーの明度と彩度を変化させていった。
それ以上に狂騒的な3楽章は、指揮者としての地位を上り詰め、山小屋で作品を量産し
ただ生きて、創造するしかなかった壮年期のマーラーで、
引き返したいが、引き返す余裕もなく、直進していく作曲家の悲鳴のような、女々しさをかき消された雄々しい響きだった。
3楽章でのヤンソンスは、指揮棒を奮うことを躊躇せず、恐るべき若々しさでこの反抗的な楽章を振った。
その猪突猛進の先には、既に死の色彩が帯のように見えている。
4楽章のアダージョは、「これが死か…」という溜息とともに聴いた。
ヤンソンスは長めの呼吸をとったあと、決然と、万感を込めて、懐かしい響きを弦セクションから引き出した。
これは呼吸の音楽なのだ。訳も分からず最初の呼吸を得て産声をあげた一人の人間が
生の意味を理解できぬまま、苦闘し悶絶し、最後の息を引き取るまでの一部始終を、目前で見せられている心地がした。
サントリーの一階前方席のありがたみをこの日ほど感じたことはない。
ヴィオラとチェロの、エモーショナルでソロイスティックな音が「矢も楯もなく」あふれだしてくるのを耳がとらえ、
有機的な生命体としてのオーケストラの凄みを体感することが出来た。
木管も金管も、「呼吸の追わり」へ向けて、惜別のサウンドを提供してくる。
そのとき、モノクロ写真のマーラーの肖像が、起こっているすべての出来事に対して
「ありがとう」と微笑を浮かべているのが目に浮かんだ。
冗談みたいな話だが、音楽の脈拍が落ち、息がいよいよ終わりに近づき
天国の光が差し込んできたとき、マーラーがそこに降りてきて、魂の報いに感謝していると「実感」したのだ。
霊魂は不滅なのか…すべてが闇に落ちたあと、雷の拍手を浴びたヤンソンスは、
「作曲家を心から愛さずにいることなどできるだろうか?」という微笑を見せた。
特別なことがたくさん起こった11月の演奏会の中でも、最も特別な日であった。
一時期、体調不良が伝えられていたヤンソンスだが、ミューザのステージにはにこやかに登場。
「颯爽」というには足取りはやや重そうだったが、あの笑顔があれば何も言うことはない。
ハイドンの交響曲第100番『軍隊』はスタイリッシュで楽し気で、近代以降に書かれた大規模な「戦闘的」交響曲を
時代を先取りして揶揄していたような、軽やかなユーモアが感じられる。
第4楽章では打楽器隊が客席を行進し、大太鼓には「We💛Japan」のステッカーがお茶目にも貼られていた。
ハイドンの洗練と瀟洒、ヤンソンスの日本への友情がミックスしたイントロダクションだった。
R・シュトラウス『アルプス交響曲』は、先日ティーレマンとシュターツカペレ・ドレスデンによる演奏を聴いたばかり。
ミューザの音響とこの大規模編成のシンフォニーは相性がよく、カウベル、チェレスタ、風音器やカミナリ音などの演劇的なディティールも素晴らしく映えた。
ティーレマンが英雄的なアルプスを描写したのに対し、ヤンソンスは太陽のもとにある人間の素朴な偉大さ、
逆境にあっても挫けない、登山者の克己心を表していたように感じられた。
ヤンソンスは1943年生まれの73歳の巨匠だが、世代的にもクラシック音楽というジャンルが
戦禍によって一度解体され、深刻な傷を負ったものだという歴史観があるのだと思う。
20世紀の大戦では、多くの指揮者、オーケストラがダメージを受け、人間の作り出した最も良質な文化が傷つけられた。
ドイツのオーケストラにも同じことが言えるだろう。欧州の中で「人間性」ということの吟味を、最も逼迫した課題として引き受けていることがオーケストラの音から感じ取れる。
ミューザの一階席で聴くと驚異的なシンフォニーで、巨大な太陽と風雨、干し草の香りや家畜の鳴き声を浴びた心地がした。
サントリーホールでのマーラー『交響曲第9番』は筆舌に尽くしがたい演奏だった。
この曲をある種の文明批評として解釈した演奏に何度も触れてきて、それに納得していたのだが、
ヤンソンスの解釈は「マーラーその人の人生」に惜しみなく接近し、そのシンパシーに染められていたと感じた。
一楽章の冒頭のクラリネットの音が、生まれたばかりの赤ん坊が揺り籠の中で聴く子守歌に聴こえ、
弦とハープと溶け合ってこの上なく優しく優雅なハーモニーを醸し出した。
ヤンソンスは手で何か丸いものを描いて、風船のように飛ばしていく仕草をしていた。
彼の指揮を見ていて、右利きなのか左利きなのか知りたくなったが
基本的に右手に指揮棒を持っているのだが、しょっちゅう左手に指揮棒を持ち替え、素手の右手を動かしているのである。
マーラーのこのデリケートな音楽を作り出すためには、指揮棒という道具は時折邪魔になっていたのかもしれない。
マーラー特有の、急に曲調が変わる場面も、ヤンソンスは子供が夜に見る夢のように
自然なイメージの変化として顕していた。
何かグロテスクなものが乱入してくるような表現ではなかった。
長大な一楽章から感じたのは、ヤンソンスのマーラーに対する、一種「母性的な」愛情で
作曲家の分裂症的な気質と、それゆえに現世において感じていた苦痛をすべて包み込んでいるようだった。
マーラーの音楽には「生まれてはみたけれど、まだ生きると決めたわけではない」といった
胎内回帰願望というか、タナトスの欲動というか、霊的に迷っている感覚がつねにある。
音楽という魑魅魍魎とした世界においては、その混迷の感覚は放蕩的なまでの霊感の宝庫であったはずだが
現実における「生きづらさ」は想像を絶するものがある。
肉体が、精神にとっての居心地のよい居場所ではないのだ。
(そういう人間の挙動不審を、マーラーをモデルにしたヴィスコンティの映画でダーク・ボガードは実にうまく演じていた)
9番は、50歳を間近に迎えたマーラーが、まだ生きようか生きるのを拒否しようか夢うつつの精神にありながら
いよいよ本物の死を受け入れるまでの、詳細なストーリーが記されている。
第2楽章は、1楽章で幼少期を終えたマーラーの意識が、若者の生命を得て
集団的な狂騒へと溶け込んでいくダンスであった。
思春期から青年期へ、木管とホルンの善良な響きが青年マーラーの声に思えた。
バイエルン放送響の合奏は真剣で、変幻自在のリズムを乗りこなし、微かな乱れもなく、膨らんだり縮んだりして、ハーモニーの明度と彩度を変化させていった。
それ以上に狂騒的な3楽章は、指揮者としての地位を上り詰め、山小屋で作品を量産し
ただ生きて、創造するしかなかった壮年期のマーラーで、
引き返したいが、引き返す余裕もなく、直進していく作曲家の悲鳴のような、女々しさをかき消された雄々しい響きだった。
3楽章でのヤンソンスは、指揮棒を奮うことを躊躇せず、恐るべき若々しさでこの反抗的な楽章を振った。
その猪突猛進の先には、既に死の色彩が帯のように見えている。
4楽章のアダージョは、「これが死か…」という溜息とともに聴いた。
ヤンソンスは長めの呼吸をとったあと、決然と、万感を込めて、懐かしい響きを弦セクションから引き出した。
これは呼吸の音楽なのだ。訳も分からず最初の呼吸を得て産声をあげた一人の人間が
生の意味を理解できぬまま、苦闘し悶絶し、最後の息を引き取るまでの一部始終を、目前で見せられている心地がした。
サントリーの一階前方席のありがたみをこの日ほど感じたことはない。
ヴィオラとチェロの、エモーショナルでソロイスティックな音が「矢も楯もなく」あふれだしてくるのを耳がとらえ、
有機的な生命体としてのオーケストラの凄みを体感することが出来た。
木管も金管も、「呼吸の追わり」へ向けて、惜別のサウンドを提供してくる。
そのとき、モノクロ写真のマーラーの肖像が、起こっているすべての出来事に対して
「ありがとう」と微笑を浮かべているのが目に浮かんだ。
冗談みたいな話だが、音楽の脈拍が落ち、息がいよいよ終わりに近づき
天国の光が差し込んできたとき、マーラーがそこに降りてきて、魂の報いに感謝していると「実感」したのだ。
霊魂は不滅なのか…すべてが闇に落ちたあと、雷の拍手を浴びたヤンソンスは、
「作曲家を心から愛さずにいることなどできるだろうか?」という微笑を見せた。
特別なことがたくさん起こった11月の演奏会の中でも、最も特別な日であった。