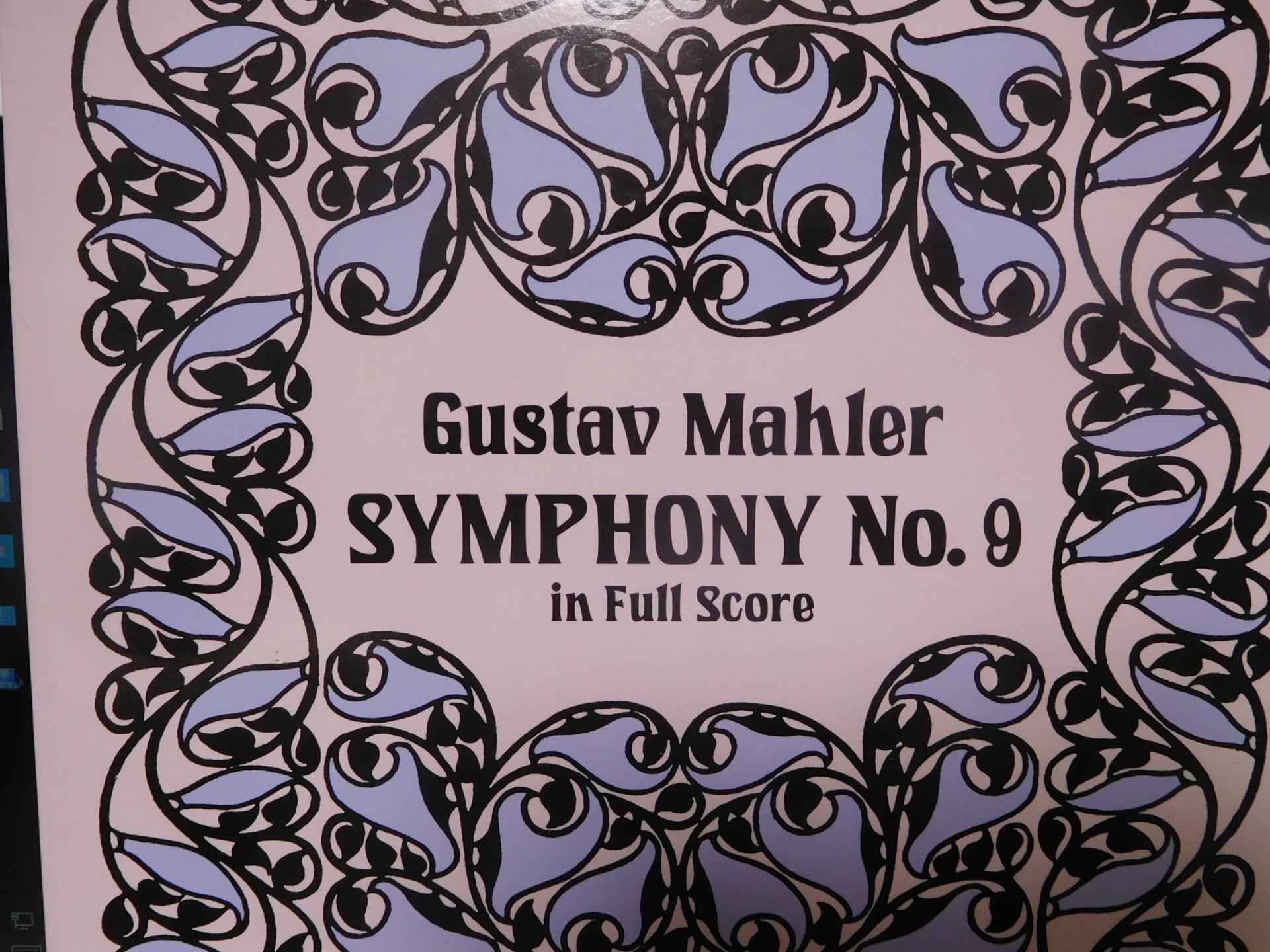フルシャ×都響の第九は最終日のサントリーホールの公演を聴いた。
超満員のソールドアウトで、なんとかチケットを購入させていただき一階前方で聴いたが、ステージと地続きになっているような聴覚体験で、床から熱い湯気が立っている熱感覚を得た。
フルシャにインタビューをするため、数日前に稽古を見学したのだが、上野の稽古場でも、実は同じ経験をした。音がすごい勢いで床に共鳴し(壁や天井ではなく)、
ティンパニだけでなく弦も管も、椅子から臀部に伝導し、臓器に響いてくるのだった。
オケが乗っている同じ床の上で聴いていたから当然のことかも知れないが、サントリーの本番でも音の重心が下にあり、特に1楽章と2楽章は臍から下に響いた。
とても肉体的なベートーヴェンで、最初から形而上的な世界へ行くのではなく「まず地上の人間ありき」という音楽に感じられた。
稽古を見学したときに思ったのは、やはり都響は「うまい」ということだった。
フルシャはほぼ出来上がっている第九の、細かいアーティキュレーションを修正し
その都度歌って聴かせたり、面白いトークをしたり、不思議な沈黙の後に爆笑をとったりしていたが、
本番では稽古のときに語ったり歌ったりしたことを、より激しくなったジェスチャーで再び伝えていたのが見事だった。
稽古のあとの取材で、フルシャが本当にプレイヤーを尊敬していること、彼が考える指揮者の役割についてなど聞いたが
音楽について「本能」「直観」という言葉が出てきたのにはっとした。
スコアの知的分析と同時に、本能と直観をハーモニーさせることが指揮者としての「美に到達するための作業」だと語ってくれた。
都響の第九にはフルシャの知性とともに本能と直観が貫かれていて
凄い緊張感で完璧な演奏をしたティンパニの久一さんが、フルシャの肉体感覚と一部始終つながっていた。
二楽章は本番であんなに野性的になるとは想像していなかったが、ベートーヴェンの痙攣的なフレーズがダイレクトに強調され、短い休符が完璧に真空になるのが見事だった。オケの集中力が尋常でない。
ベートーヴェンの極端な痙攣性は、古楽的な拍節感で切り込んでいくのがトレンドであるような気もするが、それより大きな編成で演奏することによって、別種の表現力が生まれるのだ。
二楽章でのフルシャは一人芝居の役者のようで、音楽を一秒ももらさず身体で表し、バロック彫刻の塑像のように驚いた表情で完璧に静止したポーズで終わった。
三楽章の美しさはたとえようもない。都響の弦のクオリティの高さを実感するシークエンスで、ここから声楽のソリストが入るのだが、稽古のときソリストの方の一人がこの音楽を聴いて「えっ? この綺麗なオケはどういうふうに鳴ってるの?」という表情をされ、その瞬間目があってしまった。第九を何十回聴いても巡り合えないような美音で、自然や光や神の恩恵といったものに全身が包まれるような心地になる。
ティンパニはさすがにここで休まなければしんどいよな…と思ってチラチラ久一さんを見ていたが三楽章でも実はティンパニは活動していて、とても柔らかな音を出していた。
ここで一気にアタッカで四楽章へ続くのかと思ったら、休止が入った。
最初はそのことが少し意外だった。フルシャは勢いに任せて四楽章に突っ込むのが嫌で
ヤンソンスと同い年になったらアタッカで行くのかも…などと妄想していた。
バリトンの甲斐栄次郎さんが龍神のような歌唱をサントリーの空間に響かせ、そのあとのテノール福井敬さんの輝かしい歌声を聴いたとき、第九の四楽章はそれまでとは違う世界で
未知への冒険であり、様式からはみ出してしまった想像力の膨張であり、ほとんど耳が聞こえなくなっていたベートーヴェンの「にもかかわらず」のサイケデリックな楽観の象徴であることを思った。
シラーの「歓喜に寄す」で描かれる人間賛歌には、原罪のストーリーから脱皮した
宇宙的といっていいほどのオプティミズムを感じる。音楽によってそのようなものになったのだが、これはやはり「人間が神である」ことの宣誓なのだ。
いきなり交響曲に合唱と声楽ソロが「乱入」する斬新さを、再び鮮烈に感じて心震えた。
あらゆるクラシックのモダン表現の胚珠が第九にはあり、様式から中身があふれてくることの驚きと喜びが渦巻いている。
人間が予定調和から踏み出して飛行機が飛び、宇宙ロケットが飛び、そのうちタイムワープも実現していく未来が見えるようだった。
合唱もオケも過熱し、熱狂し、強烈な光のエネルギーに昇華して、音楽は「終わる」というより、人間からのメッセージとして果てしない宇宙空間へ解き放たれていった印象を得た。
演奏会の最初から最後までがあっという間で、少しのストレスも感じなかったのは
ステージの上の都響の楽員さんたちが、真に幸福な気持ちで演奏していたからだと思う。
フルシャもそのことを望んでおり、「全員が幸福である」演奏が第九には相応しく
絶対的支配による、犠牲をともなう達成というものは不要なのだろう。
献身と犠牲とは明らかに違う。そのことをオーケストラからはいつも教わる。
音は解き放たれた物理的事象とともに、無尽蔵の無意識から成る象徴であり
成熟した指揮者は音楽のなかで、顕在意識と潜在意識の健全な交流と、男性性と女性性の幸福な結合を実現するのだ。
「どこが世界の中心か?」という疑問に、どういう答えを出すか。
書かれた歴史の合理性の裏に隠された、無尽蔵の非合理性を思い、
人類の本当の姿を顕すために、芸術表現があることの誇りを実感した。
超満員のソールドアウトで、なんとかチケットを購入させていただき一階前方で聴いたが、ステージと地続きになっているような聴覚体験で、床から熱い湯気が立っている熱感覚を得た。
フルシャにインタビューをするため、数日前に稽古を見学したのだが、上野の稽古場でも、実は同じ経験をした。音がすごい勢いで床に共鳴し(壁や天井ではなく)、
ティンパニだけでなく弦も管も、椅子から臀部に伝導し、臓器に響いてくるのだった。
オケが乗っている同じ床の上で聴いていたから当然のことかも知れないが、サントリーの本番でも音の重心が下にあり、特に1楽章と2楽章は臍から下に響いた。
とても肉体的なベートーヴェンで、最初から形而上的な世界へ行くのではなく「まず地上の人間ありき」という音楽に感じられた。
稽古を見学したときに思ったのは、やはり都響は「うまい」ということだった。
フルシャはほぼ出来上がっている第九の、細かいアーティキュレーションを修正し
その都度歌って聴かせたり、面白いトークをしたり、不思議な沈黙の後に爆笑をとったりしていたが、
本番では稽古のときに語ったり歌ったりしたことを、より激しくなったジェスチャーで再び伝えていたのが見事だった。
稽古のあとの取材で、フルシャが本当にプレイヤーを尊敬していること、彼が考える指揮者の役割についてなど聞いたが
音楽について「本能」「直観」という言葉が出てきたのにはっとした。
スコアの知的分析と同時に、本能と直観をハーモニーさせることが指揮者としての「美に到達するための作業」だと語ってくれた。
都響の第九にはフルシャの知性とともに本能と直観が貫かれていて
凄い緊張感で完璧な演奏をしたティンパニの久一さんが、フルシャの肉体感覚と一部始終つながっていた。
二楽章は本番であんなに野性的になるとは想像していなかったが、ベートーヴェンの痙攣的なフレーズがダイレクトに強調され、短い休符が完璧に真空になるのが見事だった。オケの集中力が尋常でない。
ベートーヴェンの極端な痙攣性は、古楽的な拍節感で切り込んでいくのがトレンドであるような気もするが、それより大きな編成で演奏することによって、別種の表現力が生まれるのだ。
二楽章でのフルシャは一人芝居の役者のようで、音楽を一秒ももらさず身体で表し、バロック彫刻の塑像のように驚いた表情で完璧に静止したポーズで終わった。
三楽章の美しさはたとえようもない。都響の弦のクオリティの高さを実感するシークエンスで、ここから声楽のソリストが入るのだが、稽古のときソリストの方の一人がこの音楽を聴いて「えっ? この綺麗なオケはどういうふうに鳴ってるの?」という表情をされ、その瞬間目があってしまった。第九を何十回聴いても巡り合えないような美音で、自然や光や神の恩恵といったものに全身が包まれるような心地になる。
ティンパニはさすがにここで休まなければしんどいよな…と思ってチラチラ久一さんを見ていたが三楽章でも実はティンパニは活動していて、とても柔らかな音を出していた。
ここで一気にアタッカで四楽章へ続くのかと思ったら、休止が入った。
最初はそのことが少し意外だった。フルシャは勢いに任せて四楽章に突っ込むのが嫌で
ヤンソンスと同い年になったらアタッカで行くのかも…などと妄想していた。
バリトンの甲斐栄次郎さんが龍神のような歌唱をサントリーの空間に響かせ、そのあとのテノール福井敬さんの輝かしい歌声を聴いたとき、第九の四楽章はそれまでとは違う世界で
未知への冒険であり、様式からはみ出してしまった想像力の膨張であり、ほとんど耳が聞こえなくなっていたベートーヴェンの「にもかかわらず」のサイケデリックな楽観の象徴であることを思った。
シラーの「歓喜に寄す」で描かれる人間賛歌には、原罪のストーリーから脱皮した
宇宙的といっていいほどのオプティミズムを感じる。音楽によってそのようなものになったのだが、これはやはり「人間が神である」ことの宣誓なのだ。
いきなり交響曲に合唱と声楽ソロが「乱入」する斬新さを、再び鮮烈に感じて心震えた。
あらゆるクラシックのモダン表現の胚珠が第九にはあり、様式から中身があふれてくることの驚きと喜びが渦巻いている。
人間が予定調和から踏み出して飛行機が飛び、宇宙ロケットが飛び、そのうちタイムワープも実現していく未来が見えるようだった。
合唱もオケも過熱し、熱狂し、強烈な光のエネルギーに昇華して、音楽は「終わる」というより、人間からのメッセージとして果てしない宇宙空間へ解き放たれていった印象を得た。
演奏会の最初から最後までがあっという間で、少しのストレスも感じなかったのは
ステージの上の都響の楽員さんたちが、真に幸福な気持ちで演奏していたからだと思う。
フルシャもそのことを望んでおり、「全員が幸福である」演奏が第九には相応しく
絶対的支配による、犠牲をともなう達成というものは不要なのだろう。
献身と犠牲とは明らかに違う。そのことをオーケストラからはいつも教わる。
音は解き放たれた物理的事象とともに、無尽蔵の無意識から成る象徴であり
成熟した指揮者は音楽のなかで、顕在意識と潜在意識の健全な交流と、男性性と女性性の幸福な結合を実現するのだ。
「どこが世界の中心か?」という疑問に、どういう答えを出すか。
書かれた歴史の合理性の裏に隠された、無尽蔵の非合理性を思い、
人類の本当の姿を顕すために、芸術表現があることの誇りを実感した。