今日はおひな祭り。たまには着物を着たいと思ったのですが、着物ではダンスはできません。そこでちょっと着物の話を!1994年ごろに書いたものと思います。
「三十六歌人」
昨日、義理の妹が留め袖を借りに来た。来月仲人をすることになったそうだ。三十六歌人という絵柄の留め袖は、三年前に親しい友に頼まれて仲人をしたとき、染色家の伯父に作って貰ったものだ。
伯父の家は、私の実家から三十分ほどの高田馬場にある。子供の頃は、いとこや祖母もいたので良く遊びに行った。いとことの遊びが一段落すると、仕事場を覗く。蝋の香りがする六畳間は、伯父や叔母の座卓や、顔料の棚で埋り、反物を掻き分けてそーっと潜り込む。
仮り糸で着物の形に縫われた絹の白生地に、露草からとった青紫色の液で伯父が直じかに下絵を描く。小さな元の絵を横に置いて、一気に描いていく様は、見ているこちらまで爽快になる。この液は、熱を加えると色が消えてしまうとのこと。そのあと、糊屋さんに持って行き、色を塗ったときにはみ出ないように、下絵の線を糊でなぞってもらう。仮り縫いの糸は解かれ、もとの反物になって戻ってきた着物に、今度は色を差していく。伯父の机からは、魔法のようにきれいな色ができる。座卓の真ん中はノートの大きさほどが切り取られ、夏でも小さいヒーターが付けられている。細く割った竹の両端に針の付いた伸子をたすきに架けて布をぴんと張り、滲まないように暖めながら色を差す。ぬり絵のように色とりどりの模様ができあがる。細かいところも筆を器用に使いこなして描いていく。
糊を落とした後、金箔を載せたり、金線を描いたりする。これは叔母の担当だ。四角い金箔を竹でできたピンセットで摘み上げ、息を微かに吹き掛けながら、糊を塗った所に載せていく。波打っていた箔が鏡のように鎮まりかえり、次の瞬間には着物の上に収まっている。純金と聞かされて子供心に息を殺した覚えがある。金線は金粉をセルロイドと酢酸アミールで溶かしたドロリとした液を、先を細く巻いたパラフィン紙に入れて絞り出す。ちょうどバースデイケーキに名前を絞り出す要領だ。
伯父たちが楽しそうに仕事をしているところを何時間も飽きずに見ていたものだ。数十もの工程の末やっと着物ができあがる、大勢の人の手を借りて。
私が初めて伯父の着物を着せてもらったのは、七歳の時。小さいながらも作るところを見ているだけにとても誇らしかった。白地に描かれた色とりどりの菊の図柄を今でも鮮明に覚えている。
留め袖には源氏物語絵巻のように、十二単を着たお姫様、お公家さん、お坊さんなどの三十六歌人が詩を詠んでいるところが描かれている。黒地に美しい物語りが映える。昨日も義母や妹と長いこと見ていた。
「三十六歌人」
昨日、義理の妹が留め袖を借りに来た。来月仲人をすることになったそうだ。三十六歌人という絵柄の留め袖は、三年前に親しい友に頼まれて仲人をしたとき、染色家の伯父に作って貰ったものだ。
伯父の家は、私の実家から三十分ほどの高田馬場にある。子供の頃は、いとこや祖母もいたので良く遊びに行った。いとことの遊びが一段落すると、仕事場を覗く。蝋の香りがする六畳間は、伯父や叔母の座卓や、顔料の棚で埋り、反物を掻き分けてそーっと潜り込む。
仮り糸で着物の形に縫われた絹の白生地に、露草からとった青紫色の液で伯父が直じかに下絵を描く。小さな元の絵を横に置いて、一気に描いていく様は、見ているこちらまで爽快になる。この液は、熱を加えると色が消えてしまうとのこと。そのあと、糊屋さんに持って行き、色を塗ったときにはみ出ないように、下絵の線を糊でなぞってもらう。仮り縫いの糸は解かれ、もとの反物になって戻ってきた着物に、今度は色を差していく。伯父の机からは、魔法のようにきれいな色ができる。座卓の真ん中はノートの大きさほどが切り取られ、夏でも小さいヒーターが付けられている。細く割った竹の両端に針の付いた伸子をたすきに架けて布をぴんと張り、滲まないように暖めながら色を差す。ぬり絵のように色とりどりの模様ができあがる。細かいところも筆を器用に使いこなして描いていく。
糊を落とした後、金箔を載せたり、金線を描いたりする。これは叔母の担当だ。四角い金箔を竹でできたピンセットで摘み上げ、息を微かに吹き掛けながら、糊を塗った所に載せていく。波打っていた箔が鏡のように鎮まりかえり、次の瞬間には着物の上に収まっている。純金と聞かされて子供心に息を殺した覚えがある。金線は金粉をセルロイドと酢酸アミールで溶かしたドロリとした液を、先を細く巻いたパラフィン紙に入れて絞り出す。ちょうどバースデイケーキに名前を絞り出す要領だ。
伯父たちが楽しそうに仕事をしているところを何時間も飽きずに見ていたものだ。数十もの工程の末やっと着物ができあがる、大勢の人の手を借りて。
私が初めて伯父の着物を着せてもらったのは、七歳の時。小さいながらも作るところを見ているだけにとても誇らしかった。白地に描かれた色とりどりの菊の図柄を今でも鮮明に覚えている。
留め袖には源氏物語絵巻のように、十二単を着たお姫様、お公家さん、お坊さんなどの三十六歌人が詩を詠んでいるところが描かれている。黒地に美しい物語りが映える。昨日も義母や妹と長いこと見ていた。















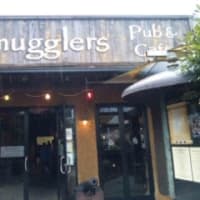










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます