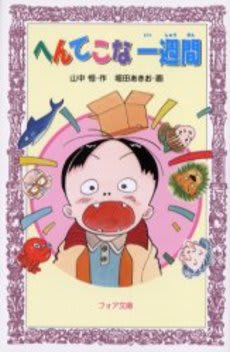友人にお薦めされた本(マンガ)ですが、とても面白かったので私も皆さんにお薦めしたいと思います。
ギリシャ神話といえば、うちの子供達は一時ハマっていてよく知っているのですが、私はとにかく何度読んだり聞いたりしても全く頭に残らない。
学生の時に英文学概論でガッチリ習ったはずが、ゼウスの妻ヘラが嫉妬深いことと、誰かが白鳥になった様な、、、、こんな程度。なんと言っても、カタカナで神々の名前を覚えるのが無理。私は特に昔からカタカナが苦手で、高校生の時に世界史を履修しなかったなんて失敗も。
それがとても読みやすくて分かり易いマンガになっているのですよ。
エピソードを通して豆知識を得られます。
オリンピックで勝者に月桂樹の冠を与えられるわけ、孔雀の羽根にはなぜ目の様なものがたくさんついているのか、砂漠ができた経緯、などなど。
結局のところ、ゼウスがあっちこっちのオンナに手を出しヘラを怒らせたためなにかしら起こってしまうことが多いのですが、怒られる度におかしな言い訳をしたり卑怯なことをするのですがまさに普通の浮気男っぽくて、こういうところなど今も昔も神々も人間も変わらなさを描いているところがギリシャ神話が長年親しまれて来た所以でしょうね。
私が読んだのは2巻で、最初のエピソードは、母親のヘラに捨てられた鍛冶屋のへパイトスがヘラを脅してモテモテのアフロディーテを妻にする話。アフロディーテはその経緯も気に食わないし、全く彼に魅力を感じず、アレスと浮気をして楽しみます。
アレスといえば、2年前息子が劇でやった役ですが、劇中ではつい余計な事を言って父親のゼウスに咎められる男でしたが、この作品の中ではチャラい好色男でした。
神話の中では不倫だろうとなんだろうと何の問題もなく子供を産むので、アレスたちにも四人の子供が。次から次へと新しい名前が、、、、結局あんまり覚えてはいけなさそうです、、、、でもそこは忘れて言葉や物の由来なんかを知ることを楽しもうと思います。
子供たちが親しんでいるギリシャ神話の本はこちら。

そしてお馴染みパーシージャクソン。