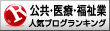どこからか聞こえてきそうな話
ケアマネ「○○さんはなかなか話を聞いてくれないんだけど、なんか方法はないかしら」
先輩「予定票なんかで説明したって駄目よ、そういう人には」
ケアマネ「どうやってるんですか」
先輩「私は説明だけでわかってもらえない人には絵とか文章とか工夫するけど」
ケアマネ「そんなことして問題にならないのですか」
先輩「なんで?ようは相手が理解できるかどうかが問題でしょ」
ケアマネ「そりゃ、そうですけど」
先輩「制度だけで考えちゃ駄目よ、問題の本質と解決の方法を考えないと自分が一番苦労するわよ」
ケアマネ「そうですよね」
ケアマネ「でも所長とか、なんかいいません」
先輩「あら、なにいってんのよ。所長なんか工夫ばっか、いろんな方法を駆使して説明しているわよ」
ケアマネ「知らなかった」
先輩「要はどれだけお客様にとって一番かってことじゃない」
ケアマネ「そうですね」
そんなこと、あたりまえという指摘がありそう
ケアマネ「○○さんはなかなか話を聞いてくれないんだけど、なんか方法はないかしら」
先輩「予定票なんかで説明したって駄目よ、そういう人には」
ケアマネ「どうやってるんですか」
先輩「私は説明だけでわかってもらえない人には絵とか文章とか工夫するけど」
ケアマネ「そんなことして問題にならないのですか」
先輩「なんで?ようは相手が理解できるかどうかが問題でしょ」
ケアマネ「そりゃ、そうですけど」
先輩「制度だけで考えちゃ駄目よ、問題の本質と解決の方法を考えないと自分が一番苦労するわよ」
ケアマネ「そうですよね」
ケアマネ「でも所長とか、なんかいいません」
先輩「あら、なにいってんのよ。所長なんか工夫ばっか、いろんな方法を駆使して説明しているわよ」
ケアマネ「知らなかった」
先輩「要はどれだけお客様にとって一番かってことじゃない」
ケアマネ「そうですね」
そんなこと、あたりまえという指摘がありそう