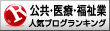予定通り、同一事業所のサービスを90%利用する事業所の介護報酬を減算する、ということについて、です。
あるかないかは別にして、考え方を少し。
特定のサービスに集中していること自体に問題はないと思う。
しっかりアセツメントをやって、それで選んだサービスがどうしても集中する、ということは想定できる。
アセツメントをしっかりやってそこからいざサービスに結びつけようと計画したらいつの間にか自社のサービスが頭をよっぎてついついアセツメントで考えるべき計画と違ってきたとしたら・・・
ですから、居宅と他のサービスが一緒になった事業所であろうとそうでない事業所であろうと形態に原因があるのではなく、アセツメントをしっかりやり、その後に続くケアプラン・ケアカンファレンスにつながる業務の一貫性。
そうです、この業務の一貫性が確保できているかでは、と思う。
業務の一貫性を確保する方法を講じるにはケアマネジャーでしょうか、事業所でしょうか。
そうです、両方ですね、実務の当事者がまず一貫性を認識する、事業所はケアマネジャーが業務遂行できる作業環境を整える。お互いがやることだと思う。
でも、何が作業の環境かは明確になっていないかな。当事者のケアマネジャーが一番知っていること、他のひとではわからないです。
どうかケアマネジャーは要望をあげて、いやそんなこと・・と思わないで、あきらめないで。
あるかないかは別にして、考え方を少し。
特定のサービスに集中していること自体に問題はないと思う。
しっかりアセツメントをやって、それで選んだサービスがどうしても集中する、ということは想定できる。
アセツメントをしっかりやってそこからいざサービスに結びつけようと計画したらいつの間にか自社のサービスが頭をよっぎてついついアセツメントで考えるべき計画と違ってきたとしたら・・・
ですから、居宅と他のサービスが一緒になった事業所であろうとそうでない事業所であろうと形態に原因があるのではなく、アセツメントをしっかりやり、その後に続くケアプラン・ケアカンファレンスにつながる業務の一貫性。
そうです、この業務の一貫性が確保できているかでは、と思う。
業務の一貫性を確保する方法を講じるにはケアマネジャーでしょうか、事業所でしょうか。
そうです、両方ですね、実務の当事者がまず一貫性を認識する、事業所はケアマネジャーが業務遂行できる作業環境を整える。お互いがやることだと思う。
でも、何が作業の環境かは明確になっていないかな。当事者のケアマネジャーが一番知っていること、他のひとではわからないです。
どうかケアマネジャーは要望をあげて、いやそんなこと・・と思わないで、あきらめないで。