私の父は私が10歳のとき死んだ。
当時命取りの病だった胃癌だった。
1964年4月29日早朝。
私と妹を起こす声がする。それは病院にいて父の看病をしているはずの
母の声なのであった。
私はとっさになにが起こったのか理解した。母は大きなため息を何度もついて、
私と妹が居住まいを正して床の上に正座するのを待ってから、こう言った。
もう病院へ行かなくてもいいのよ、お父様は亡くなりました、と。
それは私が予期していた言葉だった。
具合が悪くなってから父は病院への入退院を一年半ほど繰り返していた。
しかし母の言葉を聞いて泣き出す妹と一緒に私も泣き出した。
いや、泣き出すまねをした、
というほうが当たっているかもしれない。
その頃わたしはもう父が元気で家に戻ることはないことを、子供心に察していた。
だから泣きじゃくるまねをすることで母が喜ぶかもしれない、と思ったのだ。
離れの隠居家に父の遺体は安置されていた。長い闘病生活で
すっかり浅黒くなった皮膚が肉の落ちたほほに張り付いて、
ミイラのようになった父の顔を
わたしはじっと見つめた。
半ば開きかけたたまぶたはそれでもまだ生前の父を思わせた。
開いた口と鼻腔と両耳には真綿が詰められていた。
人の亡骸を見るのは生まれて初めてであったと思う。
父の死以前にも親戚の葬儀に参列したことはあったかもしれない。
でも今思い返して、人間の屍をまじまじと見たのは
父の遺体が初めてだったと思う。
まもなく葬儀屋さんたちがやってきてお棺や祭壇などを運び入れる。
彼らは父の遺体をみて、ドライアイスをかなり入れないといけませんね、
もうにおいがしてきていますからね、という。
わたしが感じた異様な臭い、それは目の前に横たわっている父の遺体から
漂ってくる死臭なのであった。
隠居家の廊下の籐椅子にうずまっている私に妹が泣き叫びながらこういう、
お姉ちゃんはどうして泣かないの、お父さんが死んじゃったのよ。
わたしは籐椅子に深々と身をうずめて冷ややかにこういう。
泣き叫んでももうお父さんは戻ってこないのよ。
そうすると妹はますます泣き叫ぶのだった。
お通夜のときだったか告別式の日だったか定かではない。
私と妹が通ったカトリック系の幼稚園の尼さんたちが弔問に来てくださった。
三年保育だった妹は特にお世話になったから主任のシスター・エスペランサが
わざわざいらしてくださって、祭壇の前に座り、
ていねいにお焼香をしてくださってから、
泣きじゃくっている妹を抱きかかえるようにしてこうおっしゃった。
あなたのお父様は神に召されたのです。天で安らかに眠っておられるのです、と。
あとになってから母はつぶやいていた。
亡くなったあなたたちのお父さんは天に召されて安らかかもしれないが、
残されたわたしにエスぺランサ様からは何のお言葉もなかった、と。
斎場で父の亡骸が荼毘にふされる。そこでも醒めていたわたしは
何とも形容のしがたい思いを、
いつか読んだ少女小説の一節を声高に唱えることで発散させた。
ああ、お父様が煙になって空へと消えていってしまう!
そして号泣して見せたのである。
父はわたしにとって特別な存在だった。
わたしは生来曲がった精神の持ち主だった。父をもあざむこうとした。
しかし父はそのどの欺きもみごとに見破って時には無言で時には厳しい叱責で
わたしのいじけた精神を正そうとした。
そして生まれながらに病弱な妹がいつも母の胸に抱かれていて、
私が母によりつけなかったとき、大きな愛情でわたしを包み、当時としては
実に贅沢な京橋や銀座の一流のレストランや、映画のロードショーや、釣りや、
勤めていた大手商社の社長宅などへ、黒塗りのオースティンの車で
私を連れて行ってくれた。
その父が病を得、それが当時は治療も確立していなかった胃癌であったことから
2年近くの闘病生活の末、彼は亡くなったのである。
突然亡くなったわけではない。入退院を繰り返していた父の姿を見るたび、
私はもう父が今までの元気な父に戻ることはないことを察していた。
亡くなる数週間前、父が入院していた新宿の近くの初台の病院へ
見舞いに行ったときのことだ。
やせ細り、治療の薬漬けになった父の顔の干からびて薄くなった浅黒い肌が、
小学校の理科の実験室にある骸骨の模型のように眼窩が落ち込み
こけたほほに張り付いているのを見て、わたしは気味悪かった。
父が何か言ったが、何を言ったのか覚えていない。
涙がそのくぼんだ眼窩にみるみるうちに溜まっていって
ツーッとほほを伝って流れていくのを、
私は冷ややかに観察していた。
母がガーゼを私に差し出して、拭いてあげなさいよ、と言ったのに、
私は目の前の骸骨のような人が自分の父だとは思いたくなかった。
それで嘘をついた、どうやって拭いてあげたらいいのかわからないもの。
私はしり込みしたのだ。命尽きていく父を見捨てたのだ。
そして二週間後父は死んだ。
私は今でもそのときの自分を責める。なぜ父にすがりつかなかったのか、と。
父の死の五ヶ月後、東京オリンピックが開催された。その開会式の行われる朝、
私は近所の文房具店へ買い物に出た。何を買いに行ったのか覚えていない。
鉛筆か、消しゴムか、他愛のないものだったと思う。
私とすれ違いに、店からは買い物を終えた小学4年生くらいの少年とその父親が
外へ出て行くところだった。
私は店に入り、ほしいものを店の主人に伝える。奥の部屋のテレビでは
オリンピックの開会式が今にも始まりそうな模様を実況中継している。
店主が用意するのを私が待っている間、
先ほど出て行った少年とその父親が戻ってきて、
父親が買物の包みを置き忘れたことを店主につげ、
私の目の前にあった包みを、
そうこれこれ、うっかりして、と取り上げてまた店を出て行った。
外で待っていた少年が、お父さん、ダメじゃないか、わすれちゃあ、と
大きな声で父親に言っているのが聞こえる。
精算をすませた私が店の外に出ると
その親子が手をつないでのんびりと歩いていくのが見えた。
わたしはその後姿をしばらく見守りながら、そのとき初めてわたしの父が
もうこの世にいないことを認識したのだった。














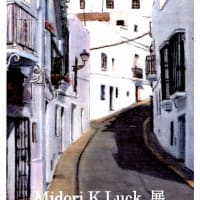





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます