
これも子供たちを主人公にしたお話である。
時代は1959年、もはや戦後の暗い雰囲気はなく、
おそらく1964年の東京オリンピック開催が決定していて
東京が変わりつつある時代だったのであろう。
東京の下町の川沿いにある新興住宅地、
建物を見ると都営住宅のような画一的な平屋だての長屋のような
家が密集している住宅地で暮らすサラリーマン家族の日常を描いている。
新興住宅地であるから、昔からの共同体のような
深いつながりがないのだろう、互助会だか婦人会だかの
会費の行方をめぐって、主婦たちのあいだでは
疑心暗鬼の会話がかわされる。
ちょうど三種の神器である、洗濯機、冷蔵庫、テレビが
普及し始めた時代である。おとなりが洗濯機を買った、
というだけで、やっかみ半分の目でみられてしまうのだ。
林一家の実という中学一年生くらいの子供と、勇という小学生の
兄弟は、隣近所の子供たちと、近所の若いカップルの家に
テレビを見に行くのが楽しみなのだが、
その若いカップルは昼間はパジャマ姿でぶらぶらしていて、
夕方から働きに出かけていく。母親たちは子供たちがカップルの
家に行くことを教育上よろしくない、と考えている。
兄弟は近くの団地に住む福井(佐田啓二)に英語を習っているが、
叔母の節子(久我良子)は福井に会社の翻訳を依頼し、失業中の
福井にとってはいいアルバイトとなっている。
実と勇は親にテレビを買ってくれ、とせがむが、
父親(笠智衆)はテレビは一億総白痴化のもと、と考えていて、
テレビなどいらん、とつっぱねる。
子供たちがあまりにしつこくせがむので、父親は
お前たちは無駄な口数が多すぎる、と叱る。
すると長男の実が口答えする、
大人だって、無駄なことばかり言っているじゃないか、
「お早う」「こんにちは」「いいお天気ですね」「どちらへお出かけ」
「ちょっとそこまで」…。
父親はとうとう癇癪をおこして怒鳴る。
男の子はしゃべるんじゃない、だまっていろ!
そこで実と勇は、口をきかないというストライキにはいる。
といった単純な筋である。結局、お隣の旦那が定年退職後に
再就職して、電器店のセールスマンになったことから、
おつきあいで、テレビを買うことになるのだが、
それで子供たちのストライキも一気におさまり、
一家安泰、また元通りの元気な子供たちの日常が
もどってくる。
福井と節子はお互いに好意をもっているのだが、
なかなか相手に自分の気持ちを切り出せない。
「お早う」とか「こんにちは」というのは無駄な会話
ではなく、そういうあいさつが社会の潤滑油になっている、
という福井に、外車のセールスをして稼いでいる福井の姉が
人間、必要なことはなかなか言えないものね、あんたも
節子さんが好きなのに、切り出せないじゃないの、と突っ込む。
晴れた日の朝、電車の駅で福井と節子が出会う。
「お早う」「いい天気だね」などと月並みな会話しか
かわせない二人だが、「好きです」などと言わなくても
お互いの気持ちは何となくそんな他愛のない会話から
察することができるものなのだ。
カラー映画で、赤と緑色がかなり意図的に画面に配置されている。
また小津映画には商品名が堂々と出てくるが、この映画でも
ナショナルのテレビの箱が画面に大きく映し出される。

しかし子供たちがおなら遊びをしたり、たちしょんしたりする場面がある。
おなら遊びでいつもパンツを汚してしまう隣の息子とか、
大きなおならをする近所のおじさんがいて、
奥さんが、「あんた、何か言った?」ときいたりする。
前の記事で紹介した『生まれてはみたけれど』でも子供たちが
立ちしょんする場面が何度かあるし、ズボンから下着がはみ出ていたり、
小津のユーモアにはかなり下品なものがある。
子供たちの世界では排泄も大切な笑いと話題の対象であるが、
こう頻繁に映画の中で見せられると、小津の美意識に少々の疑問を
感じてしまう。
しかし時代の変化を上手に風刺しているのはさすがである。
定年後の生活に不安をもち、空しい、と飲み屋で酔って
嘆くのはいつも東野英治郎の役割である。
また住宅地の中では少しでも風変りな連中はつまはじきにあう。
テレビを持っていた若い夫婦はまわりから敬遠されて
住みにくくなり、引っ越していってしまった。
互助会の会計係である林夫人(三宅邦子)は、上品でインテリぶっている、と
隣近所からかげ口をたたかれ、自分もどこか引っ越したくなった、と
妹の節子に愚痴るが、節子から、いまどき隣近所のないところなど
よほど山奥へいかなきゃないわよ、と言われてしまう。
便利な世の中になればなるほど、世の中の人間関係が
ぎくしゃくしてくる、と言うわけなのである。
そういう世界で、「お早う」などのあいさつの果たす役割は
次第に大きくなっていったのであろうか。
一つ、確実に言えることは、この映画で重要な役割を果たした
テレビの存在が、次第に映画を凌駕し、日本の映画界の
没落の原因の一つとなったことは、実に皮肉である。
『生まれてはみたけれど』ほどの強烈な印象はないものの、
この『お早よう』という映画は何度見ても笑える要素たっぷりで、
おもしろい。杉村春子や高橋とよが演じるおばさんたちが
とてもリアリスティックである。
いつの時代でもおばさんたちはしたたかで元気である。
このようなホームドラマが、60年代からはテレビの人気番組として
一世を風靡していくのである。















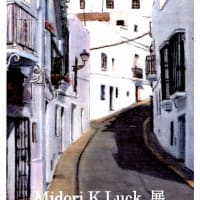





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます