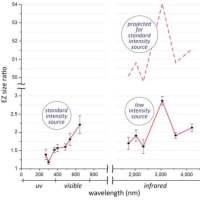2015年3月29日改訂:空に関する要約を再考察しました(赤字部分)
4.初期仏教の般若経などの空の記述と空の解釈
空に関しては、初期仏教にまで遡る必要がありますので、ネット検索をすると以下の文献を発見しました。
最初の部分は、以下の文献(A)より、学術資料として抜粋引用します。
文献(A)
Title: 仏教における空について
Author: 坂部 明
Citation: 信州大学 人文科学論集 人間情報学科編 41: 1-12(2007)
Issue Date: 2007-03-15
URL http://hdl.handle.net/10091/2783
「空」ということばは、初期仏教(原始仏教)において、ゴータマ・ブッダによってすでに説かれていた。
「世界を空なりと観ぜよ」(1)のことばをはじめとして、空についての教説は『小空経』(2)、『大空経』(3)、『無礙解道』(4)などにも説かれている。また、経典以外の論書では、『舎利弗阿毘曇論』(5)などにも説かれている
「空」の思想が前面に押し出されて登場するのは、大乗仏教の先駆的経典である般若経においてである。その後、大乗仏教運動の中で数多くの経典が登場するが、空の思想はそれらに共通する主要な概念となる。
般若経は経名にもあるとおり、六波羅蜜の中心となる実践道「般若波羅蜜」を説く経典であるが、その思想は空と深く関わっているのである。(8)
「空」とはなにか
(1)空の原語について
空の原語は、サンスクリット語では「シューニャ」、パーリ語では「スンニャ」である。これらは品詞としては形容詞または中性名詞として使われる。すなわち、述語として「…は空である」と表現する。またこの単語には、しばしば抽象名詞を作る語尾taをつけて、 「シューニャター(空であること、空性)という用語が作られしばしば仏典に現れる。ただ、これらの単語は主語としては用いられないという特徴を持っている。
◎空の原語「シューニャ」の意味
鈴木学術財団編[1986] :『漢訳対照焚和大辞典』講談社によれば、次のような意味がある。
形容詞: からの、空虚な、住む者のない、など。 「具格とともに」~を欠いている。
中性名詞: 空虚な場所、中空、非存在、絶対的空(仏教)、零
漢 訳: 壁、空無、空虚、空義、など。
(2)空の比喩について
般若経は十種の比喩を用いて空を説明する。比喩表現を多用するのは、インド人の民族性に由来する。インド論理学の五分作法にも「喩」が存在している。比喩は智者に意義を知らしめるために用いられるという。初期仏教の古層に属するとされる『スッタニパータ』、『ダンマパダ』にも比喩表現が多くみられるから、この傾向は仏教初期のころから存在していたものと思われる。
般若経に説かれる十種の比喩は次のとおりである。(19)
1.幻(māyā) 2.焔(marīci) 3.水中の月(udaka-candra) 4.虚空(ākāśa)
5.響(pratiśrutkā) 6.闥婆城(gandharva-nagara) 7.夢(svapna)
8.影(prātibhāsa) 9.鏡中の像(pratibimba) 10.化(nirmita)
この中で特に注目すべきなのは、4.虚空「アーカーシャ」(ākāśa )である
大乗経典には、空の比喩として「虚空」が多く用いられる。
『大日経』では、 「空は虚空に等しい」という。
「我本不生を覚り、語言道を出過す。 諸の過を解脱することを得て、因縁を遠離したり。
空は虚空に等しと知って、如実相の智生ず。」(22)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ブログ筆者補足: 空と虚空は実在する
虚空(アーカーシャ)に関しては、Wikipedia英語版では、
「The Vaibhashika, an early school of Buddhist philosophy, hold Akasha's existence to be real.
初期の仏教哲学バイベーシカVaibhāṣikaは、アーカーシャの存在を実在である(物理的に存在する)と捉えていた。」
と述べられている。(a)
(a) http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha
Encyclopedia of Asian Philosophy By Oliver Leaman, Contributor Oliver Leaman, Taylor & Francis, 2001, ISBN 0-415-17281-0, pg. 476
(注: realという英単語には、「実在している」「物理的に存在する」という意味があるため、上記のように翻訳しています。)
つまり、虚空、アーカーシャとは、物理的に実在しているが、物質による現象界を超越した存在であるとみなされており、大日経は「空は虚空に等しい」と述べているため、虚空=空は実在していると考えられる。
(補足終わり)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(3)般若経の主張
般若経は、この説一切有部の存在実在論に否定的な響きで対抗する形で「一切法の空」をとく。
般若経のいう一切法(存在するもののすべて)とは、『般若心経』にも現れるが、「五経(五蘊)」 (色受想行識)、「十二処(六内処-眼・耳・鼻・舌・身・意と、六外処-色・声・香・味・触・法)、 「十八界」 (十二処に眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識を加えたもの)などであり、初期仏教で説かれていた存在(法)の体系をそのまま採用したものである。
なお、般若経の原典のうちで最も大部な『十万頌般若』では、 「一切法」について次のようにいう。
「一切法とはつぎのものに云われる。すなわち、色・受・想・行・識(五経)と眼・耳・鼻・舌・身・意(六内処、六根ともいう)と、色・声・香・味・触・法(六外処、六境ともいう)と、眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識(六識)と、眼触・耳触・鼻触・舌触・身触・意触(六触)と、眼触より生じた受・耳触より生じた受・鼻触より生じた受・舌触より生じた受・身触より生じた受・意触より生じた受と、有色法・無色法と、無為法・有為法とである。これらが一切法と云われる。」
続けて次のようにいう。
「一切法は、一切法を欠いている。 (一切法は一切法として空である)常ではなく、壊ではないから。理由は何であるか。空であることが、一切法の本性(prakrti)だからなのである。」と。(30)
(ブログ著者補足: 一切法とは、縁起・現象相に存在する全てのものです。一切法空とは、縁起・現象相に存在する全てのものが、本質相では空であることを意味しています。これは別の言葉では一切皆空とも言われています。)
般若経では、空を観察するときの対象、何が空であるのかについて述べている。
大品系般若である『二万五千頌般若』では、十八種の空「十八空」をとく。
これらの原型は既に、初期仏教の仏典『舎利弗阿毘曇論』などに説かれていたが、それらに大乗仏教の特色、たとえば「一切法空」などを加えて整備したものである。 (33)
十八空の名称は、つぎのとおりである。
1.内空 2.外空 3.内外空 4.空空 5.大空 6.勝義(第一義)空 7.有為空 8.無為空 9.畢竟空10.無始空11.散空12.性空13.一切法空14.自相空15.不可得空16.無法空17.有法空18.無法有法空
ブログ筆者注:
以下は十八空に関する坂部氏による仏教界の伝統的な説明であり、空を「とらわれてはいけない」という意味にとらえています。比較のために、ここに書いておきます、この後に、空が物理的に実在することを前提とする私の解釈を示します。
坂部氏の解説:
これらについて簡略に説明すれば以下のとおりである。
内空; 六内処(眼耳鼻舌身意。すなわち自己)が空であると観察する。以下同じ。
外空; 六外処(色声香味触法。すなわち外界,六内処の対象)が空である
内外空; 六内処,六外処共に空である。内外にとらわれないように
空空; 空もまた空である, 空にとらわれてはならない, 空を実体とみてはならない
大空; 十方(東西南北, 四維-四方の中間の方角, および上下)は空である
勝義空; 最高の真理は空である。 『維摩経』における「維摩の一黙」のように
有為空; 有為法は空である
無為空; 無為法は空である。たとえば, 「涅槃」は空である
畢寛空; (虚空の)辺際(atyanta)は得られないから空である
無始空; 過去と未来, (また現在も)空である
散空; 存在は五経(五蘊)和合した仮の存在であるから空である
性空; あらゆる存在の本性は空である, だれかが造ったというものではない
一切法空; 人間が考察しうるあらゆる存在は空である(前述)
自相空; あらゆる存在の相(特徴), たとえば有為法は無常であるとか,六波羅蜜の特徴とかいろいろな特徴があるが, それらは空である,とらわれてはならない
不可得空; 過去,未来の存在は得られない, 現在の存在も常住ではないから得られない, したがって空である
無法空; 非存在, 無, あるいは形成されないものは空である
有法空; もろもろの存在は因縁和合して存在しているのであるから, 存在固有の本質は空である
無法有法空; 非存在, 存在の本質, 存在の生滅は本来空である
なお, これらは, 順序にしたがって観察されるべき空観であった。まず自己の空を観察し, 自我の執着をはなれ(人空), つぎに自己の所有になると思われる存在(身体や自己の愛着するもの, 在家の人であれば, 家族, 財産, 地位, 名誉など)の執着を離れ(法空)が基本となっていることは明らかである。それ以降は想定しうる概念を空とみる実践が連続している。
Ⅴ むすび
この般若経の空観は,やがてナーガールジュナの『中論』, 『十二門論』などによって理論化される。その弟子デーヴァの『百論』を加えて三論宗が成立し,我が国には奈良時代に中国より伝来し, 南都六宗の一つに数えられている。
空はなかなか理論としては理解しがたいものではあるが, 要は何物にも執着しない生き方の中に体得されるもの(中国的理解の用語を使えば, 体空観)なのである。
有と無という観念にとらわれないところに, 空観の実践がある。たとえてみれば, 桜の木は春となり, 諸緑が整って美しい花を咲かせる。 夏, 秩, 冬の時期には花の形はおろか何もみえなかった桜の木はいわば空なのである。しかし, それは無ではなかった。 春ともなれば, 蕾みを生じ, やがて美しい花となる。 美しく咲いたその桜の花は「妙有」というべきものであろう。 これにより, 縁起の理法がそこにあると観察するのである。有ではなく, 無でもなく, 存在は空であると観察して, 苦悩のもととなる執着を離れて彼岸に達し, しかもこの世の美しきを楽しく見るというのが, 本当に幸せな生き方なのではないだろうか。空観はそのような意味において現代においてもなお有効性は失われていないのである。
ここまでは、信州大学、坂部明氏の文献(A)からの引用抜粋です。
文献(A)の引用文献は末尾のリストの( )の数字で本文中に示してあります。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ここから先は、従来の誤解された空の既成概念にとらわれず、縁起・現象相ではなく、無為の本質相に「空という1つの統一体」が物理的に実在しているという観点から、十八空の説明を私なりに試みたものであり、まだ検討の途中段階で未完成なものであることをお断りしておきます。
私は如来ではなく凡夫ですから、空を実際に体験していませんので、完全に正しい解釈をする自信はありません。
ただし、100点満点のテストとすれば、合格点の60点はクリヤーしていると思っています。
「十八空」という名称は、空が18種類あるという意味ではなく、「空という1つの統一体」の説明を18種類考えてみたというものであり、多くのものが重複しており、中には大して意味のない屁理屈にすぎない説明もあります。
古い時代の仏典では、この説明の数はもっと少ないものでした。
坂部明氏の「空と般若波羅蜜」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ibk1952/22/2/22_2_894/_article/-char/ja/
印度學佛教學研究Vol. 22 (1973-1974) No. 2 P 894-899
によれば、空の説明の数が増えて行った様子が次のように書かれています。
『十八種の空のうちの最初の三種の空、即ち内空、外空、内外空についてみると、マッジマ・ニカーヤの『空の大経』に、「内に空を作意する」という表現がとられてはいるが、まだ「内空」というような熟語として表わされてはいない。
ところが部派仏教に入ってこの三種の空が熟語として定着し、増広され、『舎利弗阿毘曇論』では六空となり、『大毘婆沙論』では十空となり、さらに般若経は十八種の空に増広させたものと思われる。
なお、前記マッジマ・ニカーヤ『空の大経』、中阿含『大空経』、及び『舎利弗阿毘曇論』では、この三種の空を空定(空三昧)として説いているから、『般若経』の十八空がそれらを増広していったものと考えると、『般若経』の十八種の空も空三昧の点から見直される必要があるであろう。』
(引用終わり)
最初は、3種の空の解説、即ち内空、外空、内外空しかなかったものが、いつの間にか18種類にまで増やされている実態が分かります。これらは、仏教の僧侶たちが増やして行ったものです。
仏典は、如来であられるお釈迦様が直接書かれたものは一つもなく、全ては弟子や時代がかなり経過した後に僧侶により書かれたものです。
お釈迦様の弟子の大部分や後代の僧侶は如来ではありませんから、空と同化していない、つまり真如の存在ではありませんから、空の真相を体験していません。このため、理解不足、舌足らず、説明不足、言い過ぎのような問題が含まれているのは避けられないと思われます。つまり、完全無欠な経典は恐らく無いだろうということです。この問題点は、キリスト教の聖書でも同様です。
以下に、従来の誤解された空の既成概念にとらわれず、「空という1つの統一体」が物理的に実在し、縁起・現象相の存在は本質相では全て空である(一切法空)という観点から、十八空の説明を私なりに試みましたので参考になれば幸いです。
(坂部氏の「とらわれてはいけない」あるいは他の学者や僧侶の「むなしい」という伝統的な仏教の空の18種の解説と、重松氏の解釈や無為に関する資料に基づく私の解釈を比較してみてください)
(1)内空
現象界の六内処(眼耳鼻舌身意。すなわち自己)は、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
(2)外空
現象界の六外処(色声香味触法。すなわち外界, 六内処の対象)が、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
(3)内外空
現象界の六内処, 六外処共に、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
(4)空空
空空に関しては、坂部明氏が
「般若経等よりみた空空について、印度學佛教學研究 Vol. 19 (1971) No. 2」
という論説を書かれていますので、以下に引用します。
ここで論じようとする《空空》という名称は、『大品般若経』等に説かれている十八空等の中のそれである。
この名称は、小部経典『無礙解道』、及び部派の論書『舎利弗阿毘曇論』、『大毘婆沙論』等に既に現われており、『大品般若経』は、その名称を取り入れたものと思われる。なお、十八空は小品類にはまだ現われていないので、大品類以後になって発展的に採用されたものであろう。
以下に、『大品般若経』とそれに関した論書を資料として挙げて、《空空》の意義を検討したい。
『二万五千頌般若』
『そこで空空とは何であるか? 《一切法の空であるところのものは、その空によって空である》。常ではなく、壊ではないに縁って。それは何の理由であるか? 空であることが、一切法の空の本性なのである。これが空空と云われる。』
漢訳では以下の如くである。
『何等為空空。一切法空是空亦空非常非滅故。何以故。性自爾。是名空空』(『大品般若経』)
(引用終わり)
これを要約すると、
「一切法(全ての存在)が空であるということは、それが空であるから空なのである。その理由は、空であることが一切法(全ての存在)の本性(本質)だからである」
となります。
これは、次のように解釈できます:
空は空であり、「空という1つの統一体」以外のものではない。空が何か他のものにより作られているのではない。空は究極の存在であり、それより先には何も存在しない。
(5)大空
現象界の十方(東西南北、四維-東西南北の中間の方角、および上下)は、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
つまり、現象界に存在する空間、距離、位置(座標)、大きさは、空の中には存在しない。
現代科学的な表現では、空にはxyz-3次元座標系が存在せず、次元が存在しない、つまり無次元である。
空では空間、距離、座標が存在しないから、例えば東京、ロンドン、パリは同じ場所であり、地球、土星、アンドロメダ銀河も同じ場所である。
空には大きさという概念がないため、現象界の無限の全宇宙にも、微小な素粒子にも同時に対応可能である。つまり、空は現象界では無限の全宇宙の全ての場所に同時に存在している。
空は、3次元現象界の常識では考えられない「無次元」という性質を持っている。
(6)勝義(第一義)空
最高の真理と呼ばれるものも「空という1つの統一体」である。
早稲田大学 長谷川洋三名誉教授の著作「『般若心経』の研究」のp.162によれば、第一義とは「森羅万象の根本となるもの」という意味です。
このため、勝義(第一義)空とは、「森羅万象の根本となるもの」は「空という1つの統一体」であることを意味しています。
(7)有為空
有為法、つまり縁起・現象界の全ての存在は、本質相の空の中には個別には存在せず、「空という1つの統一体」である。
(8)無為空
無為法(生滅変化を超えた常住絶対なもの)
①虚空無為(ものの存在する場)
②択滅無為(ちゃくめつむい)(智慧による煩悩の消滅〕
③非択滅無為(ひちゃくめつむい)(智慧によらない煩悩の消滅)
は「空という1つの統一体」である。
(9)畢竟空
(虚空の)辺際(atyanta)は存在しない、「空という1つの統一体」には果てはないからである。
(10)無始空
空には、始まりがなく、終わりもなく、過去、現在、未来が存在しない、つまり時間が存在しない。
例えば、空では100億年前と現在と100億年後の区別はなく、今という時間しかない。
空は、3次元現象界の常識では考えられない「無時間」という性質を持っている。
これと同様の説明は、東京大学大学院大藏經テキストデータベース研究会の「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース2012版(SAT 2012)」の次の出力にも見られる:
大般若波羅蜜多經 (No. 0220 玄奘譯 ) in Vol. 05
T0220_.05.0022b02: 非造作相。諸識空彼非了別相。何以故。舍利
T0220_.05.0022b03: 子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是
T0220_.05.0022b04: 色。受想行識不異空。空不異受想行識。受想
T0220_.05.0022b05: 行識即是空。空即是受想行識。何以故。舍利
T0220_.05.0022b06: 子。是諸法空相不生不滅。不染不淨。不増不
T0220_.05.0022b07: 減。非過去。非未來。非現在。舍利子。如是空
T0220_.05.0022b08: 中。無色。無受想行識。無地界。無水火風空識
ここでは「是諸法空相 不生不滅。不染不淨。不増不減。非過去。非未來。非現在。」と説かれており、
諸法、即ち全ての存在の空という本質は、生まれることも滅することもなく、何かに染まって汚れたり清いというような何らかの性質を持つこともなく、増えたり減ったりすることもなく、過去・現在・未来のいずれでもない、つまり時間はない、無時間であると説かれている。
(11)散空
現象界の存在物は色・受・想・行・識(五経、五蘊)の因縁和合により構成され、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
(12)性空
本性空と言い換えることができ、現象界の存在物の本性は、本質相では「空という1つの統一体」である。
(13)一切法空
一切法、即ち縁起・現象界の全ての存在は、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
別の仏教用語では「一切皆空」とも言われる。
全世界、全宇宙の全ての物質、全てのエネルギー、現象界の全ての自然物及び社会的存在物や条件、全ての知識・情報・技術・智慧、全ての人の思い(心、意識)、全ての場所、全ての過去・現在・未来の時間など、現象界の全てのものは、本質相では「空という1つの統一体」である。
全ての存在は、空の中では縁起・現象界の諸々の存在の区別はない、「空という1つの統一体」である(これを仏教では諸法無我と呼ぶ)。この点は般若心経にも述べられている。
一切皆空は、別の表現では一切即是空であり、色即是空・空即是色と同様の形式で、空即是一切と表現できる。これは、空が現象界の一切の存在を生み出していることを示している。
(14)自相空
あらゆる存在の相(特徴)は、本質相では「空という1つの統一体」である。
(15)不可得空
三省堂 大辞林によれば、不可得は、
〘仏〙 真理・悟り,仏の考えなどが人間の思慮を超えていて認識できないこと。
と解説されています。
このため、不可得空とは、真理・悟り,仏の考えなどが人間の思慮を超えていて認識できず、それは、それらが本質相の「空という1つの統一体」であるためです。
(16)無法空
法すなわち存在物ではないものは、本質相では「空という1つの統一体」である。
(17)有法空
縁起・現象界の一切の存在物は、本質相では「空という1つの統一体」である。
(18)無法有法空
一切の存在物、非存在物は、本質相では「空という1つの統一体」である。
(空の実在を前提とする十八空に関する独自の解釈を終了)
これまで調べてきた空の性質を要約すると、次のようにまとめることができます。
『縁起・現象相の本質相は空であり、空は物理的に実在し、空は単なる観念や哲理ではなく物理的実在である。
縁起・現象相と本質相の空は別々の2つものがあるのではなく、1つのものを2つの面から見ているだけであり、縁起・現象相と空は一体である。
空には、時間・空間が存在せず無次元・無時間であり、空は時間・空間を超越している物理的存在である。
空の中には縁起・現象相の個別の存在物及び性質は一切存在しない。
縁起・現象相の全ての存在物・性質は、空では「空という1つの統一体」として1つに統一されたものとして存在し、空は縁起・現象相のいかなる性質にも染まっていない(諸法無我、個別性はない)。
空の中には空間がないため、空には質量もなく、空の中には現象相の性質もないため、陰または陽の電荷もない物理的な存在と考えられる。
空は、現象相で知られているようなエネルギーや波動という性質も持っていない。
空は、初めもなき、終わりもなき、永遠の、無限の力、全知全能の完全無欠な「空という1つの統一体」であり、空は現象界の全てを生み出す智慧と力を持つ。空は、「万物の創造主」「宇宙の英知」と呼ぶことが可能である。』(空は、大我ではなく、無我であると思われる)
空に関するこの概念は、キリスト教の「父なる神」「神の国」、インドの宗教ヴェーダの「ブラフマン梵天」、ヨガの「宇宙意識」、真言密教の「大日如来」に類似すると考えられる。(各宗教・宗派により定義の内容が異なり誤りも含むだろうが、基本的な部分は類似していると考えられる)
悟りを開かれた釈尊は、「空という1つの統一体」の物理的実在と機能を説くことにより、宇宙の創造と展開の原理を説かれていたと考えられる。
ただし、釈尊の説かれている「空」は、大我ではなく、無我であると思われる。
それらの教えは、如来であられる釈尊が地球におられた頃には、弟子の中でも理解力の進歩した人たちにより理解されていたが、空と同化された如来が地球を去られて数百年たつと、本当に理解している人がいなくなり、空を縁起・現象界の事象の相互関係と見なす誤解が生じ、それがさらに「空しさ」「とらわれるな」と誤解され、現在に至っていると考えられる。
現代仏教は、空という統一体の持つ恐るべき性質と能力を知らないし、活用していないと思われる。
備考
(1)大日如来
Wikipediaよりの引用
大日如来(だいにちにょらい)、梵名 マハー・ヴァイローチャナ(महावैरोचन [mahaavairocana])は、虚空にあまねく存在するという真言密教の教主[1]。
「万物の慈母」[2]、「万物を総該した無限宇宙の全一」[3]とされる汎神論的な仏[4]。
声字実相を突き詰めると、全ての宇宙は大日如来たる阿字に集約され、阿字の一字から全てが流出しているという[5]。
神仏習合の解釈では天照大神(大日孁貴)と同一視もされる。
概要
「無相の法身と無二無別なり(姿・形の無い永遠不滅の真理そのものと不可分である)」[1]という如来の一尊。摩訶毘盧遮那如来(まかびるしゃなにょらい)、大光明遍照(だいこうみょうへんじょう)とも呼ばれる[4]。
なお、宇宙とはあらゆる存在物を包容する無限の空間と時間の広がり、および宇宙空間を指す(詳細は「宇宙」を参照)。
大日如来は、無限宇宙に周遍する点では超越者だが、万物と共に在る点では内在者である[3]。
全一者であり、万物を生成化育することで自己を現成し、如来の広大無辺な慈悲は万物の上に光被[※ 1]してやまないとされる[3]。
三世(過去・現在・未来、前世・現世・来世)にわたって常に説法しているとも説かれる[6]。
出典
[1]『望月 佛教大辞典 4 増訂版』(世界聖典刊行協会)、3343-3344頁。
[2]『明鏡国語辞典』(大修館書店)、「大日如来」。
[3]林達夫他 『世界大百科事典 19』 平凡社 、1972年、163頁。
[4]『密教曼荼羅』(新紀元社)。
[5]奈良康明 『仏教名言辞典』 東京書籍、1989年、568頁。
[6]Encyclopædia Britannica, Inc. 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書版』 ブリタニカ・ジャパン株式会社、2009年、「大日如来」。
(2)仏教は「空」の真実を見失い、苦肉の策の代用品として大日如来を考案した
覚者・如来であられる釈尊は、森羅万象・全宇宙を創造・展開する存在と同化され、それを「空」と名づけられた。
しかし、如来が去られ、空の真実を体験している者がいなくなった時代になると、後世の僧侶たちは空と同化していないため、空の真実を理解できなかった。
そして、縁起・現象相の一時的な相互依存関係が空であると解釈し、空とは、これらのものに「こだわらないこと」「とらわれないこと」であると説いた。
この誤解により、仏教は、その教義の中から、森羅万象・全宇宙を創造・展開する存在を欠落させ、この誤解が八宗の祖と賞賛されている2世紀頃のナーガルジュナにより確立され現代に至っている。
しかし、後代の真言密教系の僧侶たちは、この欠落を補うために、インドの宗教ヴェーダの「ブラフマン梵天」、ヨガの「宇宙意識」に類似した大日如来(摩訶毘盧遮那如来)を導入し、宇宙の創造・展開を行う存在を説明しようとしたと考えられる。
補足
森羅万象・全宇宙を創造・展開する存在を各宗教は次のように説明している:
キリスト教---天の父
インドのヴェーダ---ブラフマン梵天
インドのヨガ---宇宙意識
仏教(釈尊)---なし(僧侶の誤解、釈尊は「空」であると説かれている)
真言密教(後代の僧侶)---大日如来(摩訶毘盧遮那如来)
(3)善と悪と空の関係
この記事を読まれている方は既にお気づきのことと思いますが、空の中では縁起・現象界のものや個別の性質はなく諸法無我(個別性はない)です。
空の中では善・悪という性質の区別はありませんので、空は本来的には善でも悪でもありません。
このため、空には愛・慈悲心と残酷な心の区別もありません。
キリスト教で言われているような、「神は愛である」という一面的な説明は、空に対しては成り立たないと思われます。
空は、宇宙を動かすシステムとして稼動している法則です。
愛・慈悲心を持つのは、空により創造された人間であり、仏陀まで進化した人は大慈悲心と呼ばれる心を持たれており、空と同化されています。
人の心が愛・慈悲心を抱けば、空はそれを現象界に実現させます。
もし人が残酷な心を抱けば、空はそれを現象界に実現させます。
要は、人間の心、想念が大きな決定権を持っていると考えられます。
(4)自然災害と空の関係
我々が自然災害と呼ぶ自然界の現象、例えば、東日本大震災、大規模な集中豪雨による洪水・土砂災害、火山噴火のようなものも、空というシステムが自然界に生み出す現象です。
自然は、情け容赦もなく、災害現場に存在するものを全て破壊し押し流していきます。
その破壊力のすさまじさを、私は大規模な自然災害の現場に行って体感したことがあります。
もし太陽系が崩壊期に入れば、空が動かす自然界は、そこに存在する人間の都合や希望を考慮することなく、全惑星を崩壊させることでしょう。
空により起きる自然災害には、仏陀の大慈悲心とは真反対の側面が見られるように思われます。
これらのものが、どのようなメカニズムにより起きるのかは、現代科学も解明していない部分が多いのが現状ですので、私にも良く分かりません。
人間に予知力があれば、災害から逃れることができるだろうと思われますが、そのためには空と同化した神通力が必要です。
しかし、現実には地球人は、その力を持っていませんので、自然災害による大きな犠牲や損害が出ています。
(5)空の技術化
余談ながら、空を技術化・工学化できれば、テレポーテーション(瞬間移動)による大量輸送、無限のエネルギー、無限の資源などを入手できます。
それは、善用すれば人類に多大な幸福をもたらすはずです。
しかし、偏狭な自我を持つ低レベルの人間がそれを手に入れれば、原爆・水爆を凌駕する兵器を生み出し、この世の地獄を作り出すことでしょう。
文献
(A)Title 仏教における空について
Author(s) 坂部 明
Citation信州大学 人文科学論集人間情報学科編 41: 1-12(2007)
Issue Date 2007-03-15
URL http://hdl.handle.net/10091/2783
以下は文献(A)の引用文献
(1) Sn.1119,中村元 訳注〔1994〕 : 『ブッダのことば』236頁, 岩波書店。
(2) M.no,121 (III, pp.104-109), 中阿含, 大正1巻, 736貢~738頁。
(3) M.no.122 (iii, pp.109-118), 中阿含, 大正1巻, 738貢~740頁。
(4)小部経典,南伝大蔵経第4 1巻, 「倶存品第十 空論」, 113頁~124頁。
(5)大正 28巻, 633頁上~中。
(6)Dhp・273,中村元 訳注〔2003〕:『ブッダの真理のことば 感興のことば』 48頁,岩波書店
(7)Dhp.274,同上書, 48頁。
(8)坂部明〔1974〕 :拙稿「空と般若波羅蜜」, 『印度学仏教学研究』第22巻第2号。
(9)中村元〔1960〕 : 『般若心経 金剛般若経』解題184貢以下,岩波書店。
(10)『大品般若経』誓喰品 第五十七(大正8巻, 329頁下~331頁中)。
(11)般若経は声聞・縁覚の智慧である「一切智」,菩薩の智慧である「道種智」,と如来の智慧である「一切種智」を区別する。 (『大品般若経』 「三慧品」,大正 8巻, 375貢中。
(12)荻原雲来 編〔1973〕 : Abhisamayālamkāar'ālokā Praňāpāramitāvyākhyā, pp.94-pp.105 山喜林佛書林,現代語訳:梶山 雄一〔1980〕 : 『大乗仏典2八千頌般若経i』, 35貢~37貢,中央公論社。
(13)大正 8巻, 250頁。
(14)大正 8巻, 253頁~256貢。
(15)坂部 明〔1986〕 :拙稿「般若経にみられる原始仏教思想」, 『初期大乗経典にみられる原始仏教思想一般若経・法華経を中心として』 (昭和58-60年度科学研究費補助金〔一般研究B〕研究成果報告書。
(16) 「空空亦如是。又如服薬。薬能破病。病巳得破薬亦応出。若薬不出則復是病。」大正 5巻, 288頁。
(17)中村 元〔1981〕:『仏教思想6 空 上』平楽寺書店。
(18)長尾 雅人〔1979〕 : 『中観と唯識』 293貢~294頁。岩波書店。
(19) 『大品般若経』七喩品 第八十五(大正8巻, 413頁), N.Dutt; PVS-PP p.4
(20)吉田 洋一〔1979〕 : 『零の発見』岩波書店。
(21)D kha, gagana, ambara, ākaśa, abhra, vyat, vyoma, nabha,など(Datta & Singh〔1962〕 History Of Hindu Mathematics, pp.63)
(22) 「入曼荼羅具縁真言門第二余」 (大正18巻, 9貢)
(23) 「十喩釈論第十一」 (大正 25巻, 102 中)
(24)同上書, 102頁 下。
(25)林 達夫 ほか監修〔1980〕 :「ニヒリズム」 『哲学事典』平凡社。
(26)詳しくは,中村 元〔1980〕 : 『人類の知的遺産13ナーガールジュナ』 48頁~50頁。
(27) M. Nagao : Madhyāntavibhāga-Bhāśya, pp.25,大正 31巻, 466頁。
(28)早島 鏡正 ほか〔1982〕 : 『インド思想史』, 76貢,東京大学出版会。
(29)平川 彰〔1983〕 : 「序章3部派仏教の教理」, 『仏典解題事典』 13頁,春秋社。
(30) N・ Ghoś'a 〔1902〕 : SS-PP, pp.1409 - 1410, Bibliotheca lndica, work 153,漢訳では, 『大般若経』初会に相当する。大正 第5巻, 291頁。
(31)早島 鏡正〔1964〕 : 『初期仏教と社会生活』 300貢,岩波書店。
(32)前掲書,長尾 雅人『中観と唯識』 294頁。
(33) N・Dutt編〔1934〕:Paňcavimśatisāhasrikā-PP, pp.195 -pp.198
漢訳では『大品般若経』「問乗品」第十八(大正8巻, 250頁中~251頁上)などに見られる。
以上
5. 空に関する長谷川洋三 早稲田大学名誉教授の見解
空に関する長谷川洋三 早稲田大学名誉教授の見解をご紹介します。
出典:
『般若心経』の研究―これは大懴悔の経典である
著者: 長谷川 洋三
1934年、新潟県生まれ。1959年、早稲田大学大学院文学研究科英文学専攻修士課程修了。早稲田大学教授を経て、早稲田大学名誉教授
単行本: 342ページ
出版社: 恒文社 (1989/01)
p.166
この空はどういう意味なのだろうか。
空という語彙を用いずして空を表現する他の語彙としては、何が最も好ましいのだろうか。
それに対する筆者の答えは、「根源の大生命」と「み仏の御命」である。
(A)空が「根源の大生命」のように扱われている例
「大品」第二奉鉢品の中で、釈尊は舎利弗に向かって、次のように述べておられる。
空中には色も無く、受想行識も無し、色を離れて亦空無し。
空は即ち是れ色、色は即ち是れ空、空は即ち是れ受想行識、受想行識は即ち是れ空なり。
(国訳大蔵経 経部第二巻、27頁)
備考
東京大学大学院 人文社会系研究科、次世代人文学開発センター、大藏經テキストデータベース研究会の「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース2012版(SAT 2012)」では次のように出力され、内容に一部相違があります。
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223 鳩摩羅什譯 ) in Vol. 08
T0223_.08.0221a21: ◎5摩訶般若波羅蜜經 奉鉢品第二
T0223_.08.0221b29: 薩字性空。空中無色無受想行識。離色亦
T0223_.08.0221c01: 無空。離受想行識亦無空。色即是空。空
T0223_.08.0221c02: 即是色。受想行識即是空。空即是識。何以故。
T0223_.08.0221c03: 舍利弗。但有名字故謂爲菩提。但有名字
(SAT 2012からの引用終わり)
空の中には色も無く、受想行識も無し、色を離れて亦空無し。受想行識を離れて亦空無し。
色は即ち是れ空、空は即ち是れ色、受想行識は即ち是れ空、空は即ち是れ識。
注意: 最後の部分が「空は即ち是れ識」となっているのはデータベースのミス、あるいは省略形で書かれていると思われます。前後関係から考えると、ここは「空は即ち是れ受想行識」となるはずです。
(備考終わり)
右の文を集合論的に整理すると、次の二つの集合になる。
(1)空の中には色・受・想・行・識などはない。
(2)空は、色・受・想・行・識そのものである。
右の二つの集合は一見、矛盾しているかにみえる。
だが、さらに整理すれば少しも矛盾していないことに気付く。
つまり、「空とは現象や精神活動以前からのものであって、しかも現象や精神の働きそのものでもある」という意味なのであり、少しも矛盾しないのである。
p.167
この解釈では、空とは、たとえば原子や素粒子などをも作動させしめる宇宙の根源の力を指すものと言える。
宇宙に充満していて、森羅万象の誕生以前のものでありながら、森羅万象そのものでもある「根源の大生命」とでもいうべきものを指しているのである。
釈尊は、物質も精神活動も、この「根源の大生命」そのものであることを看破されたのである。
それは、見ることも計量することもできないから、空という言葉で表現せられたものであろう。
それ自体は、見ることも計量することも出来ないけれど、「(色・受・想・行・識という)現象や働きによって知られ、はっきりと認められる」のである。
それは、宇宙に充満する「実在」であり、「実相」であり、「真如」であり、「真実」なるものであるが、計量不可知であるから「空」と表現され、「法華経」の中では「第一義諸法実相空」と述べられているのである。
森羅万象が生起する以前から宇宙に充満し、宇宙そのものであった、「実在」を実相というのであり、筆者はそれを「根源の大生命」と呼ぶのである。
「法華経」の中の「諸法実相空」という句をわかり易く表現するなら、「さまざまな差別相を持つ森羅万象であるが、その実の相は絶対平等の大生命である」という意味である。
この解釈は十八空のいずれとも矛盾するものではない。
(B)空が「み仏の御命」として扱われている例
ところで、宇宙の全てであり森羅万象の命そのものでもある「根源の大生命」を、筆者は人格的に捉えて「み仏の御命」と呼びもするのであるが、仏典の中で空を「み仏」と同義にみなしている例は、「大品」の曇無竭(どんむかつ)品第八十九の中にみられるのである。
善男子、諸仏は従(よ)って来る所無く、去ってまた至る所無し。
何を以ての故に。諸法如は不動相なり、諸法如は即ち是れ仏なればなり。
善男子、無生の法は来る無く去る無し、無生の法は即ち是れ仏なればなり。
無滅の法は来る無く去る無し、無滅の法は即ち是れ仏なればなり。
実際の法は来る無く去る無し、実際の法は即ち是れ仏なればなり。
空は来る無く去る無し、空は即ち是れ仏なればなり。
善男子、無染は来る無く去る無し、無染は即ち是れ仏なればなり。
寂滅は来る無く去る無し、寂滅は即ち是れ仏なればなり。
虚空性は来る無く去る無し、虚空性は即ち是れ仏なればなり。
善男子、この諸法を離れては更に仏無し、諸仏如と諸法如とは一如にして分別無し。
善男子、是の如は常一にして無二無三なり、諸数法を出で、所有無きが故に。
(国訳大蔵経 経部第三巻、372頁)
右の経文から、次の結論が導かれる。
つまり、「森羅万象には、それぞれ固有の実体がなく、その本来の真実の相は不変である。
不変なるものは真如であり仏である。
したがって、第一義諸法実相は、仏である。
故に、「第一義諸法実相は空なり」と言われる空は仏である。
そして、森羅万象は仏を離れては存在せず、故に森羅万象は仏である。
なぜなら、仏の仏たる真如と、一切の物の一切の物たる真如とは毫(ごう、少しも)異なることがないからである。
森羅万象が平等であって差別がないといわれるのは、森羅万象が仏であるからなのである。
つまり、空は仏なのである。」
ブログ著者注:
東京大学大学院 人文社会系研究科、次世代人文学開発センター、大藏經テキストデータベース研究会の「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース2012版(SAT 2012)」では次のように出力されます。
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223 鳩摩羅什譯 ) in Vol. 08
T0223_.08.0421b24: *摩訶般若波羅蜜經17法尚品第八十九
T0223_.08.0421b25: 18丹本曇無竭品
T0223_.08.0421b26: 爾時曇無竭菩薩摩訶薩語薩陀波崙菩薩
T0223_.08.0421b27: 言。善男子。諸佛無所從來去亦無所至。
T0223_.08.0421b28: 何以故。諸法如不動相。諸法如即是佛。善
T0223_.08.0421b29: 男子。無生法無來無去。無生法即是佛。無
T0223_.08.0421c01: 滅法無來無去。無滅法即是佛。實際法無 画像
T0223_.08.0421c02: 來無去。實際法即是佛。空無來無去。空
T0223_.08.0421c03: 即是佛。善男子。無染無來無去。無染即是
T0223_.08.0421c04: 佛。寂滅無來無去。寂滅即是佛。虚空性
T0223_.08.0421c05: 無來無去。虚空性即是佛。善男子。離是
T0223_.08.0421c06: 諸法更無佛。諸佛如諸法如。一如無分別。
T0223_.08.0421c07: 善男子。是如常一無二無三。出諸數法
T0223_.08.0421c08: 無所有故。譬如春末月日中熱時。有人
(SAT 2012からの引用終わり)
大般若経には、「空即是佛」と書かれており、仏陀は空と同化(一体化)されている存在であることを示しています。
「虚空性即是佛」とも書かれており、空と虚空は同じものであることを示しています。
大般若経のこの記述が示しているのは、空=虚空と仏陀が同化(一体化)されていることです。
空と仏陀のどちらが先に宇宙に存在したかといえば、空が先に存在し、空により生み出された人が進化して仏陀となり空と同化したと考えられます。
ですから、仏陀が空と同化されている存在であることは確かなことですが、空を「み仏の御命」と呼ぶのは、宗教的・信仰的な表現であり、それを是とするか非とするかは、その人の信仰心の問題であると思われます。その点はこのブログの読者ご自身で判断してください。
(ブログ著者注終わり)
(C)空とキリスト教の神との関連
p.176
たしかに五蘊(注: 色・受・想・行・識)には、それぞれの自性はない。
しかし、それを生ましめ働かせる根本となるものは、あるのである。
その根本なるものが、「み仏の御命」なのである。
したがって、「五蘊皆空」の「空」は、「神と被造物」の「神」にも匹敵し、新約聖書「ローマ人への手紙」第一章第二十節の、「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められる」という文に見られる、「神の目に見えない本性」に匹敵する、と筆者は思う。
(D)要約
長谷川洋三先生は、「空」を
宇宙の法則的表現:「根源の大生命」
仏教的表現: 「み仏の御命」
キリスト教的表現:「神の目に見えない本性」
であると述べておられます。
私が、大品系般若である『二万五千頌般若』で説かれている「十八空」を解釈して要約すると、次のようになりました:
『縁起・現象相の本質相は空であり、空は物理的に実在し、空は単なる観念や哲理ではなく物理的実在である。
縁起・現象相と本質相の空は別々の2つものがあるのではなく、1つのものを2つの面から見ているだけであり、縁起・現象相と空は一体である。
空には、時間・空間が存在せず無次元・無時間であり、空は時間・空間を超越している物理的存在である。
空の中には縁起・現象相の個別の存在物及び性質は一切存在しない。
縁起・現象相の全ての存在物・性質は、空では「空という1つの統一体」として1つに統一されたものとして存在し、空は縁起・現象相のいかなる性質にも染まっていない(諸法無我、個別性はない)。
空の中には空間がないため、空には質量もなく、空の中には現象相の性質もないため、陰または陽の電荷もない物理的な存在と考えられる。
空は、現象相で知られているようなエネルギーや波動という性質も持っていない。
空は、初めもなき、終わりもなき、永遠の、無限の力、全知全能の完全無欠な「空という1つの統一体」であり、空は現象界の全てを生み出す智慧と力を持つ。空は、「万物の創造主」「宇宙の英知」と呼ぶことが可能である。』(空は、大我ではなく、無我であると思われる)
キリスト教やヨガの記述によれば、天の父、宇宙意識が全てのものを創造し動かしていると書かれています。
このため、「空」「根源の大生命」「神の目に見えない本性」のような存在が、全てのものを創造し動かしていると解釈することは、キリスト教やヨガと類似した解釈です。
このように、仏教で説かれている「空」は、「根源の大生命」「神の目に見えない本性」と呼ぶことは可能であり、それらはキリスト教やヨガの説く天の父、宇宙意識と類似しているように私には思われます。
ここに、仏教、キリスト教、ヨガの本質的な類似性が見られるように思われます。
補足1:
神通力と空の関連
東京大学大学院 人文社会系研究科、次世代人文学開発センター、大藏經テキストデータベース研究会の「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース2012版(SAT 2012)」では次のような出力があります。
大般若波羅蜜多經 (No. 0220 玄奘譯 ) in Vol. 07
T0220_.07.0459b10: 時。不應住諸字及諸字所引。復次世尊。諸菩
T0220_.07.0459b11: 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住神
T0220_.07.0459b12: 通。何以故。世尊。神通神通性空。世尊。是神
T0220_.07.0459b13: 通空非神通。神通不離空。空不離神通。神通
T0220_.07.0459b14: 即是空。空即是神通。由此因縁諸菩薩摩訶
T0220_.07.0459b15: 薩修行般若波羅蜜多時。不應住神通
T0220_.07.0459b16: 復次世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
T0220_.07.0459b17: 多時。不應住色乃至識若常若無常。若樂若
T0220_.07.0459b18: 苦。若我若無我。若淨若不淨。若空若不空。
T0220_.07.0459b19: 若有相若無相。若有願若無願。若寂靜若不
T0220_.07.0459b20: 寂靜。若遠離若不遠離。何以故。世尊。色等
T0220_.07.0459b21: 法常無常。色等法常無常性空。世尊。是色等
T0220_.07.0459b22: 法常無常空。非色等法常無常。色等法常無
T0220_.07.0459b23: 常不離空。空不離色等法常無常。色等法常
T0220_.07.0459b24: 無常即是空。空即是色等法常無常。由此因
T0220_.07.0459b25: 縁諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不
T0220_.07.0459b26: 應住色乃至識若常若無常。色等法樂苦乃
T0220_.07.0459b27: 至遠離不遠離亦復如是。復次世尊。諸菩薩
T0220_.07.0459b28: 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住眞如
T0220_.07.0459b29: 法界法性法定實際。何以故。世尊。眞如眞如
T0220_.07.0459c01: 性空。世尊。是眞如空非眞如。眞如不離空。空
T0220_.07.0459c02: 不離眞如。眞如即是空。空即是眞如。由此因
T0220_.07.0459c03: 縁諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不
T0220_.07.0459c04: 應住眞如法界法性法定實際亦復如是。復
このように大般若経には「神通即是空、空即是神通」と書かれており、仏教の神通力は空の力であることが分かります。
また、真理の世界を仏教では真如と呼びますが、大般若経には「眞如即是空、空即是眞如」と書かれており、空が真如(眞如)、即ち真理の世界であることが分かります。
お釈迦様のような如来とは、真如から来られた方という意味ですが、その真如とは空のことであることが、この大般若経の記載は示しています。
補足2:
長谷川先生は、仏教とキリスト教の比較宗教学の研究もされており、次の著書もありますので、関心がおありでしたら読まれると良いと思います。
キリストの言葉、ヨハネの言葉と仏教の類似性に関する詳細な考察がされています。
キリスト教と仏教の同質性―東洋型神学を求めて
長谷川 洋三
単行本: 195ページ
出版社: 早稲田大学出版部 (2000/08)
キリスト教の「三位一体」と仏教の「仏の三身」との比較分析をとおして独自の解釈を試み、キリスト教と仏教が根底的に相似の構造を持つことを論証する。
以上
4.初期仏教の般若経などの空の記述と空の解釈
空に関しては、初期仏教にまで遡る必要がありますので、ネット検索をすると以下の文献を発見しました。
最初の部分は、以下の文献(A)より、学術資料として抜粋引用します。
文献(A)
Title: 仏教における空について
Author: 坂部 明
Citation: 信州大学 人文科学論集 人間情報学科編 41: 1-12(2007)
Issue Date: 2007-03-15
URL http://hdl.handle.net/10091/2783
「空」ということばは、初期仏教(原始仏教)において、ゴータマ・ブッダによってすでに説かれていた。
「世界を空なりと観ぜよ」(1)のことばをはじめとして、空についての教説は『小空経』(2)、『大空経』(3)、『無礙解道』(4)などにも説かれている。また、経典以外の論書では、『舎利弗阿毘曇論』(5)などにも説かれている
「空」の思想が前面に押し出されて登場するのは、大乗仏教の先駆的経典である般若経においてである。その後、大乗仏教運動の中で数多くの経典が登場するが、空の思想はそれらに共通する主要な概念となる。
般若経は経名にもあるとおり、六波羅蜜の中心となる実践道「般若波羅蜜」を説く経典であるが、その思想は空と深く関わっているのである。(8)
「空」とはなにか
(1)空の原語について
空の原語は、サンスクリット語では「シューニャ」、パーリ語では「スンニャ」である。これらは品詞としては形容詞または中性名詞として使われる。すなわち、述語として「…は空である」と表現する。またこの単語には、しばしば抽象名詞を作る語尾taをつけて、 「シューニャター(空であること、空性)という用語が作られしばしば仏典に現れる。ただ、これらの単語は主語としては用いられないという特徴を持っている。
◎空の原語「シューニャ」の意味
鈴木学術財団編[1986] :『漢訳対照焚和大辞典』講談社によれば、次のような意味がある。
形容詞: からの、空虚な、住む者のない、など。 「具格とともに」~を欠いている。
中性名詞: 空虚な場所、中空、非存在、絶対的空(仏教)、零
漢 訳: 壁、空無、空虚、空義、など。
(2)空の比喩について
般若経は十種の比喩を用いて空を説明する。比喩表現を多用するのは、インド人の民族性に由来する。インド論理学の五分作法にも「喩」が存在している。比喩は智者に意義を知らしめるために用いられるという。初期仏教の古層に属するとされる『スッタニパータ』、『ダンマパダ』にも比喩表現が多くみられるから、この傾向は仏教初期のころから存在していたものと思われる。
般若経に説かれる十種の比喩は次のとおりである。(19)
1.幻(māyā) 2.焔(marīci) 3.水中の月(udaka-candra) 4.虚空(ākāśa)
5.響(pratiśrutkā) 6.闥婆城(gandharva-nagara) 7.夢(svapna)
8.影(prātibhāsa) 9.鏡中の像(pratibimba) 10.化(nirmita)
この中で特に注目すべきなのは、4.虚空「アーカーシャ」(ākāśa )である
大乗経典には、空の比喩として「虚空」が多く用いられる。
『大日経』では、 「空は虚空に等しい」という。
「我本不生を覚り、語言道を出過す。 諸の過を解脱することを得て、因縁を遠離したり。
空は虚空に等しと知って、如実相の智生ず。」(22)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ブログ筆者補足: 空と虚空は実在する
虚空(アーカーシャ)に関しては、Wikipedia英語版では、
「The Vaibhashika, an early school of Buddhist philosophy, hold Akasha's existence to be real.
初期の仏教哲学バイベーシカVaibhāṣikaは、アーカーシャの存在を実在である(物理的に存在する)と捉えていた。」
と述べられている。(a)
(a) http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha
Encyclopedia of Asian Philosophy By Oliver Leaman, Contributor Oliver Leaman, Taylor & Francis, 2001, ISBN 0-415-17281-0, pg. 476
(注: realという英単語には、「実在している」「物理的に存在する」という意味があるため、上記のように翻訳しています。)
つまり、虚空、アーカーシャとは、物理的に実在しているが、物質による現象界を超越した存在であるとみなされており、大日経は「空は虚空に等しい」と述べているため、虚空=空は実在していると考えられる。
(補足終わり)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(3)般若経の主張
般若経は、この説一切有部の存在実在論に否定的な響きで対抗する形で「一切法の空」をとく。
般若経のいう一切法(存在するもののすべて)とは、『般若心経』にも現れるが、「五経(五蘊)」 (色受想行識)、「十二処(六内処-眼・耳・鼻・舌・身・意と、六外処-色・声・香・味・触・法)、 「十八界」 (十二処に眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識を加えたもの)などであり、初期仏教で説かれていた存在(法)の体系をそのまま採用したものである。
なお、般若経の原典のうちで最も大部な『十万頌般若』では、 「一切法」について次のようにいう。
「一切法とはつぎのものに云われる。すなわち、色・受・想・行・識(五経)と眼・耳・鼻・舌・身・意(六内処、六根ともいう)と、色・声・香・味・触・法(六外処、六境ともいう)と、眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識(六識)と、眼触・耳触・鼻触・舌触・身触・意触(六触)と、眼触より生じた受・耳触より生じた受・鼻触より生じた受・舌触より生じた受・身触より生じた受・意触より生じた受と、有色法・無色法と、無為法・有為法とである。これらが一切法と云われる。」
続けて次のようにいう。
「一切法は、一切法を欠いている。 (一切法は一切法として空である)常ではなく、壊ではないから。理由は何であるか。空であることが、一切法の本性(prakrti)だからなのである。」と。(30)
(ブログ著者補足: 一切法とは、縁起・現象相に存在する全てのものです。一切法空とは、縁起・現象相に存在する全てのものが、本質相では空であることを意味しています。これは別の言葉では一切皆空とも言われています。)
般若経では、空を観察するときの対象、何が空であるのかについて述べている。
大品系般若である『二万五千頌般若』では、十八種の空「十八空」をとく。
これらの原型は既に、初期仏教の仏典『舎利弗阿毘曇論』などに説かれていたが、それらに大乗仏教の特色、たとえば「一切法空」などを加えて整備したものである。 (33)
十八空の名称は、つぎのとおりである。
1.内空 2.外空 3.内外空 4.空空 5.大空 6.勝義(第一義)空 7.有為空 8.無為空 9.畢竟空10.無始空11.散空12.性空13.一切法空14.自相空15.不可得空16.無法空17.有法空18.無法有法空
ブログ筆者注:
以下は十八空に関する坂部氏による仏教界の伝統的な説明であり、空を「とらわれてはいけない」という意味にとらえています。比較のために、ここに書いておきます、この後に、空が物理的に実在することを前提とする私の解釈を示します。
坂部氏の解説:
これらについて簡略に説明すれば以下のとおりである。
内空; 六内処(眼耳鼻舌身意。すなわち自己)が空であると観察する。以下同じ。
外空; 六外処(色声香味触法。すなわち外界,六内処の対象)が空である
内外空; 六内処,六外処共に空である。内外にとらわれないように
空空; 空もまた空である, 空にとらわれてはならない, 空を実体とみてはならない
大空; 十方(東西南北, 四維-四方の中間の方角, および上下)は空である
勝義空; 最高の真理は空である。 『維摩経』における「維摩の一黙」のように
有為空; 有為法は空である
無為空; 無為法は空である。たとえば, 「涅槃」は空である
畢寛空; (虚空の)辺際(atyanta)は得られないから空である
無始空; 過去と未来, (また現在も)空である
散空; 存在は五経(五蘊)和合した仮の存在であるから空である
性空; あらゆる存在の本性は空である, だれかが造ったというものではない
一切法空; 人間が考察しうるあらゆる存在は空である(前述)
自相空; あらゆる存在の相(特徴), たとえば有為法は無常であるとか,六波羅蜜の特徴とかいろいろな特徴があるが, それらは空である,とらわれてはならない
不可得空; 過去,未来の存在は得られない, 現在の存在も常住ではないから得られない, したがって空である
無法空; 非存在, 無, あるいは形成されないものは空である
有法空; もろもろの存在は因縁和合して存在しているのであるから, 存在固有の本質は空である
無法有法空; 非存在, 存在の本質, 存在の生滅は本来空である
なお, これらは, 順序にしたがって観察されるべき空観であった。まず自己の空を観察し, 自我の執着をはなれ(人空), つぎに自己の所有になると思われる存在(身体や自己の愛着するもの, 在家の人であれば, 家族, 財産, 地位, 名誉など)の執着を離れ(法空)が基本となっていることは明らかである。それ以降は想定しうる概念を空とみる実践が連続している。
Ⅴ むすび
この般若経の空観は,やがてナーガールジュナの『中論』, 『十二門論』などによって理論化される。その弟子デーヴァの『百論』を加えて三論宗が成立し,我が国には奈良時代に中国より伝来し, 南都六宗の一つに数えられている。
空はなかなか理論としては理解しがたいものではあるが, 要は何物にも執着しない生き方の中に体得されるもの(中国的理解の用語を使えば, 体空観)なのである。
有と無という観念にとらわれないところに, 空観の実践がある。たとえてみれば, 桜の木は春となり, 諸緑が整って美しい花を咲かせる。 夏, 秩, 冬の時期には花の形はおろか何もみえなかった桜の木はいわば空なのである。しかし, それは無ではなかった。 春ともなれば, 蕾みを生じ, やがて美しい花となる。 美しく咲いたその桜の花は「妙有」というべきものであろう。 これにより, 縁起の理法がそこにあると観察するのである。有ではなく, 無でもなく, 存在は空であると観察して, 苦悩のもととなる執着を離れて彼岸に達し, しかもこの世の美しきを楽しく見るというのが, 本当に幸せな生き方なのではないだろうか。空観はそのような意味において現代においてもなお有効性は失われていないのである。
ここまでは、信州大学、坂部明氏の文献(A)からの引用抜粋です。
文献(A)の引用文献は末尾のリストの( )の数字で本文中に示してあります。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ここから先は、従来の誤解された空の既成概念にとらわれず、縁起・現象相ではなく、無為の本質相に「空という1つの統一体」が物理的に実在しているという観点から、十八空の説明を私なりに試みたものであり、まだ検討の途中段階で未完成なものであることをお断りしておきます。
私は如来ではなく凡夫ですから、空を実際に体験していませんので、完全に正しい解釈をする自信はありません。
ただし、100点満点のテストとすれば、合格点の60点はクリヤーしていると思っています。
「十八空」という名称は、空が18種類あるという意味ではなく、「空という1つの統一体」の説明を18種類考えてみたというものであり、多くのものが重複しており、中には大して意味のない屁理屈にすぎない説明もあります。
古い時代の仏典では、この説明の数はもっと少ないものでした。
坂部明氏の「空と般若波羅蜜」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ibk1952/22/2/22_2_894/_article/-char/ja/
印度學佛教學研究Vol. 22 (1973-1974) No. 2 P 894-899
によれば、空の説明の数が増えて行った様子が次のように書かれています。
『十八種の空のうちの最初の三種の空、即ち内空、外空、内外空についてみると、マッジマ・ニカーヤの『空の大経』に、「内に空を作意する」という表現がとられてはいるが、まだ「内空」というような熟語として表わされてはいない。
ところが部派仏教に入ってこの三種の空が熟語として定着し、増広され、『舎利弗阿毘曇論』では六空となり、『大毘婆沙論』では十空となり、さらに般若経は十八種の空に増広させたものと思われる。
なお、前記マッジマ・ニカーヤ『空の大経』、中阿含『大空経』、及び『舎利弗阿毘曇論』では、この三種の空を空定(空三昧)として説いているから、『般若経』の十八空がそれらを増広していったものと考えると、『般若経』の十八種の空も空三昧の点から見直される必要があるであろう。』
(引用終わり)
最初は、3種の空の解説、即ち内空、外空、内外空しかなかったものが、いつの間にか18種類にまで増やされている実態が分かります。これらは、仏教の僧侶たちが増やして行ったものです。
仏典は、如来であられるお釈迦様が直接書かれたものは一つもなく、全ては弟子や時代がかなり経過した後に僧侶により書かれたものです。
お釈迦様の弟子の大部分や後代の僧侶は如来ではありませんから、空と同化していない、つまり真如の存在ではありませんから、空の真相を体験していません。このため、理解不足、舌足らず、説明不足、言い過ぎのような問題が含まれているのは避けられないと思われます。つまり、完全無欠な経典は恐らく無いだろうということです。この問題点は、キリスト教の聖書でも同様です。
以下に、従来の誤解された空の既成概念にとらわれず、「空という1つの統一体」が物理的に実在し、縁起・現象相の存在は本質相では全て空である(一切法空)という観点から、十八空の説明を私なりに試みましたので参考になれば幸いです。
(坂部氏の「とらわれてはいけない」あるいは他の学者や僧侶の「むなしい」という伝統的な仏教の空の18種の解説と、重松氏の解釈や無為に関する資料に基づく私の解釈を比較してみてください)
(1)内空
現象界の六内処(眼耳鼻舌身意。すなわち自己)は、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
(2)外空
現象界の六外処(色声香味触法。すなわち外界, 六内処の対象)が、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
(3)内外空
現象界の六内処, 六外処共に、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
(4)空空
空空に関しては、坂部明氏が
「般若経等よりみた空空について、印度學佛教學研究 Vol. 19 (1971) No. 2」
という論説を書かれていますので、以下に引用します。
ここで論じようとする《空空》という名称は、『大品般若経』等に説かれている十八空等の中のそれである。
この名称は、小部経典『無礙解道』、及び部派の論書『舎利弗阿毘曇論』、『大毘婆沙論』等に既に現われており、『大品般若経』は、その名称を取り入れたものと思われる。なお、十八空は小品類にはまだ現われていないので、大品類以後になって発展的に採用されたものであろう。
以下に、『大品般若経』とそれに関した論書を資料として挙げて、《空空》の意義を検討したい。
『二万五千頌般若』
『そこで空空とは何であるか? 《一切法の空であるところのものは、その空によって空である》。常ではなく、壊ではないに縁って。それは何の理由であるか? 空であることが、一切法の空の本性なのである。これが空空と云われる。』
漢訳では以下の如くである。
『何等為空空。一切法空是空亦空非常非滅故。何以故。性自爾。是名空空』(『大品般若経』)
(引用終わり)
これを要約すると、
「一切法(全ての存在)が空であるということは、それが空であるから空なのである。その理由は、空であることが一切法(全ての存在)の本性(本質)だからである」
となります。
これは、次のように解釈できます:
空は空であり、「空という1つの統一体」以外のものではない。空が何か他のものにより作られているのではない。空は究極の存在であり、それより先には何も存在しない。
(5)大空
現象界の十方(東西南北、四維-東西南北の中間の方角、および上下)は、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
つまり、現象界に存在する空間、距離、位置(座標)、大きさは、空の中には存在しない。
現代科学的な表現では、空にはxyz-3次元座標系が存在せず、次元が存在しない、つまり無次元である。
空では空間、距離、座標が存在しないから、例えば東京、ロンドン、パリは同じ場所であり、地球、土星、アンドロメダ銀河も同じ場所である。
空には大きさという概念がないため、現象界の無限の全宇宙にも、微小な素粒子にも同時に対応可能である。つまり、空は現象界では無限の全宇宙の全ての場所に同時に存在している。
空は、3次元現象界の常識では考えられない「無次元」という性質を持っている。
(6)勝義(第一義)空
最高の真理と呼ばれるものも「空という1つの統一体」である。
早稲田大学 長谷川洋三名誉教授の著作「『般若心経』の研究」のp.162によれば、第一義とは「森羅万象の根本となるもの」という意味です。
このため、勝義(第一義)空とは、「森羅万象の根本となるもの」は「空という1つの統一体」であることを意味しています。
(7)有為空
有為法、つまり縁起・現象界の全ての存在は、本質相の空の中には個別には存在せず、「空という1つの統一体」である。
(8)無為空
無為法(生滅変化を超えた常住絶対なもの)
①虚空無為(ものの存在する場)
②択滅無為(ちゃくめつむい)(智慧による煩悩の消滅〕
③非択滅無為(ひちゃくめつむい)(智慧によらない煩悩の消滅)
は「空という1つの統一体」である。
(9)畢竟空
(虚空の)辺際(atyanta)は存在しない、「空という1つの統一体」には果てはないからである。
(10)無始空
空には、始まりがなく、終わりもなく、過去、現在、未来が存在しない、つまり時間が存在しない。
例えば、空では100億年前と現在と100億年後の区別はなく、今という時間しかない。
空は、3次元現象界の常識では考えられない「無時間」という性質を持っている。
これと同様の説明は、東京大学大学院大藏經テキストデータベース研究会の「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース2012版(SAT 2012)」の次の出力にも見られる:
大般若波羅蜜多經 (No. 0220 玄奘譯 ) in Vol. 05
T0220_.05.0022b02: 非造作相。諸識空彼非了別相。何以故。舍利
T0220_.05.0022b03: 子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是
T0220_.05.0022b04: 色。受想行識不異空。空不異受想行識。受想
T0220_.05.0022b05: 行識即是空。空即是受想行識。何以故。舍利
T0220_.05.0022b06: 子。是諸法空相不生不滅。不染不淨。不増不
T0220_.05.0022b07: 減。非過去。非未來。非現在。舍利子。如是空
T0220_.05.0022b08: 中。無色。無受想行識。無地界。無水火風空識
ここでは「是諸法空相 不生不滅。不染不淨。不増不減。非過去。非未來。非現在。」と説かれており、
諸法、即ち全ての存在の空という本質は、生まれることも滅することもなく、何かに染まって汚れたり清いというような何らかの性質を持つこともなく、増えたり減ったりすることもなく、過去・現在・未来のいずれでもない、つまり時間はない、無時間であると説かれている。
(11)散空
現象界の存在物は色・受・想・行・識(五経、五蘊)の因縁和合により構成され、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
(12)性空
本性空と言い換えることができ、現象界の存在物の本性は、本質相では「空という1つの統一体」である。
(13)一切法空
一切法、即ち縁起・現象界の全ての存在は、本質相の空の中には存在せず、本質相では「空という1つの統一体」である。
別の仏教用語では「一切皆空」とも言われる。
全世界、全宇宙の全ての物質、全てのエネルギー、現象界の全ての自然物及び社会的存在物や条件、全ての知識・情報・技術・智慧、全ての人の思い(心、意識)、全ての場所、全ての過去・現在・未来の時間など、現象界の全てのものは、本質相では「空という1つの統一体」である。
全ての存在は、空の中では縁起・現象界の諸々の存在の区別はない、「空という1つの統一体」である(これを仏教では諸法無我と呼ぶ)。この点は般若心経にも述べられている。
一切皆空は、別の表現では一切即是空であり、色即是空・空即是色と同様の形式で、空即是一切と表現できる。これは、空が現象界の一切の存在を生み出していることを示している。
(14)自相空
あらゆる存在の相(特徴)は、本質相では「空という1つの統一体」である。
(15)不可得空
三省堂 大辞林によれば、不可得は、
〘仏〙 真理・悟り,仏の考えなどが人間の思慮を超えていて認識できないこと。
と解説されています。
このため、不可得空とは、真理・悟り,仏の考えなどが人間の思慮を超えていて認識できず、それは、それらが本質相の「空という1つの統一体」であるためです。
(16)無法空
法すなわち存在物ではないものは、本質相では「空という1つの統一体」である。
(17)有法空
縁起・現象界の一切の存在物は、本質相では「空という1つの統一体」である。
(18)無法有法空
一切の存在物、非存在物は、本質相では「空という1つの統一体」である。
(空の実在を前提とする十八空に関する独自の解釈を終了)
これまで調べてきた空の性質を要約すると、次のようにまとめることができます。
『縁起・現象相の本質相は空であり、空は物理的に実在し、空は単なる観念や哲理ではなく物理的実在である。
縁起・現象相と本質相の空は別々の2つものがあるのではなく、1つのものを2つの面から見ているだけであり、縁起・現象相と空は一体である。
空には、時間・空間が存在せず無次元・無時間であり、空は時間・空間を超越している物理的存在である。
空の中には縁起・現象相の個別の存在物及び性質は一切存在しない。
縁起・現象相の全ての存在物・性質は、空では「空という1つの統一体」として1つに統一されたものとして存在し、空は縁起・現象相のいかなる性質にも染まっていない(諸法無我、個別性はない)。
空の中には空間がないため、空には質量もなく、空の中には現象相の性質もないため、陰または陽の電荷もない物理的な存在と考えられる。
空は、現象相で知られているようなエネルギーや波動という性質も持っていない。
空は、初めもなき、終わりもなき、永遠の、無限の力、全知全能の完全無欠な「空という1つの統一体」であり、空は現象界の全てを生み出す智慧と力を持つ。空は、「万物の創造主」「宇宙の英知」と呼ぶことが可能である。』(空は、大我ではなく、無我であると思われる)
空に関するこの概念は、キリスト教の「父なる神」「神の国」、インドの宗教ヴェーダの「ブラフマン梵天」、ヨガの「宇宙意識」、真言密教の「大日如来」に類似すると考えられる。(各宗教・宗派により定義の内容が異なり誤りも含むだろうが、基本的な部分は類似していると考えられる)
悟りを開かれた釈尊は、「空という1つの統一体」の物理的実在と機能を説くことにより、宇宙の創造と展開の原理を説かれていたと考えられる。
ただし、釈尊の説かれている「空」は、大我ではなく、無我であると思われる。
それらの教えは、如来であられる釈尊が地球におられた頃には、弟子の中でも理解力の進歩した人たちにより理解されていたが、空と同化された如来が地球を去られて数百年たつと、本当に理解している人がいなくなり、空を縁起・現象界の事象の相互関係と見なす誤解が生じ、それがさらに「空しさ」「とらわれるな」と誤解され、現在に至っていると考えられる。
現代仏教は、空という統一体の持つ恐るべき性質と能力を知らないし、活用していないと思われる。
備考
(1)大日如来
Wikipediaよりの引用
大日如来(だいにちにょらい)、梵名 マハー・ヴァイローチャナ(महावैरोचन [mahaavairocana])は、虚空にあまねく存在するという真言密教の教主[1]。
「万物の慈母」[2]、「万物を総該した無限宇宙の全一」[3]とされる汎神論的な仏[4]。
声字実相を突き詰めると、全ての宇宙は大日如来たる阿字に集約され、阿字の一字から全てが流出しているという[5]。
神仏習合の解釈では天照大神(大日孁貴)と同一視もされる。
概要
「無相の法身と無二無別なり(姿・形の無い永遠不滅の真理そのものと不可分である)」[1]という如来の一尊。摩訶毘盧遮那如来(まかびるしゃなにょらい)、大光明遍照(だいこうみょうへんじょう)とも呼ばれる[4]。
なお、宇宙とはあらゆる存在物を包容する無限の空間と時間の広がり、および宇宙空間を指す(詳細は「宇宙」を参照)。
大日如来は、無限宇宙に周遍する点では超越者だが、万物と共に在る点では内在者である[3]。
全一者であり、万物を生成化育することで自己を現成し、如来の広大無辺な慈悲は万物の上に光被[※ 1]してやまないとされる[3]。
三世(過去・現在・未来、前世・現世・来世)にわたって常に説法しているとも説かれる[6]。
出典
[1]『望月 佛教大辞典 4 増訂版』(世界聖典刊行協会)、3343-3344頁。
[2]『明鏡国語辞典』(大修館書店)、「大日如来」。
[3]林達夫他 『世界大百科事典 19』 平凡社 、1972年、163頁。
[4]『密教曼荼羅』(新紀元社)。
[5]奈良康明 『仏教名言辞典』 東京書籍、1989年、568頁。
[6]Encyclopædia Britannica, Inc. 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書版』 ブリタニカ・ジャパン株式会社、2009年、「大日如来」。
(2)仏教は「空」の真実を見失い、苦肉の策の代用品として大日如来を考案した
覚者・如来であられる釈尊は、森羅万象・全宇宙を創造・展開する存在と同化され、それを「空」と名づけられた。
しかし、如来が去られ、空の真実を体験している者がいなくなった時代になると、後世の僧侶たちは空と同化していないため、空の真実を理解できなかった。
そして、縁起・現象相の一時的な相互依存関係が空であると解釈し、空とは、これらのものに「こだわらないこと」「とらわれないこと」であると説いた。
この誤解により、仏教は、その教義の中から、森羅万象・全宇宙を創造・展開する存在を欠落させ、この誤解が八宗の祖と賞賛されている2世紀頃のナーガルジュナにより確立され現代に至っている。
しかし、後代の真言密教系の僧侶たちは、この欠落を補うために、インドの宗教ヴェーダの「ブラフマン梵天」、ヨガの「宇宙意識」に類似した大日如来(摩訶毘盧遮那如来)を導入し、宇宙の創造・展開を行う存在を説明しようとしたと考えられる。
補足
森羅万象・全宇宙を創造・展開する存在を各宗教は次のように説明している:
キリスト教---天の父
インドのヴェーダ---ブラフマン梵天
インドのヨガ---宇宙意識
仏教(釈尊)---なし(僧侶の誤解、釈尊は「空」であると説かれている)
真言密教(後代の僧侶)---大日如来(摩訶毘盧遮那如来)
(3)善と悪と空の関係
この記事を読まれている方は既にお気づきのことと思いますが、空の中では縁起・現象界のものや個別の性質はなく諸法無我(個別性はない)です。
空の中では善・悪という性質の区別はありませんので、空は本来的には善でも悪でもありません。
このため、空には愛・慈悲心と残酷な心の区別もありません。
キリスト教で言われているような、「神は愛である」という一面的な説明は、空に対しては成り立たないと思われます。
空は、宇宙を動かすシステムとして稼動している法則です。
愛・慈悲心を持つのは、空により創造された人間であり、仏陀まで進化した人は大慈悲心と呼ばれる心を持たれており、空と同化されています。
人の心が愛・慈悲心を抱けば、空はそれを現象界に実現させます。
もし人が残酷な心を抱けば、空はそれを現象界に実現させます。
要は、人間の心、想念が大きな決定権を持っていると考えられます。
(4)自然災害と空の関係
我々が自然災害と呼ぶ自然界の現象、例えば、東日本大震災、大規模な集中豪雨による洪水・土砂災害、火山噴火のようなものも、空というシステムが自然界に生み出す現象です。
自然は、情け容赦もなく、災害現場に存在するものを全て破壊し押し流していきます。
その破壊力のすさまじさを、私は大規模な自然災害の現場に行って体感したことがあります。
もし太陽系が崩壊期に入れば、空が動かす自然界は、そこに存在する人間の都合や希望を考慮することなく、全惑星を崩壊させることでしょう。
空により起きる自然災害には、仏陀の大慈悲心とは真反対の側面が見られるように思われます。
これらのものが、どのようなメカニズムにより起きるのかは、現代科学も解明していない部分が多いのが現状ですので、私にも良く分かりません。
人間に予知力があれば、災害から逃れることができるだろうと思われますが、そのためには空と同化した神通力が必要です。
しかし、現実には地球人は、その力を持っていませんので、自然災害による大きな犠牲や損害が出ています。
(5)空の技術化
余談ながら、空を技術化・工学化できれば、テレポーテーション(瞬間移動)による大量輸送、無限のエネルギー、無限の資源などを入手できます。
それは、善用すれば人類に多大な幸福をもたらすはずです。
しかし、偏狭な自我を持つ低レベルの人間がそれを手に入れれば、原爆・水爆を凌駕する兵器を生み出し、この世の地獄を作り出すことでしょう。
文献
(A)Title 仏教における空について
Author(s) 坂部 明
Citation信州大学 人文科学論集人間情報学科編 41: 1-12(2007)
Issue Date 2007-03-15
URL http://hdl.handle.net/10091/2783
以下は文献(A)の引用文献
(1) Sn.1119,中村元 訳注〔1994〕 : 『ブッダのことば』236頁, 岩波書店。
(2) M.no,121 (III, pp.104-109), 中阿含, 大正1巻, 736貢~738頁。
(3) M.no.122 (iii, pp.109-118), 中阿含, 大正1巻, 738貢~740頁。
(4)小部経典,南伝大蔵経第4 1巻, 「倶存品第十 空論」, 113頁~124頁。
(5)大正 28巻, 633頁上~中。
(6)Dhp・273,中村元 訳注〔2003〕:『ブッダの真理のことば 感興のことば』 48頁,岩波書店
(7)Dhp.274,同上書, 48頁。
(8)坂部明〔1974〕 :拙稿「空と般若波羅蜜」, 『印度学仏教学研究』第22巻第2号。
(9)中村元〔1960〕 : 『般若心経 金剛般若経』解題184貢以下,岩波書店。
(10)『大品般若経』誓喰品 第五十七(大正8巻, 329頁下~331頁中)。
(11)般若経は声聞・縁覚の智慧である「一切智」,菩薩の智慧である「道種智」,と如来の智慧である「一切種智」を区別する。 (『大品般若経』 「三慧品」,大正 8巻, 375貢中。
(12)荻原雲来 編〔1973〕 : Abhisamayālamkāar'ālokā Praňāpāramitāvyākhyā, pp.94-pp.105 山喜林佛書林,現代語訳:梶山 雄一〔1980〕 : 『大乗仏典2八千頌般若経i』, 35貢~37貢,中央公論社。
(13)大正 8巻, 250頁。
(14)大正 8巻, 253頁~256貢。
(15)坂部 明〔1986〕 :拙稿「般若経にみられる原始仏教思想」, 『初期大乗経典にみられる原始仏教思想一般若経・法華経を中心として』 (昭和58-60年度科学研究費補助金〔一般研究B〕研究成果報告書。
(16) 「空空亦如是。又如服薬。薬能破病。病巳得破薬亦応出。若薬不出則復是病。」大正 5巻, 288頁。
(17)中村 元〔1981〕:『仏教思想6 空 上』平楽寺書店。
(18)長尾 雅人〔1979〕 : 『中観と唯識』 293貢~294頁。岩波書店。
(19) 『大品般若経』七喩品 第八十五(大正8巻, 413頁), N.Dutt; PVS-PP p.4
(20)吉田 洋一〔1979〕 : 『零の発見』岩波書店。
(21)D kha, gagana, ambara, ākaśa, abhra, vyat, vyoma, nabha,など(Datta & Singh〔1962〕 History Of Hindu Mathematics, pp.63)
(22) 「入曼荼羅具縁真言門第二余」 (大正18巻, 9貢)
(23) 「十喩釈論第十一」 (大正 25巻, 102 中)
(24)同上書, 102頁 下。
(25)林 達夫 ほか監修〔1980〕 :「ニヒリズム」 『哲学事典』平凡社。
(26)詳しくは,中村 元〔1980〕 : 『人類の知的遺産13ナーガールジュナ』 48頁~50頁。
(27) M. Nagao : Madhyāntavibhāga-Bhāśya, pp.25,大正 31巻, 466頁。
(28)早島 鏡正 ほか〔1982〕 : 『インド思想史』, 76貢,東京大学出版会。
(29)平川 彰〔1983〕 : 「序章3部派仏教の教理」, 『仏典解題事典』 13頁,春秋社。
(30) N・ Ghoś'a 〔1902〕 : SS-PP, pp.1409 - 1410, Bibliotheca lndica, work 153,漢訳では, 『大般若経』初会に相当する。大正 第5巻, 291頁。
(31)早島 鏡正〔1964〕 : 『初期仏教と社会生活』 300貢,岩波書店。
(32)前掲書,長尾 雅人『中観と唯識』 294頁。
(33) N・Dutt編〔1934〕:Paňcavimśatisāhasrikā-PP, pp.195 -pp.198
漢訳では『大品般若経』「問乗品」第十八(大正8巻, 250頁中~251頁上)などに見られる。
以上
5. 空に関する長谷川洋三 早稲田大学名誉教授の見解
空に関する長谷川洋三 早稲田大学名誉教授の見解をご紹介します。
出典:
『般若心経』の研究―これは大懴悔の経典である
著者: 長谷川 洋三
1934年、新潟県生まれ。1959年、早稲田大学大学院文学研究科英文学専攻修士課程修了。早稲田大学教授を経て、早稲田大学名誉教授
単行本: 342ページ
出版社: 恒文社 (1989/01)
p.166
この空はどういう意味なのだろうか。
空という語彙を用いずして空を表現する他の語彙としては、何が最も好ましいのだろうか。
それに対する筆者の答えは、「根源の大生命」と「み仏の御命」である。
(A)空が「根源の大生命」のように扱われている例
「大品」第二奉鉢品の中で、釈尊は舎利弗に向かって、次のように述べておられる。
空中には色も無く、受想行識も無し、色を離れて亦空無し。
空は即ち是れ色、色は即ち是れ空、空は即ち是れ受想行識、受想行識は即ち是れ空なり。
(国訳大蔵経 経部第二巻、27頁)
備考
東京大学大学院 人文社会系研究科、次世代人文学開発センター、大藏經テキストデータベース研究会の「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース2012版(SAT 2012)」では次のように出力され、内容に一部相違があります。
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223 鳩摩羅什譯 ) in Vol. 08
T0223_.08.0221a21: ◎5摩訶般若波羅蜜經 奉鉢品第二
T0223_.08.0221b29: 薩字性空。空中無色無受想行識。離色亦
T0223_.08.0221c01: 無空。離受想行識亦無空。色即是空。空
T0223_.08.0221c02: 即是色。受想行識即是空。空即是識。何以故。
T0223_.08.0221c03: 舍利弗。但有名字故謂爲菩提。但有名字
(SAT 2012からの引用終わり)
空の中には色も無く、受想行識も無し、色を離れて亦空無し。受想行識を離れて亦空無し。
色は即ち是れ空、空は即ち是れ色、受想行識は即ち是れ空、空は即ち是れ識。
注意: 最後の部分が「空は即ち是れ識」となっているのはデータベースのミス、あるいは省略形で書かれていると思われます。前後関係から考えると、ここは「空は即ち是れ受想行識」となるはずです。
(備考終わり)
右の文を集合論的に整理すると、次の二つの集合になる。
(1)空の中には色・受・想・行・識などはない。
(2)空は、色・受・想・行・識そのものである。
右の二つの集合は一見、矛盾しているかにみえる。
だが、さらに整理すれば少しも矛盾していないことに気付く。
つまり、「空とは現象や精神活動以前からのものであって、しかも現象や精神の働きそのものでもある」という意味なのであり、少しも矛盾しないのである。
p.167
この解釈では、空とは、たとえば原子や素粒子などをも作動させしめる宇宙の根源の力を指すものと言える。
宇宙に充満していて、森羅万象の誕生以前のものでありながら、森羅万象そのものでもある「根源の大生命」とでもいうべきものを指しているのである。
釈尊は、物質も精神活動も、この「根源の大生命」そのものであることを看破されたのである。
それは、見ることも計量することもできないから、空という言葉で表現せられたものであろう。
それ自体は、見ることも計量することも出来ないけれど、「(色・受・想・行・識という)現象や働きによって知られ、はっきりと認められる」のである。
それは、宇宙に充満する「実在」であり、「実相」であり、「真如」であり、「真実」なるものであるが、計量不可知であるから「空」と表現され、「法華経」の中では「第一義諸法実相空」と述べられているのである。
森羅万象が生起する以前から宇宙に充満し、宇宙そのものであった、「実在」を実相というのであり、筆者はそれを「根源の大生命」と呼ぶのである。
「法華経」の中の「諸法実相空」という句をわかり易く表現するなら、「さまざまな差別相を持つ森羅万象であるが、その実の相は絶対平等の大生命である」という意味である。
この解釈は十八空のいずれとも矛盾するものではない。
(B)空が「み仏の御命」として扱われている例
ところで、宇宙の全てであり森羅万象の命そのものでもある「根源の大生命」を、筆者は人格的に捉えて「み仏の御命」と呼びもするのであるが、仏典の中で空を「み仏」と同義にみなしている例は、「大品」の曇無竭(どんむかつ)品第八十九の中にみられるのである。
善男子、諸仏は従(よ)って来る所無く、去ってまた至る所無し。
何を以ての故に。諸法如は不動相なり、諸法如は即ち是れ仏なればなり。
善男子、無生の法は来る無く去る無し、無生の法は即ち是れ仏なればなり。
無滅の法は来る無く去る無し、無滅の法は即ち是れ仏なればなり。
実際の法は来る無く去る無し、実際の法は即ち是れ仏なればなり。
空は来る無く去る無し、空は即ち是れ仏なればなり。
善男子、無染は来る無く去る無し、無染は即ち是れ仏なればなり。
寂滅は来る無く去る無し、寂滅は即ち是れ仏なればなり。
虚空性は来る無く去る無し、虚空性は即ち是れ仏なればなり。
善男子、この諸法を離れては更に仏無し、諸仏如と諸法如とは一如にして分別無し。
善男子、是の如は常一にして無二無三なり、諸数法を出で、所有無きが故に。
(国訳大蔵経 経部第三巻、372頁)
右の経文から、次の結論が導かれる。
つまり、「森羅万象には、それぞれ固有の実体がなく、その本来の真実の相は不変である。
不変なるものは真如であり仏である。
したがって、第一義諸法実相は、仏である。
故に、「第一義諸法実相は空なり」と言われる空は仏である。
そして、森羅万象は仏を離れては存在せず、故に森羅万象は仏である。
なぜなら、仏の仏たる真如と、一切の物の一切の物たる真如とは毫(ごう、少しも)異なることがないからである。
森羅万象が平等であって差別がないといわれるのは、森羅万象が仏であるからなのである。
つまり、空は仏なのである。」
ブログ著者注:
東京大学大学院 人文社会系研究科、次世代人文学開発センター、大藏經テキストデータベース研究会の「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース2012版(SAT 2012)」では次のように出力されます。
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223 鳩摩羅什譯 ) in Vol. 08
T0223_.08.0421b24: *摩訶般若波羅蜜經17法尚品第八十九
T0223_.08.0421b25: 18丹本曇無竭品
T0223_.08.0421b26: 爾時曇無竭菩薩摩訶薩語薩陀波崙菩薩
T0223_.08.0421b27: 言。善男子。諸佛無所從來去亦無所至。
T0223_.08.0421b28: 何以故。諸法如不動相。諸法如即是佛。善
T0223_.08.0421b29: 男子。無生法無來無去。無生法即是佛。無
T0223_.08.0421c01: 滅法無來無去。無滅法即是佛。實際法無 画像
T0223_.08.0421c02: 來無去。實際法即是佛。空無來無去。空
T0223_.08.0421c03: 即是佛。善男子。無染無來無去。無染即是
T0223_.08.0421c04: 佛。寂滅無來無去。寂滅即是佛。虚空性
T0223_.08.0421c05: 無來無去。虚空性即是佛。善男子。離是
T0223_.08.0421c06: 諸法更無佛。諸佛如諸法如。一如無分別。
T0223_.08.0421c07: 善男子。是如常一無二無三。出諸數法
T0223_.08.0421c08: 無所有故。譬如春末月日中熱時。有人
(SAT 2012からの引用終わり)
大般若経には、「空即是佛」と書かれており、仏陀は空と同化(一体化)されている存在であることを示しています。
「虚空性即是佛」とも書かれており、空と虚空は同じものであることを示しています。
大般若経のこの記述が示しているのは、空=虚空と仏陀が同化(一体化)されていることです。
空と仏陀のどちらが先に宇宙に存在したかといえば、空が先に存在し、空により生み出された人が進化して仏陀となり空と同化したと考えられます。
ですから、仏陀が空と同化されている存在であることは確かなことですが、空を「み仏の御命」と呼ぶのは、宗教的・信仰的な表現であり、それを是とするか非とするかは、その人の信仰心の問題であると思われます。その点はこのブログの読者ご自身で判断してください。
(ブログ著者注終わり)
(C)空とキリスト教の神との関連
p.176
たしかに五蘊(注: 色・受・想・行・識)には、それぞれの自性はない。
しかし、それを生ましめ働かせる根本となるものは、あるのである。
その根本なるものが、「み仏の御命」なのである。
したがって、「五蘊皆空」の「空」は、「神と被造物」の「神」にも匹敵し、新約聖書「ローマ人への手紙」第一章第二十節の、「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められる」という文に見られる、「神の目に見えない本性」に匹敵する、と筆者は思う。
(D)要約
長谷川洋三先生は、「空」を
宇宙の法則的表現:「根源の大生命」
仏教的表現: 「み仏の御命」
キリスト教的表現:「神の目に見えない本性」
であると述べておられます。
私が、大品系般若である『二万五千頌般若』で説かれている「十八空」を解釈して要約すると、次のようになりました:
『縁起・現象相の本質相は空であり、空は物理的に実在し、空は単なる観念や哲理ではなく物理的実在である。
縁起・現象相と本質相の空は別々の2つものがあるのではなく、1つのものを2つの面から見ているだけであり、縁起・現象相と空は一体である。
空には、時間・空間が存在せず無次元・無時間であり、空は時間・空間を超越している物理的存在である。
空の中には縁起・現象相の個別の存在物及び性質は一切存在しない。
縁起・現象相の全ての存在物・性質は、空では「空という1つの統一体」として1つに統一されたものとして存在し、空は縁起・現象相のいかなる性質にも染まっていない(諸法無我、個別性はない)。
空の中には空間がないため、空には質量もなく、空の中には現象相の性質もないため、陰または陽の電荷もない物理的な存在と考えられる。
空は、現象相で知られているようなエネルギーや波動という性質も持っていない。
空は、初めもなき、終わりもなき、永遠の、無限の力、全知全能の完全無欠な「空という1つの統一体」であり、空は現象界の全てを生み出す智慧と力を持つ。空は、「万物の創造主」「宇宙の英知」と呼ぶことが可能である。』(空は、大我ではなく、無我であると思われる)
キリスト教やヨガの記述によれば、天の父、宇宙意識が全てのものを創造し動かしていると書かれています。
このため、「空」「根源の大生命」「神の目に見えない本性」のような存在が、全てのものを創造し動かしていると解釈することは、キリスト教やヨガと類似した解釈です。
このように、仏教で説かれている「空」は、「根源の大生命」「神の目に見えない本性」と呼ぶことは可能であり、それらはキリスト教やヨガの説く天の父、宇宙意識と類似しているように私には思われます。
ここに、仏教、キリスト教、ヨガの本質的な類似性が見られるように思われます。
補足1:
神通力と空の関連
東京大学大学院 人文社会系研究科、次世代人文学開発センター、大藏經テキストデータベース研究会の「SAT大正新脩大藏經テキストデータベース2012版(SAT 2012)」では次のような出力があります。
大般若波羅蜜多經 (No. 0220 玄奘譯 ) in Vol. 07
T0220_.07.0459b10: 時。不應住諸字及諸字所引。復次世尊。諸菩
T0220_.07.0459b11: 薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住神
T0220_.07.0459b12: 通。何以故。世尊。神通神通性空。世尊。是神
T0220_.07.0459b13: 通空非神通。神通不離空。空不離神通。神通
T0220_.07.0459b14: 即是空。空即是神通。由此因縁諸菩薩摩訶
T0220_.07.0459b15: 薩修行般若波羅蜜多時。不應住神通
T0220_.07.0459b16: 復次世尊。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
T0220_.07.0459b17: 多時。不應住色乃至識若常若無常。若樂若
T0220_.07.0459b18: 苦。若我若無我。若淨若不淨。若空若不空。
T0220_.07.0459b19: 若有相若無相。若有願若無願。若寂靜若不
T0220_.07.0459b20: 寂靜。若遠離若不遠離。何以故。世尊。色等
T0220_.07.0459b21: 法常無常。色等法常無常性空。世尊。是色等
T0220_.07.0459b22: 法常無常空。非色等法常無常。色等法常無
T0220_.07.0459b23: 常不離空。空不離色等法常無常。色等法常
T0220_.07.0459b24: 無常即是空。空即是色等法常無常。由此因
T0220_.07.0459b25: 縁諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不
T0220_.07.0459b26: 應住色乃至識若常若無常。色等法樂苦乃
T0220_.07.0459b27: 至遠離不遠離亦復如是。復次世尊。諸菩薩
T0220_.07.0459b28: 摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不應住眞如
T0220_.07.0459b29: 法界法性法定實際。何以故。世尊。眞如眞如
T0220_.07.0459c01: 性空。世尊。是眞如空非眞如。眞如不離空。空
T0220_.07.0459c02: 不離眞如。眞如即是空。空即是眞如。由此因
T0220_.07.0459c03: 縁諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。不
T0220_.07.0459c04: 應住眞如法界法性法定實際亦復如是。復
このように大般若経には「神通即是空、空即是神通」と書かれており、仏教の神通力は空の力であることが分かります。
また、真理の世界を仏教では真如と呼びますが、大般若経には「眞如即是空、空即是眞如」と書かれており、空が真如(眞如)、即ち真理の世界であることが分かります。
お釈迦様のような如来とは、真如から来られた方という意味ですが、その真如とは空のことであることが、この大般若経の記載は示しています。
補足2:
長谷川先生は、仏教とキリスト教の比較宗教学の研究もされており、次の著書もありますので、関心がおありでしたら読まれると良いと思います。
キリストの言葉、ヨハネの言葉と仏教の類似性に関する詳細な考察がされています。
キリスト教と仏教の同質性―東洋型神学を求めて
長谷川 洋三
単行本: 195ページ
出版社: 早稲田大学出版部 (2000/08)
キリスト教の「三位一体」と仏教の「仏の三身」との比較分析をとおして独自の解釈を試み、キリスト教と仏教が根底的に相似の構造を持つことを論証する。
以上