急速に高まっているインターネットサービス。その中でも特に耳にするものにスポットを当ててみます。
【ツイッター<Twitter>】
ブログに代わって利用者が急増している「ツイッター」。
そもそも「つぶやき」を意味する名称ですが、その時の気分や状況を気軽にネット上にアップできることで人気があります。
自分の行動や考えといった小さな発見を広く伝えることで、その一言に共感する人とのやり取りにより関係が広がり、情報交換の場としても利用されています。
企業でも早くに取り入れるところが出ており、口コミといった広告戦略に活用しています。
【ユーストリーム<Ustream>】
他の動画サイトのようにあらかじめ撮影・編集した動画を投稿するタイプと異なり、ウェブカメラをつけたパソコンや、iPhoneで撮影したものを中継配信するシステムです。
インターネットに繋がる環境であれば前述の設備で誰もが利用することができるため、旅行先からの生中継をするなど自由な使い方をネット上で表現しています。
【ラジコ<radiko>】
インターネット経由でラジオ放送をリアルタイムに配信するサービスのこと。
近年の高層建築物によりラジオの電波が受信することが難しい状況を考え、行われたサービスです。
現在東京7局、大阪6局のラジオ局がサービスエリアは参加しており専用のアプリケーションも用意されていますが、あくまでも普段放送されている地域でのみ視聴可能となります。
これは既存の地元放送局の権利を侵害するおそれがあるためであり、今後の課題でもあります。
ツイッター http://twitter.com/
ユーストリーム http://www.ustream.tv/
ラジコ http://radiko.jp/
【ツイッター<Twitter>】
ブログに代わって利用者が急増している「ツイッター」。
そもそも「つぶやき」を意味する名称ですが、その時の気分や状況を気軽にネット上にアップできることで人気があります。
自分の行動や考えといった小さな発見を広く伝えることで、その一言に共感する人とのやり取りにより関係が広がり、情報交換の場としても利用されています。
企業でも早くに取り入れるところが出ており、口コミといった広告戦略に活用しています。
【ユーストリーム<Ustream>】
他の動画サイトのようにあらかじめ撮影・編集した動画を投稿するタイプと異なり、ウェブカメラをつけたパソコンや、iPhoneで撮影したものを中継配信するシステムです。
インターネットに繋がる環境であれば前述の設備で誰もが利用することができるため、旅行先からの生中継をするなど自由な使い方をネット上で表現しています。
【ラジコ<radiko>】
インターネット経由でラジオ放送をリアルタイムに配信するサービスのこと。
近年の高層建築物によりラジオの電波が受信することが難しい状況を考え、行われたサービスです。
現在東京7局、大阪6局のラジオ局がサービスエリアは参加しており専用のアプリケーションも用意されていますが、あくまでも普段放送されている地域でのみ視聴可能となります。
これは既存の地元放送局の権利を侵害するおそれがあるためであり、今後の課題でもあります。
ツイッター http://twitter.com/
ユーストリーム http://www.ustream.tv/
ラジコ http://radiko.jp/



















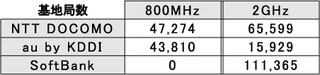

 <モニター室の様子>
<モニター室の様子> <福岡の監視カメラ>
<福岡の監視カメラ>










