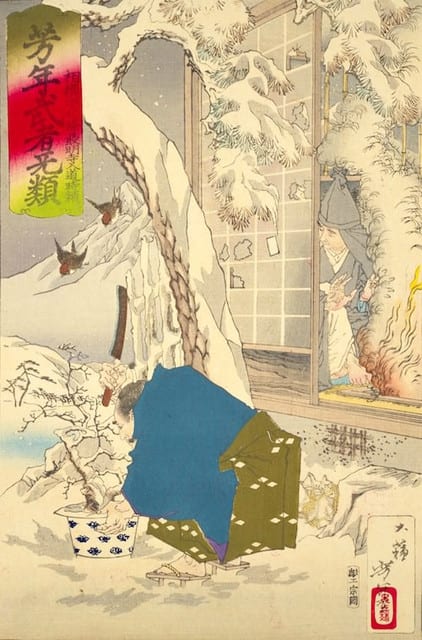
●九州探題、渋川氏の九州統治戦略
前回ご紹介した「九州探題考」で「黒嶋 敏」氏は渋川氏の筑紫・東肥前経営について次のように述べています。
「実勢力としては東肥前の一勢力として終始した」と評されるが、現在でも九州自動車道と長崎・大分自動車道が交差する鳥栖ジャンクションがあることから分かるように、肥前東部は九州各地と連絡可能な要衝で、大宰府・博多にも近く九州の喉元と言える地域である。
筑前には岩門(現:福岡県那珂川市)の他に、最後まで探題領となる姪浜(福岡市西区)唐房遺跡などからチャイナ・タウンの存在も想定される港湾都市であったし、影響力を及ぼした筑後側にも、筑後川流域には探題方となった河北一揆(河北庄→現:三井郡北野町)や河川交通だけでなく有明海交通とも関係する水運拠点が存在しており、複数国におけるこれらの物流拠点が、探題領の重要な構成要素だったことは言うまでもないだろう。
渋川氏の地政学的な戦略に基づく、筑紫・東肥前経営はなかなか優れた政策であった事が分ります。では何時頃から渋川氏の東肥前進出が始まったのでしょうか。
●肥前綾部の守護館
応永3年(1396)今川了俊の後を受け継いだ渋川満頼は少弐氏や菊池氏、阿蘇氏らの反幕府勢力の平定に努力し、少弐貞頼、菊池武朝と戦いました。満頼は肥前国を九州探題の分国と定めて渋川氏が九州における一勢力として戦国時代前期まで存続する基盤を築きました。
さらに、筑前国より肥前に本拠を遷し、肥前国養父郡綾部に守護館を設け、これが渋川氏代々の館となりました。現在、綾部城跡が残る佐賀県三養基郡みやき町あたりが守護館の所在地であったと推測されますが、城址から東南の方向の数キロ先が、肥前国養父郡江島村(現:鳥栖市江島町)なのです。
応永26年(1419年)に父・満頼に代わって、義俊が19歳で九州探題となります。『肥前国史』によれば応永30年(1423)に満頼の子「渋川義俊」が勝尾城(かつおのじょう)を築いたとあり、また応永30年に少弐満貞に博多を攻められて敗れ、肥前国山浦城(勝尾城の支城、現:鳥栖市)に逃れたとの記述もあるように、義俊の時代には完全に鳥栖地域への定着化と肥前支配が完了していたと思われます。
ちなみに勝尾城(かつのおじょう)は戦国期まで佐賀県鳥栖市河内町に存在した山城です。九千部山の山ふところ、標高約500mの城山山頂に位置しています。安良川とその支流の四阿屋川の谷に挟まれた要害で、支城に鏡城、葛籠城、鷹取城などがあります。現在はこの城の真下を九州新幹線が貫通しています。現在貴重な中世の城郭、城下町遺跡として国の史跡指定を受けています。
この遺構の規模はなかなかのものですが、後に城主となった筑紫氏によるものではなく、九州探題渋川氏の威光と権勢が土台にあるものと感じます。
また、私は江島和泉守の家老、河内九郎左衛門重家は勝尾城のあった河内村に出自があるのではないかと考えています。
●渋川氏の肥前・筑後の国衆政策
満頼、義俊時代の文献、文書類は少なく、詳細は分かりませんが、後代の渋川氏が発給した文書類によると、東肥前の国人達を被官化していた様子が伺えます。領地の安堵や官職の発給など文書や写しが現存しています。
探題は肥前守護を兼ねていた訳ですから、肥前の有力国人達に働きかけることなく、直接国人領主を被官化し、纏める事も可能だった訳です。また渋川氏の被官となる事は、室町幕府に繋がる事でもあり、国衆、特に小領主にとっては歓迎すべき事であったに違いありません。
ちなみに南北朝時代、高木、龍造寺、後藤、安富、江上等の肥前の有力国人は今川了俊の弟。仲秋に従い、南朝方と戦ってきました。前述の筑後の河北一揆の件。義俊が探題職を退いて筑後の酒見に隠居した等、東肥前の国衆だけでなく、対岸の筑後の国衆もその勢力下においていた事が推測出来ます。少弐氏が衰退していく中で、筑後江島氏、肥前江島氏も九州探題の勢力下にあったとしても不思議はありません。
永正年間に発給された文書には肥前・村田村の国人「村田総三郎」への「治部丞」への官途推挙状や安堵状が残っています。過去記事のVol 20 もう一つの江島村 「肥前江島村」で村田八幡宮の縁起に関する伝承をご紹介した、村田村の住人「村田石見」とはこの総三郎の子孫にあたる人物と思われます。
江島和泉守の官職名「和泉守」も渋川氏から与えられた正式の官職であり、それに相当した官位も発給されていたかもしれません。その理由は後述します。
●江島和泉守の肥後・小国派遣の目的と理由
過去記事にも述べましたが、当時、阿蘇氏は嫡流家と庶子家で勢力争いを行っていました。九州探題は庶子家を応援し、戦で争うのではなく訴訟でもって決着をつけるように働きかけます。こうして武力による一族内の争いは防ぐことが出来ました。嫡流家は菊池氏と結びつきがありましたし、もっと油断できないのが、島津と大友の動静でした。
このような情勢下、阿蘇氏への目付として、阿蘇氏が和解し一つになった時には帰還するという約定付で、江島和泉守が遣わされたのではないでしょうか。
阿蘇氏の目付ならばもっと本来の阿蘇氏の本拠近くが良いはずですが、何故小国となったのか。それは小国は豊後国にも接しており、室町幕府の御家人であった日田氏を通じて大友や島津の情報も収集しやすい場所に在ったからでしょう。阿蘇氏や菊池氏等肥後の情報と共に隣接する他国の情報収集が本来の派遣目的であったと思われます。
小国郷下城は探題側に与する阿蘇庶子家の支配下にありましたから、庶子家は探題側の求めに対し、田原にいた氏族を大善寺に転封させ、和泉守一族を平和裏に受け入れたと考えられます。
では何故この役に肥前江島村の江島氏が選ばれたのか。その理由についてはこう推察しています。
肥前江島村にあった江島石王社は村田八幡宮の元社であった事は過去記事「もう一つの江島村」で述べました。江島石王社から祭神を分霊し村田村に祀ったのが村田八幡宮の起源です。
★「佐賀県神社誌要」より抜粋
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1020648
村社 八幡神社 三養基郡旭村大字江島字村田
祭神 玉依姫命 應神天皇 筒男命
菅原道眞 豊玉彦命 保食神
往古は江島村石王と云へる所に,豊后宇佐八幡宮の分霊を祀りしに,天文年中時の領主筑紫椎門現社地に社殿を新築して奉遷し,神領地を献し神職数名命婦一名をして奉仕せしめ此郷の宗廟として崇敬せしか,天文五年八月島津来たりて筑紫氏を亡ほすや,社殿は兵火にかゝり,文書神寳等悉く烏有となる,其後鍋島氏の領となるや,寛文年間社殿を再興し祭資を供進して復舊を謀り,江島郷の宗廟と定め祭禮神幸式等盛大に擧行する事となりて維新に及へり。明治六年村社に列せらる。合祀により菅原道眞他二柱祭神追加す。
明治四十年二月十五日神饌幣帛料供進指定
氏子戸数 二百六十戸
大正15年に発刊された佐賀県「佐賀県神社誌要」によれば、村田八幡宮の本来の祭神は玉依姫命、應神天皇、筒男命の三神で、筒男命は筑後江島村、坂本神社の祭神の一柱、住吉神と同神です。
また明治期に合祀された、豊玉彦命はわだつみの神、海神であり、肥前江島村の周囲の人々が海や川など、水や航海に関係する仕事をしていたことが伺えます。江島石王社は現在は有りませんが、江島町公民館がその跡地です。公民館のすぐ傍には筑後川ヘと注ぐ川があります。
室町末期の時代、既に筑後江島氏と肥前江島氏は、筑後川交通、有明海沿岸交通の一端を担っていたのかもしれません。有明海を経て肥後国の海沿いのルート。さらに筑後江島氏は八女に庶流が住み着いていました。八女から一気に街道の山道(現442号)を駆ければ、そこは小国郷です。
一族間の連携で、陸路、海路をもって肥後と肥前の連絡ルートが確保できる。その様な理由で江島和泉守に白羽の矢が立ったのではないでしょうか。
杖立竹原家文書から分かるように和泉守の一族は多数の兵力を有していた訳ではありません。それはその目的が城の守備ではなく、あくまでも監視と情報収集にあったからです。
肥前の大族の国衆や、日田氏の家臣が多数の兵力を持って、小国郷に進駐してきたならば、九州探題の命であっても、阿蘇氏や小国の国衆は心中穏やかでなく、当然警戒もし、小競り合いさえあったかもしれません。
その点、肥前の一国人領主は警戒心を持たれず、適任であったと考えます。
しかしながら、九州探題は江島氏に和泉守の官職を与えます。和泉守は従五位下に相当し、探題職の渋川氏当主にも匹敵する位階に相当します。その身分と共に権威を与え、九州探題渋川氏の名代として田原に着任したのではないかと推察するのです。

阿蘇氏家紋 違い鷹の羽
●和泉守一族、違い鷹の羽を家紋とする。
江島和泉守の任務は短期間で終わるかと思いきや、阿蘇氏の内紛は半世紀以上に渡って続きました。しかし無駄な血を流さぬ、訴訟と言う方法を取った為、表面的には平和な時期が続きました。
やがて、渋川氏も同族内での権力交代が原因となって、九州探題の影響力の衰退を迎えます。江島氏も周囲の国衆に刺激を与えぬ温和な態度を続けました。
やがて和泉守もその家臣達も第二世代が誕生し、成人し、末期には第三世代も育っていた事でしょう。中には阿蘇氏所縁の一族と姻戚関係を持つ者や、阿蘇氏の臣下となる者も出たかもしれません。小国郷の社会に溶け込むうちに、江島氏自体が阿蘇氏と融合し、何時しか家紋を阿蘇氏に因み、丸に違い鷹の羽に変えるような事があったのかもしれません。

「絵本鷹かがみ」 国立国会図書館デジタルコレクション
鷹の羽について少し調べてみますと。「絵本鷹かがみ」では左ページ下段の真ん中を、「屋形符」、下段左を「四の符尾」とありますが、他書では下段左の文様を「屋形尾」と呼んでいるものもあります。いずれにせよ、違い鷹の羽の家紋デザインのような山形の柄を指す事が分りました。
田原の江島城が別名、屋形尾(矢形尾)の城と呼ばれたのも、家紋を違い鷹の羽に変えた事に起因しているのかもしれません。
●小国江島氏、故郷へ還る
阿蘇氏の見せかけの平和は永遠には続きませんでした。文明16年(1484)から文明17年にかけて、惟歳・惟家は菊池重朝の支援を得て惟憲を攻め、一方の惟憲方は相良氏の応援を得て惟歳・惟家らに対抗しました。両者は幕の平で激突し、惟憲方の大勝利となりました。こうして阿蘇氏は統一されました。そして、阿蘇氏より江島氏への立ち退きを要求されたのでしょうか、江島氏は当初の約状に従ったのか、争う事も無く静かに小国郷を去って行ったようです。
小国に生まれ育ち、姻戚関係など地元との深い関係が出来、肥後に残る事を望む者。父祖伝来の本貫の地である肥前江島村に還る事を希望する者と、一族の意見は二手に分かれた事でしょう。この時の江島氏の棟梁はそれぞれの意志を尊重し、自らの望む地に一族の未来を託
したと思われます。
この後九州は戦国期へと突入してゆきます。戦乱の中で肥後に残った一族が主家を変え、あるいは同族や縁故の者を頼って、肥後各地、豊後、日向へと移動したのではないかと推測しています。(註:日向には肥前高木氏の庶流花木氏が宮崎県延岡に土着していた)
一方肥前江島村に戻った違い鷹の羽を家紋とする江島氏も、激動の戦国期を迎え、諸事情によって肥前各地へと広がってゆきました。家紋分布調査ではないので何とも言えませんが、現在の佐賀や長崎の江島姓の分布を見ると、有明海沿岸部の湊で栄えた地区、長崎県沿岸部に多く見られます。一時は山の民となった一族も本来の川の民、海の民にもどって、遠方に進出していったのかもしれません。
福岡県に違い鷹の羽を家紋とする江島氏が見られないのは、肥後小国郷の江島氏が筑後の江島村には戻らなかったという事でしょう。つまり小国の江島氏が、肥前江島村を本貫とする一族であったという何よりの証ではないでしょうか。
違い鷹の羽の謎 (完)

筑後高木氏族 江島家 家紋 丸に違い鷹の羽
Copyright (C) 2018 ejima-yakata All Rights Reserved











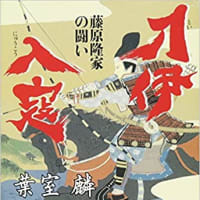







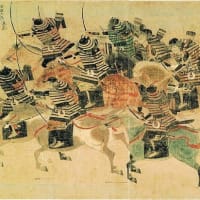





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます