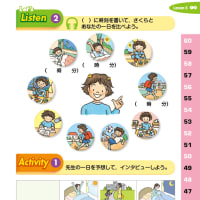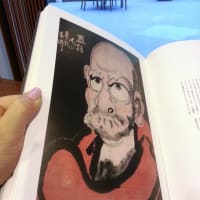「先生、英語で下敷ってなんていうの?」
「文房具」の英語表現を子どもたちと一緒に学んでいた時のことです。
 子どもたちにとって一番身近な学用品や文房具は、教室内ですぐに使える、とても有用な教材。
子どもたちにとって一番身近な学用品や文房具は、教室内ですぐに使える、とても有用な教材。
 筆箱(pencil case)、消しゴム(eraser)、はさみ(scissors)、分度器(protractor)、コンパス(compasses)、定規(ruler)、シャーペン(mechanical pencil)、蛍光ペン(hilighter)、ホッチキス(stapler)、セロテープ(adhesive tape)、画鋲(thumbtack)、修正液(whiteout)など、大人でもであったことのない単語がたくさんあります。
筆箱(pencil case)、消しゴム(eraser)、はさみ(scissors)、分度器(protractor)、コンパス(compasses)、定規(ruler)、シャーペン(mechanical pencil)、蛍光ペン(hilighter)、ホッチキス(stapler)、セロテープ(adhesive tape)、画鋲(thumbtack)、修正液(whiteout)など、大人でもであったことのない単語がたくさんあります。
目の前にあるものの名前を英語で言えるようになるということは、とても魅力的なことですよね。子どもたちに教えると、嬉しそうに何度も何度も繰り返して、忘れないようにしようとする姿に感動します。知らない言葉を「知る」って、こんなに新鮮で嬉しいものなのですよね。



さて、冒頭の「下敷」についてです。
下敷は英語でなんと言うか。
これには正解はありません。
欧米では下敷文化はないようです。
敢えてどういうか…。
ここで英語のセンスが問われるような気がしますが…。
言うとすれば‘plastic board'(プラスチックの板)とかでしょうか?
下敷で思い出したのですが、そういえば、「筆箱文化」もないようです。
基本的に文房具は、絵の具セットのように、新学期開始の際に揃えて、後は学校にすべて常備しておく、ということ。持ち運びしないので、筆箱は要らないのかも。
アメリカで大学生活を開始した時、驚いたことがたくさんありました。
驚愕の教室シーン・ベスト5をあげてみます。
①下敷を使わない…ノートの裏側のでこぼこなんて、全然気にしない!
②筆箱も使わない…筆記具は数本まとめてバックパックのポケットに入れる。
③青インクのボールペンを黒インクのボールペンと同じくらいよく使う。
④書き損じを気にしない…消さずに(というか、ボールペンなので、消えませんよね…)線を引くか、クチュクチュと上から塗りつぶして、横や上や下に、つまりどこでもスペースのあるところに書き直す。
⑤書く姿勢は気にしない…心地よいと感じる姿勢で構わない。アルファベットの書き順なんて、全然気にしない。筆記用具の持ち方も、とやかく言われることはない。
調べる対象として「各国の文房具の歴史と文化比較」なんて、おもしろそうだな~と感じました。
どなたか、どこかの国で日本と同じような文房具としての「下敷文化」をご存知の方は、ぜひ教えてください。
「文房具」の英語表現を子どもたちと一緒に学んでいた時のことです。
 子どもたちにとって一番身近な学用品や文房具は、教室内ですぐに使える、とても有用な教材。
子どもたちにとって一番身近な学用品や文房具は、教室内ですぐに使える、とても有用な教材。 筆箱(pencil case)、消しゴム(eraser)、はさみ(scissors)、分度器(protractor)、コンパス(compasses)、定規(ruler)、シャーペン(mechanical pencil)、蛍光ペン(hilighter)、ホッチキス(stapler)、セロテープ(adhesive tape)、画鋲(thumbtack)、修正液(whiteout)など、大人でもであったことのない単語がたくさんあります。
筆箱(pencil case)、消しゴム(eraser)、はさみ(scissors)、分度器(protractor)、コンパス(compasses)、定規(ruler)、シャーペン(mechanical pencil)、蛍光ペン(hilighter)、ホッチキス(stapler)、セロテープ(adhesive tape)、画鋲(thumbtack)、修正液(whiteout)など、大人でもであったことのない単語がたくさんあります。
目の前にあるものの名前を英語で言えるようになるということは、とても魅力的なことですよね。子どもたちに教えると、嬉しそうに何度も何度も繰り返して、忘れないようにしようとする姿に感動します。知らない言葉を「知る」って、こんなに新鮮で嬉しいものなのですよね。




さて、冒頭の「下敷」についてです。
下敷は英語でなんと言うか。
これには正解はありません。
欧米では下敷文化はないようです。
敢えてどういうか…。
ここで英語のセンスが問われるような気がしますが…。
言うとすれば‘plastic board'(プラスチックの板)とかでしょうか?
下敷で思い出したのですが、そういえば、「筆箱文化」もないようです。
基本的に文房具は、絵の具セットのように、新学期開始の際に揃えて、後は学校にすべて常備しておく、ということ。持ち運びしないので、筆箱は要らないのかも。
アメリカで大学生活を開始した時、驚いたことがたくさんありました。
驚愕の教室シーン・ベスト5をあげてみます。
①下敷を使わない…ノートの裏側のでこぼこなんて、全然気にしない!
②筆箱も使わない…筆記具は数本まとめてバックパックのポケットに入れる。
③青インクのボールペンを黒インクのボールペンと同じくらいよく使う。
④書き損じを気にしない…消さずに(というか、ボールペンなので、消えませんよね…)線を引くか、クチュクチュと上から塗りつぶして、横や上や下に、つまりどこでもスペースのあるところに書き直す。
⑤書く姿勢は気にしない…心地よいと感じる姿勢で構わない。アルファベットの書き順なんて、全然気にしない。筆記用具の持ち方も、とやかく言われることはない。
調べる対象として「各国の文房具の歴史と文化比較」なんて、おもしろそうだな~と感じました。

どなたか、どこかの国で日本と同じような文房具としての「下敷文化」をご存知の方は、ぜひ教えてください。