1929年、浪速区の新世界に1号店が開店。
2012年現在では新世界名物となった、串カツの誕生である。
2012年現在の店主は4代目。
もっとも当時から近年に至るまで、串カツ店のチェーン展開などの動きは見られなかった。
2000年になると、当時の店主(3代目)が病に倒れ、創立以来の閉店危機に陥ってしまう。
そこに学生時代からの常連客である俳優・赤井英和が救いの手を差し伸べた結果、店は再開されたうえにそれまで以上に繁盛するようになった。
これ以来、ミナミを中心に新世界や道頓堀周辺へ次々と出店するようになり、2010年にはキタへ進出している。
2012年現在では新世界名物となった、串カツの誕生である。
2012年現在の店主は4代目。
もっとも当時から近年に至るまで、串カツ店のチェーン展開などの動きは見られなかった。
2000年になると、当時の店主(3代目)が病に倒れ、創立以来の閉店危機に陥ってしまう。
そこに学生時代からの常連客である俳優・赤井英和が救いの手を差し伸べた結果、店は再開されたうえにそれまで以上に繁盛するようになった。
これ以来、ミナミを中心に新世界や道頓堀周辺へ次々と出店するようになり、2010年にはキタへ進出している。
兵庫県朝来市生野町は但馬地方の入口で、姫路市を基点に瀬戸内海と日本海を結ぶラインの真ん中ぐらいにあります。昭和の高度成長期の頃、生野の町は鉱山で賑わい、全国各地から大勢の人がやってきまし た。昭和30年の町の人口は約1万人。町内の社宅に、鉱山に勤める人や家族が数多く暮らしていました。都会から赴任した鉱山職員の社宅には、モダンな文化が届き、町の人はハイカラな香りを感じていました。ハヤシライスも、そのひとつ。都会育ちの奥さんが作った手づくりの洋食に、町の人は「こんなうまいもんがあるんか」とビックリしたそうです。その社宅のハヤシライスを生野鉱山の味として復活しようと取り組んだのが、生野ハヤシライスです。みんなが頑張っていた昭和の激動のあの頃を思い出す、ほんのりとした懐かしい味。どうぞ、ご賞味ください。

① 懐かしい味として、トマトソースベース、またはデミグラスソースベースの味を基本とする
②「生野ハヤシライス」のシンボルマークを使用する
③ 生野鉱山の由来等を伝える


① 懐かしい味として、トマトソースベース、またはデミグラスソースベースの味を基本とする
②「生野ハヤシライス」のシンボルマークを使用する
③ 生野鉱山の由来等を伝える

先日はラ・テラスで会食。

以前から噂を聞いていて、行ってみたかった処。

ラ・テラスは若草山の麓、春日野原生林周辺、

春日大社と東大寺の間の世界遺産の丘に佇む

「ザ・ヒルトップテラス奈良」内に併設されたフレンチレストラン。

レストランプロデュースの鈴木雅之氏とシェフ秋吉博国氏は、

ともにリッツカールトン大阪 La・Baie(ラ・ベ)でシェフのシェフを務めた方だと言う。

「ラ・ベ」といえば、東京の三ツ星レストラン「ロオジエ」のシェフ、

ブルーノ・メナール氏も務めていたところ。

その他にもフレンチの名シェフが腕を振るった名門である。

室内には桜の樹がそのまま貫き、ガラス張りの天井からは陽が降り注ぐ。

桜の季節は天井がピンク色に染まり、さぞや素敵やろう。

以前から噂を聞いていて、行ってみたかった処。

ラ・テラスは若草山の麓、春日野原生林周辺、

春日大社と東大寺の間の世界遺産の丘に佇む

「ザ・ヒルトップテラス奈良」内に併設されたフレンチレストラン。

レストランプロデュースの鈴木雅之氏とシェフ秋吉博国氏は、

ともにリッツカールトン大阪 La・Baie(ラ・ベ)でシェフのシェフを務めた方だと言う。

「ラ・ベ」といえば、東京の三ツ星レストラン「ロオジエ」のシェフ、

ブルーノ・メナール氏も務めていたところ。

その他にもフレンチの名シェフが腕を振るった名門である。

室内には桜の樹がそのまま貫き、ガラス張りの天井からは陽が降り注ぐ。

桜の季節は天井がピンク色に染まり、さぞや素敵やろう。
先日は大和郡山市筒井で会議。
昼食何にする?
あの角にあるあのお店にしよう!

今年はウナギがお高いから、あのお店なら安く食べれるはず。

とにかくここのおやじは、憎めない性格で陽気、お茶目。

生きたうなぎを見事な手さばきで目の前で裁いて焼き、本物の味楽しませてくれた。
しかも、肝吸いがついてた。

うなぎ専門店なのに、ラーメンも出てくるという。
釣り船もあって、頼めば伊勢で楽しませてくれるらしい。
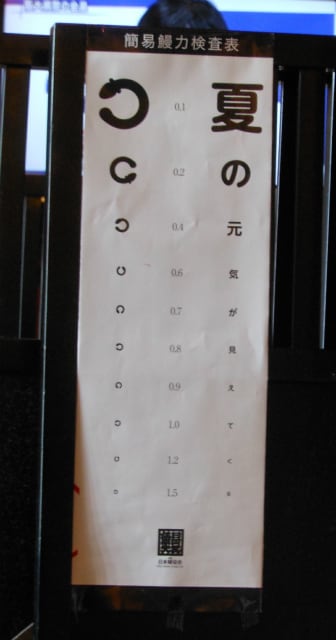
ウナギ食べて夏バテ解消や!
昼食何にする?
あの角にあるあのお店にしよう!

今年はウナギがお高いから、あのお店なら安く食べれるはず。

とにかくここのおやじは、憎めない性格で陽気、お茶目。

生きたうなぎを見事な手さばきで目の前で裁いて焼き、本物の味楽しませてくれた。
しかも、肝吸いがついてた。

うなぎ専門店なのに、ラーメンも出てくるという。
釣り船もあって、頼めば伊勢で楽しませてくれるらしい。
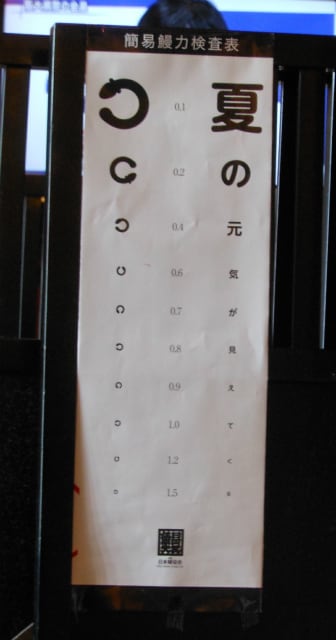
ウナギ食べて夏バテ解消や!
3月末、お気に入りのレストランへ。
息子と私の祝賀会。

@【ポンパピエロット】は、JR茨木駅近くで本格イタリアンと洋食などが楽しめるお店です。入口の曲芸ピエロに迎えられて、店内に入っていただければスタイリッシュながらも落ち着ける雰囲気と大評判です!
息子と私の祝賀会。

@【ポンパピエロット】は、JR茨木駅近くで本格イタリアンと洋食などが楽しめるお店です。入口の曲芸ピエロに迎えられて、店内に入っていただければスタイリッシュながらも落ち着ける雰囲気と大評判です!
菓匠 松福堂「ふるべの鈴」という名の和菓子。
これを鳴らすとすべての願いが叶うという石切剣箭神社の由緒あるふるべの鈴をモチーフにした和菓子。
大福よりも大きなサイズで、四切れくらいにカットして食べたけど、かなり大きい!
カットしてみると中は小豆と抹茶の二層になっていた。
これを鳴らすとすべての願いが叶うという石切剣箭神社の由緒あるふるべの鈴をモチーフにした和菓子。
大福よりも大きなサイズで、四切れくらいにカットして食べたけど、かなり大きい!
カットしてみると中は小豆と抹茶の二層になっていた。
株式会社梅の花(うめのはな)は、ゆば・豆腐レストランチェーンを展開する企業。
本社は福岡県久留米市。
2010年、梅の花のCMが、第50回ACC CMフェスティバルの最優秀賞であるACCグランプリ・総理大臣賞を受賞。
「梅の花」のCMは、店を訪れた男女がデュエットで歌いながら特徴をアピールする演出が評価された。
本社は福岡県久留米市。
2010年、梅の花のCMが、第50回ACC CMフェスティバルの最優秀賞であるACCグランプリ・総理大臣賞を受賞。
「梅の花」のCMは、店を訪れた男女がデュエットで歌いながら特徴をアピールする演出が評価された。
写真の貝は、淡嶋神社への参道で見かけた“ガンガラ”。

ニナ貝とも呼ばれている。
どちらも標準和名ではない。
この三角錐の貝の数種類を総称してガンガラもしくはニナ貝と呼んでいる。
図鑑によると
バテイラ オオコシダカガンガラ クボガイ
などがあり見分けるのが難しい。
食べ方は
簡単に塩ゆでが一番とのこと。

ニナ貝とも呼ばれている。
どちらも標準和名ではない。
この三角錐の貝の数種類を総称してガンガラもしくはニナ貝と呼んでいる。
図鑑によると
バテイラ オオコシダカガンガラ クボガイ
などがあり見分けるのが難しい。
食べ方は
簡単に塩ゆでが一番とのこと。
すし定食はネタが決まっているけど、
アラカルトは、セレクトメニュー用紙から7コ好きなのを選べる。

ここの寿司は、シャリがたっぷりネタも大きく海苔までおいしい。
ワサビの有無を聞かれたけど、当然オトナはワサビ有り!
赤だしと付き出し2品、羊羹のデザートも付いてお腹いっぱい。
アラカルトは、セレクトメニュー用紙から7コ好きなのを選べる。

ここの寿司は、シャリがたっぷりネタも大きく海苔までおいしい。
ワサビの有無を聞かれたけど、当然オトナはワサビ有り!
赤だしと付き出し2品、羊羹のデザートも付いてお腹いっぱい。
次男が、年末に買って来てくれた「デリチュース」の『和と輪』。
《味噌の風味がほのかに漂い、口に入れるとしっとりなめらかな食感にうっとり。お店のロゴマークでもあるりんごが、ちょこんと封印され、見た目も可愛らしい雰囲気です。》
(ベルメゾン作成のリーフレットより)
200年の伝統のある福井・越前産の手作り赤味噌(米みそ)、三重県山中で平飼いされた濃厚な味わい卵、油脂にはバターのみを使用、とのこと
《味噌の風味がほのかに漂い、口に入れるとしっとりなめらかな食感にうっとり。お店のロゴマークでもあるりんごが、ちょこんと封印され、見た目も可愛らしい雰囲気です。》
(ベルメゾン作成のリーフレットより)
200年の伝統のある福井・越前産の手作り赤味噌(米みそ)、三重県山中で平飼いされた濃厚な味わい卵、油脂にはバターのみを使用、とのこと
昨日まで“ポンパレ”で“新世界串かつ振興会”の“串かつ”が売られていた。
申し込みには、17000を超えるすごい数!
やっぱり、有名店「だるま」は入ってなかったけど・・・

@だるまのこだわり
昭和四年、大阪は新世界の一角で「元祖串かつだるま」の生みの親"百野ヨシエ"が、この濃い褐色のソースを世に送り出してから、七十有余年。
ただひたすら、お客さんの"これウマイなぁ"を聞きたいがために、開発を重ねようやく納得のいく味に辿り着きました。
ソースの中に"ドバッ"っとつけて食べるのが、だるま流。
他のお客さんにも快く使ってもらうため「ソースの二度付けは禁止!」しております。
【写真】だるま 道頓堀店・法善寺店
申し込みには、17000を超えるすごい数!
やっぱり、有名店「だるま」は入ってなかったけど・・・

@だるまのこだわり
昭和四年、大阪は新世界の一角で「元祖串かつだるま」の生みの親"百野ヨシエ"が、この濃い褐色のソースを世に送り出してから、七十有余年。
ただひたすら、お客さんの"これウマイなぁ"を聞きたいがために、開発を重ねようやく納得のいく味に辿り着きました。
ソースの中に"ドバッ"っとつけて食べるのが、だるま流。
他のお客さんにも快く使ってもらうため「ソースの二度付けは禁止!」しております。
【写真】だるま 道頓堀店・法善寺店
韓国では、11月ころになると、新聞に桜前線ならぬ、「キムチ前線」が南下してくるというニュースが流れるそうです。
キムチ作りに適した気候になる時期を指し、キムチ作りがはじまるのです。
特にこの季節に仕込むキムチ作りのことをキムジャンといい、家族や地域の人たちが協力しながら、大量のキムチを仕込みます。
大量に仕込むわけですから、お金もかかります。
日本では寒冷地手当という名称で、灯油代が支給される会社があるようですが、韓国ではこのキムジャンのために、キムジャンボーナスが支給されたり、キムチ休暇まであるそうです。
キムチ作りに適した気候になる時期を指し、キムチ作りがはじまるのです。
特にこの季節に仕込むキムチ作りのことをキムジャンといい、家族や地域の人たちが協力しながら、大量のキムチを仕込みます。
大量に仕込むわけですから、お金もかかります。
日本では寒冷地手当という名称で、灯油代が支給される会社があるようですが、韓国ではこのキムジャンのために、キムジャンボーナスが支給されたり、キムチ休暇まであるそうです。
































