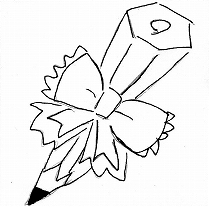1日1枚画像を作成して投稿するつもりのブログ、改め、一日一つの雑学を報告するつもりのブログ。

本文詳細↓
三十六日目。
「おはよう。今日はちょっと雲が多いね」
「うむ。今日も好き目覚めだ。案外慣れれば陸よりもよく眠れるものよな」
それからストレッチをして、朝ご飯を食べて、魚を釣って干した。最初は手間取って、転んだり零したりしょっちゅうしていたけど、時間をかけることなく終わらせられるようになってしまった。
これからの時間をどう埋めようか、と思いながら横になると、すぐさまアダムに鼻を踏まれた。
「これ、前をよく見ておかぬか。ぶつかってしまうぞ」
「ぶつかる? ああ、岩礁とか? ちょっと前にもあったよな。本当、あのときは肝が冷えたよ。海図にもいくつか点が打ってあるけど、このあたりには……」
体を起こし、海図を出そうとカバンに手を伸ばしたそのとき。
ゴンッ。
「え?」
振り返ると船が止まっていた。
壁に遮られて前に進めずにいた。
「…………ぇ」
何がどういうことなのか、理解できなかった。

本文詳細↓
一日目。望遠鏡を覗けばまだ、鳴御雷(なるみかづち)の灯台が見えていた。
七日目。海に出てから初めて雨に降られた。釣った魚を日干ししてたのに、おかげで失敗した。
十二日目。甲高い声で鳴くつるりとした皮の魚の群れを見た。絵付きで海図に描いてあった通りだった。
十六日目。もはや陸地は霞むことすらなく、ひたすら青、蒼、碧、青、蒼、青、蒼、碧、青、蒼を見ていた。
二十三日目。とても強い風が吹いた。上へ下へと揺れる波のおかげで目が回って、気分も悪くなった。
三十日目。
「アダムがいてくれることの喜びをかみしめてる」
「いきなり何を言いだすか」
「景色が変わらなさすぎて、進んでるのか止まってるのかも分からないなんて、ひとりだったら発狂してたかも。僕と一緒に来てくれてありがとう」
「ふん、今更気がついたか。もっとありがたく褒め讃え奉るとよいわ」

本文詳細↓
そうしているうちに冷たさはぬぐい去られ、穏やかな光の春を季節は迎えようとしていた。
明日出発しようという日の夜、ベットの中で僕はアダムと少し話をした。
「本当に行くのだな? やつの曾々祖父しかり、生きて帰って来れる保証はまったくないのだぞ。我はただのお調子者。何者からもおぬしを守ってはやれぬ」
「行くさ。怖くないわけじゃないけど、行きたいっていう気持ちのほうが大きいんだ。……それとも今、お前が全てを教えてくれるのか?」
「…………」
「ほら。べつにもういいけどさ、夢も預かったし。自分の目で最後まで見るよ。……昨日出した手紙が届くのと、僕が世界の果てに辿り着くのと、どっちが先だろ」
「いい勝負であろう。この大地を横断し、ほぼ正反対の場所まで来たのだから」
翌日。空は快晴、風は優しく、海は凪ぎ、船出に申し分ない日だった。
「オレは世界なんてどうでもいいけど、昔から気になってることがあるんだ。『海の上にあるのに、何故この町は[湖]城と天見の町なのか』。世界の果てにその答えがあったら、帰って来たときオレにも教えてくれよ」
そんな言葉に見送られて、僕らは世界の果てを目指して出発した。

本文詳細↓
そして、照れくさそうに、はにかんだ笑顔を見せた。
「その夢が叶ったらいいと思ってる。会ったことねえのにな。オレ、ひいひいじいさんのことが大好きみたいなんだよ」
「…………っ、ありがとう、ございます……。本当に、ありがとうございます……!」
いま知り合っただけの僕を信じてくれて。
話を聞かせてくれて。
色々と助けになってくれて。
全部の気持ちを一緒くたに混ぜて、何故か泣きそうになりながら僕は何度もお礼を言った。
まあだからといって、すぐに出発したかというとそうではなくて。船の動かし方から海の上での生活の仕方まで、一から丁寧にアスキリオさんに教わっていた。
「ところでお前の曾々祖父が船出したとき、天の火はあったのか?」
「いや、じいさんが子供の時に落ちて来たって言ってたから、そんときはなかったはずだ」
「そうか……」
その間にはアダムとアスキリオさんがそんなことを話していたり、件のひいひいおじいさんの日記かおとぎ話かを読ませてもらったりした。花と霞の里にも訪れていたみたいで、僕もあの万年桜を思い出して懐かしくなった。思い出せばつい最近のことのようなのに、ひとつひとつ振り返れば、驚くほど前のことだった。

本文詳細↓
そこでアスキリオさんはやっと箱を開けた。中に入っていたのは、黄ばんだ紙が詰められた瓶だった。
「オレのひいひいじいさんの人生は、世界の果てを目指してこの町から船出したところで終わってる。海で何があったかは誰も知らない。ただ、この海図だけが帰ってきた」
咄嗟に口を開けたものの、何を言えばいいのか分からなくて、僕もアダムも、揃ってただ唇を上下に動かしただけだった。
「どこまで参考になるか知らねえけど、これ、やるよ。船もオレのやつやる。金はいらない」
「えっ、あ、あの……待ってください。なんで、そんな良くしてくれるんですか?」
彼の中で全ての筋は通っているんだろう。でも僕には意外な言葉ばかり畳み掛けられて、たまらずストップをかけた。
「……ひいひいじいさんが何を考えて生きていたのかなんて、オレに知る術はない。でも、何かを夢見ていたのだとしたら」
僕を見据える瞳は髪と同じ色で、静かに力強い光をたたえていた。
「ひいひいじいさんが世界の果てを目指したのは運命の悪戯だったとしても、お前は違う。お前はここに来るべくして来た。ならお前に手を貸すことで、ひいひいじいさんに途切れた夢の続きを見せてやれるかもしれないだろ。……オレは日々の暮らしが第一だし、その夢に共感も共有もできねえけど」