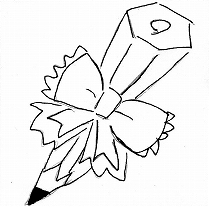1日1枚画像を作成して投稿するつもりのブログ、改め、一日一つの雑学を報告するつもりのブログ。

本文詳細↓
さらに、劇場と観客席を物理的に隔ててしまえばいいと言い出した者がいた。覗き穴を空けた屋根と壁で島を囲んで劇場とし、ブロッケン(観客)は外から眺めるだけにしようというのだ。なんと素晴らしいアイデアかと、人間たちにより強い衝撃が走った。
それを実現するべく、先頭に立ったのがイルミナリスだった。彼はエドナンティアに住みたい種族――特に、強い魔法が使える悪魔たちにこの考えに賛同してくれるよう説いて回った。
「互いに反りがあわない種族もあろうが、よく考えてみてほしい。これが叶えば、我々は皆この土地の全てを好きにできるのだ。どこにいても目についていた気味の悪いバケモノを見なくてすむようになるだろう。突然やってきて邪魔をしたかと思えば、何も言わず、何も聞かず、去っていく勝手なバケモノに煩わされることがなくなるだろう。これはとても清々しいことではないか? 無論、我々人間も約束しよう。未来永劫、この茶番劇を続けていくとっ!!」
だが島を囲うということは、太陽も月も風も雨も、巡る自然の調和がなくなり、誰かの意思で調節されるということ。それを嫌った種族は、ついに見切りをつけてエドナンティアを離れた。しかしそれは微々たるもので、大多数には好意的に捉えられた。
『ブロッケンと人間以外の種族の出入りは自由に認める』という悪魔の出した条件をイルミナリスは呑み、大掛かりな計画が始まった。

本文詳細↓
人間たちがどれだけ数を減らしたか、もう誰にも分からなくなったある日。子どもたちを逃がすため、ブロッケンの気をひこうと大声で歌い踊り、芝居を始めた夫婦がいた。子どもたちは必死で走り、無事にその場を離れることができた。そして泣き崩れた。自分たちが助かるために、大切な両親を犠牲にしたのだと。
だが不思議なことに、両親は無傷で帰ってきた。子どもたちは今度は歓喜の涙を流した。
曰く、ブロッケンたちは眺めるだけで何もせず、しばらくすると飽きて興味を失ったように、やはり何もせず立ち去ったのだと。この話はたちまち人間たちの間で広まった。人間たちはようやく、未知のバケモノに対抗する方法を手にしたのだった。
とはいえ、それも万能ではなかった。芝居を始めても見向きされなかったり、逆に癇癪を起こされたりして、これまでと同じように連れ去られ、叩き潰され、食われる者たちはいた。
ある日、悩み苦しむ人間たちの前に、世界一のお調子者として名高い《雲を歩き海を呑む放浪者》が突然現れてこう宣った。
「ならばいっそ、お前たちが笑い嘆き、怒り楽しむ生き様そのものを劇としてブロッケンに見せてやってはどうだ。この島ひとつを舞台にした、何千人もの役者が見せる群像劇だ! なんとも派手で面白そうなことではないかっ!」
なんと良い考えだと、人間たちに衝撃が走った。
ついに最終章ですが、流石に短すぎるので2ページ同時更新です。


本文詳細↓
「少し長くなるけど、昔話を聞いてくれるかしら?」
世界を二つに分ける扉の縁に座って、蒼い月夜の彼女――天使ナイトウォーカーは、そう言って笑った。
始まりは千年以上前のこと。
世界の極東にあるこの島は、鮮やかな緑と豊かな水で満たされ、実りの地という意味で[エドナンティア]と呼ばれていた。
そこに主に生息していたのはブロッケンという巨大な生き物だった。大きさだけでいえば、かのドラゴンをも凌ぐほどだ。姿こそ人に酷似していたが、その大きさに見合うだけの怪力を持ち、また一糸まとわぬ澱んだ乳白色の肌は魔力耐性がとても高く、あの悪魔をして干渉することを諦めさせるほどだった。彼らは複雑な知能や感情、言葉を持っておらず、その様子は、喩えるなら揺籃期の人間と言えた。ブロッケン同士であれば精神感応(テレパシー)で意思疎通ができると推測されてはいるが、誰も真実は知らない。
エドナンティアは肥沃な土地であったため、この地での生活を望む種族は多かったが、闊歩するブロッケンを倒すことも懐かせることもできず、彼らの目を気にしながら少し散歩する程度にとどまっていた。
そこへある日、はるばると海を越えてたくさんの人間たちが流れついた。彼らは戦争や飢饉から命からがら逃げてきた者たちだった。だが彼らの不幸は終わらなかった。ようやく辿り着いた新天地には、先住民のバケモノがいたからだ。見慣れないものに興味を持ったブロッケンは、ただ無邪気に人間を捕まえて連れ去り、またはその怪力で握りつぶし、時には口の中へ放り込んだ。
人間たちはたちまちのうちに恐怖し、慟哭した。

本文詳細↓
拝啓、家族の皆々様へ。
お元気ですか?
月並みな始め方だけど、やっぱりこれしかないと思うんだ。
……旅に出てから、初めて手紙を書きます。
といっても、何かあったとかではないので、安心してください。
僕もあいつも元気で、悠々自適にギリギリな生活を謳歌しています。
今回はなんとなく、書いてみようかなと思い立っただけです。
ここに来るまでに、いろんなことがありました。
美味しいものも食べたし、楽しいこともしたし、怖い目にもあったし、本当にたくさんのことがありました。
……いざ手紙を書こうとすると、何を書いたらいいのか分からないな。
とりあえず、僕もあいつも五体満足、元気いっぱいです。安心してください。
父さん、出発の日に僕の背を叩いてくれた力強い大人の手を、今でも忘れられません。僕も、あなたのようになれているといいな。
母さん、寒い日にはあなたのぬくもりが恋しくなります。僕をずっと守り育ててくれて、ありがとう。
兄さん、兄弟というより友達みたいなあなたとの関係も、嫌いじゃなかった。大事なお嫁さんを逃がさないようにね。
義姉さん。いつか、かわいい甥や姪に会う日を楽しみにしています。兄さんをよろしくお願いします。
僕にはみんなの様子を知ることはできないけど、楽しく健やかに日々を過ごしていることを祈ります。
今度はいつ、どこで手紙を書くことになるかな。
気長に待っていてくれると嬉しいです。
それじゃあ、また。
敬具
トルヴェール・アルシャラールより

本文詳細↓
「あ、アダ、ム。これ、は、なに。どういう……」
「触れてみれば分かるだろう」
淡々とそう返された。
ズリズリと膝を擦って進み、震える手で舳先から手を伸ばした。手が伸びきる前に、冷たくて固い壁に当たった。その感触は、僕の家の漆喰の壁に似ていた。
「でも、ほら、だって、空も海もまだずっと続いて見えて……」
「錯覚を利用して奥行きを見せる絵画技法があろう。多少魔法は使っているだろうが、原理はそれだ」
波の音、風の音、船が軋む音、あらゆる音の全てが聞こえなくなった。血の気は引いていくのに心臓がばくばくと上へはねているのが分かった。
「絵画、技法……? 世界の果ての壁、なんて……だって、それじゃ……まるで誰かが……」
「そう、ここが《世界》の果て。本当の世界の一部を囲んで作られた、偽りの《世界》の端」
顔を少し上げた先で、空色の壁に四角い穴が空いていた。その際に立っているのは、濃紺色の羽衣のようなドレスをまとったあの日の『彼女』だった。
「また会えて嬉しいわ」
ドアの向こうは茜色の光が差していた。