
「「花の下にて春死なむ」北森鴻(講談社文庫)
「かたみ歌」朱川湊人(新潮社文庫)
本屋で衝動買いした二冊、作者について予備知識ゼロで読みました。 いわゆる本能買いってやつです。
■「花の下にて春死なむ」北森鴻(講談社文庫)
こちらの連作集は、ビアバー「香菜里屋(カナリヤ)」のマスター、工藤が狂言回しの役を勤める6作の短篇集。
香菜里屋は新多摩川線・三軒茶屋の商店街からひとつ外れた路地にあって、知る人ぞ知るのお洒落な店である。
マスターの工藤哲也は40歳ほどで、控えめながら聡明で料理が上手い。
そうそう、実は推理小説なのである。
6作の短編にそれぞれに仕掛けがあってオチがあるのだが、その他に大きな流れもあって6作を通しての謎解きがある。
1.花の下にて春死なむ(飯島七緒)
2.家族写真(野田克弥)
3.終の棲家(妻木信彦)
4.殺人者の赤い手(笹口ひづる)
5.七皿は多すぎる(東山朋生)
6.魚の交わり(飯島七緒)
()の中はその作品の中の主人公である。
こうやってみると、飯島七緒が登場するのは最初と最後だけ。それ以外は独立した掌編だったのか。
にもかかわらず、6作が串団子のように一本筋が通っていると感じたのは、香菜里屋が必ず登場するからだろう。
最初と最後の2作でももちろん成立するのだけれどそれではつまらない。
間に4編を挟んで緩急をつけて面白いのだと思う。
もうひとつ、香菜里屋の工藤が作る料理の描写がたまらなく美味しくてそれだけでも読む価値がありました。
■「かたみ歌」朱川湊人(新潮社文庫)
こちらの連作短編集も推理小説である。 ホラー色も若干ありますが読んだ後に眠れなくなるほどではないからご安心を。
朱川湊人は直木賞作家、ところが申し訳なくも私は知らなかった。
狂言回しはアカシア商店街の古本屋「幸子書房」である。
店主は古希を過ぎた老人で、香菜里屋のマスターのように物語の流れを掌握するほどの存在感はない。 そう、初めのうちは・・・
1.紫陽花のころ
2.夏の落し文
3.栞の恋
4.おんなごころ
5.ひかり猫
6.朱鷺色の兆
7.枯葉の天使
題名を見てもお分かりのとおりで「かたみ歌」のほうが「花の下にて春死なむ」よりも叙情的な色合いが強い。
舞台は昭和40年代のおそらくは東京の庶民的な商店街。
作者は昭和38年生まれだからこの時代を知らないはずなのに、自分が体験しているかのように当時の風景を描いていることに驚いた。
当時の歌謡曲やグループサウンズ、流行りの洋楽が当たり前のように登場する。
舞台背景はたいへん懐かしいのであるが、これってこの時代に陰も形もなかった今の若い人にはどんな感じなのだろうか。
それにしてもどの短編もその切なさに心打たれます。
よしもとばなな風味の陽性ホラーではなく、静的なホラーに上品に包まれる感じがなんともいえない。
「ちょっと前にこの町に住んでいた子供ですよ」
「その・・幽霊とか、そういうものでしょうか」
「さぁ、どうでしょうね。 考え方一つですけれど私にとっては天使です」
時空を超えた不思議をあっさりと受け入れて普通に暮らす人たちを描いて秀逸でした。
「かたみ歌」朱川湊人(新潮社文庫)
本屋で衝動買いした二冊、作者について予備知識ゼロで読みました。 いわゆる本能買いってやつです。

■「花の下にて春死なむ」北森鴻(講談社文庫)
こちらの連作集は、ビアバー「香菜里屋(カナリヤ)」のマスター、工藤が狂言回しの役を勤める6作の短篇集。
香菜里屋は新多摩川線・三軒茶屋の商店街からひとつ外れた路地にあって、知る人ぞ知るのお洒落な店である。
マスターの工藤哲也は40歳ほどで、控えめながら聡明で料理が上手い。
そうそう、実は推理小説なのである。
6作の短編にそれぞれに仕掛けがあってオチがあるのだが、その他に大きな流れもあって6作を通しての謎解きがある。
1.花の下にて春死なむ(飯島七緒)
2.家族写真(野田克弥)
3.終の棲家(妻木信彦)
4.殺人者の赤い手(笹口ひづる)
5.七皿は多すぎる(東山朋生)
6.魚の交わり(飯島七緒)
()の中はその作品の中の主人公である。
こうやってみると、飯島七緒が登場するのは最初と最後だけ。それ以外は独立した掌編だったのか。
にもかかわらず、6作が串団子のように一本筋が通っていると感じたのは、香菜里屋が必ず登場するからだろう。
最初と最後の2作でももちろん成立するのだけれどそれではつまらない。
間に4編を挟んで緩急をつけて面白いのだと思う。
もうひとつ、香菜里屋の工藤が作る料理の描写がたまらなく美味しくてそれだけでも読む価値がありました。
■「かたみ歌」朱川湊人(新潮社文庫)
こちらの連作短編集も推理小説である。 ホラー色も若干ありますが読んだ後に眠れなくなるほどではないからご安心を。
朱川湊人は直木賞作家、ところが申し訳なくも私は知らなかった。

狂言回しはアカシア商店街の古本屋「幸子書房」である。
店主は古希を過ぎた老人で、香菜里屋のマスターのように物語の流れを掌握するほどの存在感はない。 そう、初めのうちは・・・
1.紫陽花のころ
2.夏の落し文
3.栞の恋
4.おんなごころ
5.ひかり猫
6.朱鷺色の兆
7.枯葉の天使
題名を見てもお分かりのとおりで「かたみ歌」のほうが「花の下にて春死なむ」よりも叙情的な色合いが強い。
舞台は昭和40年代のおそらくは東京の庶民的な商店街。
作者は昭和38年生まれだからこの時代を知らないはずなのに、自分が体験しているかのように当時の風景を描いていることに驚いた。
当時の歌謡曲やグループサウンズ、流行りの洋楽が当たり前のように登場する。
舞台背景はたいへん懐かしいのであるが、これってこの時代に陰も形もなかった今の若い人にはどんな感じなのだろうか。
それにしてもどの短編もその切なさに心打たれます。
よしもとばなな風味の陽性ホラーではなく、静的なホラーに上品に包まれる感じがなんともいえない。
「ちょっと前にこの町に住んでいた子供ですよ」
「その・・幽霊とか、そういうものでしょうか」
「さぁ、どうでしょうね。 考え方一つですけれど私にとっては天使です」
時空を超えた不思議をあっさりと受け入れて普通に暮らす人たちを描いて秀逸でした。










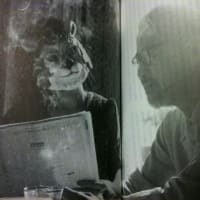
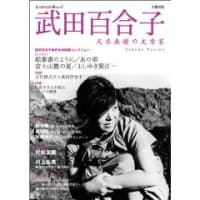

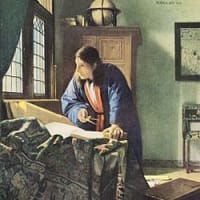

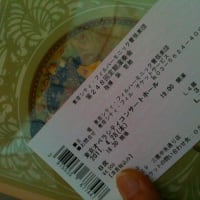




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます