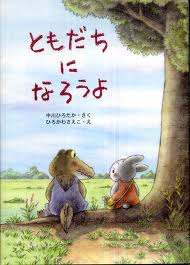2007年、講談社発行
(帯のコメント)
「男性保育士資格取得、日本第一号 中川ひろたかのすべて
歌、あそび、絵本
おもしろいこと ぎゅうぎゅうづめ!」
「おでん、おんせんにいく」という絵本を読んで以来、彼のファンになりました。
本人の自己紹介はさておき、この本の魅力はなんといっても彼の紹介する絵本画家達。
それを参考にして随分絵本を買い込みました。
お気に入りの絵本画家は・・・
■ 長谷川義史
この方のヘタウマ絵、たまらなく好きです。
荒削りだけど、醸し出す雰囲気と微妙な表情は天下一品!
「この子はこんな子」と決めつけずに、環境によってどうにでも変わっていくという子どもの無限の可能性を秘めているように見えます。
それから、なんとなく「昭和」を思い出す背景もお気に入り。
「おでんおんせんにいく」と「れいぞうこのなつやすみ」はストーリーが秀逸で大人も楽しめます。
「いいからいいから」は当院待合室の人気絵本。いたずらをして母親に叱られると「いいからいいから!」と言いながら逃げ回る子どもが増殖中です(笑)。
「おへそのあな」はこれから生まれてくる赤ちゃんがおへその穴から外を覗いたひとり言。
「ぼくがラーメンをたべているとき」は、平和な日本でラーメンを食べているこの瞬間に世界中ではどんなことが起きているのかを提示する、ハッとするような展開です。



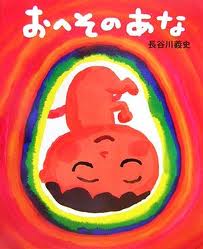

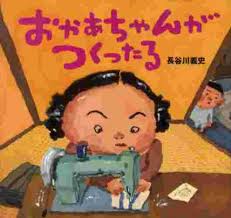

■ 村上康成


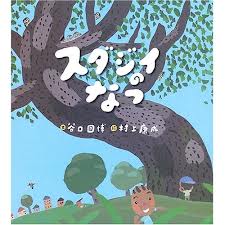

■ 長野ヒデ子



■ はたこうしろう

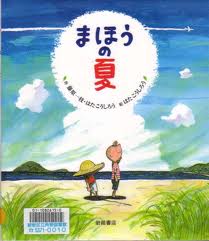
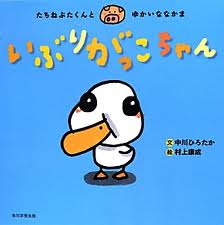
■ ささめやゆき


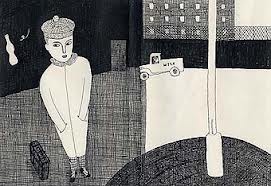
■ ひろかわさえこ
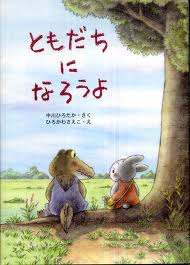


(帯のコメント)
「男性保育士資格取得、日本第一号 中川ひろたかのすべて
歌、あそび、絵本
おもしろいこと ぎゅうぎゅうづめ!」
「おでん、おんせんにいく」という絵本を読んで以来、彼のファンになりました。
本人の自己紹介はさておき、この本の魅力はなんといっても彼の紹介する絵本画家達。
それを参考にして随分絵本を買い込みました。
お気に入りの絵本画家は・・・
■ 長谷川義史
この方のヘタウマ絵、たまらなく好きです。
荒削りだけど、醸し出す雰囲気と微妙な表情は天下一品!
「この子はこんな子」と決めつけずに、環境によってどうにでも変わっていくという子どもの無限の可能性を秘めているように見えます。
それから、なんとなく「昭和」を思い出す背景もお気に入り。
「おでんおんせんにいく」と「れいぞうこのなつやすみ」はストーリーが秀逸で大人も楽しめます。
「いいからいいから」は当院待合室の人気絵本。いたずらをして母親に叱られると「いいからいいから!」と言いながら逃げ回る子どもが増殖中です(笑)。
「おへそのあな」はこれから生まれてくる赤ちゃんがおへその穴から外を覗いたひとり言。
「ぼくがラーメンをたべているとき」は、平和な日本でラーメンを食べているこの瞬間に世界中ではどんなことが起きているのかを提示する、ハッとするような展開です。



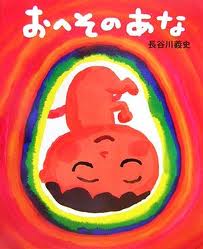

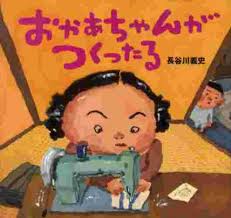

■ 村上康成


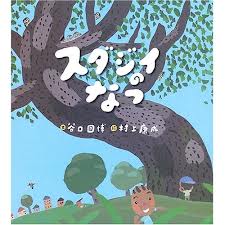

■ 長野ヒデ子



■ はたこうしろう

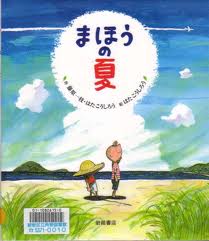
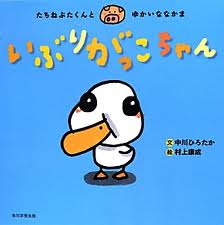
■ ささめやゆき


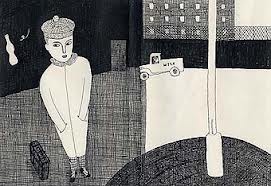
■ ひろかわさえこ