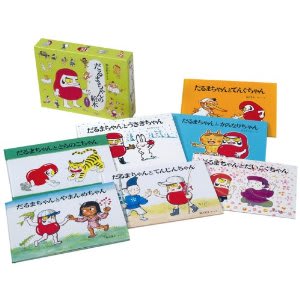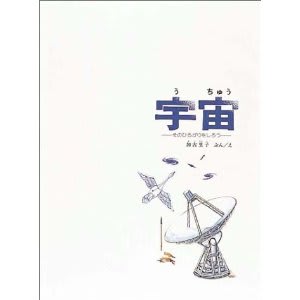あれ、この本の題名、見たことある・・・実は20年前にも発行されていました。
つまり、20年経っても、問題は解決していないということですね。
哺乳類の子どもは、愛情をたくさんたくさん必要とする生き物です。
愛情無しには、体は大きくなっても、心が育ちません。
■ 虐待した親へ…「日本一醜い親への手紙」本に
(2017年12月17日:朝日新聞)

親から虐待を受けて育った100人の手記をまとめた「日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨てちゃえば?」が10月に出版された。「ありがとう」とは言えない親への思い、大人になっても癒えない心の傷などがつづられている。
冬はご飯も食べさせず、服がビリビリに破れてほぼ裸の私に頭から水をかけ、外に放り出したね。お父さんにも殴られ、髪を引っ張られ、ふり回されて首を捻挫。すごく悲しかった。
「鈴鳴うた猫」というペンネームで、こうした体験を手記にした女性(29)に取材した。九州出身で、現在は神奈川県に住む。
妹たちは母と一緒にお風呂に入るのに、長女だった女性だけは「お前はくさいから、お父さんに洗ってもらえ」と、20歳まで父と入浴させられた。小学生の時、祖父から性器に指を入れられる性的虐待も受けたが、「誰にも言っちゃいけない」と思い込んでいた。
中学生になると、自分の指先や手首をカッターで傷つけるようになった。高校1年生の3学期、学校に行けなくなった。うつ病の症状だったが、親は「甘えだ」と言った。パジャマ姿で庭に放り出された。「学校に行けない私が悪いんだ」と自分を責めた。
大学卒業後、親からは地元の公務員になるよう言われた。でも、こっそり神奈川県内の自治体の公務員試験を受けた。合格を知った親は、「落ちればよかったのに」と言った。
25歳で親元を離れた。信頼できる主治医にも出会え、今春、結婚もした。でも、トラウマは消えない。親に怒られる幻聴は最近も聞こえる。「夜中に包丁を取り出していた」と夫に教えられることもある。
手記を募集していることをツイッターで知り、「親と向き合ってみよう」と思った。親への「手紙」を書いてみて、「少しだけ、つきものが落ちたような感じ」がしたという。「虐待を虐待として受け止める機会がなかなか無かったので、すごく良い機会になった」。ただ、親の反応が怖いので手紙を送るつもりはない。「親が好き」という気持ちも、親を責めたくない気持ちもある。
子どもの時、自分の虐待に気づいてくれる大人はいなかった。「子どもたちがこんな風に感じて生きている現状があることを知ってもらいたい」と願う。
手記には、今後の人生への決意も込めた。
私は必ず生き抜いてみせます
■編集者「まず現実を見て」
出版を企画したのは、作家で編集者の今一生(こんいっしょう)さん(52)。1997年にも「日本一醜い親への手紙」を出している。当時、親への感謝をつづった手記本がベストセラーになる中、「親に『ありがとう』と言えない育てられ方をした人の声に耳を傾けたい」と考えたのがきっかけだった。
最初の出版から20年たったが、児童虐待はなくならない。「社会の仕組みを変えるきっかけにしたい」と、再び手記を募った。暴力や性的虐待のほか、親が浪費して学費を積み立ててくれなかったり、極端な信仰を押しつけられて精神的に追い詰められたりしたことなど、さまざまな体験や思いが寄せられた。
「平穏のため、今後も絶縁し続けます」と書いた人もいれば、「ずっとさみしくて、かなしいんだよ」という人もいる。親への思いはさまざまだ。「周囲から見たら『親を捨てちゃえば?』と言いたくなるけど、捨てても捨てなくてもいい。それを決めるのは、あなただよ」との思いを込めて副題をつけた。
今さんは「子どもへの虐待は、大人がやり過ごしてきた宿題。まず現実を見て」と話す。虐待を防ぐには親への支援が必要だと言われるが、「子どもも支援すべきだ。自分がされていることが虐待なのか、最低限守られる人権は何か、教えられないまま大人になっていくのはおかしい」と問題提起する。dZERO刊。税別1800円。
つまり、20年経っても、問題は解決していないということですね。
哺乳類の子どもは、愛情をたくさんたくさん必要とする生き物です。
愛情無しには、体は大きくなっても、心が育ちません。
■ 虐待した親へ…「日本一醜い親への手紙」本に
(2017年12月17日:朝日新聞)

親から虐待を受けて育った100人の手記をまとめた「日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨てちゃえば?」が10月に出版された。「ありがとう」とは言えない親への思い、大人になっても癒えない心の傷などがつづられている。
冬はご飯も食べさせず、服がビリビリに破れてほぼ裸の私に頭から水をかけ、外に放り出したね。お父さんにも殴られ、髪を引っ張られ、ふり回されて首を捻挫。すごく悲しかった。
「鈴鳴うた猫」というペンネームで、こうした体験を手記にした女性(29)に取材した。九州出身で、現在は神奈川県に住む。
妹たちは母と一緒にお風呂に入るのに、長女だった女性だけは「お前はくさいから、お父さんに洗ってもらえ」と、20歳まで父と入浴させられた。小学生の時、祖父から性器に指を入れられる性的虐待も受けたが、「誰にも言っちゃいけない」と思い込んでいた。
中学生になると、自分の指先や手首をカッターで傷つけるようになった。高校1年生の3学期、学校に行けなくなった。うつ病の症状だったが、親は「甘えだ」と言った。パジャマ姿で庭に放り出された。「学校に行けない私が悪いんだ」と自分を責めた。
大学卒業後、親からは地元の公務員になるよう言われた。でも、こっそり神奈川県内の自治体の公務員試験を受けた。合格を知った親は、「落ちればよかったのに」と言った。
25歳で親元を離れた。信頼できる主治医にも出会え、今春、結婚もした。でも、トラウマは消えない。親に怒られる幻聴は最近も聞こえる。「夜中に包丁を取り出していた」と夫に教えられることもある。
手記を募集していることをツイッターで知り、「親と向き合ってみよう」と思った。親への「手紙」を書いてみて、「少しだけ、つきものが落ちたような感じ」がしたという。「虐待を虐待として受け止める機会がなかなか無かったので、すごく良い機会になった」。ただ、親の反応が怖いので手紙を送るつもりはない。「親が好き」という気持ちも、親を責めたくない気持ちもある。
子どもの時、自分の虐待に気づいてくれる大人はいなかった。「子どもたちがこんな風に感じて生きている現状があることを知ってもらいたい」と願う。
手記には、今後の人生への決意も込めた。
私は必ず生き抜いてみせます
■編集者「まず現実を見て」
出版を企画したのは、作家で編集者の今一生(こんいっしょう)さん(52)。1997年にも「日本一醜い親への手紙」を出している。当時、親への感謝をつづった手記本がベストセラーになる中、「親に『ありがとう』と言えない育てられ方をした人の声に耳を傾けたい」と考えたのがきっかけだった。
最初の出版から20年たったが、児童虐待はなくならない。「社会の仕組みを変えるきっかけにしたい」と、再び手記を募った。暴力や性的虐待のほか、親が浪費して学費を積み立ててくれなかったり、極端な信仰を押しつけられて精神的に追い詰められたりしたことなど、さまざまな体験や思いが寄せられた。
「平穏のため、今後も絶縁し続けます」と書いた人もいれば、「ずっとさみしくて、かなしいんだよ」という人もいる。親への思いはさまざまだ。「周囲から見たら『親を捨てちゃえば?』と言いたくなるけど、捨てても捨てなくてもいい。それを決めるのは、あなただよ」との思いを込めて副題をつけた。
今さんは「子どもへの虐待は、大人がやり過ごしてきた宿題。まず現実を見て」と話す。虐待を防ぐには親への支援が必要だと言われるが、「子どもも支援すべきだ。自分がされていることが虐待なのか、最低限守られる人権は何か、教えられないまま大人になっていくのはおかしい」と問題提起する。dZERO刊。税別1800円。