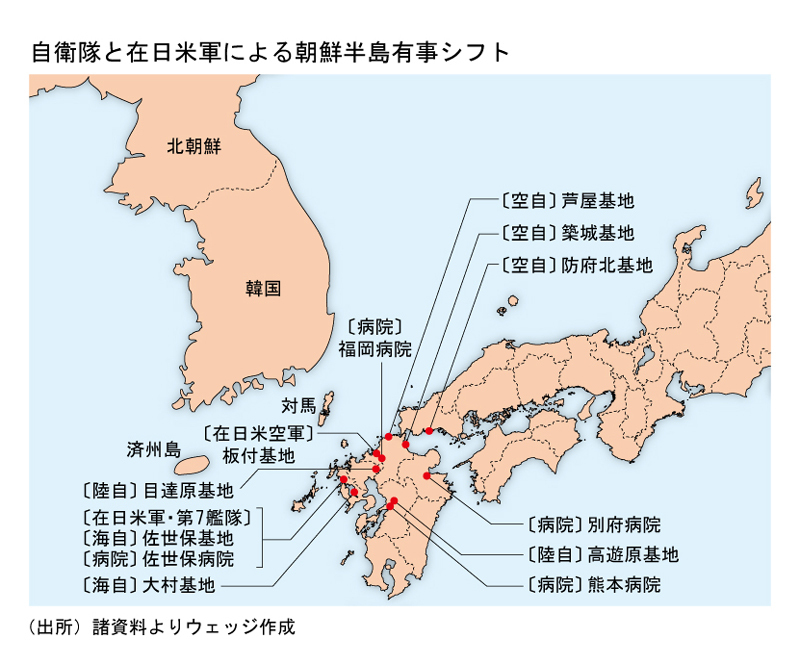2013年末の安倍晋三首相の靖国参拝。韓国は「しめた!」と叫んだ。これを言い訳に米韓関係の悪化を食い止められると思ったからだ。だが年が明けてから、韓国には失望感が広がった。
参拝を世界で一番喜んだ韓国人
12月26日に安倍晋三首相が靖国神社を参拝して、世界で一番喜んだのは韓国人だったのではないか。
12月6日に米国のバイデン副大統領から米中間での二股外交を露骨に指摘されたうえ「米国側に戻れ」と言い渡された朴槿恵大統領。韓国人はすっかりしょげ返っていた(「北朝鮮に『四面楚歌』と嘲笑された韓国」参照)。
そこに靖国参拝。駐日米国大使館は直ちに「失望した」と論評、米国務省も同じ表現で日本を批判した。韓国には「米国に叱られたのは我が国だけではない」との奇妙な安心感が広がった。そして「これは米韓関係改善のテコに使える」との期待が一気に盛り上がった。
韓国は、日本との軍事協力を強化するよう求める米国に対し「日本の右傾化」を理由に断ってきた。しかし、米国からは「日本の右傾化とは言い訳で、本当は中国が怖いのだろう」と見透かされてしまった。バイデン発言はその象徴である。
世界標準からは奇妙な告げ口外交
米国に対してだけではない。就任以来、朴槿恵大統領は世界中で日本の右傾化を言って歩く「告げ口外交」を展開してきた。しかし、韓国は世界から「奇妙な国」と冷ややかな目で見られるようになっていた。
韓国の価値観からすると別段、おかしくはない。しかし、隣国の悪口を国家元首が言って回る国は、世界標準からすればやはり変な国なのだ(「なぜ、韓国は東京五輪を邪魔したいのか」参照)。
韓国人には靖国参拝こそは救世主に見えた。なぜなら米国に対し「ほらこの通り、日本は右傾化しているでしょ。だから私は日本と軍事協力できないのです」と、言い訳の絶好の証拠を差し出せると思ったのだ。
二股外交を反日で偽装するという朴槿恵外交が限界に突き当たっていた時だから、韓国紙には「安倍外交は死んだ」「日本のオウンゴールを生かそう」「米国と共闘し日本を追い詰めよう」などと喜びの声が満ち溢れた。
「靖国」は韓国の自爆兵器
もちろん、韓国政府もこの機会を逃さなかった。世界に向け「野蛮で危険な国家、日本」と「被害者、韓国人の怒り」を宣伝した。
1月に予定されていた日韓財務担当相会談を取り止めたうえ、次官級戦略対話や局長級の安全保障政策協議会の開催のための実務協議を中断することを決めた(「靖国参拝で全対話凍結 国際協調で『日本孤立作戦』」=朝鮮日報12月28日)。
韓国国会も12月31日「靖国参拝と日本政府が狙う集団的自衛権の行使容認は、侵略戦争を美化し軍国主義を復活するたくらみ」との非難決議を採択した。
朴槿恵大統領も1月2日、潘基文国連事務総長と電話で話し「過去を直視できずに何度も周辺国を傷つけるなら、不信と反目を助長する」と日本を非難した。潘基文事務総長の対日批判も引き出した。
もっとも「靖国」は韓国にとって自爆兵器でもある。それが侵略戦争の象徴としても、韓国は日本と戦ったことはないからだ。
威張る朝鮮系日本人
それどころか日本の「侵略戦争」には、当時の朝鮮人も日本の軍人・軍属として多数参加している。もちろん彼らは靖国神社に祀られているし、中には捕虜虐待の罪で戦犯とされた人もいる(注1)。
(注1)「洪思翊中将の処刑」(山本七平、昭和61年)に詳しい。
連合国の軍人の中には太平洋戦争中に捕虜収容所で朝鮮人に酷い目にあわされた人もおり、米軍など組織の記憶となっている。
韓国が「靖国」を掲げて自らを被害者と主張すれば「本当は加害者だったではないか」と逆に糾弾されかねない。そこで国会決議では批判の対象に「集団的自衛権」を含めて、合わせ技にしたのであろう。
「靖国」に絡めた大統領の非難談話も被害者を「周辺国」とぼかし「韓国」とはしていない。やはりそれが理由の1つと思われる。
一方、中国は日本孤立策の先兵として韓国を利用したい。日米離間を実現するには中国だけではなく、米国の同盟国でもある韓国に日本批判させるのがより効果的だからだ。
しかし中国国民、ことに満州国が存在した東北部の人々には「威張り散らす朝鮮系日本人」への記憶が残っている。「靖国」を契機に、中国のネチズンが反韓的言説を展開しないとも限らない。そこで韓国を「完全な被害者」として認めてやる必要があったのだろう。
「二股外交するな」
中国の陳海・駐韓代理大使は1月8日付中央日報に、安倍首相の靖国参拝を批判する記事を寄稿した。
そこでは「日本軍国主義の侵略はアジア各国の国民にあまりに大きな厄災となった。中でも中国と韓半島の国民が最大の被害者だった」と、軍国主義を主語としたうえ韓国人を最大の被害者と認定した(注2)。
(注2)この記事の日本語版はここで読める。
もっとも、韓国は中国から呼びかけられた共闘に逡巡した節がある。12月31日に中韓外相は電話会談した。中国側は会談後に「両外相は安倍首相の行為を厳しく批判した」と発表したが、韓国側は「最近の北東アジア情勢など関心事を協議した」との文言に留めた。
それを解説した聯合ニュースは「日本と協力する分野もあり、韓米日の協力の必要もある」「歴史問題で中国と全面的に連携するのは望ましくない」との政府の中の意見を紹介した。
韓国には「二股外交するな」というバイデン発言が効き始めたのだろう。これまでなら会談後、直ちに中国と声を1つにして日本批判したうえ、国民にも外交成果として大いに誇ったものだ。
今度それをやったら米国から「まだ、中国のお先棒を担ぐつもりなのか」と言われかねない。「中国と組んで日本を叩く」構想はとりあえず棚上げせざるを得なかったのだろう。
空振りに終わった日本叩き
代わりに韓国人は「米国と組んで日本を叩く」ことに希望を見出した。聯合ニュースは1月2日配信の「韓国と日本が新年から対米外交戦」で以下のように書いた。
・韓国政府は(靖国参拝で)米国を動かす名分を手にした。ワシントンの外交筋も1日「米国で今ほど日本に対する批判の気運が高まったことはないと思う。民主主義と自由、平等など人類普遍の価値を同盟の礎石とする米国としては容認しがたい行為だった」と話す。
・(現地時間1月7日の米韓外相会談で)尹炳世(ユン・ビョンセ)外相が米国との対話の中で日本に向けた何らかのメッセージを引き出すなど、韓日の歴史問題においてそれなりに意味ある転換点を作りだす期待感がある。
もっとも、韓国人のその熱い期待も空振りに終わった。米韓外相会談後の記者発表で、ケリー米国務長官は“日本問題”に関し一切触れなかった。
それどころか発表では記者からの質問は受け付けないという異例の措置をとった。韓国人記者が“日本問題”に関し聞くに決まっている。ケリー長官がどう答えても対日批判に聞こえるから、というのが韓国紙の見立てだ。
それに尹炳世外相自身も発表の席で日本を名指しして批判しなかった。韓国紙はこれに関しては何も書いていないが、米国の強い要望の結果だった可能性が極めて高い。
日本への懲戒手段はない
韓国紙には不満が溢れた。会談を報じた中央日報の記事の見出しは「水も漏らさぬ韓米同盟……安倍への言及はなかった」(注3)。
(注3)この記事の日本版はここで読める。
「水も漏らさぬ両国の関係」(Without an inch of daylight between us)とはケリー長官の言葉だ。そう言う割には、米国は安倍批判をしてくれなかった――という韓国人の悔しさが伝わる見出しだ。
もっとも、韓国紙の米国特派員はそれ以前から「米韓による日本包囲網」への過剰な期待を諌めていた。米国の事情や本音をよく知るからだ。
その1つが朝鮮日報のワシントン特派員、イム・ミンヒョク記者の書いた「米国、安倍に厳しく警告したものの……」(12月31日)だ。興味深いのは以下の部分だ。
・米国の懸念は「安倍の歴史認識」そのものよりも「(日本の)周辺国との対立」にある。この点で韓米間には根本的な認識の差があり、今後解決を巡って意見の違いが露わになる可能性が高い。
・ニューヨークタイムズが「韓中は日本と首脳会談をすべきだ。安倍の参拝に『ライセンス』を与えたのは韓国と中国の(会談拒否という)圧迫だった」と社説に書いた。同紙論説委員と米外交当局者がしばしば会っていることを考えると、無視すべきではない。
・「北東アジア戦略の中心軸」たる日本を米国は放棄できない。安倍に痛烈な警告はしたが、さらなる懲戒手段はほとんどない。結局、韓中に「(日本との)対話により、自分たちで解決しろ」と言ったに等しい。
米国の本音を直視せよ
中央日報ワシントン支局長のパク・スンヒ記者も12月31日に「米国の本音」という記事を載せた。以下である。ちなみに原文の「本音」はハングルで「ホンネ」と表記。日本語そのままだ(注4)。
(注4)この記事の日本語版はここで読める。
・2期目のオバマ政権は、野党との政争で厳しい日が続く。内政の疲労は外交力も失わせた。シリアの状況が端的な例だ。
・米国にとって同盟とは道徳や価値のような情緒ではなく国益だ。我々が貴重なものと考える韓米同盟も、米国の国益の中にある時が安全地帯だ。
・「失望」声明に喜ぶあまり、米国が安倍の日本を嫌うことを韓国人は望んだ。しかし、その米国の国防長官は長い間の悩みだった普天間基地の移転問題が解決されるや否や「強い米日同盟」に言及した。
・米国の財政赤字は2013年11月基準で1352億ドルに達する。米国はこの赤字を埋めるためなら何でもする姿勢だ。中国に対抗せねばならない米国は、依然として安倍の日本を必要とするほかない。米国の本音を直視せねばならない。
同盟は情緒ではない
この記事のハイライトは「同盟は情緒ではなく国益だ」の部分だ。外交を感情で考えがちな韓国人に対し、筆者は「野蛮だが、カネを出す日本を大事にする米国」という現実を伝えたかったのだろう。
同時に「米国を実利で満足させないと、韓国は見捨てられるかもしれない」と警告を発したかったに違いない。「韓米同盟も……」の部分からそれが伺える。
確かにそうなのだ。日本の集団的自衛権の行使容認に対し、韓国政府は反対の姿勢を強くにじませている。日本との軍事協定も署名当日にドタキャンした。米国の強く求めるミサイル防衛(MD)にも参加しない。ことに後者は日本の右傾化とは全く関係がない。
韓国は守ってくれている米国ではなく、旧宗主国の中国の顔色を見て動くようになった。まさに「韓米同盟が米国の国益から外れ始めている」のだ。
「このままでは同盟が危機に瀕する」「日本問題など語っている場合ではない」と危機感を抱く韓国の知識人がようやく出てきたということだろう。
ただ、韓国の空気は「同盟は情緒」のままのようだ。それを背景に1月9日、最大手紙の朝鮮日報は「『歴史と安保は別』という米国の対日認識は誤り」という社説を載せた。
ケリー長官が日本批判をしなかったことを非難するために書かれたものだ。要は「靖国神社に首相が参拝し(戦争ができる国にするため)憲法を変えようとする日本を、米国は叩き直せ」という主張だ。
甘い言葉を耳元でささやく中国
もちろんこの論説自体は「情緒的」とばかりはいえない。「日本に対する貴重な外交的武器である歴史カードを、米国に陳腐化させられてはいけない」との国益を主張したものだからだ。
「中国と共闘できる歴史カードをきっちりと維持してこそ、米中二股外交が可能だ」という韓国なりの計算もそこにはある。
ただ、中国との対決に全力を挙げる米国人の目には、日本の軍国主義復活を騒ぎたてる韓国人の言説は「情緒そのもの」と映るであろうし、この訴えを米国が聞くこともないだろう。
今、中国は毎日のように「一緒に日本を叩こう」と韓国の耳元にささやいている。それは韓国人の情緒からすれば実に魅力的な呼びかけだ。
米国に叱られて「離米従中」の歩みをいったん止めたかに見えた韓国人の心は揺れるであろう。とすると韓国は、再び中国傾斜を始めるのかもしれない。