初期議会期においては富国強兵を目指す政府と民力休養を訴える民党との間において対立が続き、主に予算の通過がその焦点となっていた。しかし明治28年の日清戦争の勝利以降、政府と政党との間に次第に歩み寄りが見られるようになっていく。明治31年には初の政党内閣である大隈内閣が成立し、政党から多くの閣僚が選出されるなど政党の勢力は無視し得ないものに成長していた。
こうした政党勢力への対応は、政府中枢にある元老たちの間においてもその見解が分かれた。伊藤博文は自らが政党「政友会」を組織するなど、政党に積極的に関与していくことを企図していたが、一方で藩閥勢力の中心にいた山県有朋はこれに反対し、政府は政党の上に超然として存在すべきであるとした。山県の主張の背景には、明治26年に文官任用令が制定され、近代官僚制の整備によって政治情勢に中立である政府組織を構築し得るだけの官僚の供給が望めたことがある(中略)。
伊藤が総裁を引退した後、政友会は西園寺公望を総裁として政局に臨んだ。一方、山県有朋の影響力の下に組織された官僚等によるいわゆる藩閥勢力は、桂太郎をその代表として政友会と相対した。西園寺は政党勢力を統制し、また、桂は官僚や貴族院を統制するなどし、この両者は互いに提携することによって安定的な政局の運営を企図した。明治34年の第一次桂内閣成立より大正2年の第三次桂内閣退陣まで、桂と西園寺は交互に組閣し、両者の間の提携は維持された。これを『桂園時代』と呼ぶ。
この期間には、安定した政権運営の結果、満州と朝鮮半島の利権を巡ってロシアと日露戦争を戦い日本が勝利したり、明治27年の日英通商航海条約による領事裁判権の撤廃に続いて、明治44年の日米通商航海条約において関税自主権を回復し、幕末期以来の懸案であった不平等条約の改正に成功するなど、日本の国際的地位は著しく向上した。
以上、笠原英彦・桑原英明編『日本行政の政治と理論』(芦書房、2004年)第1章3節38-39頁より引用。
どうも、冬月です。
昨夜から東京に降り始めた雪は、一日かけて降り続け今や大変に積もっておりまして、小学生の弟は雪合戦ができると喜んでおりますが、用事があって出かける大人にとっては正直たまらない天候であります。
しかし、雪を喜べるのは子どもの特権ですね♪
私も弟ぐらいの頃は、 神社の境内で雪だるまをつくって遊んだものです。雪合戦はやりませんでしたがね、相手がいなかったので(笑。
さて、先日ようやく試験が終わりました。
同じく試験があった学生の皆さん、お疲れ様です。
ついては、試験中に見つけたしょうもない発見を今日は紹介したいと思います。
日本行政史の試験勉強で教科書をめくっておりましたら、上記のような記述を発見しました。
スクールデイズが何だか全くご存知ない方は、まあこれは、内政の安定こそが国際的地位の向上につながるという私のかねてからくどく申し上げている持論を裏付ける史実の紹介だと理解して下さい(笑。
さて、上の記述は民明書房の類ではなく、れっきとした史実です。
スクールデイズの登場人物の姓が伊藤、西園寺、桂といった具合に日本の歴代総理大臣から命名されているというのは有名な話ですが、私はてっきり、歴代総理の姓から語呂が合うものを無作為に選んでいるだけだと思っておりました。
しかしこれを読みますと、スクールデイズでの命名は無作為ではなく、何らかの意味があるのではないかと思えてなりません。
スクールデイズの製作者の中に、日本の明治期の政治に関する専門的な知識を持った人間が混ざっていたようです。
なんという才能の無駄遣いだ(笑。
この史実へのオマージュは、桂派と西園寺派との長年の文字通り「血塗られた」対立に終止符を打つ、原作者からの暗号、隠されたメッセージなのかもしれません。
つまり・・・
伊藤誠を国体と置き換えると、桂と西園寺が交互に政権をとる事で安定した「桂園時代」が実現したわけですから、スクールデイズでもそのようにすればいいと・・・?
国政ならば構いませんが、この場合かなり道徳的な問題がありそうですね(汗。
やはり唯一の理想的な解決策は、多くの方が唱えているあの言葉だけなのでしょうか。
すなわち、誠氏(以下略
さて、これから弟の雪合戦に付き合わないといけません。
かのナポレオンは陸軍幼年学校時代、雪合戦で用兵の天才としての頭角を現したそうですが・・・・・私は、発想を変えて雪で白旗をつくってみようと思います(←つくれるか










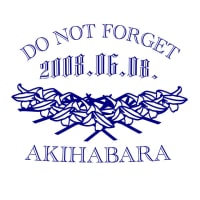








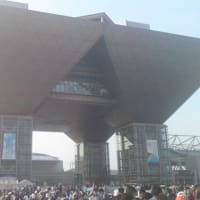
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます