
こんばんは、長江商学院の石川です。
私の悪いクセなのですが、忙しくなって追い込まれれば追い込まれる程、無関係なことに時間を費やしてしまうという傾向があります。フォーラムの感想コメントをFBで書いていたら長くなってしまい、勿体なくなったなので以下に転載します。いろいろ詳しくないことも書いていますので、誤りがあればぜひ正していただければと思います。
********************************************************************************
本学主催のイベント(日中M&Aフォーラム@長江商学院)に参加して来ました。日頃の勉強と重なる内容もあり、非常に参考になるお話でした。
前半は、マクロのお話。中期で見た場合、世界経済の牽引役はしばらく中国のまま。日本はもっとリスクを取って中国市場を開拓すべし、という主旨だったかと思います。後半は、日中のM&Aに焦点を当てた内容。政治に足を引っ張られ日中M&Aの件数は低迷しているものの、両国の産業は補完関係にありM&Aで得られるメリットは大きい。経済の発展段階、評価軸の相違、日本のソフトパワーにもっと注目すべき、というメッセージでした。
講師の方のお話からはだいぶ脱線するのですが、今日の講演を契機に私が感じたことは以下2点です。
(1)中国報道に対するバイアス
当たり前と言えば当たり前ですが、中国で得る中国情報は日本で得る中国情報より遥かに前向きなものが多いです。双方に正すべきバイアスがあるのでしょうが、日本の(一部)報道に見られる以下の論調には違和感を覚えます。
A:「中国の政治は(いずれ)崩壊する。なぜなら、共産主義と資本主義は矛盾するから。」 最近は流石に減りましたが、一時期この手の記事がよく書かれていました。古くはゴードン・チャンの「やがて中国の崩壊が始まる」とか。石原慎太郎が「シナは幾つかの小国家に分裂させた方がいい」みたいなことを言っていた時期もあったかと思います。民主主義と一口に言っても、様々な幅があります。シンガポールのように一党独裁を敷きながらも、安定した社会を築いている国家もある。共産主義一党独裁は資本主義とのイデオロギー的矛盾に耐えられないという論調はナイーブ過ぎるかと思います。
貧富の格差が社会不安を増大させるという指摘もあり、これもある程度は事実かと思いますが「全体として豊かになり続けている」うちは、これが原因で社会が崩壊するとは思えない。文革に比べれば、遥かにましだという判断が働くはずです。
B:「中国経済はバブルだから、いずれ崩壊する」
80年代の日本、またはリーマンショック以前のアメリカとのアナロジーが働いて、「中国経済は不動産価格高騰によるバブル、いずれ崩壊する。または既に崩壊が始まっている」という話になるのだと思います。確かに不動産は高いです。うちの近所の不動産屋の広告をみても、5000万円とか普通にある。東京と変わらない価格です。北京市民の平均年収が100万円(?)いかないくらいだと言われていることを考えると、めちゃくちゃに高い。確かにバブルでしょう。ただし、以下の2点で日本のバブルとは同列に並べられないのではないかと思えます。1つは、購買力の上昇ペースが速いこと。中国政府は今後10年で1人頭のGDPを倍にすると言っている。これは、年率に直すと7%ちょっとの数字です。決して高すぎる目標とは言えない。一方で、政府の様々な規制で不動産価格の上昇は抑えられている。つまり、所得の伸びを見たときの中国は、日本の1960年代~70年代に近い。80年代90年代ではない。2つめは、今日の講演にもありましたが不動産実需が強いこと。いわゆる「持家意識」(男が結婚するには持家が必要らしいです・・・)も強いし、都市化の進展も急テンポです。投機もあるが、純粋な住居としての購買意欲も高いように感じられます。
まとめると、不動産価格は確かにめちゃくちゃ高い。一時的な調整もあり得る。ただし、それを持って日本のように失われた20年が中国で再現するとは思えない、ということになります。
(2)日本人はあまり質問しない
国際会議を成功させるための条件が2つあるそうです。1つは、インド人を黙らせること。(私の知り合いの中国人でさえ、「インド人はめちゃくちゃ喋る」と言っています) もう1つは、日本人を喋らせること、だそうです。今日の講演でも、質問タイムになかなか日本人の手が挙がらなかったのが印象に残りました。自戒も含めて、発信力を高めなければと思った次第です。
さて、そろそろレポート書かないとまずい時間帯になってきました。
失礼します。










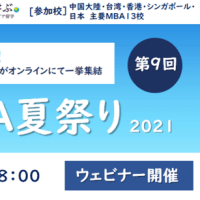









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます