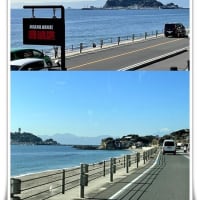文字、安易な修正するなよ
文字、安易な修正するなよ

 や、どこまで行ったんだ
や、どこまで行ったんだ
 そんなとこまで行ったのか
そんなとこまで行ったのか でもなんで?
でもなんで?

 なんか左下の写真と右下の写真、鳥居の位置と高さが若干ちがうく見えるんだけど、目の錯覚?
なんか左下の写真と右下の写真、鳥居の位置と高さが若干ちがうく見えるんだけど、目の錯覚? 老眼のくせに、そーゆーとこは目ざといな
老眼のくせに、そーゆーとこは目ざといな
 老眼は関係ないやろ
老眼は関係ないやろ

 実はこーゆーことだから
実はこーゆーことだから
 ……えっと、その男瓶、女瓶っていうのは?
……えっと、その男瓶、女瓶っていうのは?
 わかりました。老眼です。読めません
わかりました。老眼です。読めません なんて書いてあるの?
なんて書いてあるの?*日本三霊泉に数えられる『忍潮井』
常陸利根川沿いにある一の鳥居の両脇には、小さな鳥居の建てられた二つの四角い井戸「忍潮井(おしおい)」があります。それぞれの井戸の中を覗くと、うっすらと瓶(かめ)が見え、白御影石で銚子の形をしているものを男瓶(おがめ)・やや小ぶりで土器の形をしているものを女瓶(めがめ)と呼んでいます。
忍潮井は194年に造られ、両瓶とも1000年以上もの間、清水を湧き出し続けてきたとされています。辺り一面が海水におおわれており、真水(淡水)の水脈を発見し噴出させたところ、辺りの海水を押しのけて真水が湧出したことから、忍潮井の名がつけられました。
住民の生活の水として使われた、水と人類との関わりの中で最も古いかたちの井戸であり、日本三霊泉(伊勢の明星井・伏見の直井・常陸の忍潮井)の一つといわれています。
また、女瓶の水を男性が、男瓶の水を女性が飲むと二人は結ばれるという言い伝えがあり、縁結びのご利益もあるとされています。現在忍潮井の水を直接飲むことはできませんが、境内の手水舎の奥にある湧き水は、忍潮井と同じ清水で、お水取りをすることができます。
忍潮井には次のような伝説があります。
≪息栖神社が日川から今の地に遷座した際、取り残された男女二つの瓶は神のあとを慕って三日三晩哭き続けたが、とうとう自力で川を遡り、一の鳥居の下にヒタリと据え付いた。この地に定着して後も、時々日川を恋しがり二つの瓶は泣いた。≫
日川地区には瓶の泣き声をそのままの「ボウボウ川」と、瓶との別れを惜んで名付けた「瓶立ち川」の地名が今も残されています。
 銚子に土器? ぜんぜん見えないんですけど
銚子に土器? ぜんぜん見えないんですけど
 心に曇りや汚れがあるヒトには見えないそうです
心に曇りや汚れがあるヒトには見えないそうです
 クマルさん、ウソいったらダメだよ。実は水が澄んでないと見えないんだっって。だから見れたときには幸運が舞い込んでくるっていわれてるんだよ
クマルさん、ウソいったらダメだよ。実は水が澄んでないと見えないんだっって。だから見れたときには幸運が舞い込んでくるっていわれてるんだよ
 じゃあ、クマルさんは不運なんだな
じゃあ、クマルさんは不運なんだな
 ケンカ売ってんのかコラ
ケンカ売ってんのかコラ

つづく
 | 少年:くんくんとくまごろの大冒険: 新装改訂版 |
| amazon.co.jp↑↑↑ | |
| あいば くりす |
 | 依斬る |
| ↑↑↑amazon.co.jp | |
| あいば くりす |
 | 少年: くんくんとくまごろの大冒険 |
| amazon.co.jp↑↑↑ | |
| あいば くりす |
 | わらのいぬ |
| ↑↑↑amazon.co.jp | |
| Chris Aiba |
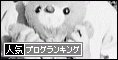
 にほんブログ村
にほんブログ村