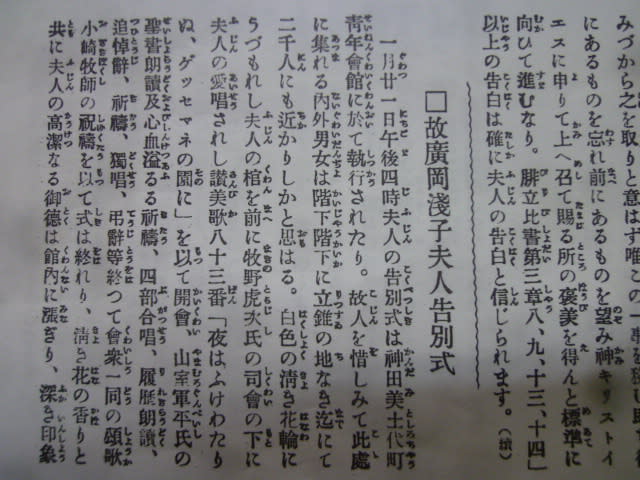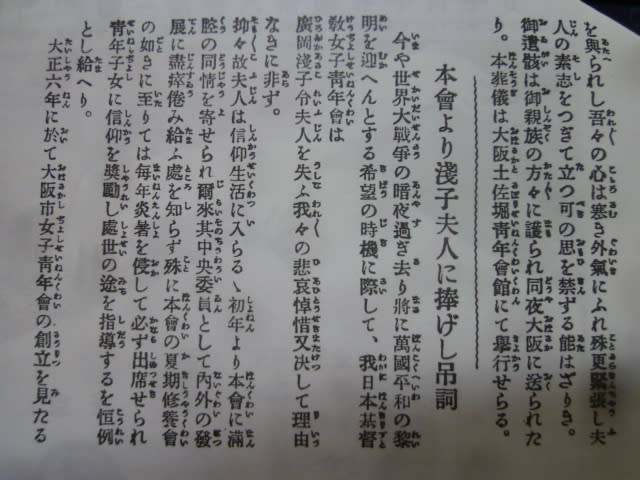浅子は、大正14年1月14日、東京麻布の広岡別邸で逝去する。
晩年、クリスチャンである浅子は、キリスト教関係の人たちと交流が密であった。
クリスチャンで「婦人週報」の主宰者・編集者である小橋三四(市谷在住)は、1月14日の夜、帰宅したところに悲報を受け、東京麻布の広岡邸(ヴォーリズ設計)に駆けつけ、3階寝室で眠る遺体の傍らで一夜を明かしている。三四は、暮に浅子の著書『一週一信』を編集出版したばかりであった。
日本キリスト教女子青年会(YWCA)では、1月14日の当夜、神田の会館で特別委員会が開催されていた。「席上、一委員が広岡夫人が御病気であると云ひ出され、一同驚き明日は御見舞申上んなど云ひ居りしに、十五日に至り既に永眠されし訃音に接したのである」と、河井道子は述べている。女子青年会も浅子から支援を受けていた。
河井道子にとって、12月の暮近く、浅子が用事があるとて神田の会館を訪れていただけに、突然の訃報は驚きであったようである。河井は、『女子青年界』に3号にわたって浅子を悼む原稿を載せており、浅子が晩年、YWCAを強力に支援したことがうかがえよう。
東京での告別式は、1月21日午後、神田美土代町の青年会館で開催され、『女子青年界』によると、「故人を惜しみて此処に集れる内外男女は階上階下に立錐の地なき迄にて二千人にも近かりしかと思はる」と記されている。
浅子が愛唱した賛美歌83番「夜はふけわたりぬ、ゲッセマネの園に」を以って開会、山室軍平の聖書朗読及心血溢れる祈祷、四部合唱、履歴朗読、追悼辞、祈祷、独唱、弔辞、頒歌、祝祷などが行われたようである。
『女子青年界』には、女子青年会代表、幹事、河井道子の名で、「本会より浅子夫人に捧げし弔詞」が掲載されている(前掲書)。
当時、成瀬仁蔵は、高木博士の診断で自らの病状ただならぬことを知り、本人も周囲もそれどころではなかったものと思われる。
「仁科節日記」によると、1月20日(月)には、「朝井上(秀)幹事長に広岡氏の話を聞きその節けふ午後の会のことを聞く。午後四時よりお話ありー平野(浜)、井上(秀)、大橋(広)、上代(たの)四氏と自分(仁科節)と」と記されており、緊迫した様子が伝わってくる。そして1月21日(火)には、「広岡夫人告別式の日」というただの一行で終わっている。
成瀬のお話というのは、もちろん広岡浅子のことではなく、日本女子大学校の今後のことなどであったものと思われる。
一方、小橋三四は、浅子の柩に随伴したようで、「広岡浅子刀自の霊柩に従って大阪に赴き、廿三日葬儀の後、安倍野に送りし遺骸の、翌朝は早くも一片の白骨に名残を止めて、、、廿五日朝帰京しました」と述べている。
井上秀と小橋三四は同じ1回生であるが、一方は大学の後継者と目されはじめ、他方は女性ジャーナリストとして新しい分野を開拓していた。
浅子の遺骨は、その後、深江の広岡別邸に安置されたままで、まだ埋骨式が行われていなかった。広岡恵三の病状回復を待っていたためである。
河井道子は、3月17日、深江の里を訪れ、浅子の遺骨と対面し、「浅子夫人と七年間も寝食を共にせられた千本木道子」から色々話を聞いている。秘書の千本木道子(みち)は、新潟県長岡市中島の出身で、日本女子大学の卒業生、7回生(家政科)である。大正3年12月発行の「桜楓会氏名簿」には、住所は「大阪市南区天王寺小宮町広岡家内」となっている。回生としては、上代タノ(のちの学長)と同じである。
日本女子大学校では、「広岡浅子刀自追悼会」がその後6月28日に開催されたが、その遅れた理由は、このような経緯によるものであろう(2015年8月4日の当ブログ「広岡浅子刀自追悼会と校長・麻生正蔵1」を参照)。

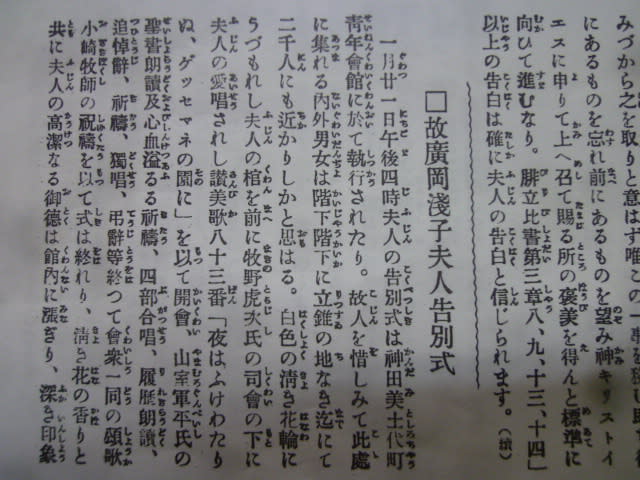
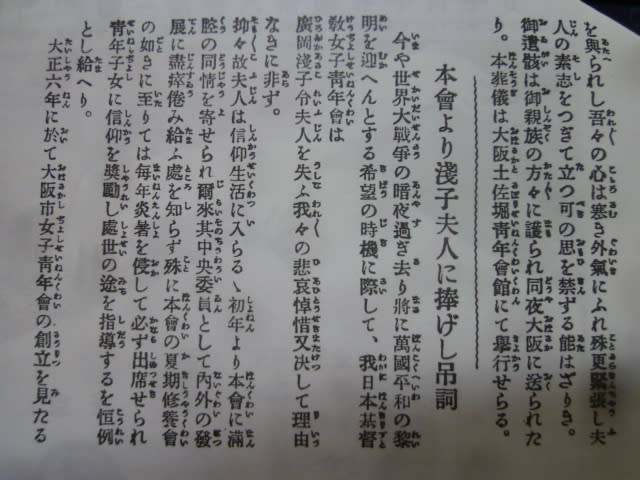



晩年、クリスチャンである浅子は、キリスト教関係の人たちと交流が密であった。
クリスチャンで「婦人週報」の主宰者・編集者である小橋三四(市谷在住)は、1月14日の夜、帰宅したところに悲報を受け、東京麻布の広岡邸(ヴォーリズ設計)に駆けつけ、3階寝室で眠る遺体の傍らで一夜を明かしている。三四は、暮に浅子の著書『一週一信』を編集出版したばかりであった。
日本キリスト教女子青年会(YWCA)では、1月14日の当夜、神田の会館で特別委員会が開催されていた。「席上、一委員が広岡夫人が御病気であると云ひ出され、一同驚き明日は御見舞申上んなど云ひ居りしに、十五日に至り既に永眠されし訃音に接したのである」と、河井道子は述べている。女子青年会も浅子から支援を受けていた。
河井道子にとって、12月の暮近く、浅子が用事があるとて神田の会館を訪れていただけに、突然の訃報は驚きであったようである。河井は、『女子青年界』に3号にわたって浅子を悼む原稿を載せており、浅子が晩年、YWCAを強力に支援したことがうかがえよう。
東京での告別式は、1月21日午後、神田美土代町の青年会館で開催され、『女子青年界』によると、「故人を惜しみて此処に集れる内外男女は階上階下に立錐の地なき迄にて二千人にも近かりしかと思はる」と記されている。
浅子が愛唱した賛美歌83番「夜はふけわたりぬ、ゲッセマネの園に」を以って開会、山室軍平の聖書朗読及心血溢れる祈祷、四部合唱、履歴朗読、追悼辞、祈祷、独唱、弔辞、頒歌、祝祷などが行われたようである。
『女子青年界』には、女子青年会代表、幹事、河井道子の名で、「本会より浅子夫人に捧げし弔詞」が掲載されている(前掲書)。
当時、成瀬仁蔵は、高木博士の診断で自らの病状ただならぬことを知り、本人も周囲もそれどころではなかったものと思われる。
「仁科節日記」によると、1月20日(月)には、「朝井上(秀)幹事長に広岡氏の話を聞きその節けふ午後の会のことを聞く。午後四時よりお話ありー平野(浜)、井上(秀)、大橋(広)、上代(たの)四氏と自分(仁科節)と」と記されており、緊迫した様子が伝わってくる。そして1月21日(火)には、「広岡夫人告別式の日」というただの一行で終わっている。
成瀬のお話というのは、もちろん広岡浅子のことではなく、日本女子大学校の今後のことなどであったものと思われる。
一方、小橋三四は、浅子の柩に随伴したようで、「広岡浅子刀自の霊柩に従って大阪に赴き、廿三日葬儀の後、安倍野に送りし遺骸の、翌朝は早くも一片の白骨に名残を止めて、、、廿五日朝帰京しました」と述べている。
井上秀と小橋三四は同じ1回生であるが、一方は大学の後継者と目されはじめ、他方は女性ジャーナリストとして新しい分野を開拓していた。
浅子の遺骨は、その後、深江の広岡別邸に安置されたままで、まだ埋骨式が行われていなかった。広岡恵三の病状回復を待っていたためである。
河井道子は、3月17日、深江の里を訪れ、浅子の遺骨と対面し、「浅子夫人と七年間も寝食を共にせられた千本木道子」から色々話を聞いている。秘書の千本木道子(みち)は、新潟県長岡市中島の出身で、日本女子大学の卒業生、7回生(家政科)である。大正3年12月発行の「桜楓会氏名簿」には、住所は「大阪市南区天王寺小宮町広岡家内」となっている。回生としては、上代タノ(のちの学長)と同じである。
日本女子大学校では、「広岡浅子刀自追悼会」がその後6月28日に開催されたが、その遅れた理由は、このような経緯によるものであろう(2015年8月4日の当ブログ「広岡浅子刀自追悼会と校長・麻生正蔵1」を参照)。