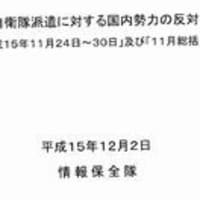メシの話を、とのリクエストにお応えして、20年近く前に喰ったものを思い出してみる。不思議なことに、不味いものほどよく覚えている。
モスクワに着いた日は、思えば長ーい一日だった。
午後の飛行機で出発して、実質8時間以上乗っていたわけだが、モスクワに着いたのは出発した時間とほぼ同じ頃。夜を挟まず、昼が連続してやってきたようなものだ。
着いてすぐ軽食をとったが、立っているのもやっとという状態で、何を食べたのかよく覚えていない。ただ、ぶっとくて水分の全くないキュウリは不味かった。
主食はパンで、食パンの薄いのが白パンと黒パンでそれぞれ7、8枚、皿に積んである。
白パンは美味しいが黒パンは不味くて、ちょっと酸っぱいような匂いがする。
「白い方だけ食べたら悪いかな」と留学生に聞くと、「構わないよ。みんなそうしてるから」と言う。
後にレニングラードで入った高級レストランでも同じ形式で白パン黒パンが出てきたところを見ると、何か意味があってそうしているのか、それともただの惰性なのか。
余談だが、旅行中、些細なことでも、何か革命にちなんだ由来があるのではないかと、しばしば考えた。何せここはソビエトなんだから!
例えばこの黒パン。革命当時の虐げられた農民の辛苦を忘れないために、わざと白パンと並べておくのかもしれないぞ、などなど。
しかし、今はわかってる。大した意味などないのだ。
どこで暮らそうと、人の考えることに大した違いなんかない。ソ連の国民はみんなレーニンだったりコルチャーギンだったりするわけじゃない。イラクの国民がみんなフセインではない。
気の弱そうなおやじ、口うるさいおばさん、お洒落に余念のない娘、口説くタイミングを横目で測ってる男の子。みんなどこにでもいる普通の人々だ。
まして、レストランのメニューに思想だの階級性だの、あるわけもない。
多分、ずっとそうしてきたから・・・ただそれだけのことだ。
今にして思えば、そんな「惰性的黒パン」が、かの国の行く末を暗示していたような気がする。
パンと一緒に出されるのは、普通にマーガリン、ベーコン。
「ここならでは」っていうのは、塩漬けの生鮭。これも、塩辛さといい生臭さといい、すごい不味かったのでよく覚えている。
その他、「ならではもの」を挙げると、ピロシキ、ボルシチ、前述のぶっとくてスカスカのキュウリ。
そういえば、生野菜は、キュウリだけだったような気がする。
スライスしたキュウリを7、8枚並べて塩をかけたものが前菜だった。
他にも野菜がないわけではない。キャベツはなにげにスープに入っていたし。野菜は煮込んで食べるものと決めているのか、もしかしたら、衛生上の問題か。野菜を洗う清潔な水がないのかもしれない。
日本以外で水道の水を飲んではいけないのは常識だが、レニングラードの水道は、その常識をも覆すシロモノだった。濁った色、異臭、細かい沈殿物・・・飲むどころか、風呂や洗濯も憚られるような水だった。
確かに、この水で洗った野菜を生で食べるわけにはいかないだろう。
不味いものを挙げていると、食費を値切ったんだろ、と思われるかもしれないが、とんでもない!(きっぱり)。
レニングラードでは、通訳のセルゲイさんが、夕食前に勤務終了となるため、自力で食べなければならない。言葉がまるでわからないので、オーダーしなくても食べられるコース料理のお店に続けて通った。あの当時で、な・なんと8000円だった。
すかすかキュウリの前菜、赤ワイン、黒白パン(毎度のことながらマーガリン・ベーコン・塩漬け生鮭添え)、ボルシチその他の郷土料理と牛肉の串焼き(これは例外的に美味かった!)、コーヒー、アイスクリーム。
そうそう。アイスクリームは格別に美味かった。公園に自転車で売りに来るアイスクリームも、レストランのデザートのアイスクリームも、レーニンが「国家と革命」を執筆したというラズリフの掘っ建て小屋で食べたアイスクリームも。ソ連のアイスクリームはすべて美味かった。
逆に、最悪だったのは、コムソモールの寮のブッフェで遭遇した「何だかわからないもの」だ。
留学生に誘われて、コムソモールの寮に行き、図々しくも食事までしてきた(タダで!)。
一見、チャーハンのようだったので、「おお、米だ米だ」と皿にテンコモリにしたのが、米ではなかった。何だかよくわからない、稗か粟か何らかの穀物にドブ臭い匂いを故意になすりつけたようなしろものだった。
あれは一体何だったのか。アジア人に仕掛けられたトラップか。
コムソモールの寮は、地域別に分かれていて、アジアと中近東が同じ棟だった。日本人留学生の部屋のあたりは、カレーらしき匂いが充満していた。
インドだったかパキスタンだったか忘れたけれど、隣の人がよく部屋で郷土料理を作っているからだという。
「彼の写真を撮ってはいけないんだ。ここに来てたってことが国にバレると殺されるから」と留学生が言った。空港に降り立ったとたん射殺されたケースが何件もあるという。
ソ連は、そう。命をかけても行くべき国だった。そういう存在だったのだ。
ソ連を語ると、どうも最後は老人の繰り言みたいになって、いけない。
※)イヴァシー=ロシア語で「いわし」。語感が酷似していて興味深い。