「幸福な子、と書いて、幸子」
そのころ、サチコは三軒茶屋の、おれは池尻の、木造アパートに住んでいた。
サチコは、離婚するまで旦那といっしょにやっていたバンド活動をやめて、渋谷のライヴハウスでピアノの弾き語りをしていた。
大阪から出てきて、髪の毛をブルーに染めたおれは、沿線のここそこのライヴハウスで、自作詩の朗読を行っていた。
おれたちが、たまたまなにかの縁で、下北沢音楽祭というイベントに出演し、はじめて出会ったときに、おたがいにこころひかれたのは、なにも不思議じゃないことのように思えた。
家が近かったせいもあって、かんたんすぎるくらい、あっけなく、お互いの家を行き来するようになった。
おれたちの部屋には、風呂がなかった。 エアコンもなかった。 夏場はおたがいにつらかった。
けれども、おれたちは、身を寄せ合って生きるほかはないかのように、じっとりと汗をかきながら、肌を重ねていた。
おれたちの身体は、ぎすぎすに痩せすぎていて、抱き合うと、痛いくらい、きしみをあげた。
ある日。
おれが、あまりの暑さに堪えかねて、「エアコン、買っちまおうかな」 とつぶやいたとき、サチコは、ポケットから、小さなスプレイの瓶を出して、おれの鼻先に、シュッとやった。
グレープフルーツの香りがひろがった。
サチコは、「気付け香水ってわけじゃないけど。 ちょっとは涼しくなるでしょう」 と言った。
たしかに、さわやかで、涼やかな香りが、ほんの気持ち暑さを忘れさせてくれるような気がした。
オレンジでは、甘ったるい。 レモンでは、すっぱすぎる。 いろいろ試してみたけれど、グレープフルーツがいちばん、すっきりするのだという。
ふたりで銭湯に行った帰り道、グレープフルーツのコロンをシュッとやってもらって、身もこころも洗われたような気持ちになって、ふっと、空を見上げたら、まん丸の月がそこにあった。
おれは、サチコの手をとって、ぎゅっと握りしめた。 サチコがそれに呼応するかのように、おれの手をぎゅっと握りかえしてくれたとき、おれは、生まれてはじめて、幸福感のようなものに身を貫かれ、その手を、さらに握りかえしても足りないくらい、動揺をかくしきれなかった。
けれど。 サチコは、もう、ここにはいない。
旦那と より を戻したのだ。
アルコール障害の旦那の暴力から逃れるために、死にそうになりながら、やっと別れることができた、と、言っていたのに ... 。
おれには、女のこころが わからない。
なぜ、じぶんを傷つけた男のところへ戻ってしまうのか。
もう、後戻りできないくらい、傷つけられた女は、無意識に、みずからしあわせになろうとすることを拒むのだろうか。
あるいは、人と幸福を分かち合うことに、不安や戸惑いを覚えるのだろうか。
「幸子」 のくせに。 あいつ。 どうして ... ?
たとえ、どんな理由があろうとも、力ずくででも、サチコを守りとおすことのできなかったじぶんの ふがいなさに、かなしいやら、くやしいやら。 涙があふれた。
おれたちは、いったい、なんのために出会ったのだろう?
ときに、運命というやつは、残酷なことをもしてくれるのか。
見上げれば、あのときの同じ、グレープフルーツみたいな月があるのに。
ビル風の吹き荒れる街中をさまよいながら、狂気的な暑さをしのぐために避難した、地下室の喫茶店では、タバコのけむりと空調の匂いが混ざった冷気が漂い、吐きそうなくらい、不快だった。
ウィリアム・サマセット・モームの、岩波文庫版 『月と六ペンス』 を読むおれの となりの席では、女が、一心不乱に、携帯電話でなにか入力をしていた。
氷で薄まった、グレープフルーツ・ジュースを飲みながら。
BGM:
Tom Waits ‘Grapefruit Moon’
そのころ、サチコは三軒茶屋の、おれは池尻の、木造アパートに住んでいた。
サチコは、離婚するまで旦那といっしょにやっていたバンド活動をやめて、渋谷のライヴハウスでピアノの弾き語りをしていた。
大阪から出てきて、髪の毛をブルーに染めたおれは、沿線のここそこのライヴハウスで、自作詩の朗読を行っていた。
おれたちが、たまたまなにかの縁で、下北沢音楽祭というイベントに出演し、はじめて出会ったときに、おたがいにこころひかれたのは、なにも不思議じゃないことのように思えた。
家が近かったせいもあって、かんたんすぎるくらい、あっけなく、お互いの家を行き来するようになった。
おれたちの部屋には、風呂がなかった。 エアコンもなかった。 夏場はおたがいにつらかった。
けれども、おれたちは、身を寄せ合って生きるほかはないかのように、じっとりと汗をかきながら、肌を重ねていた。
おれたちの身体は、ぎすぎすに痩せすぎていて、抱き合うと、痛いくらい、きしみをあげた。
ある日。
おれが、あまりの暑さに堪えかねて、「エアコン、買っちまおうかな」 とつぶやいたとき、サチコは、ポケットから、小さなスプレイの瓶を出して、おれの鼻先に、シュッとやった。
グレープフルーツの香りがひろがった。
サチコは、「気付け香水ってわけじゃないけど。 ちょっとは涼しくなるでしょう」 と言った。
たしかに、さわやかで、涼やかな香りが、ほんの気持ち暑さを忘れさせてくれるような気がした。
オレンジでは、甘ったるい。 レモンでは、すっぱすぎる。 いろいろ試してみたけれど、グレープフルーツがいちばん、すっきりするのだという。
ふたりで銭湯に行った帰り道、グレープフルーツのコロンをシュッとやってもらって、身もこころも洗われたような気持ちになって、ふっと、空を見上げたら、まん丸の月がそこにあった。
おれは、サチコの手をとって、ぎゅっと握りしめた。 サチコがそれに呼応するかのように、おれの手をぎゅっと握りかえしてくれたとき、おれは、生まれてはじめて、幸福感のようなものに身を貫かれ、その手を、さらに握りかえしても足りないくらい、動揺をかくしきれなかった。
けれど。 サチコは、もう、ここにはいない。
旦那と より を戻したのだ。
アルコール障害の旦那の暴力から逃れるために、死にそうになりながら、やっと別れることができた、と、言っていたのに ... 。
おれには、女のこころが わからない。
なぜ、じぶんを傷つけた男のところへ戻ってしまうのか。
もう、後戻りできないくらい、傷つけられた女は、無意識に、みずからしあわせになろうとすることを拒むのだろうか。
あるいは、人と幸福を分かち合うことに、不安や戸惑いを覚えるのだろうか。
「幸子」 のくせに。 あいつ。 どうして ... ?
たとえ、どんな理由があろうとも、力ずくででも、サチコを守りとおすことのできなかったじぶんの ふがいなさに、かなしいやら、くやしいやら。 涙があふれた。
おれたちは、いったい、なんのために出会ったのだろう?
ときに、運命というやつは、残酷なことをもしてくれるのか。
見上げれば、あのときの同じ、グレープフルーツみたいな月があるのに。
ビル風の吹き荒れる街中をさまよいながら、狂気的な暑さをしのぐために避難した、地下室の喫茶店では、タバコのけむりと空調の匂いが混ざった冷気が漂い、吐きそうなくらい、不快だった。
ウィリアム・サマセット・モームの、岩波文庫版 『月と六ペンス』 を読むおれの となりの席では、女が、一心不乱に、携帯電話でなにか入力をしていた。
氷で薄まった、グレープフルーツ・ジュースを飲みながら。
BGM:
Tom Waits ‘Grapefruit Moon’










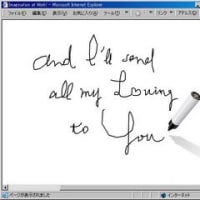



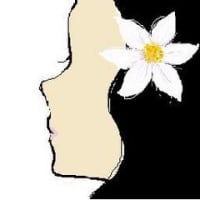










そして、名前に幸せをつけると幸せにはなれないというマーフィーの法則みたいなジンクスもあります。
そしてジョン・グッドマンの苗字は良男・・・
ありがとうございます。
グレープフルーツのように、すっぱく、ちょっぴりほろ苦い思い出を、物語ふうにしてみました。
(わたしは、男ではありませんが ... 。 わたしが、「サチコ」 だったりして ... ゴニョゴニョ ... )
名は体を現さない場合が、ときにありますね。
> そしてジョン・グッドマンの苗字は良男・・・
ゲイリー・オールドマンは、「古男」 ... 。
# ちなみに。 三軒茶屋には、ずばり、『グレープフルーツ・ムーン』というライヴハウスがあります ...
コメントありがとうございます。
いましたね。
ゲイリー・オールドマンの古男
最近会社の近くに出没した模様です。古男が。ハリポタのプロモでしょう・・・
うう~ん、じつは、『シド・アンド・ナンシー』 を観てからのファンだったりして ...
(公開当時に観たわけではないのですが)
8/10あたりに。(モーいいって!)