最新の画像[もっと見る]
-
 第14講(1月8日)講義案
10年前
第14講(1月8日)講義案
10年前
-
 第13講(12月18日)まとめ
10年前
第13講(12月18日)まとめ
10年前
-
 第13講(12月18日)まとめ
10年前
第13講(12月18日)まとめ
10年前
-
 第13講(12月18日)講義案
10年前
第13講(12月18日)講義案
10年前
-
 第13講(12月18日)講義案
10年前
第13講(12月18日)講義案
10年前
-
 第12講(12月11日)まとめ
10年前
第12講(12月11日)まとめ
10年前
-
 第12講(12月11日)まとめ
10年前
第12講(12月11日)まとめ
10年前
-
 第12講(12月11日)講義案
10年前
第12講(12月11日)講義案
10年前
-
 第11講(12月4日)まとめ
10年前
第11講(12月4日)まとめ
10年前
-
 第11講(12月4日)まとめ
10年前
第11講(12月4日)まとめ
10年前
「認知症」カテゴリの最新記事
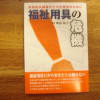 第4092号 東畠弘子『福祉用具の危機』(ワールドプランニング、2010-12)
第4092号 東畠弘子『福祉用具の危機』(ワールドプランニング、2010-12) 第4043号 認知症ケアの地域サービス連携(シンポジウム)
第4043号 認知症ケアの地域サービス連携(シンポジウム)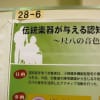 第4027号 認知症に対するさまざまな「療法」の例
第4027号 認知症に対するさまざまな「療法」の例 第3964号 池田 学『認知症/専門医が語る・診断・治療・ケア』(中公新書)
第3964号 池田 学『認知症/専門医が語る・診断・治療・ケア』(中公新書) 第3944号 認知症とバリデーション:テレビ・専門職・ブログ
第3944号 認知症とバリデーション:テレビ・専門職・ブログ 第3917号 「はじめに3歩、別れに7歩」
第3917号 「はじめに3歩、別れに7歩」 第3893号 「認知症の人」といいますが・・gitanist氏の視点
第3893号 「認知症の人」といいますが・・gitanist氏の視点 第3889号 クリステーン・ブライデン(オーストラリア)
第3889号 クリステーン・ブライデン(オーストラリア) 第3874号 アルツハイマーになった東大教授
第3874号 アルツハイマーになった東大教授 第3829号 浜六郎『認知症にさせられる!』(幻冬舎新書)
第3829号 浜六郎『認知症にさせられる!』(幻冬舎新書)
















私が今、つまずいているケースは、「買い物に出かけることが、足を使うことにもなるし、ボケ防止になる」とせっせと、買い物される方・・・。もちろん、お料理もされる(これまたおいしい!)し、編み物は、ゲージもとらずにオリジナルの編みこみセーターが出来上がる(まるでプロなみ!)でも、買い物だけは、コントロールができない。白菜、ニンジン、キャベツ、きゅうり、玉ねぎは、それぞれ、平均20個はあるか・・・豆腐も何丁も・・・。
買い物をやめて!といっても、認知症なのでやめられないし、ましてやご本人の生きがいなので、やめさせたくもない・・・。
では、どうかかわるのか・・・。それが、ケアマネ一人とサービス提供責任者一人の知恵やアイデアでは、限られた支援になってしまう。結果、家族も結局は無理なんですね・・・と諦められてしまう・・・。そうすると、支援者も無力感を覚えてしまうことにも・・・・・。
もし、私でないケアマネさんだったらどういう支援をするのだろう?もちろん包括支援センターにもSOSすることも、ケアマネどうしで話し合うこともできるだろうとも思いますが・・・
見守りやネットワーク機能の充実とともに、具体的な実践例を蓄積して、配信するような、そして、できれば、電話相談だけではなく、一緒に訪問するなどして対応してくださる(←県内に1か所や市内に1か所では対応しきれない)公的な機関(←金銭の発生がない)があったらいいな・・・と思っているのは、私だけでしょうか?
本当に自分のブログを持てば?というコメントで、すみません・・・
コメントありがとうございます。
認知症の一番の問題は
社会全体が知らないことですね
あたまから講義しても始まらないので
例に挙げられてような事例をたくさんわかりやすく伝えることですね。
少しずつ、その機会は増えてはきたと思います。
*第1740号の厚生労働省の会議資料。
私自身は、政策系の専門でほんとに苦手です。