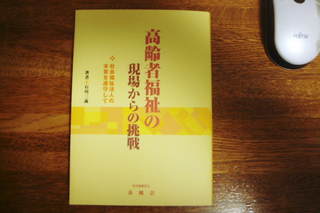
【老人福祉課長】
今夜の修士課程の「高齢者福祉学」の講義では、私が昭和58年から1年間厚生省老人福祉課長(当時の名称)だったときの話をしようと考えています。→第2842号。
昨日は、『介護の倫理』(第2844号)を読んでいて、さきほどまでその記事を書いていましたので、あまり時間の余裕がないのですが、今夜の講義ともつながると思い、ともかく本の紹介をします。
【民間主導で発展してきた日本の高齢者福祉】
藤本一司氏の『介護の倫理』では、介護保険によって多くの人の助力を得て、お母様の介護をしていること、多くの介護専門職の名前がでていました。
介護保険施行10年たって、さまざまな課題が噴出していますが、この制度自体の意義は減じていないと思います。
介護保険の一番の問題は、「措置から契約へ」という厚生労働省のスローガンの問題点を指摘できなかった政治家や研究者達の怠慢もあって、「介護保険に加入できない人達」(介護保険料を支払えない)を公的な責任でしっかりケアするという基本線が揺らいでしまったことです。
介護保険施行以前の時代、特別養護老人ホームとして社会福祉法人が経営してきた各地域の実践家たちは、いまどのように介護保険を受けとめているのだろうか?
【石川三義のこと】
私は、昭和58年夏から59年夏までの1年間、老人福祉課長をやった関係で、全国の先覚者的な方たちから多くを教わりました。
沼津市の故石川春男氏は、当時の理事長・施設長でした。
沼津市の「あしたかホーム」を勉強のため訪問したとき、冒頭、「わしらのようなもんのやっておることを聞いて何か役に立つことがあるのかのぅ」といって挨拶された父君の顔をいまでも覚えています。
石川三義さんは、現在は、理事長をされていますが、当時は、次長ということでお父さんを助けられながら、施設の方向づけをやっておられた。社会思想史が専門で翻訳などもあるということで、注目すべき論文などがあります。
社会福祉法人 春風会
【11の論文・座談会記録】
今回、自費出版としてまとめられた本:、
『高齢者福祉の現場からの挑戦/社会福祉法人の本質を遵守して』(2009.3.31刊。180ページ)には、石川三義氏が書いた論文や参加された座談会などが再録されています。
○ 座談会 「厚生白書」の「社会サービス」概念をめぐる座談会。私が司会しています。後に厚生労働次官となった辻哲夫さんがまだ室長でした。(第6章)
○ スウェーデンの視察旅行に一緒に行きました。(第5章第1節)
○ 「あしたかホーム」は、静岡県内の特別養護老人ホームの寮母が痴呆症について実地に学ぶ研修施設でした。参加した寮母の事例集が収められています。(第3章)
○ 音楽療法の効果に関する論文(第2章第3節)・・当時は、知りませんでした。(今は、ブックマーク「音縁」を通してその意義を学んでいます)
*厚生省(当時)の介護対策検討会(1989年。事務次官の諮問機関)の委員
介護対策検討会委員 (平成元年版『厚生白書』第2編第3部から)
今夜の修士課程の「高齢者福祉学」の講義では、私が昭和58年から1年間厚生省老人福祉課長(当時の名称)だったときの話をしようと考えています。→第2842号。
昨日は、『介護の倫理』(第2844号)を読んでいて、さきほどまでその記事を書いていましたので、あまり時間の余裕がないのですが、今夜の講義ともつながると思い、ともかく本の紹介をします。
【民間主導で発展してきた日本の高齢者福祉】
藤本一司氏の『介護の倫理』では、介護保険によって多くの人の助力を得て、お母様の介護をしていること、多くの介護専門職の名前がでていました。
介護保険施行10年たって、さまざまな課題が噴出していますが、この制度自体の意義は減じていないと思います。
介護保険の一番の問題は、「措置から契約へ」という厚生労働省のスローガンの問題点を指摘できなかった政治家や研究者達の怠慢もあって、「介護保険に加入できない人達」(介護保険料を支払えない)を公的な責任でしっかりケアするという基本線が揺らいでしまったことです。
介護保険施行以前の時代、特別養護老人ホームとして社会福祉法人が経営してきた各地域の実践家たちは、いまどのように介護保険を受けとめているのだろうか?
【石川三義のこと】
私は、昭和58年夏から59年夏までの1年間、老人福祉課長をやった関係で、全国の先覚者的な方たちから多くを教わりました。
沼津市の故石川春男氏は、当時の理事長・施設長でした。
沼津市の「あしたかホーム」を勉強のため訪問したとき、冒頭、「わしらのようなもんのやっておることを聞いて何か役に立つことがあるのかのぅ」といって挨拶された父君の顔をいまでも覚えています。
石川三義さんは、現在は、理事長をされていますが、当時は、次長ということでお父さんを助けられながら、施設の方向づけをやっておられた。社会思想史が専門で翻訳などもあるということで、注目すべき論文などがあります。
社会福祉法人 春風会
【11の論文・座談会記録】
今回、自費出版としてまとめられた本:、
『高齢者福祉の現場からの挑戦/社会福祉法人の本質を遵守して』(2009.3.31刊。180ページ)には、石川三義氏が書いた論文や参加された座談会などが再録されています。
○ 座談会 「厚生白書」の「社会サービス」概念をめぐる座談会。私が司会しています。後に厚生労働次官となった辻哲夫さんがまだ室長でした。(第6章)
○ スウェーデンの視察旅行に一緒に行きました。(第5章第1節)
○ 「あしたかホーム」は、静岡県内の特別養護老人ホームの寮母が痴呆症について実地に学ぶ研修施設でした。参加した寮母の事例集が収められています。(第3章)
○ 音楽療法の効果に関する論文(第2章第3節)・・当時は、知りませんでした。(今は、ブックマーク「音縁」を通してその意義を学んでいます)
*厚生省(当時)の介護対策検討会(1989年。事務次官の諮問機関)の委員
介護対策検討会委員 (平成元年版『厚生白書』第2編第3部から)


























音楽療法の効果を、特養の理事の方がどのように捉え、書いてらっしゃるのか、興味が湧きます。
コメントありがとうございます。
私自身は、自分の書いたものをまとめていないので、かえって他の人の本にでたものがまとめられて嬉しいですね。
もっとも、この本は非売品なので
該当部分のコピーを送ります。