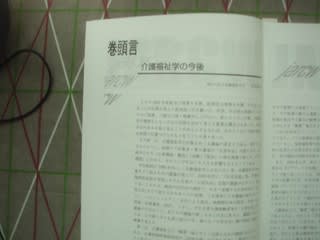
介護福祉に関する学会である日本介護福祉学会の学会誌『介護福祉学』第16巻第2号(2009.10)の巻頭言は、太田貞司先生(神奈川県立保健福祉大学)による「介護福祉学の今後」です。(写真)
6年間、この学会の「総務担当理事」をされて、今度交代されたということで、これまでのこの学会の回顧と展望をされています。
この雑誌が到着してから、そのまま「未読」の棚に置いていました。
A先生の年賀状での添え書きがなければそのままだった可能性が強いです。
*昔のことですが、
私も日本介護福祉学会の研究担当理事として、太田先生とご一緒だったことがあります。
さて、その内容:
介護(の専門職)をめぐる動向には、次の2つがあり、せめぎあっている。
・医療と介護が医療の方に統合されていく
・新しい「日常生活」支援の職業が登場する
太田先生のエッセイは、ここまでで、先生は結論をだしておられません。
ですが、
行間に注意深くしのばせてある先生のお考えは、後者の方へと踏み出しておられるのでは?
と、私には思えました。
・フィンランドで1992年から生まれた「ラヒホイタヤ」という統合的な職種に注目。
・韓国の今後の動向に注目
と言及されている点が印象に残りました。
太田先生の講演のパワーポイントをネットで見つけました。
→坂之上介護福祉研究会 P3239
6年間、この学会の「総務担当理事」をされて、今度交代されたということで、これまでのこの学会の回顧と展望をされています。
この雑誌が到着してから、そのまま「未読」の棚に置いていました。
A先生の年賀状での添え書きがなければそのままだった可能性が強いです。
*昔のことですが、
私も日本介護福祉学会の研究担当理事として、太田先生とご一緒だったことがあります。
さて、その内容:
介護(の専門職)をめぐる動向には、次の2つがあり、せめぎあっている。
・医療と介護が医療の方に統合されていく
・新しい「日常生活」支援の職業が登場する
太田先生のエッセイは、ここまでで、先生は結論をだしておられません。
ですが、
行間に注意深くしのばせてある先生のお考えは、後者の方へと踏み出しておられるのでは?
と、私には思えました。
・フィンランドで1992年から生まれた「ラヒホイタヤ」という統合的な職種に注目。
・韓国の今後の動向に注目
と言及されている点が印象に残りました。
太田先生の講演のパワーポイントをネットで見つけました。
→坂之上介護福祉研究会 P3239


























学問ですね。
・介護学
・(社会)福祉学
どちらをディサプリンにしているのか、良く整理できません。小生の見解は、介護学は、おそらく看護学と同じような方向に向かうと考えています。医療と介護は、切っても切り離せないはずです。何故なら、医療的なトラブルが原因で生じた急性期の生活障害が、慢性期に入って傷害は固定化はするけれども、依然として投薬等を肇とした治療は続くからです。
実務の世界では、知り合いのヘルパーステーションの社長さんは、昨日、こんなことを話していました。「これからは医療がわかり、看護職と医療職と連携ができないヘルパーステーション生き残れない。」「今受けているヘルパーステーションサービス提供責任者関連研修は、難病関連の講義を中心に受けている。これからは医療・リハビリに特化できない事業所はつぶれるだろうから、ホームヘルパーさんにも医療・リハビリ関連の研修を続けないと、生き残れない」と。
小生も居宅介護支援事業所に勤めていたとき、こんなことがありました。
訪問しているヘルパーさんから、嘔吐を繰り返しているをしているご利用者がいると、サービス提供責任者を通じてSOSがはいりました。在総診をしている主治医の先生にすぐに携帯で電話し、状況を話したとき、「バイタルはどうなっている?」と聞かれ、「ヘルパーさんは(体温計や血圧計を)お持ちじゃないからBPはおろかKTもわからないそうです」と報告しました。先生は、「ヘルパーさんもそういうのを持っていざというときに対応できないと…」と言いつつ、すぐに駆けつけてくださいました。
介護福祉学の行方は、介護学を中心に、看護学や医学・リハビリ関連学とも密接な関わりを持ちながら発展するような気がします。
コメントありがとうございました。
現場におられ、そしてソーシャルワークについての造詣も深いさはらさんのご意見を読んで
太田先生が明確に結論を書かれなかったわけがわかりました。
さはらさんのご指摘のように進むとすれば
私などの「介護福祉研究会」の意味もあまりなさそうで多いに考えさせられますね。
どうも私は個人的・地域的な偏りの中で
介護の中の福祉的側面を評価しすぎてきたのか
(残念ながらソーシャルワークにはあまり親和的ではないです)・・
話は、1960年、私が某公立大学医学部に合格しながら進学せず、当時の国立大学法学部に進んだことや
1966年ごろ、診療報酬を決めるセクションで医師のマイナス面をうんと見てしまったことなどに広がるので、他日を期します。
「統合化」というラインでは多くの方が賛同されると思いますが、統合化の中の綱引きのような私が苦手とする話に近づきそう・・
介護の「福祉的」なお話しについてはよくわかりませんが、大事なお話であることは間違いありません。技術的なものはノウ・ハウになりますが、哲学がないノウ・ハウほど危険なものはありません。科学で言うところの科学哲学が必要になるはずだと思います。
ソーシャルワーク分野でも、イギリスの動向をみると、「Social care Worker」となっており、イギリスと同じ道を進むとすれば、ソーシャルワークとて、先生がご指摘の介護福祉学と同じ道を辿ることになるでしょう。
しかしながら、介護の場合、何らかの障害が生じ、それが固定化したところで、不可欠な問題解決手段であるという独自性を持っています。この中で福祉的な側面は、障害学、心理学、哲学、社会学等の手法によって、介護をめぐる葛藤、価値、あり方、方向性等が議論されるような気がします。
よくわからないことを申し上げ、お許しくださいませ。