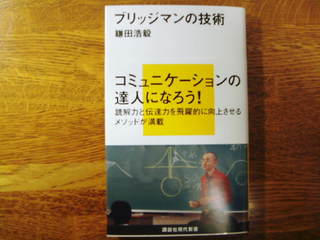
鎌田浩毅『ブリッジマンの技術』(講談社現代新書)を読みました。
*第1刷 2008.12.20
著者は、京都大学大学院の教授で、専門分野は火山学という。1955年生まれ。
専門の火山学の知識を講義したり、講演したりする経験から、「知識をどのように伝えることがいいか」→「聞き手の関心にあわせる話し方」を工夫するようになったとのことです。
「ブリッジマン」とは異分野の間で、専門家と一般の人の間を橋渡しする仕事をする人、という意味です。
私自身
若い頃、20年近くを公務員として
40過ぎから25年間、教員として
「人にものを伝える」難しさを痛感してきました。
4月からの学部1年生への講義は、もう残り2009年度1期分か、多くて2010年度を含む2期分です(定年のため)。実質的には「最後の授業」というわけで、本書のようなテーマの本を読むわけです。
この本で提案されている方法は、ほとんどは常識的によく言われていることですが、いずれも著者自身の体験(ときに失敗)を踏まえていること、心理学のコミュニケーションの理論を援用していることに特色があります。
「フレームワークの橋渡し」がキーワードです。
私が、自分の授業をするにあたって、参考にしたいと思った箇所から。
○ DJのような授業。質問をとり、それに答えていく。pp.54-55
○ ゲストを招いての授業 p.79
勉強の方法として面白いと思ったのは、「棚上げ法」p.178
・・難しくて頓挫したら、そこを「棚上げする」。30分やってだめなものは10時間やってもだめ、と。このアイデアは重要ですね。
学部1年生への講義は、知識そのものではなく、知識を得る方法、評価の方法などを体験的に教えたいし、この本の流儀でいえば、まず学生の考えというか生活をよく知ることから始まりますね。
*最近、「りちゃーど」という学生のホームページを読んでいます、18歳/19歳の生活を垣間見て大変面白いし、元気が出ます。4月からの講義に活かしたいです。
→このブログ第2138号(2009.01.22)への学生のコメント(1/23)参照。
*第1刷 2008.12.20
著者は、京都大学大学院の教授で、専門分野は火山学という。1955年生まれ。
専門の火山学の知識を講義したり、講演したりする経験から、「知識をどのように伝えることがいいか」→「聞き手の関心にあわせる話し方」を工夫するようになったとのことです。
「ブリッジマン」とは異分野の間で、専門家と一般の人の間を橋渡しする仕事をする人、という意味です。
私自身
若い頃、20年近くを公務員として
40過ぎから25年間、教員として
「人にものを伝える」難しさを痛感してきました。
4月からの学部1年生への講義は、もう残り2009年度1期分か、多くて2010年度を含む2期分です(定年のため)。実質的には「最後の授業」というわけで、本書のようなテーマの本を読むわけです。
この本で提案されている方法は、ほとんどは常識的によく言われていることですが、いずれも著者自身の体験(ときに失敗)を踏まえていること、心理学のコミュニケーションの理論を援用していることに特色があります。
「フレームワークの橋渡し」がキーワードです。
私が、自分の授業をするにあたって、参考にしたいと思った箇所から。
○ DJのような授業。質問をとり、それに答えていく。pp.54-55
○ ゲストを招いての授業 p.79
勉強の方法として面白いと思ったのは、「棚上げ法」p.178
・・難しくて頓挫したら、そこを「棚上げする」。30分やってだめなものは10時間やってもだめ、と。このアイデアは重要ですね。
学部1年生への講義は、知識そのものではなく、知識を得る方法、評価の方法などを体験的に教えたいし、この本の流儀でいえば、まず学生の考えというか生活をよく知ることから始まりますね。
*最近、「りちゃーど」という学生のホームページを読んでいます、18歳/19歳の生活を垣間見て大変面白いし、元気が出ます。4月からの講義に活かしたいです。
→このブログ第2138号(2009.01.22)への学生のコメント(1/23)参照。

























