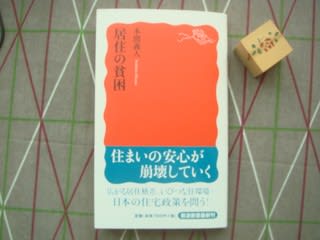
居住の貧困 が刊行されました。
【要点】
住宅政策が社会福祉政策や社会保障政策、労働政策と一緒に「社会政策」として考えられなくてはならない
という主張を随所でしています。
p.12 p.89 pp.193-4 p.216 など
・中央官庁の編成
・研究者の自戒(縦割り)
・西山卯三(京都大学)の役割を評価
【特色】
日本の現状のほか
海外の事情を詳しくルポしています。(韓国やフランスも含めています)
「住宅政策先進国」ともいうべきスウェーデンやイギリスの政策動向を含む。
巻末の文献と法制一覧が参考になります。
【松戸市常盤平団地】
著者が住んでいたという。最近は、高齢者の孤独死とその対応で評判になった。
p.34, p.52
*私も、大学3年の頃、両親が(富山県から)この団地の一角に越してきたので懐かしいです。
【早川和男先生】
昔、伊部英男先生の研究会で、当時神戸大学におられた早川和男先生のお話を聞く機会がありました。
→岩波新書『住宅貧乏物語』があります。
世界の社会政策 ミネルバ書房 1992年
では、本間先生の主張を「早川委員会」ですでに提言しています。
(この本は、絶版ですが、早川委員会の幹事・雑用は私がやりました)
第3200号 2009.09.25 でも触れましたね。
【ソーシャルワークからの視点】
本間義人のこの本に関する書評や感想を書いたブログはいまのところ少ないようです。
→先に紹介した宮本太郎著の場合との違い。(日本のインテリは肩書きや評判に弱い!?)
検索エンジンで探していたら、
次の論文を見つけました。19ページダウンロードできましたのでリンクします。
成清敦子 同志社大学大学院博士課程
「ソーシャルワークはいかに住宅問題を解決しうるか
-ソーシャルワークと社会問題-」
*本間先生の著書も文献にあげられています。
【要点】
住宅政策が社会福祉政策や社会保障政策、労働政策と一緒に「社会政策」として考えられなくてはならない
という主張を随所でしています。
p.12 p.89 pp.193-4 p.216 など
・中央官庁の編成
・研究者の自戒(縦割り)
・西山卯三(京都大学)の役割を評価
【特色】
日本の現状のほか
海外の事情を詳しくルポしています。(韓国やフランスも含めています)
「住宅政策先進国」ともいうべきスウェーデンやイギリスの政策動向を含む。
巻末の文献と法制一覧が参考になります。
【松戸市常盤平団地】
著者が住んでいたという。最近は、高齢者の孤独死とその対応で評判になった。
p.34, p.52
*私も、大学3年の頃、両親が(富山県から)この団地の一角に越してきたので懐かしいです。
【早川和男先生】
昔、伊部英男先生の研究会で、当時神戸大学におられた早川和男先生のお話を聞く機会がありました。
→岩波新書『住宅貧乏物語』があります。
世界の社会政策 ミネルバ書房 1992年
では、本間先生の主張を「早川委員会」ですでに提言しています。
(この本は、絶版ですが、早川委員会の幹事・雑用は私がやりました)
第3200号 2009.09.25 でも触れましたね。
【ソーシャルワークからの視点】
本間義人のこの本に関する書評や感想を書いたブログはいまのところ少ないようです。
→先に紹介した宮本太郎著の場合との違い。(日本のインテリは肩書きや評判に弱い!?)
検索エンジンで探していたら、
次の論文を見つけました。19ページダウンロードできましたのでリンクします。
成清敦子 同志社大学大学院博士課程
「ソーシャルワークはいかに住宅問題を解決しうるか
-ソーシャルワークと社会問題-」
*本間先生の著書も文献にあげられています。


























そもそも「住む」ということは,「当たり前」「当然」という発想だろうと思います。しかし昨年末の「年越し派遣村」等を見てのとおり,「住む」ことが当たり前ではなくなっています。また「福祉的視点」で見ても,児童養護施設の劣悪な環境や,高齢者の「行き場所」のこと等,考えていかなければならないことはたくさんあると思います。
「住む」ということは「衣食」とあわせて生活の基本です。それすらが足りていない現状を放置したまま,経済的成長を目指そうとするのは,そもそも無理でしょう。
政策においても,「住む」ということを役所横断で取り組んでほしいものです。
早々のコメント
ありがとうございます。
日本社会事業大学では
介護コースを作ったときに
住居学の先生を採ったのですが(児玉先生)
その後の経過をみても
重要な人事でした。
今だからいえますが
教授会の空気は当初反対だったのです。
頭が固いと思いましたね。
私は、住宅部門の重要性に関して
教授会で発言しましたが・・
ゼミ生で
他の大学の大学院で住宅問題を専攻した人がでました。(大塚順子さん。博士号を取った)
本間先生も指摘していますが
役所の縦割りの前に
研究者の思考やスタンスが重要ですね。
これから
ごみだしと新聞とりにいきます。
R.ティトマスは、ソーシャルポリシーの
どの範囲を教えたらよいのか?という
ある若手の教員から問いに対して、「
ソーシャルポリシーのある一部分だけ
を教えることはできない。全部だ」と返
され、驚いたという件につき、星野信也
先生はある書評の中で記されています。
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/544/544-05.pdf
このような視点に立てば、日本のソーシャ
ルポリシー(社会政策)が、かつては労
働政策と解釈され、社会福祉系の学会
でも未だに「普遍主義」と「選別主義」と
いうテーマが演題として上がるのをみて、
ため息をつきたくなります(詳しくは、上
記の星野先生の書評を見れば、一目瞭
然です)。
しかしながら、住宅問題を解決したところ
で、日本の施設偏重主義を.見直すまで
には至らないと思います。せっかくバリア・
フリーにした住宅にいても、「いつも見てい
る人がいないから何かあったら困るという
家族・親族の意向で施設に入れられる実
情を、たくさん見ているからです。
そもそも、住宅改修ででるちょっぴりの金
額は、日本の介護問題を解決するにはほ
ど遠いですし、そもそも、家を建てるとき、
自身の老いを想像できないのですから。
本気で居住福祉、在宅ケアを考えている
なら、北欧諸国の例でも明らかなようにとっ
くに施設を解体しているでしょう。
せっかく早川先生や児玉先生のようなす
ばらしい研究者がいらっしゃるのに、その
業績をソーシャルワーカー側からソフト作り
で支援するシステムが構築されていない
ようですね。
ますます少子高齢化と、単身家族、子の
ない家庭が増える中で、あえて在宅のケ
アを選ぶようにするには、区分支給限度額
のようなつまらない発想はそぐわないよう
な気がします。
大幅に改善されたことは、大変よかっ
た点でしょう。ユニット型施設等。
しかし、生活保護受給者や低所得者
等を排除している所を見ると、まだま
だ住宅に関する意識改革は、道半ば
と感じます。
適切なコメントいただきました。
「社会局」「社会福祉」へと狭く入っていく発想ではいけませんね。
私の場合、40代で伊部先生の教えを受ける機会があったことが幸いでした。
星野信也先生のHPを
「坂之上介護福祉研究会」カテゴリ204
P 0317 でリンクしています。
今日のおうぎやさんから教わった書評を
上記拙ブログのP2572
に加えました。
*後日、「社会政策」で簡単に読めるように・・