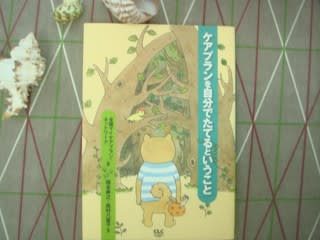
【ケアプランを自分で立てる】
勤務する大学の図書館で、
橋本典之・島村八重子『ケアプランを自分で立てる』(CLC,2010)を借りました。(写真は、その表紙)
そのポイントは、
「介護保険の給付を受ける際に策定するケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)に策定してもらうのが普通ですが、被保険者が希望すれば自分自身でケアプランを策定することができる」
よいうことです。
以下は、出版社CLCのサイトから:
「介護を受けていても人生の主役は自分!
「介護」のマイナスイメージを払拭する取り組みが始まっています。ケアプランを自分で作成するということ。
本書は、マイケアプランとは何かを紹介するとともに、事例や、介護をプラスに転じるヒントをギュッと集めました。
――ケアプランを自己作成した人が、口を揃えて言うことがあります。「介護をしたことが、自分のこれからの人生の大きな糧となった」また、自分で自分のケアプランをたてながら暮らす人は、「介護を受けていても人生の主役は自分」と胸を張ります。そしてさらに続けて、「自己作成を通して、自己作成をすることのたいへんさ以上に、大切なことに気づいた」。それを私たちはマイケアプランと呼んでいます。
――本書「はじめに」より
<<主要目次>>
■はじめに
■旅立ちの前に
■“私”一人め 高木洋子さんを訪ねて
コラム1 自己作成の担当件数は一件デス
■“親子”二人め 中村達雄さんを訪ねて
コラム2 素人による素人のためのケアプラン
■“価値観”三人め 平岩千代子さんを訪ねて
コラム3 「どちらか一方」ではない
■“専門性”四人め 山田圭子さんを訪ねて
コラム4 「うちは自己作成しかなかったと思う」
■“個別性”五人め 國光登志子さんを訪ねて
コラム5 順番が逆?
■“つながり”六人め 島村八重子さんを訪ねて
コラム6 人財産のはなし
■旅を終えて
■全国マイケアプラン・ネットワークの変遷
■おわりに 」
この本には、ケアプランを自分で作成した6つの事例について報告されています。
昨日、鹿児島県の南部地域にあるA地域包括センターを研究調査のために訪問しましたが、そこで介護支援専門員さんから、「そのような方法は確かにあるし、意味のあることだ。この地方ではまだ実際に行った例はないようだ」と、教わりました。
実際に、自分でケアプランを作成しない場合でも、ケアマネジャーに頼らないでサービス計画を作成する気持ちで手続きを知ることは介護保険を活用する場合に参考になることは確かですね。
【法的な根拠】
「ケアプランを(ケアマネジャーに頼まないで)被保険者本人が作成できる」とは、どのような法律上の根拠によっているのでしょうか?
介護保険法のサービスを受ける場合に重要な点は、
① 介護認定を受けること
② ケアプランを立てること
の2つです。
いま調べているのは、このうち②の点ですね。
介護保険法による給付の支払いは、「金銭給付の支払い」を建前とする方法を原則とすることが定められています。これを、実際上、一部負担を支払うだけで、保険者が事業者に支払えるようにすることを「金銭給付の現物給付化」といいます。法律上の性格は、健康保険法の「療養費」の現物給付扱いと同様です。
そこで、具体的に条文をあげておきます。
しっかり知っておきたいという人は是非読んでみてください。
・ 介護保険法第46条第1項は、「居宅介護サービス計画費」の本則です。
・ 第46条第4項が、代理受領の根拠条文で、「厚生労働省令で定めるところにより」代理受領ができるとしています。
・ その「厚生労働省令で定めるところ」とは、具体的には、介護保険法施行規則第64条第1項第1号ニの規定です。
・ つまり、受けようとするサービスを含む利用計画をあらかじめ市町村に届けていればいいわけです。
介護保険法
(居宅介護サービス計画費の支給)
第四十六条 市町村は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。
介護保険法施行規則
(居宅介護サービス費の代理受領の要件)
第六十四条 法第四十一条第六項 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項 の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号 に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第七十四条第一項 の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。
ニ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
【詳しいことは】
法律上は、自分の介護サービス計画が自分で作成できるように定めていることがわかりました。まだ、市町村の窓口では、この場合の具体的な手続きについては承知していない場合が多いようですが、「自分のケアプランは自分で作ろう」というネット上のサイトも複数あります。計画書のダウンロードができるサイトもあります。
全国マイケアプラン・ネットワーク この本の編者。
京都発 マイプラン研究会
《3120字》
勤務する大学の図書館で、
橋本典之・島村八重子『ケアプランを自分で立てる』(CLC,2010)を借りました。(写真は、その表紙)
そのポイントは、
「介護保険の給付を受ける際に策定するケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)に策定してもらうのが普通ですが、被保険者が希望すれば自分自身でケアプランを策定することができる」
よいうことです。
以下は、出版社CLCのサイトから:
「介護を受けていても人生の主役は自分!
「介護」のマイナスイメージを払拭する取り組みが始まっています。ケアプランを自分で作成するということ。
本書は、マイケアプランとは何かを紹介するとともに、事例や、介護をプラスに転じるヒントをギュッと集めました。
――ケアプランを自己作成した人が、口を揃えて言うことがあります。「介護をしたことが、自分のこれからの人生の大きな糧となった」また、自分で自分のケアプランをたてながら暮らす人は、「介護を受けていても人生の主役は自分」と胸を張ります。そしてさらに続けて、「自己作成を通して、自己作成をすることのたいへんさ以上に、大切なことに気づいた」。それを私たちはマイケアプランと呼んでいます。
――本書「はじめに」より
<<主要目次>>
■はじめに
■旅立ちの前に
■“私”一人め 高木洋子さんを訪ねて
コラム1 自己作成の担当件数は一件デス
■“親子”二人め 中村達雄さんを訪ねて
コラム2 素人による素人のためのケアプラン
■“価値観”三人め 平岩千代子さんを訪ねて
コラム3 「どちらか一方」ではない
■“専門性”四人め 山田圭子さんを訪ねて
コラム4 「うちは自己作成しかなかったと思う」
■“個別性”五人め 國光登志子さんを訪ねて
コラム5 順番が逆?
■“つながり”六人め 島村八重子さんを訪ねて
コラム6 人財産のはなし
■旅を終えて
■全国マイケアプラン・ネットワークの変遷
■おわりに 」
この本には、ケアプランを自分で作成した6つの事例について報告されています。
昨日、鹿児島県の南部地域にあるA地域包括センターを研究調査のために訪問しましたが、そこで介護支援専門員さんから、「そのような方法は確かにあるし、意味のあることだ。この地方ではまだ実際に行った例はないようだ」と、教わりました。
実際に、自分でケアプランを作成しない場合でも、ケアマネジャーに頼らないでサービス計画を作成する気持ちで手続きを知ることは介護保険を活用する場合に参考になることは確かですね。
【法的な根拠】
「ケアプランを(ケアマネジャーに頼まないで)被保険者本人が作成できる」とは、どのような法律上の根拠によっているのでしょうか?
介護保険法のサービスを受ける場合に重要な点は、
① 介護認定を受けること
② ケアプランを立てること
の2つです。
いま調べているのは、このうち②の点ですね。
介護保険法による給付の支払いは、「金銭給付の支払い」を建前とする方法を原則とすることが定められています。これを、実際上、一部負担を支払うだけで、保険者が事業者に支払えるようにすることを「金銭給付の現物給付化」といいます。法律上の性格は、健康保険法の「療養費」の現物給付扱いと同様です。
そこで、具体的に条文をあげておきます。
しっかり知っておきたいという人は是非読んでみてください。
・ 介護保険法第46条第1項は、「居宅介護サービス計画費」の本則です。
・ 第46条第4項が、代理受領の根拠条文で、「厚生労働省令で定めるところにより」代理受領ができるとしています。
・ その「厚生労働省令で定めるところ」とは、具体的には、介護保険法施行規則第64条第1項第1号ニの規定です。
・ つまり、受けようとするサービスを含む利用計画をあらかじめ市町村に届けていればいいわけです。
介護保険法
(居宅介護サービス計画費の支給)
第四十六条 市町村は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。
介護保険法施行規則
(居宅介護サービス費の代理受領の要件)
第六十四条 法第四十一条第六項 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項 の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号 に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第七十四条第一項 の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。
ニ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
【詳しいことは】
法律上は、自分の介護サービス計画が自分で作成できるように定めていることがわかりました。まだ、市町村の窓口では、この場合の具体的な手続きについては承知していない場合が多いようですが、「自分のケアプランは自分で作ろう」というネット上のサイトも複数あります。計画書のダウンロードができるサイトもあります。
全国マイケアプラン・ネットワーク この本の編者。
京都発 マイプラン研究会
《3120字》

























