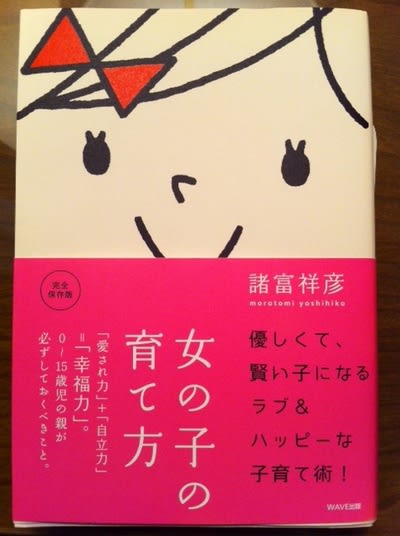今回の米国出張で、ワシントンDCからオースティンに5時間ほど立ち寄りお客と打合せ、またLAに移動したが、オースティン空港でLA行きのフライトを待っていた際に、オバマ大統領を乗せた米国政府の大統領専用機、『エアフォースワン』がオースティン空港にやってきたのだ。我々のオースティン到着から遅れること3時間、同じワシントンDCからの到着である。


オースティン空港ではオバマ大統領到着にあわせて、全ての飛行機の離着陸がホールドとなり、空港の人々はターミナルから滑走路を眺め、みんなエアフォースワンの到着を心待ちにして大いに盛り上がった。
やがてアナウンスが流れ、空からジャンボジェットのエアフォースワンが着陸。みんなカメラでエアフォースワンを追い、写真を取り巻くっていた。

遠くてはっきりは見えなかったものの、滑走路上でエアフォースワンからオバマ大統領が降り立ち、待っていた政府車両に乗り換え、空港を後にしたのだが、何とパトカーに先導され、約10台の大型SUVが等間隔に列を作って移動していったが、さすがの厳戒態勢であった。特に、ビンラディン殺害直後、報復テロを警戒する緊迫した状況の中でもあり、オバマ大統領の行動は特に注目を集めている。

この時は何の目的でオバマ大統領がオースティンを訪れたのかわからなかったが、その後ニュースを調べたところ、2012年に行われる大統領選挙に再選する為、オースティンでの選挙資金集めキャンペーンの為に訪れていたようだが、もう選挙戦は着々と始まっているのである。

それにしても、今回の出張で、『生エアフォースワン』をオースティンで見ることが出来たことはかなりラッキーであった。


オースティン空港ではオバマ大統領到着にあわせて、全ての飛行機の離着陸がホールドとなり、空港の人々はターミナルから滑走路を眺め、みんなエアフォースワンの到着を心待ちにして大いに盛り上がった。
やがてアナウンスが流れ、空からジャンボジェットのエアフォースワンが着陸。みんなカメラでエアフォースワンを追い、写真を取り巻くっていた。

遠くてはっきりは見えなかったものの、滑走路上でエアフォースワンからオバマ大統領が降り立ち、待っていた政府車両に乗り換え、空港を後にしたのだが、何とパトカーに先導され、約10台の大型SUVが等間隔に列を作って移動していったが、さすがの厳戒態勢であった。特に、ビンラディン殺害直後、報復テロを警戒する緊迫した状況の中でもあり、オバマ大統領の行動は特に注目を集めている。

この時は何の目的でオバマ大統領がオースティンを訪れたのかわからなかったが、その後ニュースを調べたところ、2012年に行われる大統領選挙に再選する為、オースティンでの選挙資金集めキャンペーンの為に訪れていたようだが、もう選挙戦は着々と始まっているのである。

それにしても、今回の出張で、『生エアフォースワン』をオースティンで見ることが出来たことはかなりラッキーであった。