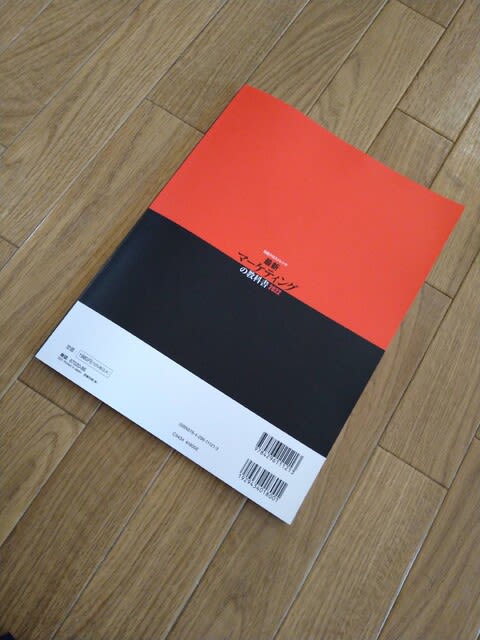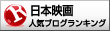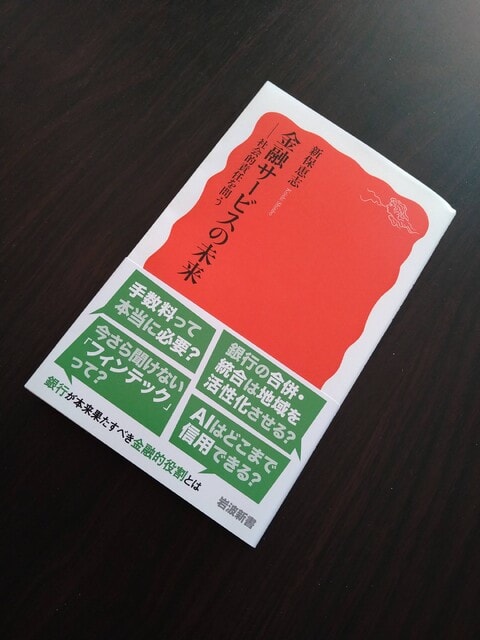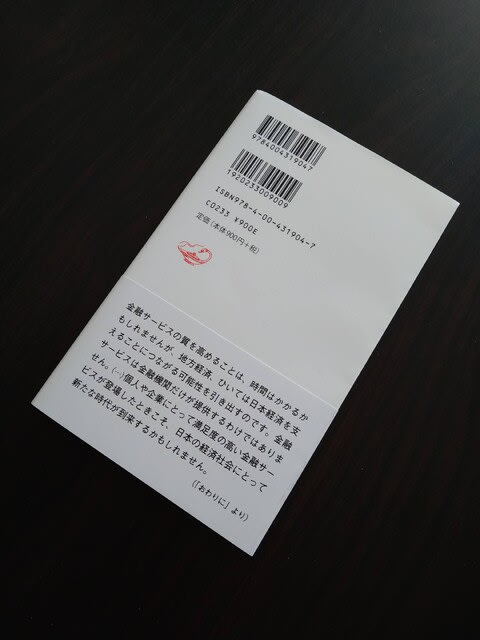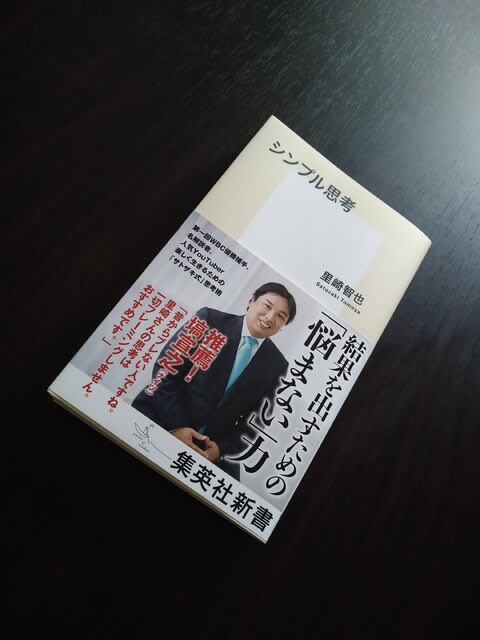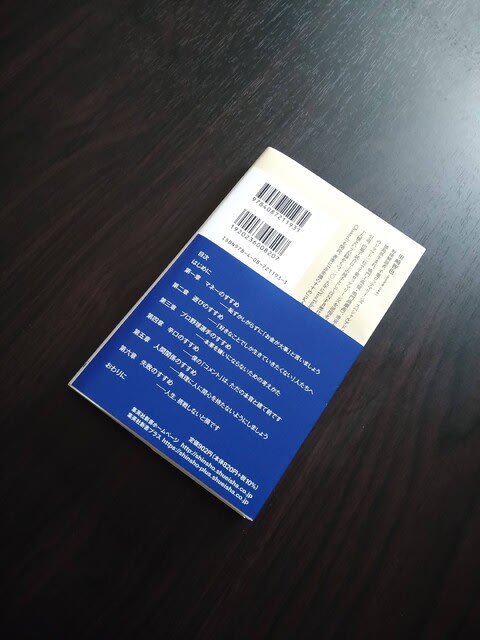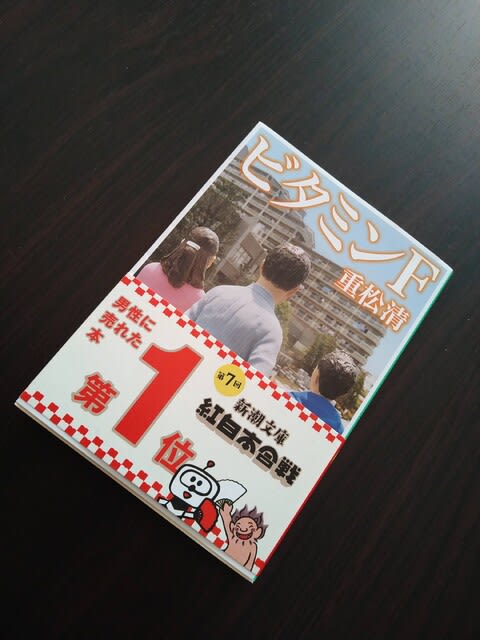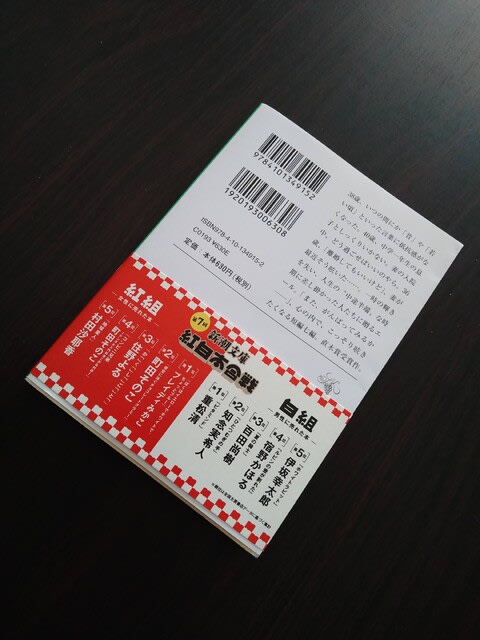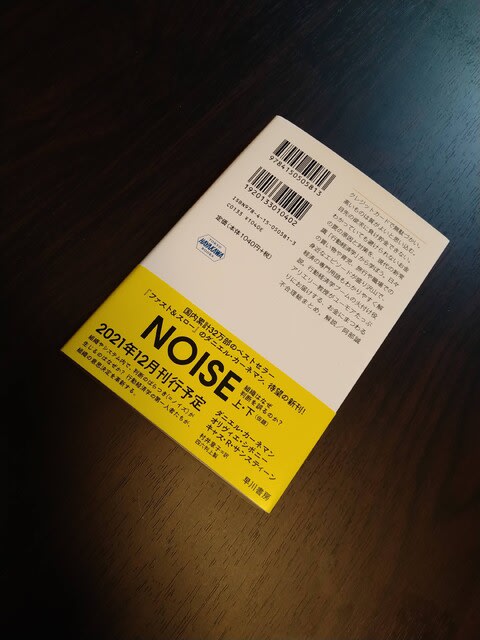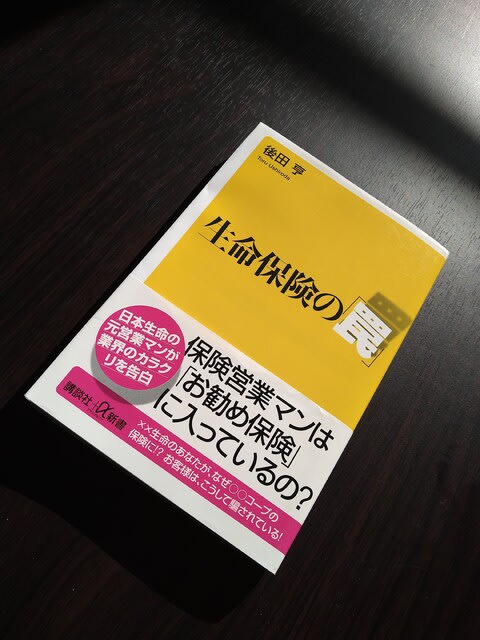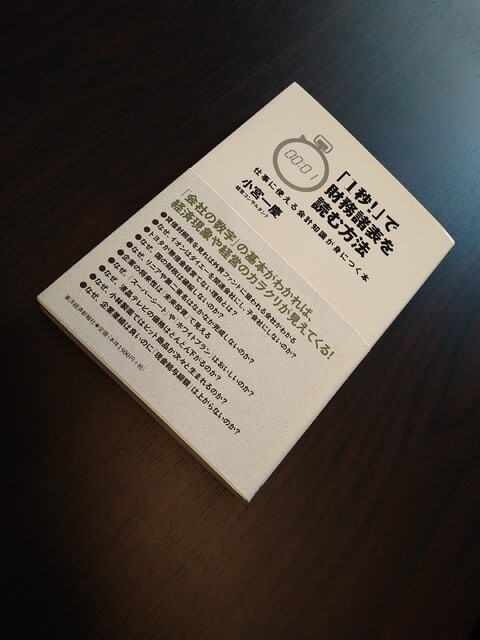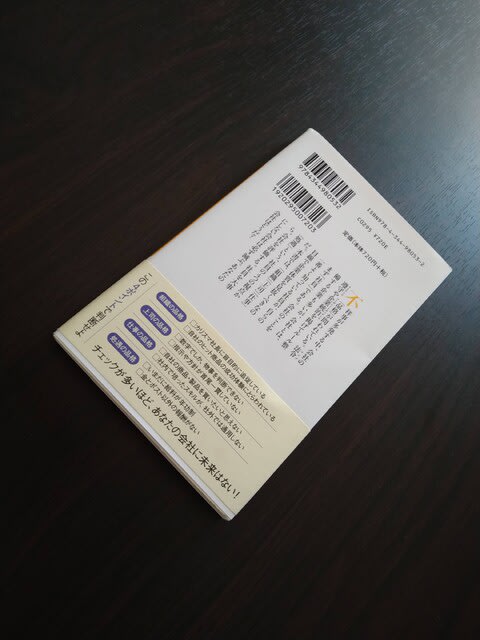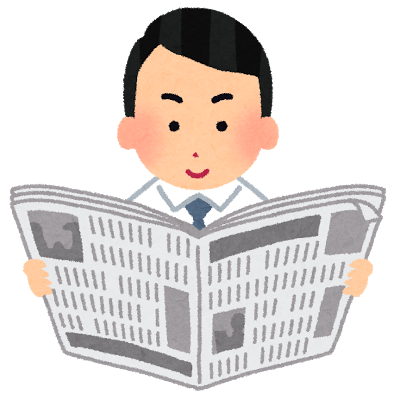日経BP、2022年2月
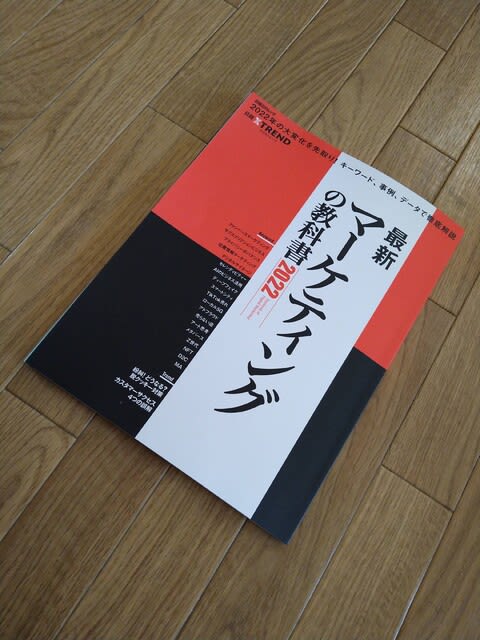
マーケティングのキーワードやトレンドを集めたムック本。
「Chapter2 最新&基本キーワード」ではマーケティングに関係する38のキーワードを解説しています。
マーケティングの中でもネット広告について自分が思うのは、
見たくもない広告の部分をたまたまクリック(タッチ)してしまい、
広告のページに飛んでしまうことが多々あります。
この事象に名前を付けて(アドフラウドとは違うと思います)、
広告代理店やアドテック企業はどう考えているのか(クリック数が増えればよし?)、
広告主は消費者を欺くような仕組みの広告に出稿したいと思うのか、
などを調べてほしいです。
専門誌ではすでに行っているのかもしれませんが。
「Chapter4 先進企業ケーススタディ」
以前から「商品ではなく、体験やストーリーを訴求」すべきと言われていましたが、
実際にそのような広告を展開している、ホンダ、ソニー、パナソニックの事例など。
「Chapter6 パッケージ比較」
麦茶、糖質ゼロビール、グミなど、競合商品がどのようなイメージを持たれているかを比較しています。
例えば麦茶では、コカ・コーラ「やかんの麦茶」と伊藤園「健康ミネラル麦茶」を比較。
昔からコカ・コーラがマーケティングに長けている印象ですが、今も同じようです。
「Chapter7 データ&ランキング」で注目したのは、
40代以上のフリマアプリ利用が進んでいるとのこと。
Chapter1 トレンド分析
Chapter2 最新&基本キーワード
Chapter3 先端技術ワード
Chapter4 最新企業ケーススタディ
Chapter5 米国最新事情リポート
Chapter6 人気パッケージ比較調査
Chapter7 データ&ランキング