高齢者の解雇法制について
高齢者(定年後、年金を受給しながら働く人を想定する)の雇用については、近い将来重要な課題になることが見込まれるが、通常の労働者と解雇権濫用法理の適用を等しくするべきか、という問題がある。この点について、横浜地判平成11年5月31日労判769号44頁(大京ライフ事件)は、①労働者が年金等を受給していること、②高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の努力義務を超えていることを理由に解雇権濫用法理の適用を緩和して判断を行っている。この判例に対しては、濫用法理の適用を緩和する理由が正当か疑問が出されている(小畑史子[判批]労働基準53巻4号26頁)。また、東京地判平成16年8月6日労判881号62頁(ユタカサービス事件)では使用者側が同様の主張をしたものの、裁判所はこの主張を考慮することなく判断を下しており、高齢者だから解雇が緩やかに認められるという規範は確立していない。
そこで緩和の理由、中でも①労働者が年金等を受給していることが正当と言えるかどうか検討する。そもそもなぜ解約の自由のうち解雇の自由が多くの国で規制されているかというと、解雇が経済的耐久力のない労働者に与える打撃の大きさを考慮したものだとされる(菅野和夫『労働法』第8版・444頁)。このような経済的打撃の大小という観点は、整理解雇の4要件(要素)のひとつ「人選の合理性」の中で、若年者は転職が比較的容易であり経済的打撃が低い、あるいは高年者は早期退職の退職金等で生活資金が豊富で年金の受給も近いため経済的打撃が低い、といったことが論じられており、具体的場面でも判断の材料として使われている。このことからすれば、高齢者の生活保障を目的とした老齢年金を受給していることから解雇制限の緩和を導いたとしても的外れというわけではない。もっとも、年金の受給水準が生活維持のために十分でないと言える場合には、緩和を導くことは難しいであろう。
しかし一方で、単純に「経済的打撃の大小」を問題とするなら、若くても保有資産が多い人は労働しても解雇されやすくなるのか、という疑問が出てこよう。保有資産の大小で解雇のしやすさが変わるというのは妥当でない。これと年金受給の場面はどのように違うかというと、「経済的打撃を和らげるものを国家が提供しているかどうか」という点を指摘することができよう。労働契約は本来契約自由の原則が妥当する私法上の契約ではあるが、現実として国民の生活保障という公共政策の一部を担わせられ、種々の規制がかかっているとみることができる。そして、社会保障制度との役割分担という観点から規制の強弱が変わってくるのであり、国家から十分に提供される場合には労働契約上の規制を及ぼす必要性は少なくなると言うことができるようになる。
日本の生活維持に関わる社会保障制度をみるにあたっては、(a)雇用のネット、(b)社会保険のネット、(c)生活保護のネットの三層構造になっているという整理が参考になる(湯浅誠『反貧困』(岩波新書・2008年)19頁)。(a)雇用のネットを既存の雇用の維持という方法で実現し、(b)もそれなりに用意するが、(c)は疎か、というのが日本のやり方ということになるだろう。アメリカは、(a)雇用のネットを自由な転職というかたちで機能させ、(c)生活保護のネットを用意するやり方をとっていると言える。高齢者の解雇の場面に話を戻すと、①年金等を受けていることは(b)社会保険のネットが働いているということであり、現にある労働契約に生活保障を担わせる必要性が低い、と言うことができる。こうなると、解雇制限の緩和は的外れではないと言うに止まらず積極的な評価が可能になる。【追記】仮にこれに反論するとすれば、年金は現役時代の払込みの対価であることを強調し、自己資産と同様にみるべきと主張することになるだろう。
労働契約の社会保障機能
労働契約が国民の生活保障という公共政策の一部を担わせられていることは「労働契約は社会保障機能をもつ」という言葉でまとめることができる。同様の機能をもつ私法上の契約として、他に不動産賃貸借契約を挙げることができる。不動産賃貸借契約の解除には信頼関係の法理が判例上確立しており、その理由として賃貸借契約が①継続的契約であること、②当事者の信頼を基礎とする契約であることを挙げることができる。しかし、弁護士の顧問契約も継続性と信頼性を兼ね備えたものであるが、解約に制限をつける必要性は考えられない。生活の基盤となる住居や事業所の維持が国民の生活保障に資する点に鑑み、公共政策の一部を担わせられているから、と説明するのが適切であろう。これは定期借地権の導入の議論にあたり「貸主が社会保障を国の代わりにやっている」と従来の法制への批判があったことからも見出される。【追記】また、公営住宅にも信頼関係の法理が適用されるとする最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁も説明しやすいであろう。
なお、民法学では「官から民へ」の政策が進められるにあたり公共性をもつ契約として「制度的契約」という視点が提供され、自社年金契約が制度的契約であると松下年金裁判で意見書として出されるなど、さらに広い視点からの性格付けが議論されているが、詳細を整理できていないので立ち入らない(詳細は内田貴「制度的契約と関係的契約」新堂・内田編『継続的契約と商事法務』1頁、同氏のジュリストの連載等を参照)。
労働契約が社会保障機能をもち三層構造の一部をなしていることを意識することにより、労働法制や解釈論を考える場面において有益な指針を導くことができると考えられる。第一には、上で論じたように経済的打撃の大小といった「合理性」の判断枠組の中の視点を体系化・理論化することができる。第二には、「派遣切り」の問題がある。派遣労働は雇用調整が容易であるということに特性をもった労働契約形態であり、従来の(a)雇用のネットを崩すに等しい。したがって、日本国総体として生活保障の水準を維持するためには、転職のコストを下げるといった(a)雇用のネット内での対応に加え、(b)社会保険のネットあるいは(c)生活保護のネットを充実させることが必須であったが対応は乏しかった。このため現実に雇用調整が進められた場合に適切な生活保障のネットがないという事態に陥り、重大な社会問題になったと言うことができる。
第三には、労働時間の問題を挙げることができる。労働時間規制の目的としては、労働者の身体の保護、余暇の保障、ワークシェアリング、柔軟性・効率性等が挙げられている。このうち、社会保障機能との関係で注目すべきはワークシェアリングである。すなわち、一人の労働時間を短縮することにより、他者の労働の機会を増加させるということである。仮にこれを当否は別として社会保障政策として推進していくとすれば、(a)雇用のネットを充実させるという公益的理由から労働時間規制をかけることになるだろう。この際、労働契約が国民の生活保障という公共政策の一部を担わせられていることを重視すれば、より強力な形で推進することが可能となる。
従来、労働契約の特殊性と言えば、一般的には、①交渉力の不均衡(労働者は使用者より交渉力において弱い立場にある)、②継続性(状況の変化により変更が必要になる)、③集団性(秩序維持・公平性の観点が働く)、④白地性(契約は枠を提供するもので、具体的な労働の内容は決められていない)、⑤労務と人の不可分性(労働者の人格を保護する必要性がある)、が挙げられている。 社会保障機能は、このうち労務と人の不可分性の中のひとつですでに考慮されてきたものではあるが、独立して論じることにより、より明確になると考えられる。この社会保障機能は、解雇制限のように労働者自身に働く場面と、労働時間規制のように他の労働者との関係で働く場面とがある。後者の場面は経済規模の拡大が容易には見込めない現在の状況に照らすと、今後重要性を増していくと予想される。
【注意】以上の記述は一学生の試論であり、思考の材料としてではなく現実の事件に参考にするのは避けてください。

にほんブログ村
高齢者(定年後、年金を受給しながら働く人を想定する)の雇用については、近い将来重要な課題になることが見込まれるが、通常の労働者と解雇権濫用法理の適用を等しくするべきか、という問題がある。この点について、横浜地判平成11年5月31日労判769号44頁(大京ライフ事件)は、①労働者が年金等を受給していること、②高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の努力義務を超えていることを理由に解雇権濫用法理の適用を緩和して判断を行っている。この判例に対しては、濫用法理の適用を緩和する理由が正当か疑問が出されている(小畑史子[判批]労働基準53巻4号26頁)。また、東京地判平成16年8月6日労判881号62頁(ユタカサービス事件)では使用者側が同様の主張をしたものの、裁判所はこの主張を考慮することなく判断を下しており、高齢者だから解雇が緩やかに認められるという規範は確立していない。
そこで緩和の理由、中でも①労働者が年金等を受給していることが正当と言えるかどうか検討する。そもそもなぜ解約の自由のうち解雇の自由が多くの国で規制されているかというと、解雇が経済的耐久力のない労働者に与える打撃の大きさを考慮したものだとされる(菅野和夫『労働法』第8版・444頁)。このような経済的打撃の大小という観点は、整理解雇の4要件(要素)のひとつ「人選の合理性」の中で、若年者は転職が比較的容易であり経済的打撃が低い、あるいは高年者は早期退職の退職金等で生活資金が豊富で年金の受給も近いため経済的打撃が低い、といったことが論じられており、具体的場面でも判断の材料として使われている。このことからすれば、高齢者の生活保障を目的とした老齢年金を受給していることから解雇制限の緩和を導いたとしても的外れというわけではない。もっとも、年金の受給水準が生活維持のために十分でないと言える場合には、緩和を導くことは難しいであろう。
しかし一方で、単純に「経済的打撃の大小」を問題とするなら、若くても保有資産が多い人は労働しても解雇されやすくなるのか、という疑問が出てこよう。保有資産の大小で解雇のしやすさが変わるというのは妥当でない。これと年金受給の場面はどのように違うかというと、「経済的打撃を和らげるものを国家が提供しているかどうか」という点を指摘することができよう。労働契約は本来契約自由の原則が妥当する私法上の契約ではあるが、現実として国民の生活保障という公共政策の一部を担わせられ、種々の規制がかかっているとみることができる。そして、社会保障制度との役割分担という観点から規制の強弱が変わってくるのであり、国家から十分に提供される場合には労働契約上の規制を及ぼす必要性は少なくなると言うことができるようになる。
日本の生活維持に関わる社会保障制度をみるにあたっては、(a)雇用のネット、(b)社会保険のネット、(c)生活保護のネットの三層構造になっているという整理が参考になる(湯浅誠『反貧困』(岩波新書・2008年)19頁)。(a)雇用のネットを既存の雇用の維持という方法で実現し、(b)もそれなりに用意するが、(c)は疎か、というのが日本のやり方ということになるだろう。アメリカは、(a)雇用のネットを自由な転職というかたちで機能させ、(c)生活保護のネットを用意するやり方をとっていると言える。高齢者の解雇の場面に話を戻すと、①年金等を受けていることは(b)社会保険のネットが働いているということであり、現にある労働契約に生活保障を担わせる必要性が低い、と言うことができる。こうなると、解雇制限の緩和は的外れではないと言うに止まらず積極的な評価が可能になる。【追記】仮にこれに反論するとすれば、年金は現役時代の払込みの対価であることを強調し、自己資産と同様にみるべきと主張することになるだろう。
労働契約の社会保障機能
労働契約が国民の生活保障という公共政策の一部を担わせられていることは「労働契約は社会保障機能をもつ」という言葉でまとめることができる。同様の機能をもつ私法上の契約として、他に不動産賃貸借契約を挙げることができる。不動産賃貸借契約の解除には信頼関係の法理が判例上確立しており、その理由として賃貸借契約が①継続的契約であること、②当事者の信頼を基礎とする契約であることを挙げることができる。しかし、弁護士の顧問契約も継続性と信頼性を兼ね備えたものであるが、解約に制限をつける必要性は考えられない。生活の基盤となる住居や事業所の維持が国民の生活保障に資する点に鑑み、公共政策の一部を担わせられているから、と説明するのが適切であろう。これは定期借地権の導入の議論にあたり「貸主が社会保障を国の代わりにやっている」と従来の法制への批判があったことからも見出される。【追記】また、公営住宅にも信頼関係の法理が適用されるとする最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁も説明しやすいであろう。
なお、民法学では「官から民へ」の政策が進められるにあたり公共性をもつ契約として「制度的契約」という視点が提供され、自社年金契約が制度的契約であると松下年金裁判で意見書として出されるなど、さらに広い視点からの性格付けが議論されているが、詳細を整理できていないので立ち入らない(詳細は内田貴「制度的契約と関係的契約」新堂・内田編『継続的契約と商事法務』1頁、同氏のジュリストの連載等を参照)。
労働契約が社会保障機能をもち三層構造の一部をなしていることを意識することにより、労働法制や解釈論を考える場面において有益な指針を導くことができると考えられる。第一には、上で論じたように経済的打撃の大小といった「合理性」の判断枠組の中の視点を体系化・理論化することができる。第二には、「派遣切り」の問題がある。派遣労働は雇用調整が容易であるということに特性をもった労働契約形態であり、従来の(a)雇用のネットを崩すに等しい。したがって、日本国総体として生活保障の水準を維持するためには、転職のコストを下げるといった(a)雇用のネット内での対応に加え、(b)社会保険のネットあるいは(c)生活保護のネットを充実させることが必須であったが対応は乏しかった。このため現実に雇用調整が進められた場合に適切な生活保障のネットがないという事態に陥り、重大な社会問題になったと言うことができる。
第三には、労働時間の問題を挙げることができる。労働時間規制の目的としては、労働者の身体の保護、余暇の保障、ワークシェアリング、柔軟性・効率性等が挙げられている。このうち、社会保障機能との関係で注目すべきはワークシェアリングである。すなわち、一人の労働時間を短縮することにより、他者の労働の機会を増加させるということである。仮にこれを当否は別として社会保障政策として推進していくとすれば、(a)雇用のネットを充実させるという公益的理由から労働時間規制をかけることになるだろう。この際、労働契約が国民の生活保障という公共政策の一部を担わせられていることを重視すれば、より強力な形で推進することが可能となる。
従来、労働契約の特殊性と言えば、一般的には、①交渉力の不均衡(労働者は使用者より交渉力において弱い立場にある)、②継続性(状況の変化により変更が必要になる)、③集団性(秩序維持・公平性の観点が働く)、④白地性(契約は枠を提供するもので、具体的な労働の内容は決められていない)、⑤労務と人の不可分性(労働者の人格を保護する必要性がある)、が挙げられている。 社会保障機能は、このうち労務と人の不可分性の中のひとつですでに考慮されてきたものではあるが、独立して論じることにより、より明確になると考えられる。この社会保障機能は、解雇制限のように労働者自身に働く場面と、労働時間規制のように他の労働者との関係で働く場面とがある。後者の場面は経済規模の拡大が容易には見込めない現在の状況に照らすと、今後重要性を増していくと予想される。
【注意】以上の記述は一学生の試論であり、思考の材料としてではなく現実の事件に参考にするのは避けてください。
にほんブログ村











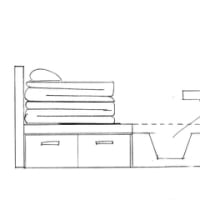















です。原告側の理由不備が要因ともいえます。
判示理由のご指摘の点も問題点ですが、重要なことは、むしろ高齢者の雇用をする企業側の労働環境の劣悪性なのです。雇用は労働条件と労働環境=提供労務内容に値する賃金待遇でなければなりません。この大京ライフは、60歳以上を高齢者雇用助成金で給与の三分の一税金で賄われる厚遇の下に採用している企業です。
また大京ライフは厚労省から是正勧告を受けている「偽装請負」システムの下で、高齢労働者を酷使し、莫大な収益を受けています。故に
高齢者の「使い捨て」不当解雇が生じているわけですが、該判示はこの部分が欠落した誤判と
いえます。我々は高齢者非正規労働者として、
高齢労働者の奴隷雇用制度と闘っています。
当該判決は労働環境の悪さを見落としているとのことですが、解雇の法的判断に当たって労働環境如何は論理必然につながるものではないように思います。先日の記事でも書いたようにジョブを基礎としない日本の雇用体系では働きの内容と賃金が当然に対応するものではないため、労働組合のような交渉力の格差を是正するために法が用意している手段を使っていく必要があります。コメント主さまの活動により多くの関係者の方々にとって満足のいく状態が実現されることを願っています。