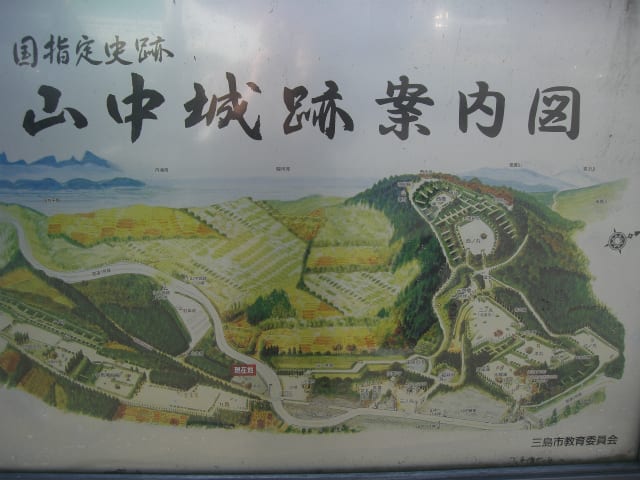二の丸東大手門【復元】から、いったん霞城公園を出た。


二の丸堀もかなりの規模を誇る。

二の丸堀に沿って桜が植えられている。
山形城は桜の名所としても知られる。
霞城公園から徒歩5分ほどで、最上義光歴史館へ。

最上氏関連の資料を保管・展示し、最上義光と最上氏を顕彰することを目的とした博物館。
入館料は無料。
受付でさっそく・・・

10番、山形城!
絵柄は二の丸東大手門。
最上義光歴史館へ来た理由は、スタンプだけではない。
最上義光は出羽国の大名で、最上義守の嫡男。
妹は義姫(保春院)で、隣国米沢の大名・伊達輝宗に嫁ぎ、政宗を産む。
家督を継ぐと、出羽の統一に乗り出す。
その過程で父や伊達と対立するが、これを乗り切り村山地方(山形盆地周辺)の領域を統一。
最上地方(新庄盆地周辺)を制し、庄内地方(庄内平野周辺)へ進出するが、庄内は越後の上杉景勝に先んじられる。
義光は調略を得意とし、敵の重臣を寝返らせて内紛を生じさせる策を多用した。
その謀将ぶりは、「出羽の驍将」と称される。
豊臣秀吉の政権下で、米沢の伊達政宗は陸奥国岩出山(宮城県北部)へ、上杉景勝は会津若松へ、上杉の陪臣・直江兼続は米沢へ移封となる。
庄内は依然として上杉領であり、最上領が上杉領を分断する格好になっていた。
1600年の関ヶ原の戦役では東軍につき、西軍に着いた上杉景勝を牽制する役を担う。
しかし、所領の状況から直江兼続率いる上杉軍は最上領へ攻め込む。(慶長出羽合戦)
兵力では劣勢であったが、長谷堂城の戦いで防ぎ切った。
関ヶ原の戦後は庄内地方も所領に与えられ、出羽山形57万石の大名となった。
だが、最上家は一気に没落していく。
後を継いだ子・家親は若くして死亡、その後を継いだ孫・義俊の代でお家騒動が勃発。
義光の死後10年もたたず、最上家は改易となってしまった。

前話でも登場した最上義光公勇戦像。
この像がかぶっている兜と、右手に握っている指揮棒が、歴史館に保存され展示されている。
兜は
最上義光愛用の兜で、織田信長より贈られたものという。
1600年の慶長出羽合戦で、義光は先陣を切って直江兼続の軍を追撃するが、直江勢の鉄砲隊に逆襲され狙撃されてしまう。
銃弾は左の額!!に飛んでいったが、この兜のおかげで助かった。
その時の弾痕が生々しく残っている。
指揮棒は鉄製で重量は1,750グラム、刀の2倍ほどもある。
(長さは、銅像のものほどは長くないです)
義光は相当腕力のある人物だったといい、そういうエピソードも残っている。
はぁ~、撮影禁止&係員べったりのため画像はありません・・・。
城の北側に回る。
山形城もなかなかでかいのぅ。


北側では、民家のすぐ裏側が城の水濠(二の丸堀)になっている。


二の丸堀ぞいを歩いて、二の丸北不明門跡に着いた。
ここからもう一度霞城公園(二の丸)に入っていく。

西側の門、二の丸西不明門跡。
石垣のならびが枡形を構成している。

二の丸沿いの土塁に上がり、西側を見る。
二の丸堀をほぼ一周し、スタート地点の二の丸南大手門跡へ。
山形城はここをゴールとして、城を出た。