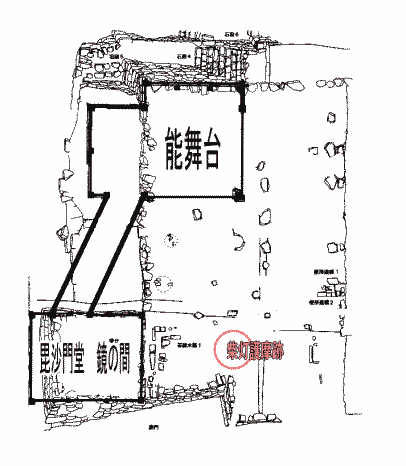祭神は熱田大神宮との伝承で、通常より横長の社殿なのは、
熱田の五柱の神座を置くためと考えられることから、
中央は熱田社で良いと思われます。
問題なのが南側の”石組遺構1”で、記録には
梁行3尺・桁行□尺6寸の鎮守社、と書かれているのだが、
現在この場所には、(発掘調査報告書P15)
「宝篋印塔の台座が置かれている」
火災の後、見寺はこの場所から移転するので、
石が据えられたのは、火災の前の可能性が高く、
この”宝篋印塔の台座”に被せるような形で、
鎮守社が置かれていたと考えられます。
ところで、この石は本当に”宝篋印塔の台座”なのでしょうか?
3月の説明会の時に、現物を見て来たのですが、
側面に格狭間が彫られてはいるものの、石の上部は平らで、
滋賀県に現存する宝篋印塔の台座は、調べた限り、
台座が、上部の段形や蓮華座と一体になっている形なので、
これは宝篋印塔ではなく、宝塔か層塔の台座であると思われます。
では、宝塔か層塔のどちらかというと、
本尊が一字金輪仏頂尊なので、
須彌壇前の大壇に宝塔が置かれていたであろうから、
この場所は、本堂に対し三重塔と対になる形で、
層塔が置かれていたと考えます。
熱田社の本地仏は大日如来であり、
三重塔の来迎壁には金剛界の大日如来が描かれているので、
創建時、ここにあった層塔は、
月輪内に、胎蔵界五仏の種子の書かれた塔身を持つ、
胎蔵界の大日如来を表すものであったと考えられます。
その後、秀吉の頃の近畿地方の大地震により、
見寺周辺部の、盛り土の厚かった部分が変形して、
重心が不安定な層塔が崩壊し、
秀頼の修複時に、鎮守社が置かれたものではないでしょうか、
秀頼の修複時に、あらたに置かれたとすれば、
祭神についての伝承は残っていないようなので、
江戸時代には禁忌であった、豊国大明神が
秘かに祭られていたのではなかったかと思います。