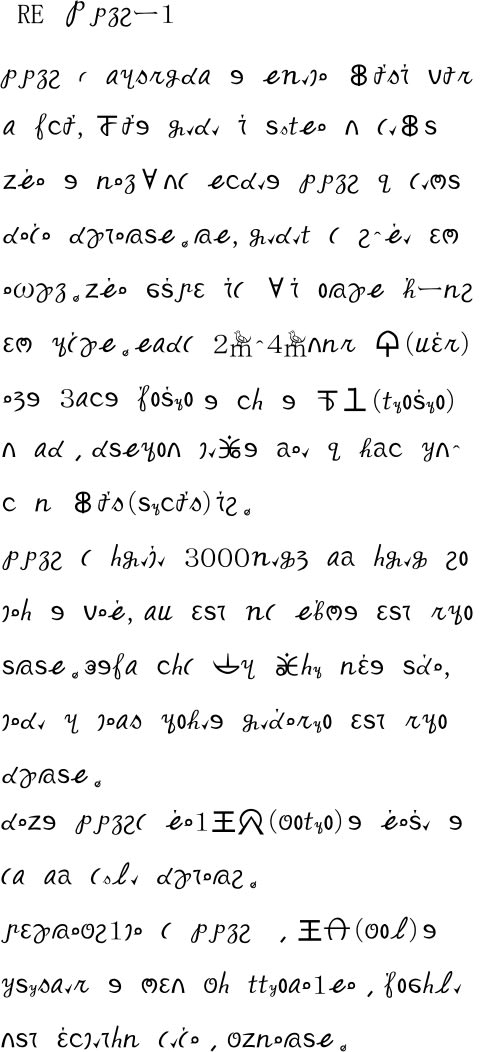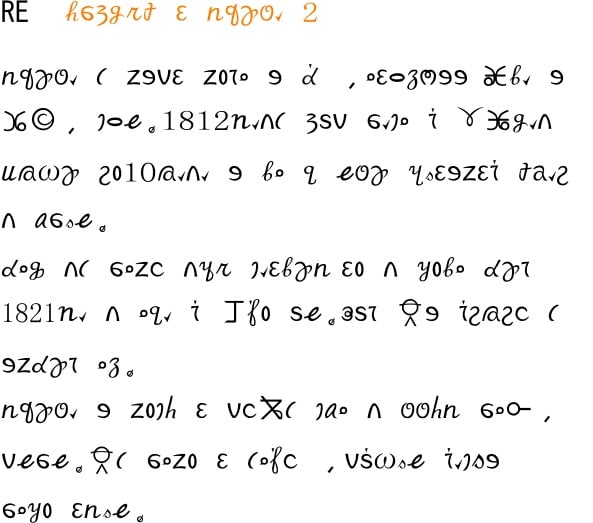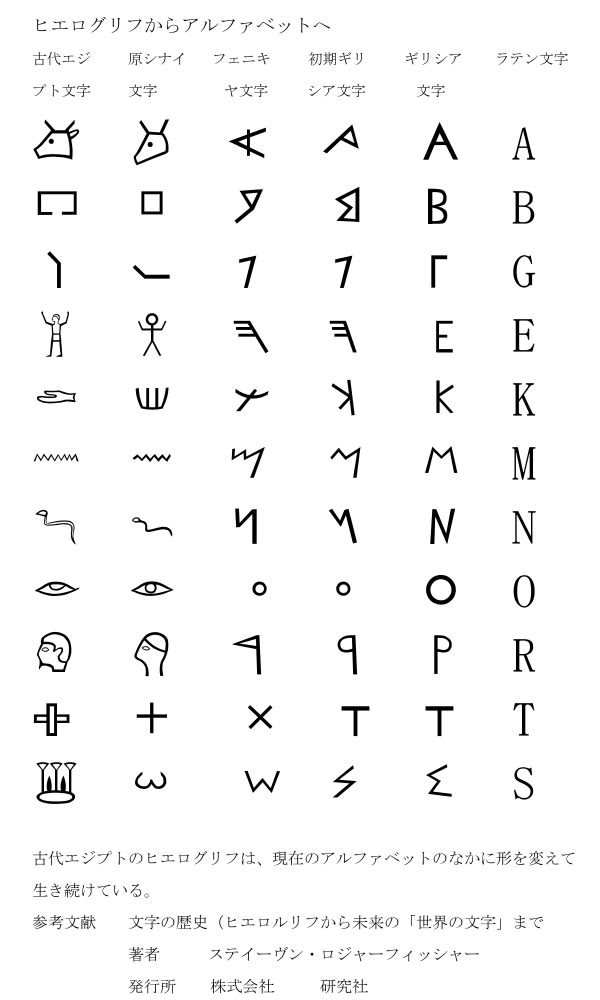クレオパトラが遠ざかっていく船団に向かって手を振る姿を妹のアルシノエは敵意の目で見つめていた。港に集まったアレキサンドリアの人たちは自国の船が沢山の穀物を積んで出港していくのを見ていた。アルシノエは姉のことを弟のプトレマイオス13世に告げ口した。3人の執行官はこの機会を逃さずにクレオパトラを非難して民衆の怒りを煽った。
「女王はローマ人の妾になったぞ」「飢饉で食べ物がないのに、沢山の穀物を外国人に渡したぞ」民衆はたちまち扇動にのって宮殿に押し寄せて来た。
クレオパトラはわずかの従者をつれてシリアの砂漠へと逃れて行った。シリアに入るとシリア総督のビブルスとも会い、兵を集めだした。「再びアレキサンドリアに帰り復権をしよう」クレオパトラは弟王と3執行官たちと戦う決意を固めた。
この情報は王側に知られて、アキラス軍司令官らはクレオパトラを撃つべく、大軍を率いてペリシウムの河口に陣を敷いた。