「英国人記者が見た 連合国戦勝歴史観の虚妄(祥伝社新書)」を改めて紹介してみます。
筆者のヘンリー・S・ストークス氏は英国人で『フィナンシャル・タイムズ』『ロンドン・タイムズ』『ニューヨーク・タイムズ』各東京支局長を歴任した。
奥様は日本人であるが、歴代の外国人マスコミ担当で最長の勤務をし、三島由紀夫氏との親交も深いなど異色の経歴の持ち主である。
英国人の彼は、来日時には「日本=戦争犯罪国家」論、「南京大虐殺」を疑うことなく信じていた。しかし、この大物ジャーリストは、以降歴史観を180度転換してゆく、何故か? この推移が興味深い。
「戦勝国史観」は、有色人種を蔑視した白人優位主義から発している。それなのに、日本国民の多くが、なぜ、そのような史観を信じているのか、理解に苦しんでいる。さらに著者は「戦勝国史観」は歴史をあざむいており、日本は侵略国家ではなかったと反論する。いわゆる「南京大虐殺」や「慰安婦」問題についても、日本がいわれのない非難を蒙(こうむ)っていることを、証している。
例えば「南京大虐殺」、今は日本軍が南京で三十万人を虐殺したことになっている。しかしこれは中国のプロパガンダ(諜略宣伝)であって、その理由を具体的事実をもって証明している。そして、韓国の光州事件を引き合いに局地で起こった事件(暴動)の実態解明がどれほど複雑怪奇で難しいかを解説している。
また大物ジャーナリストとして色々なリーダーと会っている、その描写も興味深い。
金大中、金日成、シアヌーク殿下、岸信介、安倍晋太郎、中曽根康弘等々の人物評価も、意外な事実に驚く。また、1943年に東京で開かれた「大東亜会議」にも触れ、”日本はアジアの希望の光”であったことを詳細に語っている。
私の生涯の愛読の書となるであろう、
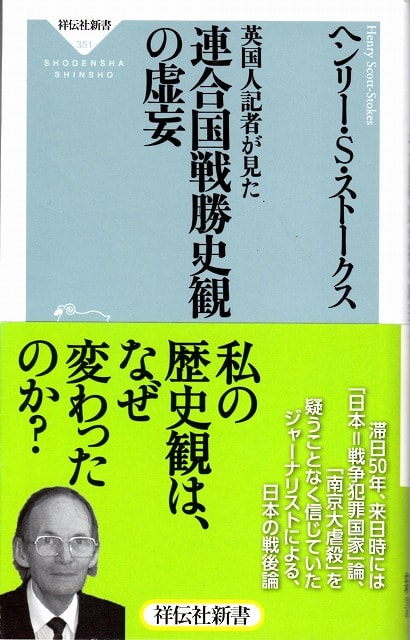 以下はこの本を読んだ読者の感想文のコピペである。
以下はこの本を読んだ読者の感想文のコピペである。
「私は日本が大英帝国の植民地を占領したことに、日本の正義があると思った。それを戦後になって、まるで戦勝国が全能の神であるかのように、日本の罪を裁くことに違和感を感じた」。
イギリス人ジャーナリストの立場から、それぞれの国から見た太平洋戦争の正義の意味が異なることを指摘し、日本はどのように歴史と向かい合い、「戦後レジームからの脱却」を位置づけるべきかについての自説を述べた本。著者は『フィナンシャル・タイムズ』『エコノミスト』の東京特派員、『ロンドン・タイムズ』『ニューヨーク・タイムズ』の東京支局長を務めてきた経歴を持つ。
「侵略が悪いことなら、世界史で、アジア、アフリカ、オーストラリア、北米、南米を侵略してきたのは、西洋諸国だ。しかし、今日まで、西洋諸国がそうした侵略を謝罪したことはない。どうして日本だけが欧米の植民地を侵略したことを、謝罪しなければならないのか」。
日本人は、太平洋戦争で戦った相手というとまずアメリカを思い浮かべるが、実はイギリスがこの戦争をきっかけに失ったものは実に膨大だった。著者が子供の頃に地球儀を使って説明されたという栄光の大英帝国の基盤の要はアジアの植民地であり、しかし、日本の快進撃とともにその数百年の支配が一気に崩れ、その後これらの地域が独立に向かって大英帝国は消えることになった。そこに、日本軍捕虜収容所での英兵の扱いの問題が加わり、イギリスの日本への戦後の国民感情は相当ひどいものであったそうだ。同様に、オランダ、フランス、アメリカもアジアの植民地を失った。著者は、そのような歴史を振り返りながら、引用した上記のようなごく基本的な問いかけを行っている。他にも、南京や朝鮮半島における歴史的争点や、靖国神社参拝といったことについて、著者の見解が次々と書き連ねられている。
50年間の長きにわたって欧米を代表する一流紙の記者であったため、たくさんの有名人に会っていて、その思い出話を披露しているのも本書の特徴である。特に親交が深かった三島由紀夫については多くのページを割いており、三島が命を賭けて伝えようとしていたものを今を生きる日本人に改めて問いかけている。他にも戦後の重要人物が目白押しである。田中角栄、岸信介、安倍晋太郎、中曽根康弘、白洲次郎、麻生和子、シアヌーク、スカルノ、金大中、金日成。例えば、シアヌーク殿下が、みずから日本軍将校を主役にした映画を監督・主演して作って、金日成・正日親子の前で上映して賞賛されたというようなエピソードも登場する。また、駆け出しのころには、後にイギリスの首相になるエドワード・ヒースにも会っているし、戦後日本を世界に紹介する上で大きな貢献を果たしたドナルド・キーン、エドワード・サイデン・ステッカー、アイヴァン・モリスのことも語っている。
これは本文において著者が書いているだけでなく、解説部分において加藤英明氏も全く同じことを書いているが、敗戦国であるという以外に日本が誤解を受けている理由として、日本から正しい情報があまり発信されていない点を上げているのは気になった。現在、日本が中国や韓国から非難を受けているあの時代の論点のいくつかは、元をたどれば日本のメディアが火付け役になっているものだ。また、著者は「日本の主張が、英語で発信されてこなかったことが大きい」とも述べている。
内容を要約すると、大東亜戦争はアジア解放戦争だった、
南京大虐殺や慰安婦はただの捏造、東京裁判は無効。
亡命中の故シアヌーク殿下が「ボゴールの薔薇」という映画を撮影、
自ら日本軍将校を演じ、日本軍を解放軍として描いた・・・
北朝鮮兵が演じる日本兵が「捧げ銃」をする姿は奇観・・・
という小話がかなり気に入った。
歴史の予備知識がなくとも読めるので幅広い方々にお勧めする。
色々な意味で優れたジャーナリストだなぁと思う。
日本人には持ち得ない新鮮な視点で、元々フェアな人が、より一層フェアであろうと努力して、書き上げたと感じられた。
youtube「ハリー杉山 Henry Scott-Stokes 息子へのまなざし」がいい。
こんな人を父に持った人は、さぞ誇らしいだろうなぁと思う。
(他人に誇るのではなく、胸の内、密かに誇る誇らしさ)
優れたレビューが既に幾つもついており、付け加えたいことなどほとんどない。
本筋ではないけれども、既についたレビューの中で、あまり触れられていない事柄に、クエーカー教徒のことがあった。
p.209
私(筆者)が・・・、日本人に親しみを感じるのは、クエーカー教徒だからかもしれない。
クエーカー教徒も差別を受けてきた。・・・役人にも、軍人にも、法律家にもなれなかった。土地も所有できなかった。キリスト教新教の一派だが・・・・。特色は、権威に対して頭を下げないことだ。自由と独立を信条としている。・・・一方で真摯で、礼儀正しいことで知られる。
少数派・・・。
クエーカー教には神職がいない。集まって瞑想し、霊感を受けた者が、立ち上がって感じたままを話す。一人が話しすぎた場合は先達が穏やかな語り口調で終えるよう促す。賛美歌を歌うこともない。教義を押しつけることもなく個人が霊感することを尊重する。一人ひとりが良心と向き合う。
クエーカーの集会所は、木で建築され、派手な装飾が一切ない。素朴なところが、神道の神社と結びつく。聖書も丸呑みにすることがない。キリストを信仰するが、盲信よりも、「いったいキリストは、どういう方か」と問い続ける。形式や教義がない。
戦中までのドナルド・キーン氏の経歴に触れた箇所も、面白かった。
禍福は糾える縄の如し(Good luck and bad luck alternate like the strands of a rope.)だなと思った。
p.211
戦後の日本兵の気高さに打たれたドナルド・キーン
エドワード・サイデンステッカー、アイヴァン・モリスの三人が、日本文学を世界に紹介するうえで、大きな貢献をした外国人として、よく知られている。
筆者のヘンリー・S・ストークス氏は英国人で『フィナンシャル・タイムズ』『ロンドン・タイムズ』『ニューヨーク・タイムズ』各東京支局長を歴任した。
奥様は日本人であるが、歴代の外国人マスコミ担当で最長の勤務をし、三島由紀夫氏との親交も深いなど異色の経歴の持ち主である。
英国人の彼は、来日時には「日本=戦争犯罪国家」論、「南京大虐殺」を疑うことなく信じていた。しかし、この大物ジャーリストは、以降歴史観を180度転換してゆく、何故か? この推移が興味深い。
「戦勝国史観」は、有色人種を蔑視した白人優位主義から発している。それなのに、日本国民の多くが、なぜ、そのような史観を信じているのか、理解に苦しんでいる。さらに著者は「戦勝国史観」は歴史をあざむいており、日本は侵略国家ではなかったと反論する。いわゆる「南京大虐殺」や「慰安婦」問題についても、日本がいわれのない非難を蒙(こうむ)っていることを、証している。
例えば「南京大虐殺」、今は日本軍が南京で三十万人を虐殺したことになっている。しかしこれは中国のプロパガンダ(諜略宣伝)であって、その理由を具体的事実をもって証明している。そして、韓国の光州事件を引き合いに局地で起こった事件(暴動)の実態解明がどれほど複雑怪奇で難しいかを解説している。
また大物ジャーナリストとして色々なリーダーと会っている、その描写も興味深い。
金大中、金日成、シアヌーク殿下、岸信介、安倍晋太郎、中曽根康弘等々の人物評価も、意外な事実に驚く。また、1943年に東京で開かれた「大東亜会議」にも触れ、”日本はアジアの希望の光”であったことを詳細に語っている。
私の生涯の愛読の書となるであろう、
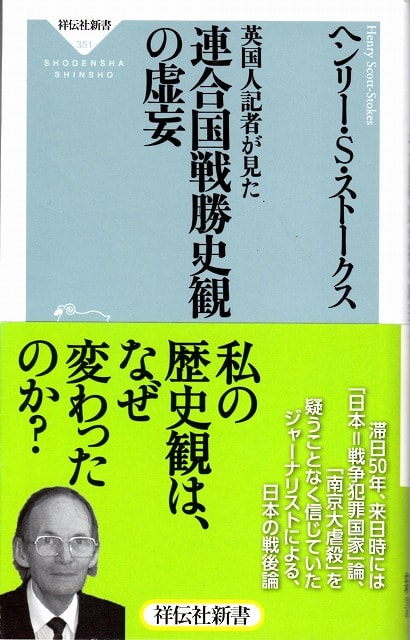
「私は日本が大英帝国の植民地を占領したことに、日本の正義があると思った。それを戦後になって、まるで戦勝国が全能の神であるかのように、日本の罪を裁くことに違和感を感じた」。
イギリス人ジャーナリストの立場から、それぞれの国から見た太平洋戦争の正義の意味が異なることを指摘し、日本はどのように歴史と向かい合い、「戦後レジームからの脱却」を位置づけるべきかについての自説を述べた本。著者は『フィナンシャル・タイムズ』『エコノミスト』の東京特派員、『ロンドン・タイムズ』『ニューヨーク・タイムズ』の東京支局長を務めてきた経歴を持つ。
「侵略が悪いことなら、世界史で、アジア、アフリカ、オーストラリア、北米、南米を侵略してきたのは、西洋諸国だ。しかし、今日まで、西洋諸国がそうした侵略を謝罪したことはない。どうして日本だけが欧米の植民地を侵略したことを、謝罪しなければならないのか」。
日本人は、太平洋戦争で戦った相手というとまずアメリカを思い浮かべるが、実はイギリスがこの戦争をきっかけに失ったものは実に膨大だった。著者が子供の頃に地球儀を使って説明されたという栄光の大英帝国の基盤の要はアジアの植民地であり、しかし、日本の快進撃とともにその数百年の支配が一気に崩れ、その後これらの地域が独立に向かって大英帝国は消えることになった。そこに、日本軍捕虜収容所での英兵の扱いの問題が加わり、イギリスの日本への戦後の国民感情は相当ひどいものであったそうだ。同様に、オランダ、フランス、アメリカもアジアの植民地を失った。著者は、そのような歴史を振り返りながら、引用した上記のようなごく基本的な問いかけを行っている。他にも、南京や朝鮮半島における歴史的争点や、靖国神社参拝といったことについて、著者の見解が次々と書き連ねられている。
50年間の長きにわたって欧米を代表する一流紙の記者であったため、たくさんの有名人に会っていて、その思い出話を披露しているのも本書の特徴である。特に親交が深かった三島由紀夫については多くのページを割いており、三島が命を賭けて伝えようとしていたものを今を生きる日本人に改めて問いかけている。他にも戦後の重要人物が目白押しである。田中角栄、岸信介、安倍晋太郎、中曽根康弘、白洲次郎、麻生和子、シアヌーク、スカルノ、金大中、金日成。例えば、シアヌーク殿下が、みずから日本軍将校を主役にした映画を監督・主演して作って、金日成・正日親子の前で上映して賞賛されたというようなエピソードも登場する。また、駆け出しのころには、後にイギリスの首相になるエドワード・ヒースにも会っているし、戦後日本を世界に紹介する上で大きな貢献を果たしたドナルド・キーン、エドワード・サイデン・ステッカー、アイヴァン・モリスのことも語っている。
これは本文において著者が書いているだけでなく、解説部分において加藤英明氏も全く同じことを書いているが、敗戦国であるという以外に日本が誤解を受けている理由として、日本から正しい情報があまり発信されていない点を上げているのは気になった。現在、日本が中国や韓国から非難を受けているあの時代の論点のいくつかは、元をたどれば日本のメディアが火付け役になっているものだ。また、著者は「日本の主張が、英語で発信されてこなかったことが大きい」とも述べている。
内容を要約すると、大東亜戦争はアジア解放戦争だった、
南京大虐殺や慰安婦はただの捏造、東京裁判は無効。
亡命中の故シアヌーク殿下が「ボゴールの薔薇」という映画を撮影、
自ら日本軍将校を演じ、日本軍を解放軍として描いた・・・
北朝鮮兵が演じる日本兵が「捧げ銃」をする姿は奇観・・・
という小話がかなり気に入った。
歴史の予備知識がなくとも読めるので幅広い方々にお勧めする。
色々な意味で優れたジャーナリストだなぁと思う。
日本人には持ち得ない新鮮な視点で、元々フェアな人が、より一層フェアであろうと努力して、書き上げたと感じられた。
youtube「ハリー杉山 Henry Scott-Stokes 息子へのまなざし」がいい。
こんな人を父に持った人は、さぞ誇らしいだろうなぁと思う。
(他人に誇るのではなく、胸の内、密かに誇る誇らしさ)
優れたレビューが既に幾つもついており、付け加えたいことなどほとんどない。
本筋ではないけれども、既についたレビューの中で、あまり触れられていない事柄に、クエーカー教徒のことがあった。
p.209
私(筆者)が・・・、日本人に親しみを感じるのは、クエーカー教徒だからかもしれない。
クエーカー教徒も差別を受けてきた。・・・役人にも、軍人にも、法律家にもなれなかった。土地も所有できなかった。キリスト教新教の一派だが・・・・。特色は、権威に対して頭を下げないことだ。自由と独立を信条としている。・・・一方で真摯で、礼儀正しいことで知られる。
少数派・・・。
クエーカー教には神職がいない。集まって瞑想し、霊感を受けた者が、立ち上がって感じたままを話す。一人が話しすぎた場合は先達が穏やかな語り口調で終えるよう促す。賛美歌を歌うこともない。教義を押しつけることもなく個人が霊感することを尊重する。一人ひとりが良心と向き合う。
クエーカーの集会所は、木で建築され、派手な装飾が一切ない。素朴なところが、神道の神社と結びつく。聖書も丸呑みにすることがない。キリストを信仰するが、盲信よりも、「いったいキリストは、どういう方か」と問い続ける。形式や教義がない。
戦中までのドナルド・キーン氏の経歴に触れた箇所も、面白かった。
禍福は糾える縄の如し(Good luck and bad luck alternate like the strands of a rope.)だなと思った。
p.211
戦後の日本兵の気高さに打たれたドナルド・キーン
エドワード・サイデンステッカー、アイヴァン・モリスの三人が、日本文学を世界に紹介するうえで、大きな貢献をした外国人として、よく知られている。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます