2013年12月、イタリアに行って来ました。
LOOK・JTB(黄色いパンフレットの安価な方です)さんの、<添乗員がご案内するミラノからの人気の4都市めぐりイタリア満喫8日間>です。
初日は、11時00分成田空港集合、13時00分ルフトハンザ航空ミュンヘン行き発、17時20分ミュンヘン着、19時35分ミラノ行き発、20時40分ミラノ着。
ルフトハンザ航空のエコノミークラスは、人間工学的に作られたシートだということで長時間のフライトにも耐えられました。
ヘッドレストはありますが、フットレストはありません。
機内食サービスの時間外は、ギャレーにドリンク・軽食がありました。
ミラノ到着後、空港建物内にある<シェラトン・ミラノ・マルベンサ・エアポートホテル&コンフェレンスセンター>に宿泊しました。
スーツケースを引いて空港建物内を少し歩いたらホテルというのは、長いフライトで疲れた身体に本当にありがたかったです。
2日め午前中は、ミラノ市内観光(ドゥオモ・スフォルツェスコ城中庭・スカラ座・ピットリオエマヌエレ2世ガレリア)です。
ミラノは、人口130万人の県の県都だそうです。
スフォルツェスコ城。
素敵なおじさまのガイドさん。
ウィキによれば、1450年にミラノ公爵のフランチェスコ・スフォルツァがヴィスコンティ家の居城を改築して建設した城塞で(都市を守りつつ、都市住民からも王族らを守るために設計されているもの)、もともとは星型の形状の広大な城郭だったそうですが現存しているのは元々の面積の1/4程度以下だそうです。

内部は現在は市立博物館となっていて、ミケランジェロの最後の作品「ロンダニーニのピエタ」などが展示されているそうです。
JTBさんの日程表の記述が「スフォルツェスコ城中庭」となっているのは、この博物館の見学はないという意味でしょうね…。


石でできた大砲の弾。
大砲は13世紀半ばに中国で最初に開発されたそうですが、太さが均一な管の形をした大砲(射石砲と呼ばれ石の砲丸を発射するものだったそうです)がヨーロッパで使われるようになったのは15世紀初頭だったそうです。

ミラノ・スカラ座。下車して外観のみの観光です。
1778年サンタ・マリア・アラ・スカラ教会のあった場所に建設され、ここから劇場名がとられたそうです。
イタリアオペラ界の最高峰とされる歌劇場だそうです。

ピットリオエマヌエレ2世ガレリアに向かいます。

1877年に完成し、イタリア王国の初代国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世にちなんで名づけられたガラス張りのアーケードで、ミラノドゥオーモ広場の北に位置しミラノスカラ広場へ通じている(ミラノのドゥオーモとスカラ座に繋がっている)そうです。
東京ディズニーランドのワールドバザールはこのガッレリアをモデルに作られているそうですよ。

ガラス製のドームで覆われた中央天井。

2つのアーケード(8角形の建物に2つのアーケードが交差する)の交わる場所に、青いタイルで囲まれた牡牛のモザイクがあり、その股間部分の窪みに踵を合わせてクルリと一回転すると幸せが訪れるとの言い伝えがあるそうで、私もやってみました。
(幸せって何だろーね?)


いよいよドゥオモです。
14世紀末、ミラノの君主ジャン・ガレアッツォ・ヴィスコンティが聖母マリアに捧げる壮大な大聖堂の建築を思い立ちバチカンのサン・ピエトロ大聖堂を目標に1386年に着工され、1813年に完成したイタリア最大のゴシック様式(12世紀後半にフランスを発祥としイギリス・イタリア・ドイツ・ポーランドなどの大河川流域に伝播した建築様式だそうですが、ゴシック建築とは何かという定義づけが難しいのだそうです)の建築物だそうです。
第二次大戦の爆撃を免れ、その後木製扉が青銅製に改修されたそうです。
ミラノ近郊にあるマッジョーレ湖が大理石の産地だそうで、その大理石を利用し、外壁はやや赤みを帯びた白大理石、内部の床は色とりどりの大理石を組み合わせたモザイク模様だそうです。
3600の彫像とともに135の尖塔があり、尖塔の天辺には一つ一つに聖人が立っており一番高い位置に金のマリア像が輝いているのだそうです(尖塔が間近に見られるドゥオモの屋根に上がることができるみたいです)。
500万人のカトリック信者がいる世界最大の司教区であるミラノ大司教区を統括する首都大司教の司教座聖堂だそうです(司教・大司教が教区内の信徒を教導し司式するための着座椅子のことを司教座というそうで、司教座のある聖堂のことを大聖堂=カテドラルというそうです)。

聖堂の内部は52本の巨大な石柱が並んでいます。

ステンドグラスは55枚あるそうです。

教会の発展に貢献した歴代の聖人たちが葬られています。




20世紀になって木製から改修された青銅の扉は5枚あり、それぞれ、聖堂の歴史・ミラノの歴史・マリアの生涯・聖アンブロージョの生涯・コンスタンティアヌス帝の勅命が浮き彫りされているそうです。

自由時間はドゥオモ目の前のデパート「リナシェンテ」に行きました。
7階にはフード・マーケットと、ドゥオモが綺麗に見えるカフェがありました。
地下1階にはスーパーマーケットがあるそうですが行けなかった。

クリスマスのプレゼント用にチョコレートがたくさん売られていました。
靴やバッグや果物の形をしていますが、みーんなチョコレート。




イタリアはカソリックの国。
クリスマスマーケット等は本来ないのですが、出店が増えているそうです。

ランチは、リゾットとミラノ風カツレツ。






ミラノといえば世界遺産の「レオナルド・ダ・ヴィンチの<最後の晩餐>があるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会とドメニコ会修道院」ですが、このツアーでは行程にありません。
1回10人ほどで15分までと制限も厳しく予約も取りにくいと聞きますねー。
ランチの後、167km走ってベローナへ。
午後はベローナのジュリエットの家観光です。
ベローナは、ローマ時代の遺跡や中世の街並みがよく残されていて、「ベローナ市街」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されているそうです。
ウィキによれば、古くから交通の要衝の地であり、13世紀から14世紀はデッラ・スカラ家の統治、その後ミラノのヴィスコンティ家の支配下に入り、15世紀初めからはベネチア共和国に属したそうです。
人口約25万人のベローナ県の県都だそうです。
可愛いガイドさん。

舗道の敷石にアンモナイトが入ってます。
アンモナイトとは、アンモン(Ammon)の石(-ites)という意味で、頭に牡羊のような巻き角があるギリシャ神話のアンモン神もしくはエジプトのアメン神から付いた名前だそうです。
アンモナイトは、約4億4370万年前から6600万年前までのおよそ3億5,000万年間海洋に広く分布し繁栄したそうです。
アンモナイトの化石はその種類が限定的・規則的で、発見される地層の年代をアンモナイトで特定できる有用な示準化石だそうです。

古代ローマ時代の遺跡。

ローマ帝国時代の門の跡で、ポルタ・レオーナ(獅子の門)と呼ばれているそうです。

ランベルティの塔。
12世紀に建設されたそうです。

ジュリエットの家。
ジュリエットのモデルとなったカプレーティ家の娘の家です。
ロミオとジュリエットはシェイクスピアによる悲恋物語で、ロミオの実家モンタギュー家(教皇派)とジュリエットの実家キャピュレット家(皇帝派)の対立は、支配層が教皇派と皇帝派に分かれて争っていた当時のべローナ情勢を背景にしたものだそうです。

バルコニー。

ジュリエット像の右胸に触れると幸運になると言われているそうです。

バルコニーに行くのは有料。

自由行動はウインドウショッピング。



スカラ家の教会。

こんな高い所に…スカラ家の4代カングランデ1世の墓だそうですが、前期ゴシック様式の彫刻の一部とされているそうです。

古代ローマ時代の屋外闘技場、アレーナ・ディ・ヴェローナ。
紀元後30年頃に完成したそうで、長径139m・短径110mの楕円形で、観客席は44段の大理石製で約25,000人を収容したそうです。
バックスタンド席でステージ上の息遣いが聞こえるほどの音響効果があるそうで、1913年から世界最大規模の屋外オペラ会場として利用されていることで知られているそうです。

夕景。

ベローナ観光の後、124km走ってベネチア(メストレ)へ。
2泊めは、ベネチア(メストレ)<ホテル・ノボテル・ベネチア・メストレ・カステラーナ>泊です。
3日めは、ベネチア市内観光(サンマルコ寺院・ドゥカーレ宮・サンマルコ広場・ベネチアングラス工房)です。
人口約26万人の県都だそうです。
べネタ潟の島々やメストレなどの本土側を含み面積は412.54 km²だそうですが、その中心はべネチア本島の5.17km²にあるそうです。
潟(ラグーナ)の上に築かれた運河が縦横に走る水の都とは、知るところですよね。
ウィキによれば、150をこえる運河が177の島々を分け運河には400におよぶ橋がかかるそうです。
すごーい。
水上タクシーに乗ってベネチア本島に向かいました。

ベネチア島到着。
「ベネチアとその潟」として世界遺産(文化遺産)に登録されています。
古代ウェネティア人が住んでいたことからベネチアと呼ばれるようになったそうです。
大母神ウェヌス=ヴィーナスから取ったと聞いたこともあります。

そこはいきなり広々としたサン・マルコ広場なのですが、正面のサン・マルコ寺院と繋がるドゥカーレ宮殿を見学しました。


この後は撮影禁止。
美人のガイドさん。
ここはドゥカーレ宮殿の前。

運河に架かる小さい可愛い橋を渡り、ベネチアングラス工房に向かいました。



きれーい。目の保養です。




自由行動。ジェラートを食べてみました。


国立考古学博物館とコッレール博物館に行ってみました。
同じ建物にあり、共通のチケットでした。

いよいよゴンドラに乗ります。


ゴンドリエさんと(私の乗ったゴンドラのゴンドリエさんではないのだけど)。

ゴンドリエは個人事業主だそうでその技術は親から子へ受け継がれてきたそうですが、若者に敬遠されその習慣が崩れてきたそうです。
現在は、ゴンドリエ養成所で外国語・べネチア史・ベネチア美術史等の基礎知識を学び、ゴンドラ協会が行う筆記試験・6ヶ月から12ヶ月間の実地訓練・実施試験の後、交代要員として経験を積むのだそうです。
自分の船だそうで、80万円くらいするそうでした。
1500年代貴族の乗り物となりきらびやかに豪華になり、時の元老院が黒(防水のために塗られる松脂の色)に統一し、現在に受け継がれているそうです。

魚もたくさんいるそうですよ。



ランチを含む自由時間です。
ランチはツアーのお仲間と一緒にしました。


イカ墨のパスタ。




レモンチェッロはサービス。

サン・マルコの鐘楼に上りました。
高さは98.6m、上部の鐘架の上にベネチアを象徴するライオン、さらにその上のピラミッド型の尖塔の頂上に大天使ガブリエル。
サン・マルコ広場とサン・マルコ寺院が見えます。
サン・マルコ寺院は1090年代に建設された十字形平面で中央部に円蓋を持つクロス・ドーム形式のビザンティン建築だそうです。
当時総督の礼拝堂であったためサン・マルコ寺院(もしくは聖堂)と呼ばれてきたそうですが、1807年ヴェネツィアを占領したナポレオンの命により司教座(祭壇の内陣中央に設けられる司教が座るための椅子・司教座)が移され、司教が長を務める大聖堂となった後もサン・マルコ寺院と呼ばれているそうです。
えーとね、828年のことだそうですが(当時ヨーロッパの都市は守護聖人を置くのが流行りだったそうで)、聖(サン)マルコ(新約聖書の4人の福音書記者の1人)の遺骸がエジプトのアレキサンドリアの教会にありイスラム勢力がそれを奪取しそうだという情報をつかんだベネチア商人がアレキサンドリアに赴き、遺骸を買い取り、イスラム勢力に見つからないようイスラム教徒が嫌う豚肉(コーランが「豚は汚れた動物なので食べてはいけない」と定めている)を満載した籠の中に遺骸を入れ、ベネチアに持ち帰ったそうです。
マルコが有翼のライオンであらわされるのは、「新約聖書・ヨハネの黙示録」に記されているヨハネの幻視である神の玉座のまわりに控える4種類の天使的存在の記述から来ていると考えられるそうです。
6枚の翼と多数の目を持ち、その姿は、第一が獅子、第二が雄牛、第三が人の顔、第四が鷲のような姿であったそうです。
「マルコ福音書」でヨハネが砂漠の獅子として登場し、そこから「翼ある獅子」が聖マルコの象徴となったと考えられるそうです。

ドゥカーレ宮殿かなー?
ドゥカーレ宮殿とは「総督の宮殿」の意味だそうです。
このベネチアのドゥカーレ宮殿は、1465年頃に完成したルネッサンス建築(フィレンツェで1420年代に始まり17世紀初頭まで続いた建築様式で古典古代を理想とするもの)の傑作だそうで、現在はマルケ国立美術館になっているそうです。


有名なカッフェ・フローリアン 。
1720年に創業というベネチアに現存する最も古い喫茶店で、カフェ・ラテの発祥店として有名だそうです。

年末のディナーの案内が張ってありましたがかなり高級な料金だったので、カフェ・ラテも飲まず退散しました><。

ショップの数々。
見ているだけで楽しい。


さよなら、ベネチア。
ベネチアは12世紀から16世紀にかけて強力な海軍を背景に東西貿易の基地として勢力を持ち巨万の富を築き、アドリア海・東地中海沿岸がベネチアの影響下に置かれたていたそうです。
この時期にベネチアの商人だったマルコ・ポーロがシルクロードを経て元へと旅行し「東方見聞録」を書いたそうです。
しかし15世紀半ばにヨーロッパ人によるインド・アジア大陸・アメリカ大陸などへの植民地主義的な海外進出を行う大航海時代を迎え、アドリア海・東地中海貿易の重要性の低下・オスマン帝国の侵攻等により衰退し、1797年ナポレオン・ボナパルトに征服されたそうです。

ベネチア観光の後、269km走ってカンピ・ビゼンチオへ。
3泊めは、<スターホテル・ベスブッチ>泊です。
ホテルそばのショッピングモールに行きました。





クリスマスになると「人々の救いのために貧しい馬小屋で赤ん坊として生まれてくださったイエスさまのことを思い起こし」馬小屋でのイエスの誕生の場面をかたどったものを造り(プレゼピオと言い飼い葉桶のことだそうです)、感謝と賛美を捧げるのだそうです。
プレゼビオ、大小さまざまなものがたくさん売ってました。
街角や教会のプレゼピオには赤ちゃんイエスがいません。
12月24日一斉に赤ちゃんイエスが飼い葉桶に置かれるそうです。

4日めは、ピサ観光・フィレンツェ(ウッフィ美術館・ドゥオモ・シニョーリア広場・ミケランジェロ広場・皮革製品工房)です。
108km走ってピサへ向かいました。
ピサ到着~。
ここから園内バスで向かいます。
ピサは人口約8万6000人のピサ県の県都です。
14世紀に衰退するまで、古代から海運により力を持った都市だったようです。
ガリレオ・ガリレイの生誕地だそう。へー。

わーっ。

綺麗なガイドさんと合流。

洗礼堂。
高さ54.85m、直径35.5m。
クーポラ(半球形の天井ドーム)がある円形の大理石の建造物で、1層目はロマネスク様式(10世紀から12世紀頃にフランス・スペイン・ドイツ・イングランド等西ヨーロッパに広がったゴシック建築以前の建築)・2層目はゴシック様式になっているそうです。
クーポラの上にサン・ジョヴァンニ(聖ヨハネのこと。フィレンツェの守護聖人)の像が乗っているそうです。

大聖堂。
バシリカ式(十字架型平面形)と言われ、ラテン十字形(縦長で横木が軸木のやや上方に付けられているもの)の平面形体だそうです。
ロマネスク建築といいつつ、ビザンティン文化(東ローマ帝国4世紀~15世紀=ビザンティン帝国で栄えた古代ギリシア・古代ローマの文化にキリスト教・ペルシャ・イスラムなどの影響が加わった文化)の影響も見受けられるそうです。

大聖堂・洗礼堂・鐘楼の3セット。
「ピサのドゥオモ広場」として世界遺産(文化遺産)となっています。
ピサの斜塔は鐘楼にあたります。
1064年大聖堂起工・1152年洗礼堂起工・1173年鐘楼起工で、それぞれ14世紀後半に完成されたそうです。

あのね、デジカメの補正機能ってすごくて、ピサの斜塔をまっすぐにしちゃうと聞いてはいたおですが、本当でした><。
ピサの斜塔を支えるという画像も成り立たず…。あーあ。


斜塔に登ります。
斜塔は倒壊の危険により観光客の立ち入りが禁止されてきたそうですが、2001年に修復・補強工事が完了し(日本企業も土壌の安定化の工事に携わったとか)、40人限度で40分毎と制限がありつつも上れるようになっています。
高さ55m・階段297段だそうです。
1173年大聖堂の鐘楼として着工し、200年後の1372年に完成したそうです。
ピサ大学の教授だったガリレオ・ガリレイ(1564~1642年)が頂上から大小2個の球を落下させ、同時に地上到達する落下の法則を見せたことも有名です。




磨り減った狭い階段。危険かも…。
(あのね、ヨーロッパの美術館の階段から落ちた方を知っています。大腿骨を骨折して現地で手術を受け入院したそうです。気をつけねば…)

斜塔てっぺんからの眺め。

鐘。

さよなら、ピサ。

108km走ってフィレンツェへ。
人口約36万人のフィレンツェ県の県都です。
ウィキによれば、中世には毛織物業と金融業で栄えフィレンツェ共和国としてトスカーナの大部分を支配し、メディチ家による統治の下15世紀のフィレンツェはルネッサンスの文化的な中心地となったそうです。
市街中心部が「フィレンツェ歴史地区」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)になっています。
古代ローマ時代、花の女神フローラの町としてフロレンティアと名付けた事が語源とされているそうです。
ミケランジェロ広場。
フィレンツェの美しい町並みが一望できる場所です。
ドゥオーモとヴェッキオ橋も見えています。

ダビデ像。
ミケランジェロ(1475-1564)の彫刻のコピー。
実物はフィレンツェのアカデミア美術館に収蔵されているそうです。

橋の欄干に立つ電灯の脚が面白くて撮りました。

ヴェッキオ橋(イタリア語で古い橋)を間近に。
アルノ川(ファルテローナ山を源にピサの西側でティレニア海に注ぐ)に架かる橋でフィレンツェ最古の橋だそう。
橋の上に宝飾店が建ち並んでいるそうです。

ランチはきのこのパスタ。
きのこってボルチーニ茸です。良い香りでした。
日本ではヤマドリタケといい、とっても美味しいきのこです。








ドゥオモが見えてきました。
ドゥオーモ(大聖堂)、サン・ジョヴァンニ(聖ヨハネ。フィレンツェの守護聖人)洗礼堂、ジョット(イタリア人画家・建築家1267年-1337年)の鐘楼の3点セット。
世界遺産(文化遺産)「フィレンツェ歴史地区」の一部です。
ドゥオモの107メートルあるクーポラに464段の階段を使ってのぼることができるそうです。

ドゥオモ。サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂。
1296年から140年以上をかけて建設され、外装は白大理石を基調とし緑・ピンクの大理石で装飾されたゴシック様式だそうです。
ファサード(建物の装飾的正面)は19世紀に完成したネオ・ゴシック様式だそうです。

内部はイタリア独特のゴシック様式で、簡素だからこそ映える大理石の床やステンドグラス、とのこと。

24時間時計文字盤。
「I」がミサが行われる日没を示し、逆回転する針は残り時間を示しているそうです。

ジョルジョ・ヴァザーリ(イタリア人画家・建築家1511年-1574年)、フェデリコ・ツッカリ(イタリア人画家・建築家1542年-1609年)によるフレスコ画「最後の審判」。


プレゼピオ。
イエスはユダヤの町ベツレヘムで処女マリアより生まれたとされています。
皇帝アウグストにより徴税のための住民登録を命じられ、ヨセフとマリアは先祖の町ベツレヘム(古代イスラエルの王ダビデの町でメシアはそこから生まれるという預言があった)へ赴き、宿屋が混んでいたため馬小屋に泊まり、干草の中でイエスを生み、飼い葉桶に寝かせたとされているそうです。
べツレヘムの星に導かれてやってきた東方の三博士は、救世主イエス・キリストの降誕を拝し、乳香(神聖な香)・没薬(もつやく。香・鎮静薬・鎮痛薬)・黄金を贈り物としてささげたとされています。
まだイブではないので、飼い葉桶に赤ちゃんイエスはいません。

シニョーリア広場。
ヴェッキオ橋・ドゥオモ広場・ウフィツィ美術館へ向かう道があり、いつも観光客や地元の人で賑わっているそうです。
古代ローマ時代は、ローマ劇場・公衆浴場・市場などがあったそうです。

ヴェッキオ宮殿。1314年に完成したロマネスク様式の宮殿。
フィレンツェ共和国の政庁舎だったそうです。
現在は、フィレンツェ市庁舎として使われているそうです。

ウフィツィ美術館に隣接しているランツィの回廊(ランツクネヒト(ドイツ人傭兵)が使ったことに由来する名前)には、古代およびルネサンス美術の野外彫刻が展示されています。
ベンヴェヌート・チェッリーニ作のブロンズ像「ペルセウス」。
チェリーニの傑作と言われているそうです。
ギリシャ神話から、ゴルゴン3姉妹のうち唯一不死の身ではなかったメドゥーサの首を、王命により討ち取った場面。

バンディネーリ作の大理石像「ヘラクレスとカクス」。
粗野で野暮な彫刻と酷評されたそうです。
カクスは、3つの首を持ち火を噴き、人間や家畜を襲っては食べる怪物。
ギリシャ神話から、ヘラクレスが「十二の功罪」の一つゲリュオンの牛の確保を終え帰途ティベリス川の近くで野営したとき、こっそりこの牛を盗んだカクスをヘラクレスが締め殺した場面。
河童みたいのが押しつぶされていておかしい。

このほかにも、ギリシャ神話を題材にした彫刻がたくさん展示されていました。
「パトロクロスを抱きかかえるメネラウス」「ケンタウルスを倒すヘラクレス」「サビニの女達の略奪」などありました。
いよいよ、ウフィツィ美術館。
建物は、初代トスカーナ大公コジモ1世がフィレンツェの官庁をひとつの建物に収めさせた庁舎だったもので、1580年に完成したルネッサンス様式(14世紀にイタリアで始まり西ヨーロッパ各国に広まり17世紀まで続いた古典古代=古代ギリシャ・ローマを理想とする表現)の建築物だそうです。
内部は撮影禁止。
メディチ家歴代の美術コレクションを収蔵し、イタリアルネッサンス絵画の宝庫だそうです。
ウィキによれば、展示物は2,500点にのぼり、古代ギリシア・古代ローマ時代の彫刻から、ボッティチェッリ・レオナルド・ミケランジェロ・ラファエロらイタリアルネッサンスの巨匠の絵画を中心に、それ以前のゴシック時代、以後のバロック(16世紀末から17世紀初頭にかけイタリアで発祥しヨーロッパの大部分に広まった豪壮・華麗な様式)・ロココ(18世紀フランス宮廷で発祥しヨーロッパの各国に伝わった曲線を多用する優美・繊細な様式)などの絵画が系統的に展示されているそうです。
「ヴィーナスの誕生」(1485年頃、サンドロ・ボッティチェッリ)
「受胎告知」(1475年頃 レオナルド・ダ・ヴィンチ)
「ウルビーノ公夫妻の肖像」(1472年頃 ピエロ・デラ・フランチェスカ)
等が印象に残りました。
コジモ1世は、住まいだったピッティ宮殿からベッキオ橋の2階部分を通り庁舎(現・ウフィツィ美術館)へ通う約1kmの通路(ヴァザーリの回廊)も造らせたそうで、この回廊の中にも700点を超える絵画があるそうです。
なんか壮大な話です…。

コジモ1世が毎日歩いたのかとしみじみベッキオ橋を眺めました。
そのために屋根も壁もあったのでしょうねー。

ドゥオモの前を警護するパトカー。

1939年創業のフィレンツェ老舗ジェラート屋さん「ペルケ・ノ!」。
日本語のメニューもあるそうです。
保存料・添加物を使用していないジェラートの味は40種類ほどあるそう。

「FESTIVAL DEL GELATO」
ガイドさんのお勧めは「ペルケ・ノ!」と、この「FESTIVAL DEL GELATO」でした。
何たって「スリ・置き引き・つり銭詐欺・ぼったくり」が日常だと、旅行社からの注意書きに大きく書いてあった国ですので、ジェラート屋のぼったくりも有名です。
料金を確認しないで注文しちゃうと、10ユーロとかぼったくられてしまうそうです。
手作りで良心的なジェラート屋さんに入りたいものです。
ここは、たーくさんの手作りジェラートがあり、2ユーロくらいでした。







夜のドゥオウモ。

行列ができるバニーニ屋さん。

その並び客を呼び込むお隣の手品屋さん。

夕暮れのドゥオモ周辺での自由行動はとても楽しかったです。
夕食はカンピ・ビゼンチオに戻り、フォレンツェ風ステーキ。








4泊めも、<スターホテル・ベスブッチ>泊です。
これにて<イタリア旅行 ダイジェスト その2-1>終了。
<イタリア旅行 ダイジェスト その2-2はこちら>。
<イタリア旅行 ラウンジ・エア・ホテルはこちら>


















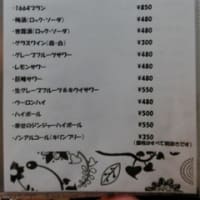

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます